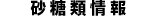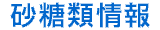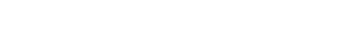
[2000年12月]
わが国に、初めて砂糖が持ち込まれたのは、奈良時代唐の高僧鑑真によるものだといわれています。当時は薬用として用いられ、一般に広く入手できるようになり調味料として用られたのは江戸時代からという。食物史家平野雅章氏に砂糖の歴史や日本における郷土料理における砂糖の使い方などを執筆していただきました。
食物史家 平野 雅章
砂糖以前の甘味料
「甘い」と書いて「美味(うまい)」「旨い」と読ませるほど、 日本人は甘味に眼がなかった。それほど甘味は味の中でも魅力的な味覚で、砂糖がなかった時代の古代の人は、いかに苦労して甘味料を入手したか、また、どんな甘味料を用いていたかについて、探ってみよう。
砂糖以前に、わが国ではどんな甘味料があったか、食物史から探索してみると、蜂蜜、蘇(そ)、甘葛煎(あまずらせん)、飴(あめ)などがその主なものである。蜂蜜や飴は今日でも用いられているが、蘇や甘葛煎は、現在実物を味わうチャンスはほとんどない。甘葛煎は最も多量に用いられ、ごく普通の甘味料として重宝されたらしいが、それはどのようなものであったか、分らない点が多いが、大体このようなものであったらしい。
甘葛煎は深山に自生する蔦(つた)の一種で、蔓液に濃い甘味を含んでいる。秋から冬にかけて葉の紅葉する頃、松や杉にからんでいるものを、地上より少し上のところを切断し、そこから液を採る。この液汁は蜜のように甘く、甘味料として利用されてきた。奈良や和歌山県の山間部では、今でもこれを採取する風習があると聞く。『延喜式(えんぎしき)』(平安時代の法令集) には、諸国からこれを貢進したことが記されている。古名をととき、味煎などともいった。『枕草子』には、
「あてなるもの、削(けず)り氷(ひ)にあまづら入れて、あたらしき金鋺(かなまり)に入れたる」
などとみえている。また、平安時代、宮中において読経がいとなまれるとき、僧に茶を賜うの儀が行われ、煎茶の中に甘葛煎を加えたとの記録もある。蜂蜜は供給量の少ない貴重な甘味料で、飴は加工工程が面倒で、量産が難しかったせいか、供給量の豊かな甘葛煎が多大な貢献をしたことが文献からうかがわれるが、中世以降、砂糖が出回るにつれ、次第に表舞台から姿を消し、今日では、その実態すらハッキリしないほどになってしまった。蜂蜜や飴が依然として用いられるのに対し、この甘葛煎が顧られなくなったのは、甘味の質に問題があったのではなかろうか。『枕草子』のように、削り氷に甘葛煎入れてと見えるように、砂糖水のように使われたのだろう。飴や蜜のように薬用にも使ったようだ。
次に蘇であるが、これは動物質の甘味料である。乳から酪(らく)を作り、酪から蘇を作り、蘇から醍醐(だいご) を作る、つまり乳製品である。奈良朝の頃、すでに諸国に牧場があり、蘇が作られていた。その蘇は貢進の重要な一品で、薬用に供されたのである。「醍醐」 は酪の精汁で、蘇の上に浮かぶ油のようなものであり、その味が甘味を極めたものであるところから、仏法の妙趣に譬(たと)えて、これを「醍醐味」といい、薬用として珍重されたが、転じて調味料として供されもしたのである。今でいえば極上の生クリームかチーズといったところであろう。
次いで蜂蜜であるが、今日でも甘味料にも薬用にも使われている。薬用としての価値は、ローヤルゼリーが出現するに及んで神秘化されるにまで至っている。もともとは山野にある蜜蜂の巣から蜂蜜を採取したのが起こりであろうが、養蜂による蜂蜜の採集は、意外なほど古くから始められていたようだ。『日本書紀』皇極天皇2年(643)、
「百済(くだら)の太子余豊(よほう)、蜜蜂の房四枚(すよつ)を以て、三輪山に放ち養(か)ふ、而して終(つい)に蕃息(はびこ)らず」
蜜蜂の4家族を三輪山に放ったが、ついに繁殖しなかった――という記述がある。文献として最古のものである。百済ではすでに養蜂が行われていたことをうかがわせる。『延喜式』の諸国年料供進の項に、甲斐、相模、信濃、能登、越中、備中、備後の7ヵ国から1ないし2升の蜜を供進させたことが載っているから、平安時代には朝廷に蜜を供進させていたことは明らかであるが、この蜜がいかなる方法で得られたかはハッキリしない。しかし、少量で貴重品であったから、当初は薬用にするのが関の山であったろう。蜜は当時ミチと呼び、調味料として用いたにしろ、どのように使われたか、うかがい知ることはできない。
最後に飴について触れておこう。飴は音はイで、古書には「阿女」と訓じ、今もアメで通っている。『日本書紀』神武紀に、
「水無くして飴を造らん」
と、出ているが、飴を「たがね」と読ませている。『延喜式』に「糖」とあるのは飴のことで、砂糖のことではない。『和名抄』に、
「飴は米もやしの煎なり。阿女」
と、記されており、古くは米もやしを使ったもののようだ。『箋註和名抄(せんちゅうわみょうしょう)』には、
「今の俗、飴を作るに麦もやしを用ふ。米もやしを用ひず」
とあるから、麦もやしを用いるようになったのは、後のことらしい。江戸期の百科辞典『倭漢三才図会』には、麦もやし、あるいは穀芽同諸米を用いる――とあって、麦芽を用いるようになったのは後世のことである。飴造りを業とするものが多くなったのは、室町時代からで、その頃から飴に豆を入れた菓子が上流の人たちの間で賞味されるようになった。
砂糖の日本小史
紀元前4世紀に東方に遠征し、一時ギリシャからインドに至る大帝国を作ったアレキサンダー大王(前356〜前323)がインドを攻めたとき、兵士たちがインドで砂糖を見たというのは、紀元前320年前後の頃であった。兵士たちが北インドに進入したとき、「蜂が作ったのではない固い蜜」を見つけて大喜びしたというのである。このとき以来、ごく僅かな砂糖が隊商を組んだ商人たちの手によってヨーロッパにもたらされていた。
しかし、砂糖の生産がヨーロッパその他の地域に広く伝播したのは、イスラム教徒の手によってであった。「砂糖はコーランと共に」西へ西へと旅して行った。7世紀初頭にアラビア半島で生まれたイスラム教は、たちまち広い地域に広がり、のちには東方ではインド、インドネシア、中国の一部にも伝わり、西方は今日のトルコや北アフリカにも布教の手を広げた。西方に広がったイスラム教徒の支配した地域には、砂糖黍(さとうきび)の栽培と製糖の技術が次々と伝えられていった。中でもキプロス、ロドス、クレタ、シチリアなど、今のトルコからイタリアにかけての地中海東部の島々で、その栽培が盛んになった。そればかりか、モロッコなどの北アフリカやスペインにも、栽培が導入されていった。
中国史の上では漢時代から存在していたといわれるが、文献上に砂糖のことが多くみられるようになったのは唐の時代からである。
『木草綱目』沙飴の項には、唐の太宗が初めて人を遣してその法を伝え、中国に入る――とある。その頃、南方から貢進されたものらしい。唐より宋にかけて製糖法が発達し、濃汁から結晶砂糖を作るようになった。太宗以前にも、西域の製法によって作られた紫沙糖(黒砂糖)があったが、太宗が人を遣して天竺で作られている糖霜(白砂糖)の製法を学ばせたのである。
日本に初めて砂糖が伝来したのは、太宗より百年後の孝謙天皇の天平勝宝6年(754)、唐僧鑑真が来朝したときの舶来品の中に、「石蜜、蔗糖、蜂蜜、甘蔗」とあるのがそれである。石蜜とあるのが今の氷砂糖あるいは堅飴製品であり、蔗糖が今の砂糖である。これらは薬用品で、調味料ではなかった。石蜜、蔗糖などは「七日薬」と称し、不食戒を護持する律僧の所持する品であった。
もっとも砂糖は奈良朝時代の学問僧や遣唐使によって輸入されたことも考えられる。時代は平安時代になるが、延暦20年(801)に帰朝した最澄の「献物目録」の中には、砂糖を進上したことが見え(『伝教大師正伝』二)、奈良朝時代にもこのようなことがあったと推定し得るからである。鑑真は初め砂糖黍を船に積んで航海したが難破して、積荷は沈んでしまった。それからたびたび航海に失敗しながらも、遂にわが国へ渡来した。もしそのとき、砂糖黍を持って来ていたら、ヨーロッパより早く日本で砂糖が作られているはずである。
宋貿易の輸入品目のうち、砂糖は薬品の中に含まれているが、その頃は薬用のほかに、上流社会の調味料、菓子原料としても使われていたようだ。室町時代になると、黒糖、白糖ともに、主として明の江南地方から輸入されていたが、輸入量は少なく、薬用が主で、貴族や富豪の間で甘味料として珍重されていたにすぎない。
狂言「附子(ぶす)」は黒砂糖が生附子(トリカブトの根から採った汁を日に晒(さら)して作った毒薬)に似ているのを、うまく利用した狂言。主(あるじ)は太郎冠者と次郎冠者に附子という大毒のものがあるから注意するように言い置いて外出する。太郎と次郎は附子が気になり、蓋を開けてみると意外にも砂糖なので、全部平らげてしまう話である。砂糖が極めて貴重品であった時代の背景がよく描かれている。室町中期になると琉球からも輸入され、砂糖羊羹、砂糖饅頭が作り出されるようになり、ようやく菓子の甘味料として使われ出した。南蛮交易が始まるに及んで、砂糖の輸入量が増えたとみえて、信長時代にはようやく調味料として使われたようだ。でも一部の人が使うのみで、広く菓子として、また調味料として使われるようになったのは江戸時代の中頃からだ。その間に砂糖は国産ものが少しは出回ったものの、輸入によってこれを補い、明治このかた台湾を領有するに及んで、国産品で自給自足できるまでに至った。
国産の砂糖は、3代将軍家光や8代吉宗が砂糖黍の栽培を半ば命令みたいな形で奨励して、薩摩、紀伊、讃岐、阿波、和泉、駿河、遠江、三河などに砂糖黍畑が広まり、砂糖の製造も始まり、さらに輸入糖も加えて、たやすく砂糖が入手できるようになった。砂糖が菓子だけでなく、調味料に使われたのは江戸の町だった。いかなる理由があってのことか詳しいことは分からないが、推定できることは、調味を濃厚にする材料は、昆布や淡口醤油より野田や銚子の濃口醤油に、さらに砂糖を加えたものが、江戸の人の好みに投じたのだろう。
郷土料理と砂糖
郷土料理というと、郷里を持たない都会人には地方の野趣に富んだ料理――と受け取られがちである。地方に育ったが、都会に出て住みつくようになった人々には、郷土料理はノスタルジーも手伝って、自分の味覚のふるさととして懐しむが、材料や気候風土との関係もあって、必ずしもいつも郷土の料理を食べているとは限らない。地方地方には、それぞれの郷土料理があるはずだが、雑誌、テレビによる様々な料理法の普及と、交通手段の発達で、食材料の交流が盛んになり、大都会における同様な各種の料理が一般に試みられるようになり、地方特有の郷土料理は、その土地でも次第に名物扱いにされるような始末である。
また、妙なことに温泉宿で当地名物の山菜料理にあずかろうと思っていても、特別に注文しないかぎり、マグロの刺身やてんぷらといったような、どこでも似たりよったりのものを出す。山菜などは大抵のお客さんが喜びませんから――と仲居さんは言う。悪いことに、田舎の人たちは、都会風のものを、いつも自分たちのところのものより上等なものだと思い込んで、卑下する傾向があるので、こんなものは、都会のお客さんの口に合わないものと頭から思い込んでいるようだ。
たまに言われぬ先に土地の名物の山菜料理が出たとして、精一杯ごちそうする気で、砂糖のたっぷり入った山菜が出てくる。好みや食べる人の食体験にもよろうが、甘過ぎるきゃらぶきはどうか。きゃらぶきは酒の肴にしても、ましてごはんのおかずにも、お茶請けにもいい。きゃらぶきの調味は醤油が主で、それにみりんと酒を少々足し、汁気がなくなるまで、じっくり煮た少々辛めのものがいい。きゃらぶきに限らず、煮物や保存食に砂糖を多用するのは、1つには生活の知恵で、防腐効果を期待してのことと思われる。今1つは海に遠い山村では、新鮮な魚など入手困難で、少し古くなった魚も、砂糖味を強くきかせると、ある程度おいしくいただける。そのような働きも知ってのことだろう。砂糖が調味料として一般的になったのは、明治中期以降、台湾領有以後のことであって、明治の田舎の生活では、まだまだ砂糖は貴重品であった。その貴重な砂糖をたっぷり使うことは、相手に対する心からなるもてなしであった。中学の歴史科の先生が、育ち盛りの明治の後期、東北の田舎では、砂糖は盆と正月に小豆を煮て食べる時しか使わなかった――と想い出話をしてくれたことを、今でも忘れかねている。
森口多里の『町の民俗』によると、明治11年頃、岩手県水沢町の高野という医者の嫁入振舞いに、初めて砂糖の入った小豆餅(お汁粉)が出たというので、町中の評判になったとあるから、いかに田舎では砂糖が貴重品であったかが分かる。砂糖味のきつい田舎の郷土料理は、そういった貴重品だった頃の名残りのサービスだろう。
砂糖の種類と活用法
生臭い魚やクジラなど甘辛く煮ると、生臭味を感じなくなる。甘味が味覚をカモフラージュする性質を持っているからだ。甘い味は、塩からい、酸っぱい、苦いといった基本の味に対して相乗、あるいは相殺的に働く。まず塩味に対しては相乗的に働く。塩と砂糖を合わせると、どちらか多い方の味が強調される。お汁粉にちょっぴり塩を加えて、コッテリした甘味を強調するのは、どなたも経験があろう。甘味は酸味や苦味に対しては、相殺的に働く。すっぱい夏みかんに砂糖をよく浸み込ませてから口にすると、酸味が和らぐ。また、コーヒーを強く出すと、いやな苦味が出てくるが、砂糖を加えると、その苦味が分からなくなって、おいしく飲めるのもそれ。砂糖はお酒と同様、用い方によっては人生の憂いを掃くこと多大である。お菓子がなかったら、食生活は味気ないものになってしまう。
締めくくりに砂糖の種類と活用法について触れておこう。今一般に使われているのは白砂糖で、いわゆる精製糖だが、その結晶を大きく発達させたのがザラメ。純度が高く99パーセントの蔗糖を含んでいる。このうち結晶の特に小さいものをグラニュー糖と呼び、コーヒー、紅茶などを飲む際に使う。さらっと溶けて、甘味だけ強く、クセがない。氷砂糖は糖液を温室内に長期間保って結晶を大きく成長させたもので、最も純粋な砂糖である。これらの砂糖は不純物を除き、蔗糖だけといっていいくらい純度が高い。黒砂糖にはアク(灰汁分)がある。このアクの中には、カルシウムなどのミネラルがたくさん含まれている。味はあくどいが甘味は少ない。もし白砂糖を白米にたとえるなら、黒砂糖は玄米ということになる。
砂糖は甘味の元となる食品であるが、単なる調味料ではない。砂糖は多様な性質を持っていて、それぞれの性質をうまく活かすことにより、調理に一層豊かな深みを与えるものである。調味料として用いる場合にも、その種類によって使い分けがあり、活かし方がある。以下、種類と用い方を見てみよう。
ザラメは主に加工用(キャラメル、つくだ煮)、一般家庭では煮豆、あん作りに上白糖と併用する。グラニュー糖は、紅茶、コーヒーのほか、カクテル用、また乳幼児の人工栄養にも用いられる。車糖に分類される上白は熱を加えなくともすぐ溶ける性質を利用して、一般家庭用の飲み物、料理に用いられる。中白は煮物向き。茶色をした三温糖は、つくだ煮、煮物向き。角砂糖はグラニュー糖にグラニュー糖飽和糖液を加え、立方体に成型して完成させたものである。コーヒー、紅茶など香気を尊ぶ飲み物に使われる。氷砂糖は梅酒をはじめ果物の砂糖漬けになくてはならぬものである。最後に黒砂糖であるが、カリン糖などの駄菓子に用いられ、またようかんや蜜にも珍重される。上白糖に混ぜ、アクを利用して特殊な風味を持たせるのに効果がある。