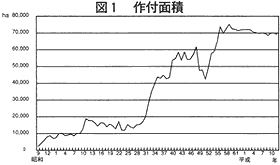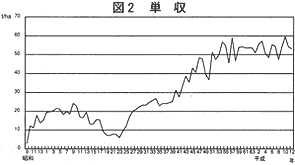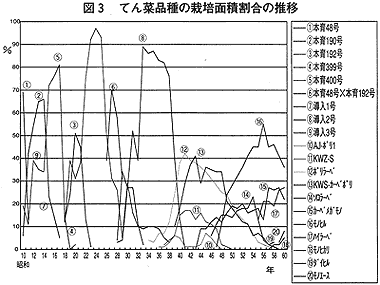�z�[�� > ���� > ���_ > �Y�� > �Ă�ؕi��̕ϑJ1
�ŏI�X�V���F2010�N3��6��
 |
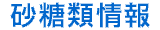 |
 |
�@�k�C���ɂ�����Ă�؍͔|�̗��j�͊J��j����Ɏn�܂������̂́A�{�i�I�ɂ͑�ꎟ���E�����_�@�ɔ��W���Ă����܂����B�����Ă�̕i��́A�h�C�c��t�����X������A�k�C���ɓK��������̂�I�����Ă����A�琬����Ă��܂����B�����A���ʂ��m�ۂ��邽�߂̓w�͂��d�ˍ��ł̓��[���b�p�����̂����Y���̍����Ă�����Y����Ă��܂��B
| (��) �k�C���Ă�؋��� �Z�p�����@���� ���� |
| 1 �͂��߂� | |
| 2 �k�C���ɂ�����Ă�؍͔|���t������蓜������܂� | |
| �@ | (1) �i�퓱���̏����`�{��n���̈琬 |
| (2) ��2�����E����̊O���i�퓱�� | |
| (3) ����킩��P���̓]�� | |
| (4) �i��ƍ͔|�Z�p�̊J���ɂ�鐶�Y���̌��� | |
�@�k�C���ɂ�����Ă�͔̍|�́A1871�N�i����4�N�j�ɊJ��g�ɂ���ē����A���삳�ꂽ���ƂɎn�܂����B���̌�1880�N�i����13�N�j�ɈɒB�A1890�N�i����23�N�j�D�y�ɂ��ꂼ�ꐻ���H�ꂪ�ݗ�����A���̎����ɐ��Y���ꂽ�����Ă�̕��ύ��d��15t/ha,������3.6�����x�ƒႩ�������ߗ��H��Ƃ��̎Z����ꂸ�A1897�N�i����30�N�j�ɂĂ�؍͔|�͒��f���ꂽ�B
�@���̌�A��1�����E���u���ɂ�铜���̖\���ƍ������Y�̕s�����̏�f���ĂĂ�ؓ��Ƃ��ċ�����A1919�N�i�吳8�N�j�эL�ɐ����H�ꂪ�ݗ�����āA�{�i�I�ȍ͔|���n�܂����B�Ȍ��2�����E��풆����ɋK�͂��k�����ꂽ�����͂��������A�����Ȕ��W�𐋂��A�ߔN�͐}1�A2�Ɏ����悤�ɍ͔|�ʐς͖�70,000ha�Ő��ڂ��A�P�ʖʐϓ���̎��ʂ͖�55t/ha�Ő��E�ł��g�b�v���x���̐����ƂȂ����B
�@���̂悤�ȂĂ�؍͔|�̐��ڂ̒��ŁA�͔|�Z�p�̉��ǁA�V�Z�p�̊J���ƂƂ��ɂĂ�̕i����ǂ͂Ă�؎��ʂ̑����⍪�������̌���ɑ傢�ɍv�����Ă��Ă���A����ɂ��Ă͂���܂Ő������L�q����Ă��邪�A�����ł́A���݂܂łɍ͔|���ꂽ�i��̕ϑJ�ɂ��ĊT�v���Љ��B
(1) �i�퓱���̏����`�{��n���̈琬
�@�O�q�̂悤�ɁA�k�C���ɂ�����Ă�؍͔|�̗��j�́A����4�N�ɊJ��g����̎D�y�����ł̎���Ɏn�܂邪�A��q�͓����Ȃ��C�O�������B�i��̓h�C�c�̃N���C�������c���[�x���n�ƃt�����X�̃r�����[�����n�ł������B �@�i��̓����ɓ������ẮA�k�C���ɓK������i��̑I����s��˂Ȃ�Ȃ����A�Ă�̕i���r������1906�N�i����39�N�j�ɖk�C���_��������i�D�y�s�j�ɂ����ď��߂čs���A���̌�A1910�N�㒆���i�吳�����j�Ɏ���܂ŁA��Ƀh�C�c��t�����X�n�̕i�킪��r����A���삳�ꂽ�B1920�N�i�吳9�N�j�ɂĂ�ؓ��Ƃ��ċ����ꂽ�̂��_�@�ɁA�킪���̂Ă�؈���1922�N�i�吳11�N�j�k�C���_�������ꓜ�ƕ��ŊJ�n���ꂽ�B�܂��O���i�킪������������A�K��������ƈ��f�ނ̒T�����s��ꂽ�B���̌��ʁA�h�C�c�̃N���C�������c���[�x���Ђ̎�q���������Ƃ��Ă̓������D��Ă������߁A�Ȍ��10�N�Ԃ͂��̕i�킪�͔|���ꂽ�B���̌�A���̕i�킩��I�����ꂽ�n���̒�����1929�N�i���a4�N�j �u�{��48���v ���琬���ꂽ�B���̕i��͊����a�ɂ͎ォ�������A������������r�I�����A�}3�Ɏ����悤�ɑ�2�����E����Ɏ���܂ō͔|��������ꂽ�B�����̌������ł͊����a�̔�Q���Ђǂ��A���ꂪ�싵���x�z�����v���ł���A�����a��R���i��̈琬���Җ]���ꂽ�B�����a��R���n���̑I���͑吳�����ɂ͂��łɎn�߂��Ă������A1935�N�i���a10�N�j�ɃN���C�������c���[�x�� �u�f�B�b�yK�v �ƃr�����[���� �u�z���C�g�t�����`�v �Ƃ̌��G�g�����̒����� �u�{��192���v ���琬���ꂽ�B���̕i��͓����Ƃ��Ă͊����a��R���ɗD��Ă��������ɁA���ʁE�����Ƃ��ɗǍD�������̂őS���e�n�Ŋ�i��Ƃ���1963�N�i���a38�N�j�܂ō͔|���ꂽ�i�}3�j�B�u�{��192���v �̈琬�ɂ�芌���a�̔�Q��������x����ł���悤�ɂȂ�A���̒i�K�Ƃ��đ�������ړI�Ƃ��ĎG�틭���𗘗p�����i���1��G��̈琬�����{���ꂽ�B���̌��ʁA���ʕ��тɓ��ʂɂ����đ��ɒ������D����̂Ƃ��� �u�{��48���v �~ �u�{��192���v�A�u�k��1���v �i�u�{��162���v �~ �u�{��401���v�j�A�u�k��2���v �i�{��390���v �~ �u�{��401���v�j ����� �u�k��3���v �i�u�{��191���v �~ �u�{��404���v�j �����琬����A��ɋL��GW�n���̓����܂�2�`4�N�ԍ͔|���ꂽ�B
�@�{�����𗘗p��������1941�N�i���a16�N�j�ȍ~��10�N�ԁA���s��w�A�k�C����w�A�k�C���_�������ꂨ��ѓ��{�[�ؐ���������Ђ̋��͂̂��Ƃ�3�{�̕i��̈�킪���E�ɐ�삯�Đi�߂�ꂽ�B���̌��ʁA1951�N�i���a26�N�j �u4398���v�i4�{�́j�~�u�{��162���v�i2�{�́j�� �u3N�|1���v �Ƃ��ĔF�肳�ꂽ�B���̕i��͎��ʂ��������D��Ă������A�����������Ⴍ�A�܂��̎��Ƃ����G���������Ƃ��玎�삳�ꂽ���̂́A���ۂɍ͔|�͍s���Ȃ������B
(2) ��2�����E����̊O���i�퓱��
�@��2�����E������Ă�͔̍|�i��� �u�{��n�v �������������ߊT���Ċ����a�Ɏキ�A�ϕa���i��̈琬���}���ƂȂ����B��2�����E����A�C�O����̐V�Z�p�������e�ՂɂȂ����̂��@�ɍĂё����̕i�킪�A������A�������肪�s��ꂽ�B���̂Ȃ��� 1951�N�i���a26�N�j�A�����J�̃O���[�g�E�F�X�^��������ЁiGreat Western Sugar Company�j���瓱������ �uGW304�v�A�uGW359�v�A�uGW443�v ����� �uGW476�v �͊����a��R��������߂č����A���ʂ��D��Ă����̂ŁA1954�N�i���a29�N�j�ɂ��ꂼ�� �u����1���v�A�u����2���v�A�u����3���v�A�u����4���v �Ɩ�������D�Ǖi��Ƃ��ĔF�肳�ꂽ�B���̂Ȃ��� �u����2���v �͓��ɑ����ł������̂Ŗk�C����~�ɍL���͔|����A1958�N�i���a33�N�j�ɂ͂Ă�؍͔|�ʐς�90�����߂�Ɏ���A1965�N�i���a40�N�j���܂Ŗk�C���̎�v�i��ł������i�}3�j�B
���̂悤�ɐ��̕i����ǂ̕����������a��R���ɏd�_��u�������̂ł��������A1960�N�㒆���ɂȂ��Ċ����a�ɑ������L����L�@���܂��J�����ꂽ���ߖh���Z�p���������i�����A�����a�ɜ�a���̃��[���b�p�n�i����Ăё������肳�ꂽ�B���[���b�p����A�����ꂽ�i��͈�ʂɁu�����n���v�ɔ�ׂĎ��ʐ��y�ђ��ۑϐ��ɗD��Ă������߂ɋ}���ɍ͔|�ʐς����債�A1960�N��㔼�ɂ͑S���͔|�ʐς̑啔�����߂�Ɏ������B1964�N�ɂ͂���烈�[���b�p�i��̒��Ő��h�C�c�A�N���C�������c���[�x����튔����ЁiKWS�Ёj�́uKWS-E�v���т� �uKWS-�|���x�[�^�v�A�I�����_�A���@���f���n�[�x�Ђ� �u�|�����[�x�v�A����у|�[�����h�A�A���L�T���_�[����[�i�X�ЁiAJ�Ёj�� �uAJ�|��1�v �����ꂼ��D�Ǖi��ɔF�肳�ꂽ�B�����̕i��̂��� �uKWS-E�v ������3�i��͂������2�{�̤3�{�́A4�{�̎�q�̍��݂���{���̕i��ianisoploid�j�ł���A�ł��������Y�͂̊��҂����3�{�̂̊�����50�`70���ł������B
�@��2�����E������Ă�͔̍|�i��� �u�{��n�v �������������ߊT���Ċ����a�Ɏキ�A�ϕa���i��̈琬���}���ƂȂ����B��2�����E����A�C�O����̐V�Z�p�������e�ՂɂȂ����̂��@�ɍĂё����̕i�킪�A������A�������肪�s��ꂽ�B���̂Ȃ��� 1951�N�i���a26�N�j�A�����J�̃O���[�g�E�F�X�^��������ЁiGreat Western Sugar Company�j���瓱������ �uGW304�v�A�uGW359�v�A�uGW443�v ����� �uGW476�v �͊����a��R��������߂č����A���ʂ��D��Ă����̂ŁA1954�N�i���a29�N�j�ɂ��ꂼ�� �u����1���v�A�u����2���v�A�u����3���v�A�u����4���v �Ɩ�������D�Ǖi��Ƃ��ĔF�肳�ꂽ�B���̂Ȃ��� �u����2���v �͓��ɑ����ł������̂Ŗk�C����~�ɍL���͔|����A1958�N�i���a33�N�j�ɂ͂Ă�؍͔|�ʐς�90�����߂�Ɏ���A1965�N�i���a40�N�j���܂Ŗk�C���̎�v�i��ł������i�}3�j�B
���̂悤�ɐ��̕i����ǂ̕����������a��R���ɏd�_��u�������̂ł��������A1960�N�㒆���ɂȂ��Ċ����a�ɑ������L����L�@���܂��J�����ꂽ���ߖh���Z�p���������i�����A�����a�ɜ�a���̃��[���b�p�n�i����Ăё������肳�ꂽ�B���[���b�p����A�����ꂽ�i��͈�ʂɁu�����n���v�ɔ�ׂĎ��ʐ��y�ђ��ۑϐ��ɗD��Ă������߂ɋ}���ɍ͔|�ʐς����債�A1960�N��㔼�ɂ͑S���͔|�ʐς̑啔�����߂�Ɏ������B1964�N�ɂ͂���烈�[���b�p�i��̒��Ő��h�C�c�A�N���C�������c���[�x����튔����ЁiKWS�Ёj�́uKWS-E�v���т� �uKWS-�|���x�[�^�v�A�I�����_�A���@���f���n�[�x�Ђ� �u�|�����[�x�v�A����у|�[�����h�A�A���L�T���_�[����[�i�X�ЁiAJ�Ёj�� �uAJ�|��1�v �����ꂼ��D�Ǖi��ɔF�肳�ꂽ�B�����̕i��̂��� �uKWS-E�v ������3�i��͂������2�{�̤3�{�́A4�{�̎�q�̍��݂���{���̕i��ianisoploid�j�ł���A�ł��������Y�͂̊��҂����3�{�̂̊�����50�`70���ł������B
(3) ����킩��P���̓]��
�@�Ă�̎�q�͎틅�ł���A1�̎틅�ɒʏ�2�`4�̎�q���܂܂�Ă�����̂����Ə̂��邪�A�d�킷���2�`4�̂����肷��̂ŁA�Ԉ������s��1�{���Ăɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̊Ԉ����͏t��Ƃ̒��ő����̎��Ԃ�v���Ă�����Ƃł���A�}3�ɂ����M�J�|�x�|���܂ł̕i��͂��ׂĂ��̗l�ȑ���̕i��ł���B����A1�̎틅��1�̎�q���������Ă��Ȃ����̂͒P���Ə̂��A�Ԉ�����Ƃ��������y���o���邩�A���邢�͕s�v�Ȃ��߁A��ƘJ�͂̌y���Ɋ�^����Ƃ��낪��ł���B���̒P����1948�N�i���a23�N�j�ɃA�����J�l�̃T���B�c�L�[�ɂ��A�����J�Ŕ�������A�Ȍ���ɗ��p����邱�ƂƂȂ����B�P���̔����ɐ旧���A1942�N�i���a17�N�j�ɂ̓A�����J�l�̃I�[�G���ɂ��A�\�͂�L����ԕ�����邱�Ƃ̂ł��Ȃ����������A�Ă�̗Y���s��������������Ă����B���̗Y���s�����ƒP�𗘗p�����P��1��G��̈�킪�e���ŋ����Ďn�߂�ꂪ�A�i��Ƃ��ĔF�肳���܂łɂ͐��N��v�����B�킪���ŒP����G�킪�D�Ǖi��Ƃ��ĔF�肳�ꂽ�̂́A1971�N�i���a46�N�j�Ƀ��@���f���n�[�x�Ђ� �u�\�����[�x�v�A1972�N�i���a47�N�j��KWS�Ђ� �u�J�[�x���K���m�v�A1973�N�i���a48�N�j�ɃX�E�F�[�f���A�q���X�w�b�O�Ђ� �u���m�q���v ���ł���A����ȍ~�F�肳�ꂽ�i��͂��ׂĒP����G��ł���B
�@�킪���ɂ�����P�i��̈���1960�N�i���a35�N�j�ɂĂ�ؐU����Ă�،������ŊJ�n����A1973�N�i���a48�N�j���{�ōŏ��̒P�i�� �u���m�z�[�v�v ���F�肳�ꂽ�B�ȗ����X�ƒP�i�킪�琬����ѓ���������p�������悤�ɂȂ����B1981�N�i���a56�N�j�ɂ͒P�i��̍�t�ʐς�90���ȏ���߁A1986�N�i���a61�N�j�ɂ͂��ׂĒP�i��ɂȂ����i�}3�j�B
�@�Ă�̎�q�͎틅�ł���A1�̎틅�ɒʏ�2�`4�̎�q���܂܂�Ă�����̂����Ə̂��邪�A�d�킷���2�`4�̂����肷��̂ŁA�Ԉ������s��1�{���Ăɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̊Ԉ����͏t��Ƃ̒��ő����̎��Ԃ�v���Ă�����Ƃł���A�}3�ɂ����M�J�|�x�|���܂ł̕i��͂��ׂĂ��̗l�ȑ���̕i��ł���B����A1�̎틅��1�̎�q���������Ă��Ȃ����̂͒P���Ə̂��A�Ԉ�����Ƃ��������y���o���邩�A���邢�͕s�v�Ȃ��߁A��ƘJ�͂̌y���Ɋ�^����Ƃ��낪��ł���B���̒P����1948�N�i���a23�N�j�ɃA�����J�l�̃T���B�c�L�[�ɂ��A�����J�Ŕ�������A�Ȍ���ɗ��p����邱�ƂƂȂ����B�P���̔����ɐ旧���A1942�N�i���a17�N�j�ɂ̓A�����J�l�̃I�[�G���ɂ��A�\�͂�L����ԕ�����邱�Ƃ̂ł��Ȃ����������A�Ă�̗Y���s��������������Ă����B���̗Y���s�����ƒP�𗘗p�����P��1��G��̈�킪�e���ŋ����Ďn�߂�ꂪ�A�i��Ƃ��ĔF�肳���܂łɂ͐��N��v�����B�킪���ŒP����G�킪�D�Ǖi��Ƃ��ĔF�肳�ꂽ�̂́A1971�N�i���a46�N�j�Ƀ��@���f���n�[�x�Ђ� �u�\�����[�x�v�A1972�N�i���a47�N�j��KWS�Ђ� �u�J�[�x���K���m�v�A1973�N�i���a48�N�j�ɃX�E�F�[�f���A�q���X�w�b�O�Ђ� �u���m�q���v ���ł���A����ȍ~�F�肳�ꂽ�i��͂��ׂĒP����G��ł���B
�@�킪���ɂ�����P�i��̈���1960�N�i���a35�N�j�ɂĂ�ؐU����Ă�،������ŊJ�n����A1973�N�i���a48�N�j���{�ōŏ��̒P�i�� �u���m�z�[�v�v ���F�肳�ꂽ�B�ȗ����X�ƒP�i�킪�琬����ѓ���������p�������悤�ɂȂ����B1981�N�i���a56�N�j�ɂ͒P�i��̍�t�ʐς�90���ȏ���߁A1986�N�i���a61�N�j�ɂ͂��ׂĒP�i��ɂȂ����i�}3�j�B
(4) �i��ƍ͔|�Z�p�̊J���ɂ�鐶�Y���̌���
�@���̂悤�ɂĂ�̕i��͎���ƂƂ��ɕϑJ���A�i�W���Ă��������A�͔|�ʂł͐V�Z�p���J������傫�ȕϊv�������炵���B�k�C���ɂ�����Ă�̐�����Ԃ̓��[���b�p�̎�v�͔|�n�тɔ�ז�1�J���Z���A���ꂪ���[���b�p���̎��ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ̂ł��Ȃ���v���ł������B���̒Z��������Ԃ��������邽�߂̋Z�p�Ƃ��Ď����ڐA�͔|�@�����a30�N�㒆���ɊJ������A���̑��������������ɂƂ��Ȃ��ċ}���ɕ��y���A1986�N�ɂ͂��̕��@���Ă�؍͔|�ʐς�96�����߂�ɂ��������i�}4�j�B
�@���̂悤�ɂĂ�̕i��͎���ƂƂ��ɕϑJ���A�i�W���Ă��������A�͔|�ʂł͐V�Z�p���J������傫�ȕϊv�������炵���B�k�C���ɂ�����Ă�̐�����Ԃ̓��[���b�p�̎�v�͔|�n�тɔ�ז�1�J���Z���A���ꂪ���[���b�p���̎��ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ̂ł��Ȃ���v���ł������B���̒Z��������Ԃ��������邽�߂̋Z�p�Ƃ��Ď����ڐA�͔|�@�����a30�N�㒆���ɊJ������A���̑��������������ɂƂ��Ȃ��ċ}���ɕ��y���A1986�N�ɂ͂��̕��@���Ă�؍͔|�ʐς�96�����߂�ɂ��������i�}4�j�B
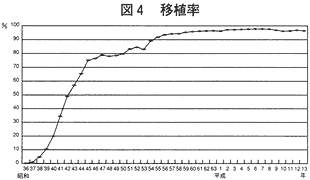 |
�@���[���b�p�̑����i��̓�������ю����ڐA�͔|�@�̊J���A���y�ɂ��ߔN�ł̓��[���b�p�𗽂��قǂ̎��ʂ������Ă��邪�A�����m�ۂ̕K�v����A�܂��Ă�̎�����d�ʂɂ���Ă������ƂȂǂɂ�葽���ɂȂ����ō��������͒Ⴍ����Ă����B
�@���Y���ꂽ�Ă�������Ƃ��Ĕ������ۂɓ������l�����铜��������x�́A�i�N�ɂ킽�肻�̓�������������Ă������A1986�N�i���a61�N�j�Ɏ��{�Ɉڂ��ꂽ�B���̏̕ω��ɂƂ��Ȃ��������i��̎��p�����]�܂ꂽ�B1982�N�i���a57�N�j�ɂ͏]���̕i��ɔ�������������k�C���_�Ǝ�����琬�� �u���m�q�J���v ���D�Ǖi��ɔF�肳��Ă������A1985�N�i���a60�N�j�ɂ͂����������ɍ��������̍����i��Ƃ��āA���h�C�c�AKWS�Ј琬�� �u���m�G�[�X�v ���F�肳�ꂽ�B�u���m�G�|�X�v �͂���ȑO�̎�͕i��ł��������Ј琬�� �u�J�[�x�|���v ���ɔ�ׁA���������������A�����d�̖ʂł��D��Ă����B
�@�ȏ�A����������x�̓����܂ŕi��̕ϑJ�ɂ��ċL�������A�����ł��̕ϑJ����ՓI�ɂ݂�Ӗ��ŁA�i����ǂ̐i�W���������ʂ��Љ�����B
�@���Â��Ȃ��Ă��܂������ʂł��邪�A���a63�N�Ɏ��{���������ŁA�\1�Ɏ�����1935�N�i���a10�N�j�ɔF�肳�ꂽ �u�{��192���v ����A����������x�J�n�O�N��1985�N�i���a60�N�j�ɔF�肳�ꂽ �u���m�G�[�X�v �܂ŁA�e����̎�v��4�i��ɂ��āA����̕W���I�ȈڐA�͔|�@�Ŏ��{�������̂ł���B
�@�\1�Ŗ��炩�Ȃ悤�ɁA�u�{��192���v �Ƃ���50�N��ɔF�肳�ꂽ �u���m�G�[�X�v �Ƃ̎��ʍ��̓w�N�^�[�����������14�g��������A�������������ʂ̍��� �u���m�G�[�X�v �̕������������B50�N���̉i���X�p���ł݂�ƕi��̐i�W�̒����͂����肷��ƂƂ��ɁA�{�����̑��֊W�ɂ��鍪�d�ƍ����������Ƃ��Ɍ��サ�Ă��邱�Ƃɂ��ẮA�i����ǂɌg����Ă����W�҂̓w�͂����̂�錋�ʂł������B
�@���Y���ꂽ�Ă�������Ƃ��Ĕ������ۂɓ������l�����铜��������x�́A�i�N�ɂ킽�肻�̓�������������Ă������A1986�N�i���a61�N�j�Ɏ��{�Ɉڂ��ꂽ�B���̏̕ω��ɂƂ��Ȃ��������i��̎��p�����]�܂ꂽ�B1982�N�i���a57�N�j�ɂ͏]���̕i��ɔ�������������k�C���_�Ǝ�����琬�� �u���m�q�J���v ���D�Ǖi��ɔF�肳��Ă������A1985�N�i���a60�N�j�ɂ͂����������ɍ��������̍����i��Ƃ��āA���h�C�c�AKWS�Ј琬�� �u���m�G�[�X�v ���F�肳�ꂽ�B�u���m�G�|�X�v �͂���ȑO�̎�͕i��ł��������Ј琬�� �u�J�[�x�|���v ���ɔ�ׁA���������������A�����d�̖ʂł��D��Ă����B
�@�ȏ�A����������x�̓����܂ŕi��̕ϑJ�ɂ��ċL�������A�����ł��̕ϑJ����ՓI�ɂ݂�Ӗ��ŁA�i����ǂ̐i�W���������ʂ��Љ�����B
�@���Â��Ȃ��Ă��܂������ʂł��邪�A���a63�N�Ɏ��{���������ŁA�\1�Ɏ�����1935�N�i���a10�N�j�ɔF�肳�ꂽ �u�{��192���v ����A����������x�J�n�O�N��1985�N�i���a60�N�j�ɔF�肳�ꂽ �u���m�G�[�X�v �܂ŁA�e����̎�v��4�i��ɂ��āA����̕W���I�ȈڐA�͔|�@�Ŏ��{�������̂ł���B
�@�\1�Ŗ��炩�Ȃ悤�ɁA�u�{��192���v �Ƃ���50�N��ɔF�肳�ꂽ �u���m�G�[�X�v �Ƃ̎��ʍ��̓w�N�^�[�����������14�g��������A�������������ʂ̍��� �u���m�G�[�X�v �̕������������B50�N���̉i���X�p���ł݂�ƕi��̐i�W�̒����͂����肷��ƂƂ��ɁA�{�����̑��֊W�ɂ��鍪�d�ƍ����������Ƃ��Ɍ��サ�Ă��邱�Ƃɂ��ẮA�i����ǂɌg����Ă����W�҂̓w�͂����̂�錋�ʂł������B
�\1 �e�N��̎�v�i�������r����
| �i�� | �F��N | ���d | �������� | ���� | |||
| t/ha | �w�� | �� | �w�� | t/ha | �w�� | ||
| �{��192�� | 1935�N�@���a10�N | 34.9 | 100 | 16.35 | 100 | 5.72 | 100 |
| ����2�� | 1954�N�@���a29�N | 37.0 | 106 | 15.97 | 98 | 5.91 | 103 |
| �J�[�x�|�� | 1964�N�@���a39�N | 44.7 | 128 | 16.57 | 101 | 7.41 | 130 |
| ���m�G�[�X | 1985�N�@���a60�N | 48.9 | 140 | 17.11 | 105 | 8.36 | 146 |
|
�Q�l���� ���������� (1953)�@�[��3�{�̂ɂ���� ���k�C�������o�ό������� (1963)�@�k�C���_�Ɣ��B�j ���k�C���_�Ǝ����� (1967)�@�k�C���_�ƋZ�p���B�j ���_�ѓ��v���� (1971)�@���_�ƋZ�p���B�j ���_�ƋZ�p���� (1984)�@�_�앨�i���� ���k�C���Ă�؋��� (1994�A2001��)�@�Ă�ؓ��ƔN�� |
| �y�[�W�̃g�b�v�� |
|
�u�����̎��_�v�@ 2002�N6���@ |
�������Ɠ��A�a �@�`������H�ׂ�͓̂��A�a���N�������������K�����H�` �@�������M�a�@ ���ȕ����@�{�� �� ���Ă�ؕi��̕ϑJ 1 �@(��) �k�C���Ă�؋��� �Z�p�����@���� ���� |