

ホーム > 砂糖 > 調査報告 > その他 > 国内産糖および甘味資源作物の産業構造分析
最終更新日:2010年3月6日
1 国内生産の地理的不均衡化
1980年代以降、北海道におけるてん菜糖の増加、南西諸島(鹿児島・沖縄)における甘しゃ糖の減少、輸入糖の減少が長期的な趨勢として観察されている(図1)。現行の枠組みでは、国内甘味資源作物と国内産糖は輸入糖・異性化糖からの調整金や国からの交付金を財源として助成されている。異性化糖はほぼ同じ水準で推移しているが、輸入糖が減ってきたために調整金の収支構造が悪化して、国内産糖に対する交付金は助成財源を大幅に上回るようになった。
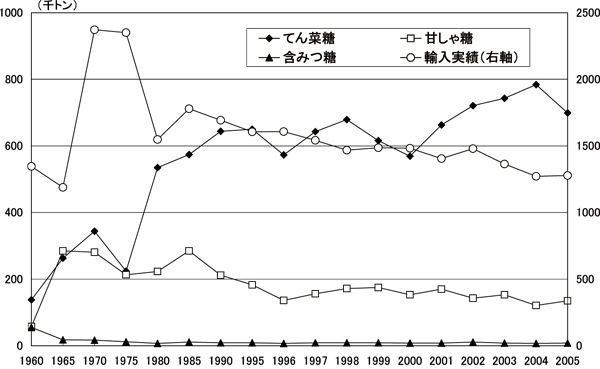 |
図1 わが国の砂糖の供給 |
コスト面から見た国内産糖の内外価格差はてん菜糖で約3倍、甘しゃ糖で約8倍といわれていて、そもそも保護と助成なしでは国内の砂糖ビジネスは成立しない。保護や助成を行う理由は後に検討するように甘味資源生産に様々な公益的機能の存在が認められているからである。ところが甘味資源作物生産が北海道で拡大し沖縄で縮小してきたということは、公益的機能の地理的なバランスが崩れたことを意味している。北海道と沖縄とは地理的に遠く離れているが、最終製品の砂糖のマーケットを通じて間接的に競争していて、この四半世紀はてん菜糖の方が競争優位になっているようである。しかしそれ以外にさとうきび生産が伸びない制度的・構造的要因にも留意しなければならない。
(1) 北海道のてん菜糖生産の成長と変動
図2は、北海道におけるてん菜糖の産糖量、てん菜の生産量・作付面積の推移について1955年を100とした指数で表している。産糖量は上下に変動しながら、例外的に1970年代には大きな落ち込みがあったものの、長期的に上昇し続けた。50年間で20倍にもなっている。80年以降についてみると、作付面積は徐々に減少しながらも安定しているから、産糖量の大きな変動は、単収とてん菜糖歩留(主に糖度)の変化によって引き起こされた。
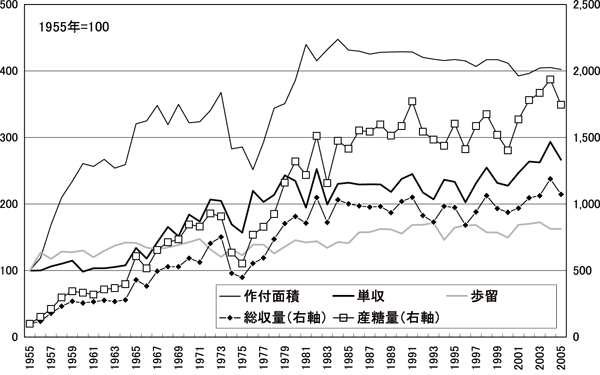 |
図2 てん菜糖生産の推移(指数) |
産糖量の伸びは、面積、単収、歩留(糖度)それぞれの伸びによって引き起こされるが、それらの貢献度はこの50年間必ずしも一貫したものではなかった。最近20年間では、作付面積はマイナスに作用しているが、単収は、80年代後半はプラス、90年代はマイナス、2000年以降は再びプラスに作用した。歩留まりは90年代後半を除いてプラスに作用している。てん菜の場合、糖度取引は1986年に開始したが、このことが糖度向上へのインセンティブとして働いたことは確かである。しかし天候に左右されるため単収も含めて結果は不安定である。なお、このことが引き起こす予測しにくい産糖量は製糖業の操業度にとって大きなリスクとなっている。
支庁別の糖度別生産量の平均と標準偏差の経年変化を観察してみると、全体的にみて糖度は地理的バラツキを小さくしながら平均を高めていることがわかる。その背景には、できるだけ糖度の高いてん菜をつくるのに適した土地を選んで利用しようとする農家の態度があるのではないかと推測される。相対的に過剰生産傾向にあり北海道として作付けは制限されているので、その限られた土地でできるだけ収入を多くするためより糖度を高めようとするはずなのである。生産調整時のこのような行動はスリッページと呼ばれる現象で、過剰生産を解消することを難しくしている。
(2) 沖縄の甘しゃ糖生産の停滞
甘しゃ糖生産は、てん菜糖と比べるならば、産糖量も作物総収量も伸びなかった。1964年に年間約29万3,000トン(分みつ糖換算)と最大量を記録したが、その後は長期的に生産量を低下させている(図3)。それは単収も歩留も向上しない一方で、作付面積は減っていったからである。
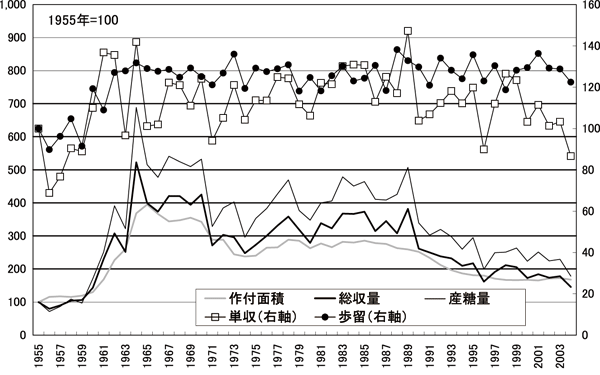 |
図3 甘しゃ糖生産の推移(指数) |
時期によって若干違いはあるもの、全体的に単収も歩留も低下傾向にあるため、産糖量を引き下げるようにマイナスに作用していた。90年代前半、例外的に単収と歩留は向上したのだが、作付面積が大幅に減少したため、産糖量は低下することになった。
甘しゃ糖の糖度取引は1994年に開始したが、糖度向上をもたらすインセンティブはてん菜糖で観察されたほど大きなものにはならなかったようである。そして単収についてはますます低下する一方である。
さとうきび栽培には、夏植、春植、株出の3体系がある。春植は栽培期間が短い分だけ収量は少ないが栽培コストが少なくてすむという利点がある。夏植は栽培期間が1年半なのでコストはかかるが収量は多い。株出は複数年栽培するものである。どの作付体系が好まれるかは島によって差がある。例えば、沖縄本島では全体の7割は株出であるが、宮古地区は9割、八重山地区は6割が夏植である。次期作のための株出作業は収穫と時期的に競合するために、労働力が不足する地域では株出を避ける傾向にある。一部の地域で単収の低い春植が伸びてきているが、現時点で沖縄全体のさとうきび生産に影響を与えるまでにはなっていない。もし春植を伸ばすのならば、より単収を高める技術を開発しなければ、生産の停滞がますます進んでしまうであろう。
2 原料生産変動がもたらす製糖業におけるリスク
さとうきびの単収、歩留は、台風と干ばつのために年によって大きく変動していて、てん菜糖と同様、甘しゃ糖においても製糖業の操業度は大きなリスクを抱えている。
1971年から2004年までに操業実績のある分みつ糖は14工場、含みつ糖は7工場であったが、一部の工場は操業度が低く、操業休止や廃止に追い込まれている。工場の稼働状況の不安定性は年間の実圧搾時間から観察できる。
分みつ糖の工場は概して平均圧搾時間が長く変動が小さいものが多く、含みつ糖の工場は平均圧搾時間が長いが変動が大きいか、もしくは平均圧搾時間が短いが変動が小さいものになっている。変動係数(標準偏差/平均)は0.25から0.3程度におさまっている。
分みつ糖は製品差別化が難しく、いかに製造コストを下げるかが経営上のポイントとなる。そのためには規模の経済を発揮させることができるかが重要であるから、できるだけ多くの原材料を安定的に確保できるかどうかが経営上最も重要となる。
小さな離島では含みつ糖製造が立地している。小さな島だとそもそもの生産量が少なく、他からの原料調達も難しいために調達に限界があって分みつ糖生産はできない。他方、含みつ糖は、黒糖として地域性・独自性を出しやすいので相対的に小規模で変動があっても耐えられる。
分みつ糖であっても含みつ糖であっても、いずれにしても原料調達は工場の経営を左右する最大の要因である。そしてそのためにはいかに良好な生産を維持するかが鍵を握る。原料を生産してもらわなければ工場は存続できないし、一方で工場がなければ生産は存続できない。このような相互依存の構図があるため、原料生産が落ち込みはじめると操業度が低下、経営状態が悪化してしまう。その結果、工場が閉鎖されると生産しても買い取ってくれるところがなく、生産を断念せざるを得なくなる。このような悪循環が懸念されるのである。
沖縄本島にあった分みつ糖工場の多くは、閉鎖されてしまった。ただ沖縄本島の工場は何カ所かあったので閉鎖しても、遠くはなるが引き受けてくれる工場は存在している。ただし多くの工場が閉鎖されたので、今後はその選択肢も非常に限られてしまう。
地域の生産を継続するにも、工場の経営内容を改善するにも、とにかくできる限りさとうきび生産を増やすことが必要である。問題は現場の生産者に、単収を上げてしかも安定させるようなインセンティブを与えることができるかどうかにかかっている。
この点、甘しゃ糖でもてん菜糖でも各工場は地元と密着した農務部を配置して農家と顔の見える関係を築き、直接営農を把握するように努力してきた。新たな制度改革にあわせてこの体制が見直されている。このことは、甘味資源作物生産から製糖までの砂糖のフードシステムのパフォーマンスに大きく影響を与えることになるに違いない。
3 糖度向上のインセンティブ
すでに指摘したように、てん菜では1986年に糖分取引、甘しゃでは1994年に品質取引として、糖度が高くなるにつれて追加的なプレミアムを与える制度がどちらの甘味資源作物にも導入されたのだが、てん菜に比べてさとうきびの生産者には収量や糖度を上昇させるインセンティブがそれほど与えられなかったようである。
1995年から2005年までの実際の糖度実績を確認してみると、気象条件に左右されやすいものではあるが、さとうきびでは平均甘しゃ糖度がおおむね基準糖度帯に収まっている。一方、てん菜は成績が悪かった1998〜2000年の3年間を除くといずれの年も基準糖度帯を超えていた。てん菜の基準糖度帯は16.8%〜17.1%、さとうきびは13.1%〜14.3%である。
品質取引価格は、基準糖度帯では一定の価格となり、その前後では糖度が上がると価格が高くなるように設定されている。
特に、さとうきびの場合、天候や土壌に影響されるので、生産者の不利を緩和すべく、基準糖度帯が広く設定されている。
しかし、そもそも高い糖度に高い価格が支払われるからといって、いくらでも糖度を引き上げるわけではない。糖度を上げた時のプレミアムが、それによる追加的なコストを上回っているならば、生産者はその糖度を上げる努力を行うことになる。したがって最適な糖度は糖度に関する限界価格(プレミアム)と限界費用が一致するレベルに決定されることになる。
基準糖度帯の区間だと、いくら糖度を引き上げても追加のプレミアムを得ることはできないので、そこでの最低糖度に貼り付いてしまうであろう。もしも基準糖度帯の設定が広すぎると、このような状態に陥りやすい。少々の技術改善の努力をしてもトラップ状態を抜け出せなくなる。
このようにさとうきびに糖度を向上させるインセンティブを与えられないでいる原因は、第一に構造改善が進まず糖度向上の技術改良が進まないことがあるが、そのことに加えて、てん菜に比べてさとうきびの基準糖度帯が広くなっていることも影響していると考えられる。
4 農場における生産性向上の選択
甘味資源生産において、どの程度の土地生産性〔単収〕を目指すかは経営戦略上の大きなポイントである。労働生産性のレベルをどうするかについてもあわせて検討しなければならない。図4で示すように既存の技術体系のもと、労働生産性と土地生産性はトレードオフの関係にある。経営規模を拡大して大型機械を導入することで労働生産性を向上させると、それまでのような十分な肥培管理ができずに土地生産性が低下することが一般的におこる(図4の点Aから点Bへ移動)。しかし土地生産性が低下して生産物の収入が減少しても、労働生産性の向上による経営費の節約がその収入減以上に進むならば利益は上昇するのである。現在、北海道で実験的に検討が進められているてん菜作の直播技術は、まさにその方向に誘導しようというものである。
ところが十勝地域や網走地域におけるてん菜生産では大型機械導入によって労働生産性を向上させながら、土地生産性〔単収〕についても上昇させている。このことは、新たな技術の進歩がなければ起こりえない。
南北大東島では、大型ハーベスターの導入が進んで著しい労働生産性の向上が見られる。一戸あたりのさとうきび平均収穫面積が、南大東島では5.49ha、北大東島では3.46haと、沖縄の中でもずば抜けた経営規模が成立しているのである。これによって大幅な労働費用の節約があれば土地生産性の低下という代償を受け入れることは合理的であろう。しかし他の離島では構造改善が進まず、必ずしも労働生産性の上昇は見られないのであるから、単収の維持はどうしても必要なはずである。ところが沖縄では必ずしも労働生産性が向上していないにもかかわらず、土地生産性が低下するという事態が発生している。その背景には従事者の高齢化や兼業化などの進行がある。
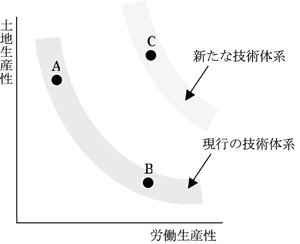 |
図4 労働生産性と土地生産性の組み合わせ |
5 甘味資源生産における多面的機能
甘味資源作物生産と製糖業は地域での唯一の産業となっている場合が多い。そのために産業の公益的機能が強く意識されることになる。
甘味資源生産に期待される最も重要な役割は地域振興である。北海道農村部や沖縄の離島では農業以外に中心となる産業を見いだすことは難しい。特に沖縄は台風の被害、水不足のためにさとうきび以外の作物の栽培も難しい。野菜作を試みる動きはあるが、離島から運搬するためにはコストも時間もかかる。生食用の場合、ますます鮮度を重視した生産・流通が指向されているということからするならば、現段階では、沖縄で特殊な作目や時期を除き野菜作の優位性を見いだすことは難しい。
原料運送費の大きさ、原料鮮度保持の必要性を考慮すると、製糖業はやはり原料生産地に近接していることが最も効率的である。現地での工場操業や原料運搬によって、数多くの直接的な雇用が地元で発生する。地域経済が最も賑やかになるのは、収穫期であることはてん菜でもさとうきびでも同様である。そして最盛期には潤沢な資金が地域経済を潤す。この時期は商店街の販売額も確実に増えている。すなわち産業連関における後方連関効果と所得を介した乗数効果(拡大産連表効果)とが甘味資源作物を栽培している地域で毎年恒例のように発生しているのである。
離島においてさとうきび生産は地域の基幹産業であるという認識は決して間違っていないが、しかし県や市町村ベースの「経済計算」で確認すると、どの地区でも最も大きい部門は、建設・土木そしてサービス業である。
そもそも産業連関の波及効果が現れるのは、産業間で相互に原材料の調達と提供を行って密接な取引関係を構築しているからである。電気機械、輸送機械(自動車)、建築は非常に多くの製造業と取引していて、波及効果が大きくなっている。ところが砂糖の場合、砂糖(粗糖)自身と、あとは商業や運輸などサービス部門との取引だけである。
ただし見逃すべきでないのは、さとうきび生産のインフラ整備のため、圃場整備や農道整備などの公共事業が行われていることであり、それがさらに地域の雇用に貢献していることである。これらの工事はさとうきびがあってこそ実施する意味がある。しかしこの連関性は、産業連関表には現れてこない。通常の産業連関表による波及効果を計算しても、この部分を捕捉することはできない。
公共事業による「インフラ部門」は、建築部門と同様に、投資活動における幅広い資材調達が経済波及効果をもたらしている。一方、インフラ部門は様々な経済部門へ役務(サービス)を提供する重要な役割をもっているのだが、公共財として対価なしで利用されているために産業連関表の中にその関係が計上されてこない。もちろん経済的金銭のやりとりはないから経済波及効果はないのは確かなのだが、この連関性は注意すべきことであろう。
地域経済の姿をコマに例えれば、さとうきび生産はコマの軸に相当する(図5参照)。もしもさとうきび生産が存続しなければ、この逆ピラミッドのように上に積み重なった産業、生活、経済活動はすべて崩れてしまう。そのさとうきびを加工する製糖業者も原料を運ぶための運送業もいずれも重要である。
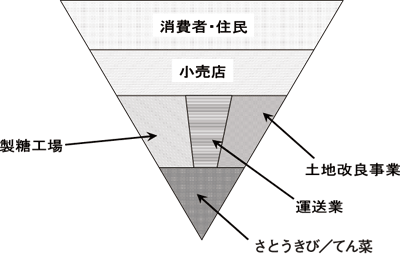 |
図5 甘味資源作物生産が地域経済に果たす役割 |
これらの経済活動は、砂糖産業に対する公的な助成なくして成立しない。前述したように、大きな内外価格差に対する支援がなければ、これらの地域活動は存続することも地元雇用することも難しくなるのである。
このような支援が社会的に認められるのは、産業としての経済活動を超えた社会的価値、いわば多面的機能を生み出しているからである。先ほどのコマの図にこの多面的機能を付け加えると図6のようになる。
 |
図6 甘味資源作物生産のもつ社会的な役割 |
多面的機能の一つは、土壌流亡を防止するいわば国土保全機能、またさとうきび生産による土地利用による農村景観の創出といった環境保全機能も期待されている。もう一つは、国境界に近いところに立地していることから、その地域に人々が住み続けてもらうことで他国からの介入や侵害を阻止する国防・安全保障機能である。前者の環境保全機能による効果は地域内にとどまる場合もあるが、後者の国防・安全保障機能は広く国民に利益をもたらしている。
甘味資源作物生産の経済活動の波及効果は、図6に示した記号で整理すると、Aの活動を行うことでBの活動がB/A倍に増幅されること、もう一つはXの活動を続けることでYの機能が結合的に生み出されることにある。
一方、てん菜は農産物本来の重要な役割をもっている。麦、大豆、ばれいしょとの輪作体系に組み込まれていて、持続的な農業を行うためにてん菜は欠かせない作目になっている。てん菜はそれらの作物との組み合わせにおいて、農作業労働を効果的に配分する上で、他の作物を補完する役割を果たしていることにも注目すべきであろう。
6 おわりに
平成19年度から需要に即した甘味資源作物生産を促進するための新しい制度が始まる。この制度は困難な2つの誘導目標に対処しなければならない。第一に市場状況に配慮した生産の誘導と効率的な農家の積極的育成、第二に外部経済効果としての多面的機能を適切に発揮させるための生産支援である。
国内産糖が輸入糖との競争の中で生き残っていけるためには、原料価格をかなりの程度引き下げなければならない。しかしそのままでは国内の甘味資源作物の生産は減少し、かなりの土地が耕作放棄されてしまう。多面的機能が失われないように生産を維持するには甘味資源作物に対する経営安定対策が必要となる。
多面的機能のため耕作放棄を防止するということからすると、甘味資源作物の代わりに別の作物を増産するならばこれらの問題も軽減される。ところが、北海道の場合、栽培できる作物は多いが、てん菜だけが他の畑作3品(麦、大豆、でん粉原料用ばれいしょ)とは栽培・収穫期間が異なっているので、必ずしもこれらの作目へ生産がシフトしていくわけではない。一方、沖縄の場合、台風や農業用水の制約を考えるとさとうきび生産しか考えられないところが多い。したがって、いずれにしても代替する有力な作物は乏しい。そうなると土地利用の粗放化は避けられないことになり、新たな食料・農業・農村基本計画の目指している自給率向上と多面的機能の発揮の面で課題が残ってしまう。
地域の土地利用を甘味資源作物に頼るということならば、単に作付けしておけばよいというわけにはいかず相当量の生産量の確保が必要となる。すでに述べたように、もし作物が減産してしまうとその地域の糖業部門の成績を悪化させてしまう。その結果、操業停止を引き起こすようなことがあれば、その結果作物の引き受け手がいなくなって生産そのものが壊滅する恐れがあるからである。
てん菜では、品目横断経営安定対策によって、生産量とは切り離された「緑ゲタ」支払いと生産量ベースの「黄ゲタ」支払いとの二段構えでの支援策が導入された。これによって「緑ゲタ」分だけ生産を抑制することになり、ある程度の過剰抑制措置が導入されたことになる。一方、さとうきびでは「黄ゲタ」支払いである収量ベースの支払いが実施されることになっている。今後は、新しい制度における経営安定対策を実施していく中で、品質取引において農家へ適切なインセンティブを与えつつ、単収を増加するような技術改良の普及も併せて実施すべきだろう。
| ページのトップへ |
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03-3583-8713
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03-3583-8713










