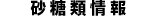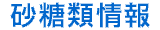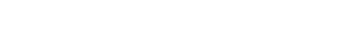
[1999年11月]
お茶と砂糖とは、日本のみならずイギリスでも密接な関係にあります。そして、イギリスにおいてお茶と砂糖を結びつけたルーツはアジア・日本にあったのです。日本においては、お茶受けの和菓子として砂糖は用いられ、イギリスにおいては、ミルクとともに砂糖を紅茶に入れる習慣として発展しました。当時、どちらの国においても大変な貴重品であった砂糖は、現在でもそれぞれの食文化にとって欠くことのできない重要な食材であり続けているのです。茶の文化などを研究し、その歴史について詳しい角山榮氏に執筆していただきました。
ヨーロッパ人、日本で茶を発見
近代の歴史はお茶の歴史であり、お茶の歴史は砂糖の歴史である。砂糖の歴史は菓子の歴史である。
私たちが日常何気なく飲んでいるお茶、いまやお茶を飲まない民族、国民はないといわれるように、世界中お茶が普及している。お茶は、元来中国・雲南省とタイ、ミャンマーの国境あたりの照葉樹林帯をルーツとするアジアの特産物である。
現在、世界で1人当たり1番良くお茶を飲むのは、アイルランド、英国、ニュージーランドである。これらの国をはじめ、ヨーロッパでは昔も今もお茶の木は育たない。それではお茶がいつヨーロッパへ入ったのかというと意外に新しい。実際、ヨーロッパ人がお茶を初めて知るのは、時期的には彼らが海のルートでアジアへやって来た16世紀中頃、イエズス会宣教師たちが中国・日本へ来た時なのである。
特に彼らがお茶を知る契機になったのは、日本で直接「茶の湯」という奇妙な茶の文化に接したからである。16世紀中頃の日本といえば、武たけ野の紹じょうおう、今井宗久、津田宗及、千利休などの茶人を輩出した堺を中心に、「茶の湯」文化が最高に華開いた時代である。狭い茶室の中で展開される宗教的・神秘的・芸術的パフォーマンス、それが彼らの心に与えた芸術的感動が、茶の文化への魅力をかき立てたのである。
こうして1609年、日本の平戸を出帆したオランダ船によって、ヨーロッパへの最初の茶がアムステルダムに到着したのである。茶の歴史上、画期的な交流・伝播の出来事であった。それ以後、お茶はオランダからイギリス、そして全ヨーロッパへと拡大して行く中で、17世紀中頃以降、お茶はイギリス人の暮らしにとって欠くことのできない国民的飲料として定着するのである。
茶に砂糖を入れる
イギリスへ入ったお茶、それが次第に上流階級から中産階級へ、さらに農民や労働者階級へと広がって行く中で、元来アジアでアジア風に飲まれていたお茶が、次第にイギリス風の入れ方、飲み方に変わって行く。
アジアと違う最大の特色の1つは、お茶に砂糖とミルクを入れる飲み方を開発したこと、もう1つは、アジアにおける緑茶に対し、紅茶が主流になって行くことである。
砂糖とミルクを入れる飲み方のうち、ミルクを入れる方法は、アジアでは蒙古のように山羊の乳を入れて飲んでいる地域もあって、決して珍しいものではないが、砂糖を入れるという方法は従来アジアの喫茶の歴史にはなかったことである。牛や羊を飼育しながら農業を営む有畜農業に依存するイギリス人にとって、ミルクをお茶に入れることは、特に取り立てて論ずる必要はない。問題は砂糖である。
それでは当時のヨーロッパ人にとって砂糖とは何であったのか。また、どうして砂糖を入れる飲み方を開発したのか。
そこでどうしても当時の世界における砂糖の状況を振り返って見ておく必要がある。
「辛さの文化」から「甘さの文化」へ
現在、世界で消費される砂糖は、大きく分けて甘しゃ(さとうきび)糖とビート糖から成る。その割合は大雑把に言って、両者ほぼ半分ずつ分け合っていると言って良い。歴史的に言えば、ビート糖の方は、19世紀初めからヨーロッパで本格的に生産され始めたものである。それ以前の砂糖は甘しゃからとったものである。したがって、お茶に砂糖を入れる飲み方を開発した時の砂糖も、当然甘しゃ糖であった。
元来、甘しゃの原産地はニューギニアと言われ、その後インドに伝わって第2次原産地となり、インドから各地に伝播したと言われる。ヨーロッパが甘しゃを知ったのは、紀元前327年にアレキサンダー大王のインド遠征によって、「甘い葦(あし)」から蜜がとれることが伝えられたのが最初である。といって、寒冷なヨーロッパでは甘しゃは育たないから、中世ヨーロッパ人は甘味料としては、主として輸入ものの砂糖か蜂蜜を用いていた。
確かに砂糖は古代から知られていたが、一般には古代・中世を通じ、砂糖への需要はごく限られたものであった。薬の一種として、あるいは金持ち階級のぜいたく品として知られていた程度である。むしろ当時は、食肉や魚の貯蔵や調味料などには、上流階級から庶民にいたるまで生活に欠かせないものといえば、砂糖ではなく塩であった。インドから輸入され、珍重されていた砂糖も、「インドの塩」と呼ばれていたのである。古代・中世はまさに「辛さの文化」の時代であった。
ところが、ヨーロッパ人の海外進出、いわゆる大航海時代の到来とともに、食文化は「辛さの文化」から「甘さの文化」へ大きく変貌をとげる。特に熱帯地域との接触でヨーロッパ人の生活を大きく変えたのは、甘しゃ栽培と砂糖の魅力にとりつかれたことである。
すなわちポルトガルは、1500年いち早く南米の一角ブラジルを獲得、ここにおいて甘しゃ栽培に乗り出した。熱帯のジャングルを開墾する苛酷な労働に耐えられなかったポルトガル人は、アフリカからの奴隷を労働力とするプランテーション方式を導入して、甘しゃ栽培の経営に当たった。ヨーロッパ人による砂糖生産のための奴隷制プランテーションの始まりである。とは言っても、砂糖の消費需要がすぐにヨーロッパに拡大したわけではない。砂糖は相変わらず高価で、薬の一種として上流階級の間で限られた需要があったにすぎない。
砂糖の需要拡大の契機になったのが、17世紀中頃から始まった相次ぐ新しい非アルコール飲料のヨーロッパへの到来である。メキシコからココア、アラビアからコーヒー、アジアからお茶の3者が、相次いでほとんど同時にヨーロッパに入ってきた。元来、良好な飲料水に恵まれないヨーロッパでは、ワインやビール、エールといったアルコール飲料の利用は盛んであったが、乏しかった非アルコール飲料の分野に、世界各地からどっと参入してきたのが3大非アルコール飲料である。
持参金・銀塊の代わりに砂糖を持ってきた女王
3大非アルコール飲料のうち、イギリスでは17世紀中頃、コーヒーがひと足先に入って来ていた。しかし、やがて遅れて来たお茶が、コーヒーにとって代わって国民的飲料として定着する。その時、お茶の普及に最も大きな影響を与えたのが、1662年、国王チャールズII世のもとへポルトガル王室から嫁いで来たキャサリン王妃である。
彼女は結婚するに際し、王家からの手土産代わりにポルトガル領であったインドのボンベイを持ってきたのは、あまりにも有名な話である。もう1つ、面白いエピソードが語られている。それはキャサリンがリスボンから軍艦に守られ、テムズ河からロンドンに輿入れした際に、持参金として大量の銀塊を持って来る約束であった。しかし、波止場まで花嫁を出迎えに来たチャールズII世は、約束の銀塊ではなく、バラスト代わりに砂糖が積まれていたのには驚いた。「約束がちがう」と言って怒り出すかと、みんなハラハラしていたら、チャールズII世の態度はたちまちニコニコ顔になって、砂糖を大いに歓迎したという。
銀塊が砂糖に化けても怒らなかった国王、ともかく砂糖は銀塊に匹敵するほど貴重品であり、王侯貴族といえども簡単に手に入らないぜいたく品であったことが分かる。ちなみに、1665年におけるイギリスの砂糖輸入量はわずかに88トンにすぎなかった。キャサリン王妃が格好よく持参金代わりに砂糖を持って来られたのは、実家がブラジル砂糖をヨーロッパに独占的に供給していたポルトガルだからできたのである。
18世紀の砂糖は20世紀の石油だった
キャサリン王妃について、もう1つ特筆すべきは、彼女がアジアとの交易から学んだアジア文化、特に喫茶の風をイギリス宮廷にもたらしたことである。お茶がまず貴族の女性たちの飲み物として嗜(たしな)まれたのは、キャサリンのひそみに倣(なら)ったものであろう。イギリスに本格的な東洋の喫茶文化を導入した功績を称え、彼女は「茶の女王」として永遠にその名を遺のこしている。
ところで、彼女が持参した砂糖は、いったいその後どうなったのか。その一部は、お茶に入れて飲んだのかもしれない。銀と同じくらい貴重な砂糖、そんな貴重なものもお茶に入れればたちまち溶けてしまう。お茶とひと口に言うが、そのお茶も中国からイギリス東インド会社の船によって運ばれて来た高価な貴重品である。お茶に砂糖を入れたのは、お茶が辛(にが)かったからだという説があるが、貴重な砂糖をそれだけの理由で入れて飲むだろうか。お茶もぜいたく、砂糖もぜいたく、2つ合わすと最高のぜいたく。これこそまさに『有閑階級の理論』の著者ベブレンの言う「見せびらかしのぜいたく」ではなかったか。
それにしても、18世紀になると、イギリスの茶の需要は増大する一方で、それとともに砂糖の消費も右肩上がりの上昇を示す。つまり、砂糖の消費の最大の要因は、お茶の補完材としての消費であった。さらに、料理とケーキへの砂糖の需要の増大も注目すべきである。18世紀初めの料理書にはアップル・プディング、カリフラワー・プディングといったプディングには、たっぷり砂糖を使った作り方が現われる一方、ビスケット、ケーキ、キャンディーも甘い物が好まれるようになる。同じ頃、砂糖を使ったジャムが出現する。こうした甘さの文化を代表するのが、フランスの宮廷で甘いお菓子作りに日々を送ったマリー・アントワネットであった。
さて、お茶と砂糖の消費が増大するにつれ、その恒久的確保が政府及び国民にとって最大の課題になった。茶の自給自足問題、中国との間の茶輸入をめぐる英中貿易摩擦の問題はさて置くとして、砂糖はあたかも20世紀の石油のような18世紀国際戦略商品として重要な地位を占めていた。
すなわち、砂糖の確保は、西インド諸島の砂糖プランテーションにおける奴隷労働力の確保にかかっていた。奴隷労働力を確保するためには、法王がスペインに認めていた奴隷貿易権(ASIENTO)を入手せねばならない。そこで、奴隷貿易権をめぐって、英仏の間にスペイン王位継承戦争(1701〜13年)が起こった。勝利を握ったのはイギリスであった。
その結果、イギリスは砂糖の支配権を掌握して、その利益が産業革命の資本に提供され、世界最初の産業革命に成功した。こうして、お茶と砂糖が近代イギリス史を作ったのである。
日本のお茶と砂糖
砂糖がお茶と密接な関係にあったことは、イギリスも日本も同じである。ただ、日本のお茶がイギリスと違うのは、日本では砂糖を直接お茶の中に入れない点である。お茶と分離された砂糖は、日本では姿を変えて和菓子という形をとる。それでは、お茶と和菓子がどのような方法で合体するのか。普通お茶を飲む前に美しく作られた和菓子を鑑賞する。そして、おもむろに甘い和菓子を口中で味わい、舌先に甘さが残っているところで、お茶を飲んでその渋みと甘さを嗜むという微妙な味わい方をする。その味わい方は、抹茶でも煎茶でも基本的には同じである。
お茶受けは東西古今さまざまな種類があるが、砂糖を素材とするものは、西洋ではケーキ、日本では総称して和菓子と言う。ひと口に和菓子と言うが、中国文化と西洋文化の交流点である日本ほど、多種多様な菓子文化が発展した国はほかにない。その中でも、近世城下町各地において、藩主の「茶の湯」とともに発展した和菓子は、砂糖を素材とした芸術作品で、日本が世界に誇る砂糖文化であり、茶の文化である。お茶を嗜むことは、形、色彩、趣向、好みを含めた総合芸術作品としての銘菓を器とともに鑑賞することから始まる。
こうして、近世「茶の湯」文化は、砂糖と和菓子の歴史を作ってきたのである。
世界一の砂糖輸入大国であった日本
日本における甘しゃ糖の歴史は、天平勝宝6(754)年、鑑眞和尚が来日に際し中国から携えてきたものの中に「蔗糖等500余斤」「甘蔗80束」と記録されているのが最初である。
その後、室町初期までは、ほとんど記録がなく、たとえあったにしても世間の注目を集めるほどのものではなかった。むしろ、当時甘味料といえば、主としてアマズラで、その他の甘味料としては蜂蜜と飴があったにすぎない。
日本で砂糖が注目され始めるのは、16世紀末から17世紀初めにかけての頃からである。当時、世界有数の金銀の産出国であった日本は、東アジア海域で最大の輸出大国であった。その豊富な銀を輸出し、中国から生糸・絹織物が輸入され、17世紀初めからは砂糖も輸入された。
どれだけ砂糖を輸入したか。鎖国体制以後、唯一の輸入窓口であった長崎のオランダ商館の砂糖販売量(日本の輸入量)は、1641〜1670年頃では約138トン(23万3,000斤)〜252トン(42万2,000斤)にのぼっている。一方、中国からは、1656年頃約1,140トン(190万斤)、両者合わせて約1,380トン(約230万斤)、その後も両国から年約1,800トン(約300万斤)輸入された。これを当時のイギリスの輸入量(1665年、88トン)と比較すると、日本の方がはるかにイギリスを上回っている。したがって、恐らく日本は当時世界一の砂糖輸入国であったのではないか。
しかも注目すべきは、経済大国だった日本はその砂糖を甚だ高価な価格で買っていたことである。ポルトガル商人がマカオで買い入れた白砂糖が、日本ではその10倍ないし20倍の値段で売れたと言われる。それほど高価でなくても、普通中国で仕入れた砂糖は、日本へ持ってくると仕入値の2倍ないし4倍の値段で売れた。このことは、ヨーロッパでは有名だったようで、モンテスキューもその著『法の精神』(1748年)の中で、日本がいかに異常な高値で砂糖を買っているかを述べている。確かに、日本は初め砂糖を高価な薬として買っていたし、その輸入に携わっていたのは大阪の薬種問屋であった。
高価な砂糖は和菓子に
それにしても大量の高価な砂糖が、単に唐物薬物として使用されたとは考えられない。やはり考えられるのはお茶との関係である。お茶と言っても庶民の飲んでいる番茶ではない。最高のぜいたくな遊芸といわれた「茶の湯」において、当時最高の奢侈(しゃし)品であった砂糖でできた和菓子がお茶受けに用いられたのである。
16世紀末、古代きっての茶人といわれた千利休の晩年、天正18(1590)年8月から翌年の正月までに行われた『利休百会(ひゃっかい)記き』において使われた菓子のリストがある。(『別冊太陽、69、利休の茶会』1990、春)。それによれば
ふ(ふのやき、その他) 72会(かい)
栗 55会
椎茸 19会
いりかや 15会
こふ 7会
やき餅、とうふ湯皮 各5会
柿、煎餅 各4会 その他
このうち、5種の菓子が出た茶会が2会、3種が22会、2種が63会(そのうち、ふのやきと栗の組み合わせが最も多かった)となっている。1番多い「ふのやき」という菓子は、小麦粉を水で練って、お好み焼き風に焼いて、焼いた片面に味噌を塗って巻いたものである。いずれにしても、これらの菓子には砂糖は使われていなかった。
ところが17世紀初めになると、イエズス会宣教師など南蛮人がもたらした金平糖、有平糖、カルメラといった砂糖をたっぷり使った菓子が登場する。そして、日本は本格的な砂糖輸入時代を迎えることになる。こうして寛永期ともなると、茶会に餡あんの入ったよもぎ餅などが出るようになる。また、その頃には餡子餅、きな粉餅など従来の塩餡から甘い餡に変わって行く。さらに地方の大名、特に茶の心得のある大名の城下では、銘菓といわれる茶菓子が多数育つことになる。
輸入から国産へ
輸入大国日本の資金源になっていたのは、日本産の豊富な銀であったが、その銀も底をつき、幕府は1668年には銀の輸出禁止に乗り出した。そして、18世紀初め徳川吉宗は生糸・絹織物・砂糖の輸入に代わって、これらを国内で自給する政策転換を打ち出した。こうして、幕府は全国各地で養蚕業を振興するとともに、関東から九州にいたる太平洋沿岸各藩では甘しゃ栽培、砂糖生産を奨励した。
日本の甘しゃ栽培がヨーロッパと違うのは、日本人は奴隷労働に頼ることなく、すべて日本人の手で成功したことである。技術的に最も難しかったのは、粗糖を白糖に精製する工程であった。1730年代から50年代にかけ、幕府は中国の技術を導入することで再三駿河、武蔵で作らせたが成功しなかった。それを最初に成功したのが元文5(1740)年オランダの技術を導入した紀州の安田長兵衛であった。(『紀伊国続風土記』)
やがて讃岐では独自の方法で三盆白(現、和三盆)という世界でも最高級の白砂糖を作ることに成功した。こうして幕末にかけ砂糖生産は讃岐、阿波、和泉をはじめ全国的に増産を達成し、安政5(1858)年には国産糖合計1万3,374トン(2,229万斤)にのぼった。
なお、砂糖輸入は引き続き行われていたが、国内需要は国内産砂糖でほぼ充たされていた。したがって、砂糖価格は下落し、高い価格で日本へ砂糖を供給していたオランダと中国は深刻な打撃を受けた。砂糖価格が下落したといっても、所得の低い庶民にとって砂糖は高級消費財であって、戦前までずっと季節の贈答品やお祝い用の品など、貴重品として扱われていたのである。