

ホーム > 砂糖 > お砂糖豆知識 > お砂糖豆知識[2009年8月]
最終更新日:2010年3月6日
|
|
|
|
|
|
[2009年8月] |
甘いものはなぜおいしい? |
| 畿央大学 健康科学部 健康栄養学科 教授 大阪大学 名誉教授(歯学博士) 山本 隆 |
1.甘味の意義
味覚は、味の質の認識とともに必ず快・不快の感情を伴います。例えば、砂糖を口にすれば、甘いという味の質の認知とともに、おいしいという快感が生じます。濃すぎるコーヒーなら苦いという味の質とともにまずいという不快感が生じます。このような快・不快の感情が飲み込むか吐き出すか、もっと欲しいかもう要らないかを決定しているのです。
表1は、5つの基本味の嗜好性と生体への信号をまとめたものです。甘味に関して言えば、低濃度から高濃度にわたり快感を呈します。そして、甘味は、エネルギーの源を摂取しているという信号だと解釈されています。体のエネルギー源となる食べ物は炭水化物であり各種の糖類です。そして、直接のエネルギー源はグルコース(ぶどう糖)で、これが血液中に入ると血糖とよばれます。エネルギー源は体が必要とするものですから、生体はこのような物質を味わったとき、おいしいという快感を生じることによって摂取を促進するのです。これは遺伝情報に組み込まれていますから、生まれてすぐの赤ちゃんの口の中に砂糖溶液を入れると、にこやかな表情とともにそれを摂取しようとします。
表1
基本味の嗜好性と代表的物質
|
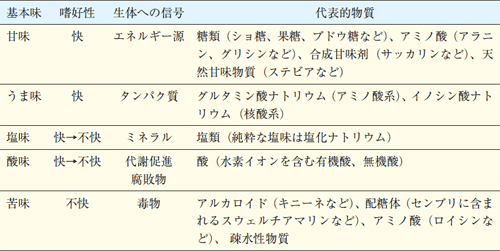 |
体内の血糖量が一定レベルを超えると、血糖すなわちグルコースは膵臓の内分泌細胞を刺激し、インスリンという血糖値を下げるホルモンを分泌し、血糖値を正常レベルに下げようとします。ノンカロリー甘味料(例えば、スクラロース)は甘いのですが、血糖値は上昇しません。さらに、最近の研究によると、インスリンを分泌する膵臓細胞はグルコース以外の甘味物質(スクラロースなど)にも反応してインスリンを分泌するということです。血糖値の下がった空腹時にノンカロリー甘味飲料を摂取するとますます低血糖状態になりますから、体にはよくないといえます。
2.甘味受容機構
図1に示すように、味覚の受容器は、口腔粘膜に存在する味蕾の中の味細胞です。水や唾液に溶解した食物成分は、イオンや分子となって味細胞表面膜に作用し、味細胞を興奮させます。その結果、味細胞に連絡している味覚神経がパルス状の電気信号を多数発生し、この神経情報が脳に送り込まれます。成人では、味蕾が豊富に存在する場所は、舌前方部の茸状乳頭、舌縁部の葉状乳頭、舌根部の有郭乳頭、軟口蓋部、咽頭喉頭部です。味細胞が、基本味を生じさせる砂糖(甘味)、食塩(塩味)、塩酸(酸味)、キニーネ(苦味)、グルタミン酸ナトリウム(うま味)を受容するしくみはそれぞれ異なります。
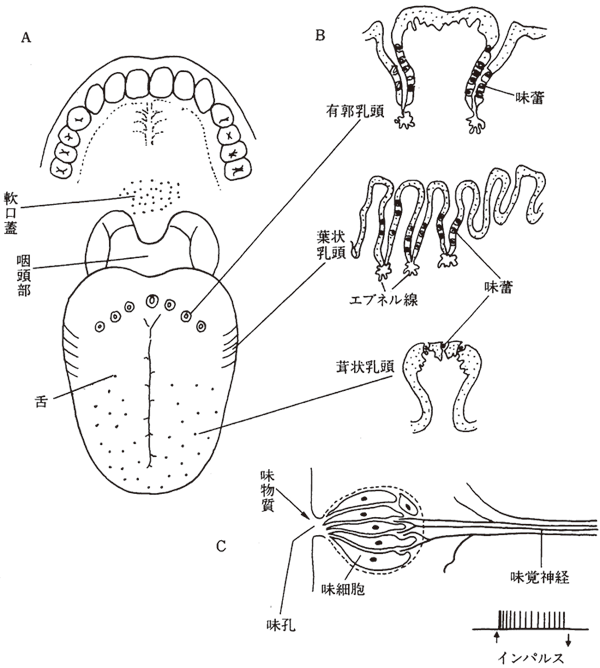 |
(山本隆:脳と味覚、共立出版、1996より)
|
図1
味蕾の分布と構造
|
甘味物質には、種々の糖、サッカリンやサイクラメート(チクロ)などの人工甘味物質、グリシンやアラニンなどのアミノ酸、フェニールアラニンとアスパラギン酸のジペプチドであるアスパルテーム、ステビアやモネリンなどの天然甘味物質など多くの種類があります。これらの物質は味細胞中の甘味受容体の異なった部分に結合することが分かっています。甘味受容体は1つの種類しかなく、そこに多様な甘味物質が結合するのです。それに対して、苦味の受容体はT2Rと呼ばれる別のタンパク質グループで、それぞれのタイプのT2Rの苦味受容体はある特定の苦味物質とのみ結合します。
同じ甘味受容体に種々の甘味物質が結合するということは、どの甘味物質も同じ味がしてもいいはずですが、異なった構造の甘味物質は微妙に異なった味の質や後味があります。甘味受容体のみならず他の受容体も同時に刺激するからかもしれませんし、さらに別の甘味受容体が存在するのかもしれません。今後の研究課題です。
甘味受容体は各動物種において必ずしも同一のものではありません。例えば、ギムネマ酸は人間やチンパンジーにだけ甘味抑制効果がみられ、アスパルテーム、タウマチン、モネリンなどのペプチド性、タンパク質性の甘味物質は、人間とマカクザルなど人間に近い一部の動物で有効です。また、ギムネマ茶から抽出されるグルマリンというポリペプチドはラットやマウスの甘味応答を選択的に抑制しますが、人間の味覚には影響を与えません。ネコの味細胞も人間の甘味受容体と同様のタンパク質を持つのですが、一部の形質に不全なところがあって甘味物質が結合できません。ネコは甘味を感じないといわれるのはそのためです。
3.甘味のおいしさ
ラットをケージに入れ、水の入ったボトルと砂糖水の入ったボトルを置き、自由に摂取できるようにすると、どのラットも、水にはほとんど見向きもせず砂糖水のみを選んで飲みます。動物にとっても甘味が大好物なのです。
赤ちゃんに対する外科処置の際に、哺乳ビンの中に砂糖水を入れて吸わせておくと、水だけを与えた場合に比べて、痛がって泣く回数が大幅に減少します。また、母親から離されると示す子供の不安行動も、砂糖水を与えておくと生じなくなります。このような甘味の作用は、ナロキソンという麻薬の阻害剤の注射で消失することから、甘い味の刺激で脳の中に麻薬類似物質が放出され、抗不安作用や鎮痛作用が生じることが示唆されます。
アヘンやモルヒネなどの麻薬には、鎮痛作用や陶酔作用のほかに、摂食を促進する作用もあります。脳内に存在する麻薬類似物質はβ―エンドルフィンです。ラットに数種類の味溶液を摂取させたあとで脳脊髄液のβ―エンドルフィン量を測定すると、ラットのもっとも好む砂糖やサッカリンを摂取したときに最大値を示しました。β―エンドルフィンは脳内麻薬ともいわれ、いったんくせになるとやみつきにさせる作用があります。ケーキなどの甘いものが大好物になって手放せなくなるのはβ―エンドルフィンの作用効果によるのです。
おいしいものなら食が進み、大好物ならたとえ満腹でも別腹と称して食べることができます。おいしさのしくみを考えるには連動する摂食促進作用を無視することはできません。β―エンドルフィンという快感物質が出されることはすでに述べましたが、その次の段階として、脳の報酬系が働き、もっと欲しいという欲求が生じます。報酬系で働く物質はドーパミンです。ドーパミンは「やる気」を起こす物質とも言われ、前向きの気持ちで、自分の欲求するものを獲得するための行動を引き起こします。
報酬系を通った情報は視床下部外側野(摂食中枢があります)に到達し、オレキシンという摂食促進物質を分泌します。この物質は、摂食を促進する物質ですが、特に、甘くて好ましい溶液をより多く摂取させる脳内物質の有力な候補です。
おいしさは消化管の活動を活発にします。甘い味付けをしたおいしいエサと苦い味付けをしたまずいエサを用意し、ラットにいずれかのエサを一定量与え、2時間後に胃内の残量を測定すると、甘い味のエサの残量が有意に少ないことがわかりました。このことは、おいしい食べ物はまずい食べ物に比べて、胃での消化速度が速いことを意味しています。おいしいものを口にした時は、視床下部外側野に味覚情報が送り込まれ、オレキシンが遊離し、覚醒作用とともに摂食行動が誘発され、消化管も活発に活動して積極的に食が進むのです。
おいしそうなものや自分の好物を見たとき食欲がわき、おなかがぐーと泣く現象にもオレキシンが関与するものと思われます。例えば、満腹でも甘くておいしいデザートが出ると、ぺろりと平らげることができますが、このいわゆる別腹現象は、オレキシンが、甘いものや大好物を見ただけで脳の中に分泌されて、胃の運動を活発にすることに関係します。
図2は、おいしさと食行動に関わる脳内物質(上記の物質以外のものも含む)の相互作用についてまとめたものです。摂食中枢の活動のあとは、満腹中枢が活動して、摂食行動は停止するはずですが、甘くておいしい味覚情報はおいしさ、欲求、摂食に関わる脳内物質をお互いに刺激しあい、満腹中枢になかなか情報が到達しません。すなわち、食べ過ぎてしまうのです。
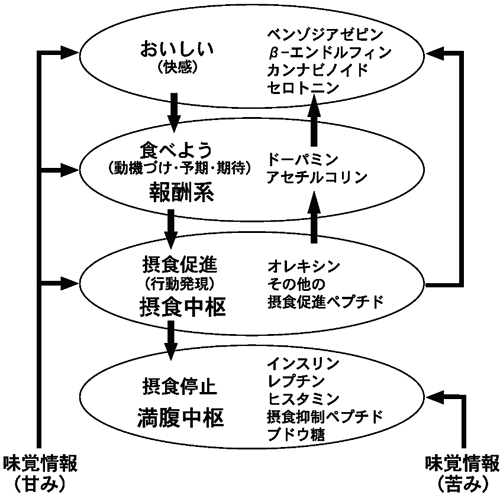 |
(山本隆:化学と生物、45:21−26、2007より)
|
図2
おいしさから食行動に至る各種脳内物
質の役割 |
4.甘味の男女差
女性は男性に比べて、ケーキやアイスクリーム、チョコレートなどの甘いものに目がないといわれますが、甘味の嗜好性に性差はあるのでしょうか? 甘いものに対する男女差として考えられるのは、男性は甘いものを食べたくても人前では堂々と食べにくいという心理的な要因、社会的な固定観念によるものかもしれません。これはジェンダー(gender)という言葉で表わされる男らしさ女らしさの概念で、社会的・文化的に形成される男女の意識や役割の差違を言います。鎌倉時代以降の日本社会では、酒は男らしさ、甘いものは女らしさという考えが定着し、酒が好きということと甘いものが好きということは対立した概念として今日まで受け入れられてきました。
このような社会的・文化的な背景とは別に、一般に女性の方が男性より味覚が鋭敏であるという報告がいくつかあります。また、動物を用いた研究では、メスのほうがオスより甘味に対する好みが強いことが示されています。しかし、味覚神経の応答には性差が認められません。味を受け取る味蕾の働きには差がないということです。おいしさのしくみに関わる物質であるモルヒネに対する感度がオスに比べてメスの方が高いことも分かりました。同じ甘味情報が脳に送られてきてもメスの方がおいしさに対する「感激度」が大きく、その結果、摂取量も多くなるのだろうと解釈できます。
結論ですが、「味の感受性や嗜好性に性差があるのか?」という最初の質問には、生物学的にはイエスと答えるのが正しいようです。性差を決めるのは脳内での性ホルモンの作用の違いです。女性ホルモンの重要な働きの1つに、皮下脂肪の蓄積があります。この脂肪のもとになる原料は食べ物から摂らなくてはなりません。効率のよい材料は糖ですから、皮下脂肪の材料を得るために、甘い糖をとらねばならず、必然的に女性は甘いものが好きにならざるを得ないのかもしれません。
5.甘味との上手なつきあい
各種の糖はエネルギー源として生きていく上で必要不可欠です。特に、保育期から学童期の子どもは育ち盛りで、活動も激しいのでエネルギー消費量も大きく、必然的に甘味物質を要求します。砂糖は、エネルギー源としてはもとより、その甘味の質と強度を考えればもっとも良質の甘味物質と言えましょう。
砂糖の摂取は体の働きに種々の悪影響を及ぼすとの指摘がなされたこともありましたが、極端な過剰摂取さえ注意すればほとんど問題はないとされています。甘味は、β―エンドルフィン、ドーパミン、オレキシンなど脳内物質の生理作用により、魅惑の快感と摂取の高進を引き起こします。つまり、甘味は魔力の側面を持っていますから、自制心がなくなると歯止めがきかず、過剰摂取による副作用が問題となります。砂糖自身は毒物でも危険物でもありません。間断なく取り過ぎることが、肥満や虫歯の誘発などに結びつくのです。
甘味のない食生活は考えられません。太るから、ダイエットのためだからといって、甘味を有する魅力的な食べ物を避けるとすれば、残念なことです。生きる楽しみを犠牲にしていると言っても過言ではありません。適度な砂糖摂取は体にとって必要なことは言うまでもありませんし、豊かなQuality of Lifeのためにも欠かすことはできません。その魔力に負かされることなく、自制心を持って甘味の魅力をエンジョイしたいものです。
| ページのトップへ |










