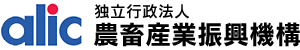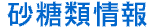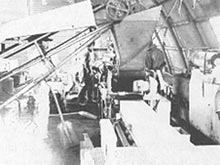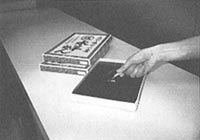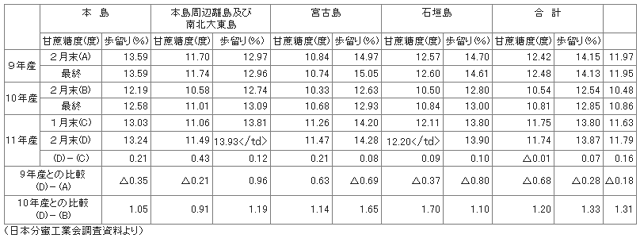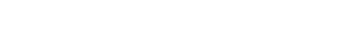
[2000年4月]
札幌事務所
○平成12年度のてん菜優良品種の認定と作付計画について
北海道種苗審議会において、平成12年度優良品種として「のぞみ」及び「HT14」の2品種が認定されたので、その特性等を紹介する。
また、北海道がとりまとめた平成12年産の品種別作付計画によると、2品種とも認定初年度から中心的品種として期待されている。
〔のぞみ〕
ドイツで育成された二倍体の単胚一代雑種で、葉長はやや短く、葉姿は直立型である。
根重は「ストーク」、「モノホマレ」より多く、根中糖分は「モノホマレ」よりやや高く「ストーク」よりやや低い。糖量は「モノホマレ」、「ストーク」より多く高糖量型で品質も良好で「ストーク」並である。
抽苔耐性は「モノホマレ」並みの強で、褐斑病抵抗性は「モノホマレ」よりやや弱く「ストーク」並の弱である。耐湿性は「ストーク」よりやや弱く「モノホマレ」並みである。
適応地帯は全道一円で、褐斑病、根腐病には弱いので適期防除に留意する必要ある。
高糖量型で農家の収益性改善に役立つ。
〔HT14〕
スウェーデンで育成された三倍体単胚一代雑種で、葉長は中、葉姿は「ユーデン」と同じやや開平型である。
根重は「モノホマレ」より多く、「ユーデン」よりやや少ない。根中糖分は「モノホマレ」よりやや高く、「ユーデン」と同等。糖量は「モノホマレ」より多く、「ユーデン」と同等である。
抽苔耐性は「モノホマレ」並みに強く、褐斑病抵抗性、根腐病抵抗性は「モノホマレ」より弱く、耐湿性は「モノホマレ」、「ユーデン」よりやや強い傾向がある。
適応地帯は全道一円で、「ユーデン」に比べて根腐病状てん菜の発生が少ないので、「ユーデン」 に代えて普及することにより、農家の収益性向上に寄与できる。
| 品種名 |
アーベント |
めぐみ |
HT14 |
サラ |
ユーデン |
のぞみ |
ハンナ |
作付割合
(前年度) |
26.7
(3.1) |
13.5
(10.6) |
11.4
(−) |
10.6
(16.8)
|
9.9
(19.7) |
7.2
(−) |
5.7
(6.5) |
| 品種名 |
フルーデン |
ストーク |
リーランド |
モリーノ |
ハミング |
メガエース |
その他 |
作付割合
(前年度) |
4.3
(4.6) |
4.3
(9.0) |
4.2
(8.7) |
1.1
(0.9)
|
−
(18.4) |
−
(0.8) |
1.1
(0.9) |
○平成12年産てん菜の生産振興計画に関する会議の開催
北海道は2月24日、平成12年産てん菜の生産振興に関する会議を開催し、甘味資源特別措置法に基づき平成12年てん菜生産振興計画に関する意見を聞いた。以下その概要を紹介する。
1. 作付面積及び生産数量に関する事項
てん菜は北海道の冷涼な気候に適した安定作物で、畑作の輪作体系を維持していく上で欠くことのできない作物であり、てん菜糖業とともに地域経済に重要な地位を占めていることから、北海道の畑作農業の持続的な振興とてん菜糖業の安定操業を図るため、7万haを基本に据えた計画的な作付けのもとに安定生産を推進する必要があるとしつつ、平成12年産については、最近の砂糖の需給動向や地域の営農条件に即した輪作の定着化等を考慮し、6万9千500haを設定、単収53.8トン、生産量3,736.7千トンを見込む。
2. 土地基盤の整備に関する事項
てん菜は深根性で酸性土壌や排水不良土壌では生育が抑制されやすく、近年、気象変動による作柄の不安定や品質の低下も見られることから、適正な輪作や栽培管理と併せて、土地基盤の整備による透排水性の改善に重点的に取り組む必要がある。このため、基盤整備事業の生産者負担の軽減対策を講じるとともに、明暗渠と併せて心土破砕や浅層排水等を計画的かつ効率的に推進する。
3. 優良種苗の生産及び普及に関する事項
てん菜の品質及び収量の安定向上を図るため、それぞれの地域に適応した優良品種の普及に努める。
4. 栽培技術の改善及び農業経営の合理化に関する事項
栽培技術の改善や農業経営の合理化を図るため、栽培技術の改善及びその普及指導に努めるとともに、農業生産総合対策事業、農畜産業振興事業団の砂糖類関係助成事業の活用や試験研究を推進する。
5. 集荷及び販売に関する事項
生産されたてん菜は、各糖業者の工場ごとの集荷区域の定められた集荷場所において受渡し、販売するものとし、集荷は10月から12月までに行う。
○平成12年産てん菜のペーパーポット播種作業開始
平成12年産てん菜のペーパーポット育苗の播種作業が開始された。
勇払郡早来町では、てん菜育苗組合によるペーパーポットの播種作業が3月12日にスタートした。当育苗組合では直播栽培を除く早来町全域約44農家、230haを対象に、平成12年度の優良品種に認定されたHT14とモリーノの2品種が播種された。
作業は、山土に肥料と有機質等を混合した床土作りや、ペーパーポットを広げ、土詰め、播種、覆土等が、農家の主婦の方や高校生のアルバイト達と共に手際良い流れ作業で行われていた。
当組合でのペーパーポットの播種作業は3月28日頃までの予定で行われ、潅水作業後1〜2週間で発芽、温度管理(10℃〜25℃を上限)、また、苗ずらし等により苗が大きくなりすぎないような管理をし、45日〜50日の育苗期間を経て、4月25日頃からゴールデンウィーク明けにかけて畑に移植される。
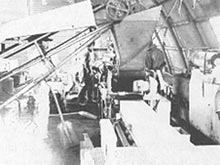
播種作業 |

育苗ハウス |
千葉出張所
○第25回国際食品・飲料展(FOODEX JAPAN 2000)における砂糖の展示について
第25回「国際食品・飲料展」(主催:日本能率協会等)が3月7日から10日までの4日間、千葉市の幕張メッセにおいて開催された。
これは食品業界が一堂に会し、各社の商品を売込む商談の場であり、国内外合わせて2,400社が参加し、砂糖業界からも精製糖5社がそれぞれの商品を出展していた。
今年の展示は、「健康志向食品」、「FOODEX ORGANIC & NATURAL FOODS」、「日本の味全国食品博」、「新商品・イチ押し製品」の4つのテーマ別にコーナーが分けられ商品の紹介が行われていたが、近年、消費者の健康・安全志向の高まりにより健康食品、オーガニック食品等が関心を集めていることから砂糖関係商品の出展状況を取材した。
精製糖各社から数多くの商品が出展されていたが、その中でも商社系精製糖企業が輸入販売しているオーガニックシュガーが関係者の注目を集めていた。
現在輸入されているオーガニックシュガーは、主にオーガニック食品の原料として使用されている。その多くは粗糖(分蜜工程を経たもので精製されていない砂糖)で、かつ、糖度が98.5度以上であるため、「砂糖の価格安定等に関する法律」の中では“特殊糖”に分類され、税関へ輸入申告する前に当事業団と売買契約することが義務付けられている。
同企業の担当者によると、今回展示されているオーガニックシュガーはフロリダの農場で契約栽培されたさとうきびを原料に現地工場で製造され、オーガニック認証機関OCIA(Organic Crop Improvement Association)の認定を得ているものであるという。現在は業務用のみの販売であり、近く家庭用として小袋も販売していきたいが、オーガニックシュガーの良さをどうやって消費者に分かってもらうことが課題だという。
消費者の健康志向、低甘味嗜好等の中で砂糖の売り上げを伸ばすために付加価値を付けた商品の開発・提供が行われているが、そもそも砂糖は、さとうきびやてん菜に含まれているショ糖を抽出・結晶化した“安全な食品”であることを、まず消費者に正しく理解してもらうことが重要なことと思われる。
○「砂糖と食文化セミナー2000」アンケートの集計結果
このアンケートは、農畜産業振興事業団が平成12年2月9日に千葉市文化センターにおいて「砂糖と食文化セミナー2000」を開催した時に、入場者を対象に実施したものです。
1. セミナーの概要
日時:平成12年2月9日
開場:12時45分
開演:13時15分〜16時
場所:千葉市文化センター 千葉市中央区中央2-5-1 定員400名
内容:ビデオ 「不思議な魅力〜砂糖〜」
講演 橋本 仁氏(株式会社横浜国際バイオ研究所代表取締役社長)
「砂糖への疑惑」
藤野真紀子氏(料理研究家)
「海外最新お菓子事情」〜N.Y.のお菓子とParisのお菓子〜
2. アンケート人数及び対象
事業団確認入場者数377人にアンケートをお願いし、363名分を回収(96.2%)した。
3. アンケート集計結果
(1)性別及び年齢
| 年齢 |
男性
(名) |
女性
(名) |
計
(名) |
構成比
(%) |
回収数363に対する割合 |
| 男性(%) |
女性(%) |
| 10歳代 |
1 |
1 |
2 |
0.6 |
0.3 |
0.3 |
| 20歳代 |
3 |
27 |
30 |
8.3 |
0.8 |
7.4 |
| 30歳代 |
4 |
37 |
41 |
11.3 |
1.1 |
10.2 |
| 40歳代 |
5 |
53 |
58 |
16.0 |
1.4 |
14.6 |
| 50歳代 |
12 |
98 |
110 |
30.3 |
3.3 |
27.0 |
| 60歳代以上 |
40 |
82 |
122 |
33.6 |
11.0 |
22.6 |
| 合計 |
65 |
298 |
363 |
100.0 |
17.9 |
82.1 |
|
参加者のうち80%以上が女性で、 中でも40代以上の主婦が全体の半数以上を占めていた。
 |
(2)職業
| |
男性
(名) |
女性
(名) |
計
(名) |
構成比
(%) |
回収数363に対する割合 |
| 男性(%) |
女性(%) |
| 会社員 |
24 |
28 |
52 |
14.3 |
6.6 |
7.7 |
| 主婦 |
1 |
233 |
234 |
64.5 |
0.3 |
64.2 |
| 学生 |
1 |
7 |
8 |
2.2 |
0.3 |
1.9 |
| その他 |
39 |
30 |
69 |
19.0 |
10.7 |
8.3 |
| 合計 |
65 |
298 |
363 |
100.0 |
17.9 |
82.1 |
|
(3)砂糖のどのようなことに一番関心がありますか
| |
男性
(名) |
女性
(名) |
計
(名) |
構成比
(%) |
回収数363に対する割合 |
| 男性(%) |
女性(%) |
| 健康 |
48 |
223 |
271 |
74.5 |
13.2 |
61.3 |
| 料理 |
8 |
46 |
54 |
14.8 |
2.2 |
12.6 |
| 性質 |
5 |
25 |
30 |
8.2 |
1.4 |
6.9 |
| 価格 |
4 |
2 |
6 |
1.6 |
1.1 |
0.5 |
| 無回答 |
0 |
3 |
3 |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
| 合計 |
65 |
299 |
364 |
100.0 |
17.9 |
82.1 |
注:2つ以上○を付けた人がいたため合計欄と回収数とは一致しない
性別・年代を問わず「健康」に対する関心が最も高く、全体の7割以上を占めていた。
(4)コーヒー・紅茶に砂糖を入れますか
| 年齢 |
男性
(名) |
女性
(名) |
合計
(名) |
構成比
(%) |
回収数363に対する割合 |
| 男性(%) |
女性(%) |
| いつも入れる |
31 |
72 |
103 |
28.4 |
8.5 |
19.8 |
| 時々入れる |
16 |
108 |
124 |
34.2 |
4.4 |
29.8 |
| 入れない |
17 |
115 |
132 |
36.4 |
4.7 |
31.7 |
| 無回答 |
1 |
3 |
4 |
1.1 |
0.3 |
0.8 |
| 合計 |
65 |
298 |
363 |
100.0 |
17.9 |
82.18 |
| 構成比(%) |
72.3 |
60.4 |
62.5 |
砂糖入れる人(男:47、女180) |
| 26.2 |
38.6 |
36.4 |
砂糖入れない人(男:17、女:115) |
|
 |
「いつも入れる、 時々入れる」と答えた人が男性で72%、女性で60%以上占めており、入れる量は「スプーン1杯」と答えた人が58%と最も多かった。
(5)(入れると言った人に)どのくらい砂糖を入れますか
| 年齢 |
男性(名) |
女性(名) |
合計(名) |
構成比
(%) |
回収数363に対する割合 |
| 男性(%) |
女性(%) |
| 2杯分以上 |
4 |
10 |
14 |
6.2 |
1.8 |
4.4 |
| 1.5杯 |
7 |
16 |
23 |
10.1 |
3.1 |
7.0 |
| 1杯 |
29 |
104 |
133 |
58.6 |
12.8 |
45.8 |
| 0.5杯 |
7 |
44 |
51 |
22.5 |
3.1 |
19.4 |
| 無回答 |
0 |
6 |
6 |
2.6 |
0.0 |
2.6 |
| 合計 |
47 |
180 |
227 |
100.0 |
20.7 |
79.3 |
|
(6)よく召し上がるお菓子は何ですか(複数回答)
| |
男性(人) |
女性(人) |
合計(人) |
| 10〜20歳代 |
30〜40歳代 |
50歳代以上 |
10〜20歳代 |
30〜40歳代 |
50歳代以上 |
| ケーキ類 |
2 |
1 |
13 |
12 |
40 |
51 |
119 |
| 和菓子類 |
1 |
2 |
32 |
5 |
39 |
133 |
212 |
| チョコレート類 |
0 |
2 |
7 |
15 |
32 |
39 |
95 |
| スナック類 |
1 |
6 |
6 |
7 |
17 |
26 |
63 |
| 無回答 |
4 |
20 |
24 |
| 合計 |
77 |
436 |
513 |
6割近い人が「和菓子類」と答え、男女ともに年齢層が高くなるほどその割合が高くなっている。次いでケーキ類、チョコレート類の順となっている。
(7)砂糖以外の甘味料でご存知のものは何ですか(複数回答)
| |
男性
(名) |
女性
(名) |
計
(名) |
構成比
(%) |
回収数363に対する割合 |
| 男性(%) |
女性(%) |
| サッカリン |
61 |
248 |
309 |
85.1 |
16.8 |
68.3 |
| アスバルテーム |
27 |
61 |
88 |
24.2 |
7.4 |
16.8 |
| マンニトール |
8 |
12 |
20 |
5.5 |
2.2 |
3.3 |
| マルチトール |
17 |
33 |
50 |
13.8 |
4.7 |
9.1 |
| ソルビトール |
26 |
101 |
127 |
35.0 |
7.2 |
27.8 |
| パラチノース |
23 |
95 |
118 |
32.5 |
6.3 |
26.2 |
| ステビア |
36 |
146 |
182 |
50.1 |
9.9 |
40.2 |
| エリスリトール |
16 |
28 |
44 |
12.1 |
4.4 |
7.7 |
| キシリトール |
38 |
157 |
195 |
53.7 |
10.5 |
43.3 |
| フラクトオリゴ糖 |
46 |
202 |
248 |
68.3 |
12.7 |
55.6 |
| 知らない又は無回答 |
0 |
5 |
5 |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
| 合計答 |
298 |
1,088 |
1,386 |
− |
− |
− |
サッカリンを8割以上、フラクトオリゴ糖をおよそ7割、キシリトール、ステビアを5割以上の人が知っていると答えている。また、最近流行のニアウォーターの影響もあるのかソルビトール、エリスリトール、マルチトールといった糖アルコールの甘味料もかなり浸透しているようだ。
(8)砂糖のイメージ(自由記入)
| |
男性
(人) |
女性
(人) |
合計
(人) |
| 料理に必要不可欠なもの |
6 |
43 |
49 |
| カロリーが高く太る、摂りすぎると体に悪い(虫歯、糖尿病等) |
17 |
143 |
160 |
| 疲れた時のエネルギー補給源。自然と体が欲するもの |
9 |
43 |
52 |
| 甘い、おいしい食品・甘味料 |
15 |
42 |
57 |
| 豊かさ・幸せ・ほっとする |
2 |
21 |
23 |
| 美しい・白い・自然 |
4 |
1 |
5 |
| 食品の保存に役立つ |
1 |
4 |
5 |
| 適度に摂れば健康に良い |
1 |
0 |
1 |
| 貴重なものである |
1 |
2 |
3 |
| 価格が安い食品 |
2 |
2 |
4 |
| 脳の栄養素(活性化) |
4 |
10 |
14 |
| なるべく摂らない方がよいもの(有害説により不信感を抱く) |
1 |
9 |
10 |
| 合計 |
63 |
320 |
383 |
「カロリーが高く太る」、「摂りすぎると体に悪い(虫歯、 糖尿病等)」、「なるべく摂らない方がよいもの」といったマイナスイメージを、「料理に不可欠なもの」、「エネルギー補給源」、「豊かさ・幸せ・ほっとする」等といったプラスのイメージが上回った。中でも 「脳の栄養素(活性化)」と答えた人も14名いるなど、砂糖啓蒙普及活動が徐々に浸透していることがうかがえる。
(9)本セミナーについて
アンケート結果をみると大半は「砂糖」の必要性は理解しているものの、依然として悪いイメージを抱いている人も少なくない。特に、健康面でのマイナスイメージが強く、生活習慣病への影響を心配する声が多かった。
しかし、ビデオ、講演の感想では、「砂糖に対する間違った考えをしていた」、「砂糖に対するイメージが変わった」、「砂糖と糖尿病の考えが再認識され勉強になった」等々の意見が多くあり、セミナーの前と後では確実に参加者の認識が変わっていることが分かる。ただ、一方で 「砂糖の長所ばかりを強調しすぎる」、「砂糖の効用は解ったが、摂りすぎは悪いと思うので、もっと中立な情報も伝達してほしい」、「砂糖に対する誤解を解きたい趣旨は理解できるが、消費量が減っていることの対策に思えなくも無い」といった厳しい意見もあり、今後のセミナーの課題となる点も指摘された。
名古屋事務所
○寒い冬に暖かい部屋で食べる水羊羹
福井を代表する菓子の一つとして求肥注)1(ぎゅうひ)でできた羽二重餅が良く知られているが、珍しいものとして寒い冬の季節に暖かい部屋で食べる水羊羹がある。水羊羹は、普通、暑い夏に一服の涼を求めて食べられる涼菓とか冷菓と思われているが、福井では夏とはまるで反対の寒い冬に食べる習慣があり、家族が集まる正月には欠かせない菓子となっている。この水羊羹は、福井県菓子工業組合に加盟する半数以上(約200軒)の菓子店で11月から3月までの期間限定の菓子として作られ、販売されている。
この時期、菓子店だけでなくスーパーや駅の売場には厚さ2cmほどの四角の紙箱(内側に防水加工がされ、水羊羹が流し込まれている。)が高く重ねて並べられ、買い物客や旅行者の目を引いている。最近では、県内のコンビニエンスストアにも1人用のサイズで置かれているという。不思議なことに冬だけの水羊羹は和菓子の盛んな隣の石川県など近県では見られず、福井県独特のものとなっている。最近は福井県出身者や東京などの都会のファンからの注文が多く、県外への発送が増加しているという。
材料は、主に小豆(こし餡)が1に対し砂糖が2の割合で使用され、これに寒天と水が加わる。使われる砂糖は黒砂糖とざらめなどで、福井の水羊羹は黒砂糖のこくのある風味がキーポイントとなっており、冬に食べてもおいしい理由はここにあるといわれている。黒砂糖をどの位加えるかは200を数える店ごとに異なり、各店によって味が微妙に違うといわれている。加えて福井の良質の水の存在もおいしさを支えている。ピーク時には1日に3トンの砂糖を使用する菓子店もあり、冬季限定ということからこの時期に大量の砂糖が水羊羹向けに使われている。
寒い冬に水羊羹を食べる珍しさと寒いからこそ日持ちが良く微妙な味と自然食品だというこだわりを持てることは逆転の発想に通じると思われ、また、そのことが福井だけに見られるということに興味を覚える。
大正時代にはもう食べられていたという冬の水羊羹の起こりについてはこれといった明確な文献等の記述はないというが、なかには「丁稚羊羹」注)2の流れを汲むものという説もあるそうである。
残念ながら今シーズンの販売は終わっているので、今年の冬が始まる11月の頃にこの福井の水羊羹を一度味わってみてはいかがでしょうか。
なお、今回の取材に際して次の方々に協力いただいた。
福井県菓子工業組合 理事長 前田 勇氏
(有)えがわ 代表取締役 江川正典氏
福井県米穀株式会社 取締役社長 加藤武敏氏
注)1 こねた白玉粉を蒸し、水あめ・砂糖を加えて練り、薄いもちのようにした菓子
注)2 里帰りに主人が羊羹を奉公人持たせたということからこのような名前がついたといわれている。
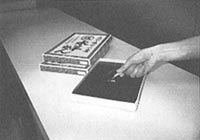
(1)福井の冬の水羊羹 |

(3)流し込み作業中の工場内
((有)えがわ) |

(2)砂糖、こし餡、寒天などを煮る蒸気釜
(1釜で500箱分の水羊羹ができ、
100kgの砂糖を使う。) |
福岡事務所
○さとうきび種苗供給安定化対策事業現地検討会
2月18日、徳之島において「平成11事業年度さとうきび種苗供給安定化対策事業」(事業実施団体:社団法人鹿児島県糖業振興協会)の現地検討会が開催された。
本事業は、メリクローン技術を使った苗の本格的な普及に向けて、低コスト生産技術、大量生産技術、種苗栽培技術などの開発や技術の確立を目指すため試験研究や現地検証を行い、生産性の向上、安定生産を図ることを目的としており、平成9年度から本団の助成対象事業として実施しているものである。
メリクローン苗は、(1)分けつ力が旺盛で慣行苗に比べて多くの二芽苗が採苗できる (2)農家にとっても採苗ほ場面積が小さくて済む(3)健全な種苗が得られる (3)短期間に大量生産できるなどのメリットがある。
検討会では、本年度事業の総括的な取りまとめを行うため同協会が事業委託している鹿児島県農業試験場徳之島支場、南西糖業(株)、沖永良部農業開発組合から試験の内容、成果、問題点等について報告された。
報告では、生長点から苗の培養→メリクローン苗の増殖→メリクローン苗から二芽苗の生産(メリクローン二芽苗)という生産工程を経るが、より良いメリクローン二芽苗を得るには、生長点の摘出部位(頂芽、側枝、芽子)は、頂芽から摘出したものが一番生育が旺盛で原料としても安定的かつ多くの収量が得られること。また、効率的な貯蔵方法(貯蔵形態(苗か二芽苗か)と貯蔵スペースとの関係)や株出し後の生育状況(検定)が未知数など多少の問題が報告された。
メリクローン苗、メリクローン二芽苗の一般農家への普及については、概ね目途が立ち、今後が期待されている。
○さとうきび収穫機械の稼動状況 (その1)
福岡事務所では、これまで鹿児島県南西諸島(屋久島は除く)における作物別生産状況及びさとうきび栽培規模別農家戸数を紹介してきた。
作物別生産状況では、同地域のさとうきびの生産高がほかの作物の生産高を大きく引き離しており、さとうきび栽培が島にとって農業だけでなく、原料糖の生産などをとおして島の経済に大きく寄与していることを紹介した。また、さとうきび栽培規模別農家戸数では、農家戸数が毎年減少していく中で、農家のさとうきび栽培規模が徐々にではあるが拡大してきていることを明らかにした。
次に、鹿児島県南西諸島(屋久島は除く)のさとうきび栽培農家戸数は、平成元年産には15,871戸あったものが平成10年産には11,124戸と、この10年間で30%近く減少している。農家がさとうきび栽培から離反していく要因として担い手農家の減少や高齢化などが挙げられているが、もう1つの要因として、さとうきび栽培での収穫作業の過大な労力が挙げられている。一般的にさとうきび収穫作業では栽培作業全体の50〜60%の労力を費やすために、さとうきび栽培を維持、拡大していくためには、収穫作業の機械化、省力化が欠くことのできないものとなっている。
平成10年産における刈り取り作業は、収穫面積に対して人力が約67%、機械が約33%となっており、脱葉作業は収穫面積に対して人力が約47%、機械が約53%となっている。
表は鹿児島県農政部農産課のまとめた平成3年産以降の鹿児島県南西諸島のさとうきび収穫作業における機械の稼動状況である。平成7、8年頃までは、脱葉機、搬出機などが収穫作業の主だった機械であったが、平成6年産頃からハーベスターが、その利便性と改良が加えられたことから、かなりの割合で伸びてきており、ハーベスターでの作業がさとうきび栽培農家や農業生産法人に定着しつつあることを示している。また、平成12年度においても前年度に引き続きハーベスターの導入が予定されていることから同地域での稼動台数は更に増加し、さとうきびの植付けから収穫までの機械化一貫体系が着実に確立されてくるものと思われる。
表 さとうきび収穫機械の稼動状況
| 単位:台 |
| 年産 |
ハーベスタ |
刈取機 |
脱葉機 |
脱葉搬出機 |
搬出機 |
運搬車 |
| 平成3 |
8 |
49 |
1,136
|
89 |
726 |
− |
| 4 |
19 |
45 |
1,193
|
102 |
968 |
− |
| 5 |
36 |
38 |
1,258
|
111 |
1,071 |
− |
| 6 |
58 |
36 |
1,284
|
171 |
1,068 |
139 |
| 7 |
94 |
33 |
1,275
|
183 |
1,078 |
139 |
| 8 |
130 |
25 |
1,211
|
137 |
657 |
140 |
| 9 |
153 |
21 |
1,225
|
169 |
449 |
117 |
| 10 |
152 |
6 |
1,177
|
98 |
614 |
167 |
|
| 出典:鹿児島県農政部農産課発行 「さとうきび及び甘しゃ糖生産実績」 より |
那覇事務所
○平成11年産沖縄県産甘しゃ糖の製糖歩留り(平成12年2月末現在)
前月号で既報のとおり、11年産沖縄県甘しゃ糖の平成12年1月末時点における製糖歩留りは、平成6年産から10年産までの過去5年最終実績の平均値11.59%を0.04ポイント上回る11.63%と好調な成績でのスタートとなったが、同年2月末の製糖歩留りは、1月末を0.16ポイント上回る11.79%と、ここにきて歩留りの上昇度合いがやや緩慢な状況になっている。
沖縄県では、2月に入って過去にもあまり例をみない長雨が続いており、2月1日から3月13日までの42日間で那覇で降雨のなかった日は2日だけで、地域によっては2月の降水量は平年の2倍以上、日照時間は平年の3分の1程度となっている。この時期におけるさとうきびの糖分上昇の気象条件は、少雨で日照時間が多いことが好条件とされているが、この極端な多雨と日照不足が糖分の上昇に悪影響を及ぼしているものと考えられている。
そのほとんどのさとうきびの収穫を大型ハーベスタによっている南北大東島は、ほ場がぬかるんでハーベスタが入れずに収穫作業が行えない日が多いため、原料不足で工場の操業が中断するなど、製糖にも悪影響がではじめている。ハーベスタ刈りの比率が高い石垣島も同様の状況となっている。
さとうきびは4月の中下旬に入ると、茎から側芽が出て、それに養分を吸収されて糖分が低下し、精製歩留りも低下することから、1日も早く天候が回復して糖分が上昇し、製糖が順調に進むことが期待されている。
平成11年産2月末現在の製糖歩留り等
○平成11年事業年度製糖歩留り・品質向上技術開発に関する検討会(第2回)の開催
3月7日に那覇市の自治会館において日本食品分析センター主催の平成11年事業年度製糖歩留り・品質向上技術開発に関する検討会(第2回)が開催され、沖縄県、鹿児島県、製糖業者、糖業関係団体及び有識者等の関係者多数が出席した。
これは同センターが実施している「平成11年事業年度甘しゃ糖低コスト製造技術開発事業」の一環として開催されたものであり、さとうきび収穫後における転化酵素の経時変化の分析を行うとともに、甘しゃ糖製造工程における歩留り低下及び品質劣化の要因と考えられる非糖成分の分析等を行うことにより甘しゃ糖の製造コストの低減を図ることを目的としている。今回は以下の調査研究等に対して中間的な報告がなされた。報告の内容は概ね次のとおりである。
1.さとうきび収穫後の搾汁液成分変化の調査
冷蔵状態で輸送されたさとうきびを恒温機(15℃と30℃)で保存し、保存開始日から0、1、3、6日後に搾汁し、それぞれの搾汁液について糖組成(蔗糖、ぶどう糖、果糖)、デンプン、デキストラン、酢酸や乳酸等の酸、細菌やカビ等の変化の状態を調査した。
・糖組成は時間の経過とともに蔗糖が減少し、ぶどう糖及び果糖が増加した。恒温の条件が15℃に比較して30℃の方がこの傾向が顕著であった。
・デンプンは恒温条件にかかわらず1日経過後は増加したが、6日後は減少し保存開始日と同程度の量になった。デキストランは、15℃のものが、3日後、6日後と時間の経過とともに増加した。
・酸の量は、大きな変化が見られなかった。
・細菌等の中には、1日経過後に大きく増加するものがあった。
2.廃糖蜜の成分調査
結晶化阻害物質を検索する目的で、廃糖蜜に多く含まれる多糖類を分析した結果、その構成糖としてぶどう糖、アラビノース、ガラクトースが多く検出された。
3.多糖類の検索
(1)微生物が生成する多糖類の調査
さとうきび等から分離された粘性物質生産能力を持つ微生物を培養して、得られた粘性物質の成分検索を行ったところ、微生物が生成した多糖類の平均分子量は、廃糖蜜中に含まれる多糖類の平均分子量よりも極めて大きな値を示した。
(2)製造工程中の多糖類の動態調査
・混合汁、シラップ及び工程に混在するスライム(不溶性物質)中に含まれる多糖類の成分検索を行ったところ、混合汁にはデキストラン、デンプンの順に、またシロップにはデンプン、デキストランの順に濃度が高く検索された。
・スライムにもデキストラン、デンプンが検索されたが、その構成糖はぶどう糖が最も多く、次いでキシロース、マンノース、ガラクトース、アラビノース等が検出された。
4.混合汁の清澄化に関する検討(非糖分の除去)
実験室で調製した搾汁液を用い、石灰処理を行う際に多糖類等の除去に有効と考えられる物質(清澄剤)を石灰に加えて処理し、多糖類等の沈殿効果について調査を行った。
・調査データ等については検討中である。
5.酵素処理に関する検討
アミラーゼ、デキストラナーゼ、ペクチナーゼ等の酵素を用いて搾汁液、シラップ及び2番糖蜜の粘性に関して調査を行った。
・これらの酵素(とりわけデキストラナーゼ)は、2番糖蜜の粘度の低下に有用と考えられる。

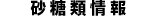
「地域だより」インデックスへ

砂糖のトップへ|ALICのページへ|