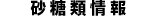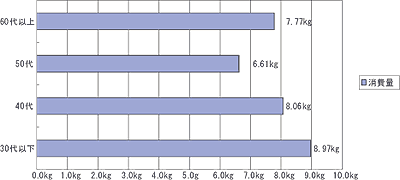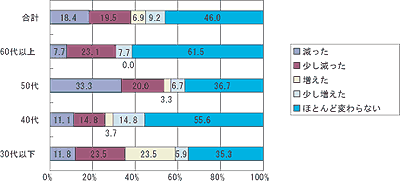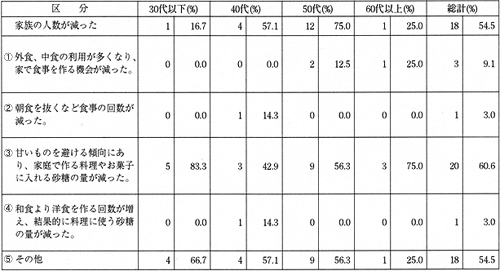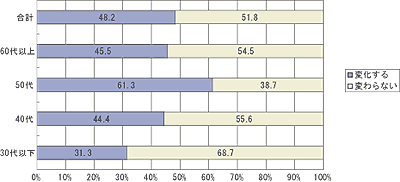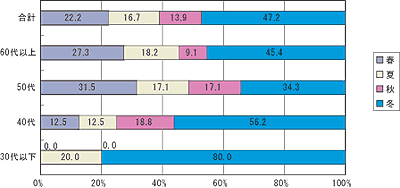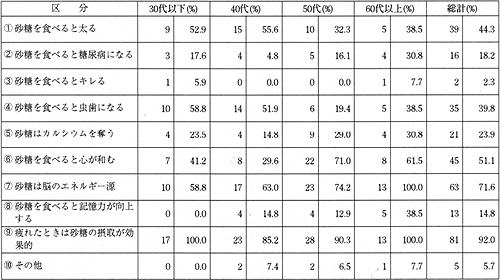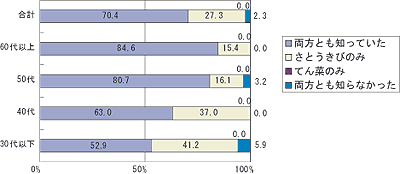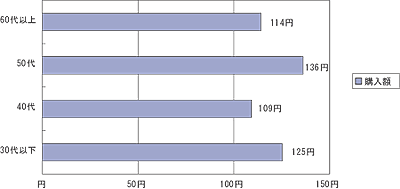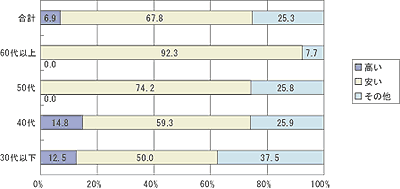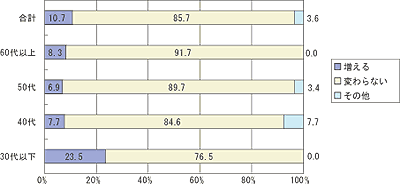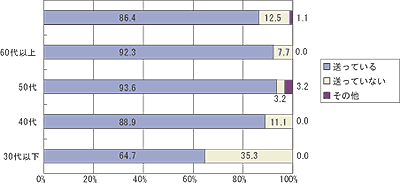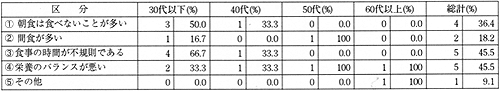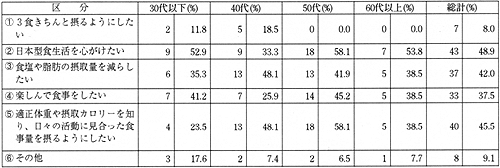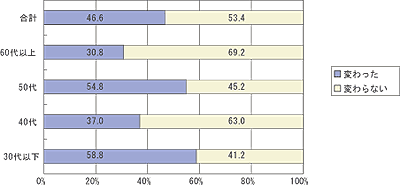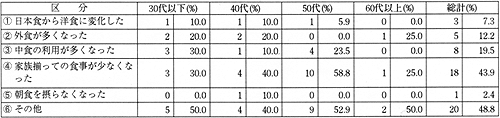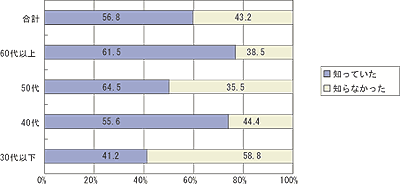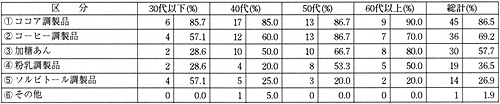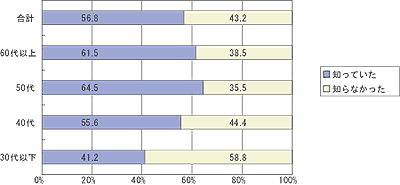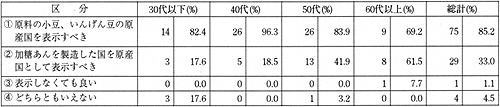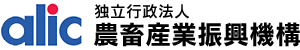[2004年1月]
機構の各事務所に設置されています15年度地域情報モニターへのアンケートを実施しました。その集計結果について紹介します。
1.はじめに
地域情報モニターは、各地域において消費者に提供されている砂糖に関連する情報を把握するとともに、消費者の砂糖の購入状況及び砂糖に関する消費者の意識等を把握するため、平成13年度より各事務所に設置しており、今年度においては88名の方々にご協力いただいております。具体的調査内容は、(1) 意識調査、(2) 購入量及び購入価格調査、(3) 砂糖関連情報調査、(4) 砂糖類に関するパンフレット等の評価把握調査等をお願いしています。
| モニターの構成 |
|
(1) 年齢
| 年齢 |
人数 |
構成比 |
| 30代以下 |
17 |
19.3% |
| 40代 |
27 |
30.7% |
| 50代 |
31 |
35.2% |
| 60代以上 |
13 |
14.8% |
| 合 計 |
88 |
100.0% |
|
(2) 家族
| 家族構成 |
人数 |
構成比 |
| 1人 |
4 |
4.6% |
| 2人 |
19 |
21.6% |
| 3人 |
23 |
26.1% |
| 4人 |
25 |
28.4% |
| 5人 |
14 |
15.9% |
| 6人 |
3 |
3.4% |
| 合 計 |
88 |
100.0% |
|
(3) 職業
| 職業 |
人数 |
構成比 |
| 主婦(無職) |
63 |
71.6% |
| 会社員 |
15 |
17.0% |
| その他 |
10 |
11.4% |
| 合 計 |
88 |
100.0% |
|
2.調査結果と考察
【砂糖の消費量】
| 問1 |
現在、あなたの家庭での砂糖の年間消費量は年間どのくらいですか? |
| 平均1家族 7.68kg … |
30kgを超えているのは3家族でみんな30代以下であり、最高は35kgという家庭もあった。 |
| 年代別に見てみると、50代の人が最も少なく、家族が減ったことによるものである。 |
|
| 問2 |
5年前と比較してあなたの家庭における砂糖の消費量は変化しましたか? |
| どの年代もほとんど変わらないという回答が一番多く全体の46%であった。「減った」又は「少し減った」という回答は38%であり、「増えた」又は「少し増えた」は16%となった。 |
| 問3 |
問2で「減った」又は「少し減った」と答えた方にお聞きします。
それはなぜですか?(複数回答) |
| 家族数の減少や家庭で作る料理やお菓子に入れる砂糖の量が減ったという回答が多くみられた。その他の意見として、肥満、成人病を避けるためとか糖尿病患者が近親にいることを挙げていた。 |
| 問4 |
問2で「増えた」又は「少し増えた」と答えた方にお聞きします。
それはなぜですか? |
| 「家族が増えたり成長したためお菓子を作るようになった」という意見がほとんどだが、「モニターになって砂糖の誤解が減り、砂糖に対する意識が変化し砂糖を使うようになった」といったモニター員もいた。 |
| 問5 |
あなたの家庭における砂糖消費量は季節によって変化しますか? |
| 若い世代ほど変化はないようである。 |
| 問6 |
問5で「変化する」と答えた方にお聞きします。砂糖の消費量が増える時期はいつですか? また、増える要因となる料理等は何ですか? |
| 30代では、圧倒的に冬場に砂糖を消費するが、これはおせち料理やすき焼きなどに多く使われている。また、50代、60代は梅酒作りのため春に多く使うようだ。 |
【砂糖に対するイメージ】
| 問7 |
あなたは、砂糖に対してどのようなイメージを持っていますか?(複数回答) |
| 「疲れたときは砂糖の摂取が効果的」や「砂糖は脳のエネルギー源」といった項目は、各年代とも認識されており、特に60代以上の人は両方とも100%理解していた。しかし、「砂糖を食べると太る」と思っている人は44%もおり、砂糖についての正しい知識が浸透していないことがわかる。 |
| 問8 |
あなたは、砂糖がさとうきびやてん菜から作られていることをご存知でしたか? |
| 年齢が上がるにつれて「両方とも知っていた」人の割合が増えている。去年には見られなかったことだが今年は「両方とも知らなかった」人が数人いた。 |
【砂糖価格】
| 問9 |
現在、あなたは砂糖をいくら位で購入していますか? |
| 平均1家族 122円/kg …あまり特徴は見られないが、50代の人は高くても購入している。 |
| 問10 |
あなたは現在の砂糖価格についてどのように思いますか? |
| 約7割の人が安いと思っている。その他の3割弱の人の中には、「特に何とも思わない」、「値段にばらつきがありすぎる」などの意見があった。 |
| 問11 |
砂糖の価格が下がればあなたの家庭での砂糖消費量が増えると思いますか? |
| ほとんどの人が砂糖の価格が下がっても消費量は変わらないということは、価格の問題ではないということであろう。 |
【食生活について】
| 問12 |
あなたは規則正しい食生活を送っていますか? |
| (1) |
あなたの食生活についてお尋ねします。 |
| 40代以上の人の90%近くは、規則正しい食生活を送っているが、30代以下の人は、60%強しかいなく、不規則な食生活を送っていることがわかる。 |
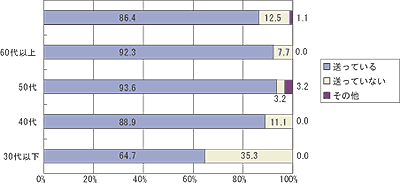 |
| (2) |
問12(1)で「規則正しい食生活を送っていない」と答えた方にお聞きします。
その内容または要因を教えて下さい。(複数回答) |
| 規則正しい食生活をおくっていない人は、食事の時間が不規則になりがちで、栄養のバランスが悪いと感じている人が多い。 |
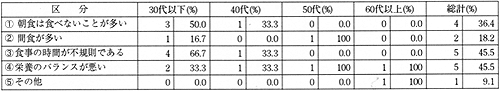
|
| (3) |
今後、あなたの食生活において改善していきたいと思っていることはありますか?(複数回答) |
| どの年代とも約半数の人が、ごはんを主食として多彩な副食を組み合わせた日本型食生活を心がけたいと思っているのが分かる。 |
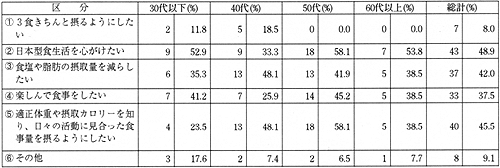
|
| 問13 |
あなたの食生活の内容、形態等は5年前と比較して変わったと思いますか? |
| 30代以下の人はどちらかというと、変わったと思う人が多い。一方、60代以上の人は約70%の人が変わらないと思っている。 |
| 問14 |
問13で「変わった」と答えた方にお聞きします。どのように変わりましたか? |
| 変わったと答えた人の多くは、家族揃っての食事が減ったことを挙げている。その他の意見としては、洋食から和食に変化した人が多かった。 |
【加糖調製品について】
| 問15 |
あなたは、加糖調製品をご存知でしたか? |
| 全体の約60%の人は知らなかったが、60代以上の人は77%の人が知っていた。 |
| 問16 |
問15で「知っていた」と答えた方にお聞きします。
あなたは、どのような加糖調製品をご存知でしたか?(複数回答) |
| ココア調製品は全体で86.5%、コーヒー調製品は69.2%の人がこれらを挙げた。ソルビトール調製品は、あまり知られていないようだ。 |
| 問17 |
あなたは、国内で製造されるあんの原料として輸入品の小豆やいんげん豆が使用されていることを知っていましたか? |
| 若い年代ほど知らないようである。 |
| 問18 |
加糖あんを原材料とする商品には、原材料の原産国について明確に表示をすべきと思われますか? |
| 全体の85%の人が、原料の原産国を表示すべきと考えていることがわかる。表示しなくても良いと考えている人は2%しかいなかった。 |
【その他】
| 問19 |
あなたの砂糖に対する日頃の思い、疑問点等についてご自由にお書き下さい。
(健康・料理・糖種・包装形態・容量・表示・その他) |
その他の意見・感想・要望等として下記のようなものがあった。
消費期限が袋に表示されていないので、製造年月日をいれてほしい。
上白糖の値段のバラつきにはびっくりする。
料理教室で「上白糖=健康な食生活に疑問、三温糖=健康に良い」と言われた。
今まで上白糖は漂白しているものだと勘違いしていました。
甘いものを食べると太る → 甘いもの=砂糖、よって砂糖を控えるという考え方が、自分も含めみんなの中で深く根付いているのを感じる。
健康の事を考えて出来るだけ砂糖は摂らないようにしているが、疲れたりするとつい手が伸びてしまう。
いろんな種類の砂糖があるけれど、違い、効能、調理上の効果が良く分からない。
袋一杯に入っているので、固まっていると容器に移しにくい。
砂糖の良い面、悪い面(摂りすぎは良くない)をもっと伝えるといい。
輸入品等の安全性が気になります。
黒砂糖の健康効果が本当はどうなのか知りたい。
上白糖の袋には小さな穴がいくつか開いていますがそれは何故ですか?やはりないといけない穴なのでしょうか。
効果的摂取の仕方、料理法、健康法を科学的、化学的にPRしてはどうだろうかと思う。
空口のところをチャック口にする事はできませんか。
|
3.まとめ
このアンケートは、砂糖と健康、食生活の中における砂糖の位置付け、砂糖の価格等に関する意識について行った。地域情報モニターはいろいろな年代、家族構成及び各地域に存在しており、様々な角度から砂糖に対する認識等について調べる事ができた。
季節による砂糖の消費量については、30代以下の年代では、圧倒的に冬場(特に12月)が多く、50代以上の年代では、梅酒作りのために春に多くなる。そのため、どの年代も全国的に砂糖を消費した次の月は反動で消費量が落ちている。
また、「砂糖を食べると太る」などについてのマイナス面は、昨年度より低い率を示しているが、相変わらず半数近くが誤解を持っている。逆に「砂糖は脳のエネルギー源」などの効用についてのプラス面は、昨年度より高い率を示している。
今回のアンケート等を通じて、砂糖に対してのイメージが変わったとする地域情報モニターが多数おり、消費者に対する砂糖についての正しい知識の普及という面で一定の効果があったのではないかと考える。
このように地道に普及活動することが正しい知識の普及につながると感じた。