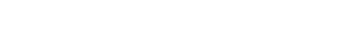
[2000年4月]
シチュー肉に砂糖をまぶしておくと煮たとき軟らかくなる、すき焼きを作る際に肉に砂糖をからめるよう煮ると肉が軟らかくなる、豚肉を乾燥させるときに浸漬液に砂糖等を加えておくと軟らかくなると一般的に言われています。こうした現象のメカニズムを証明するため、様々な実験・研究が行われました。醤油との相性の良さなどを含め、甘いだけではない砂糖の効用の一部について、その研究成果を中心に分かりやすく報告していただきました。
世界的にみた肉料理に砂糖を用いる割合
肉類は、世界中どこにおいても食べられ、また、好まれている食品である。肉の調理において、西欧諸国では食塩と胡椒を用いた味付けが主であり、砂糖などの甘味料を加えることは非常に少ない。しかし、全くないわけではなく、蜂蜜やチョコレートを加えて煮込む例、ソースに甘みを使う例、肉をローストする時に照りを出すために使うことなどがある。多くの調理では、加熱した時に肉から浸み出してきたうま味のある汁をソースやスープに利用し、そのにおいを消すために、たまねぎ、セロリー、トマトなどの野菜類を用いる。
『週刊朝日百科、世界のたべもの』1(1980)〜97(1982)に掲載された1,400種類の伝統的肉料理の調味料を調べ、この中で砂糖を用いている割合を調べたものを図1に示した。
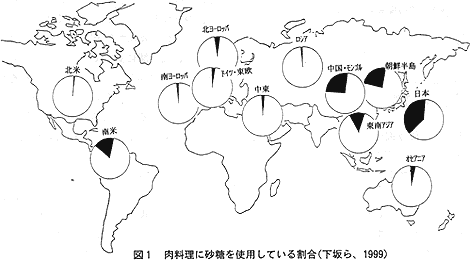
東洋に位置する日本、中国、朝鮮半島、東南アジア諸国においては、肉を加熱する時に醤油やみそなどを用いて、砂糖を併用することが多い。日本の代表的な肉料理すき焼きでは、鍋に肉を入れて加熱する時、先に砂糖を加えて、その後で醤油を入れる方が軟らかくできあがると言われている。東アジア、東南アジアでは米を主食にしており、ご飯を食べる時に塩味の強い、うま味の強いおかずがご飯にあうので、調味料として醤油やみそが作られ、使われてきた。これらの調味料は、肉類を加熱するとき発するにおいを消すのに効果的であり、この調味料の塩辛さを和らげる効果がある砂糖が加えられてきたものであろう。
砂糖は肉を軟らかくする
牛肉の薄切り肉をすき焼き程度の味付けで、10分間醤油で煮たものとこれに砂糖を加えたものの両方を食べ比べてもらい、どちらが硬いか、どちらが歯切れが良いのか、弾力性があるのはどちらかなど、20名に聞いたところ、表1のようになった。すなわち、砂糖を入れた方が硬くなく、総合的においしいとされた。また、砂糖を加えた方が歯切れが良い、汁気を多く感じるという人が多くいた。
| 表1 牛肉醤油煮の砂糖添加効果 |
| 試料 |
醤油煮(注2) |
砂糖・醤油煮(注2) |
硬さ
歯切れやすさ
弾力の強さ
多汁性
においの強さ
総合的なおいしさ |
15(注1)
6
13
6
10
4 |
5
14
7
14
10
16(注1) |
|
注1:危険率5%で有意差あり
注2:塩分2.5%の醤油煮、砂糖は肉の20%を添加 |
シチューに使う肉は一般には硬い肉で長い時間煮込んで汁にうま味を出すとともに肉を軟らかくするのであるが、この時に肉を砂糖にまぶしておき、それから煮ると肉が軟らかくなりやすいとも言われている。実際に、シチュー用のすね肉のまわりに5%の砂糖をまぶしておいたものと砂糖をまぶさなかったものを、それぞれ圧力鍋で10分間煮て、ルーを入れてシチューにし食べ比べてみると、砂糖をまぶした方が軟らかく、歯切れが良いという結果であった(表2)。砂糖を加えると口当たりが良く、味がまろやかになるので、それに多少影響されることも考えられるが、肉は軟らかく感じるという結果になった。
| 表2 牛すね肉シチューにおける砂糖添加の効果 |
| 試料 |
砂糖なし |
砂糖添加 |
硬さ
歯切れやすさ
弾力の強さ
においの強さ
総合的なおいしさ |
16(注)
5
9
12
8 |
4
15(注)
11
8
12 |
|
|
注:危険率5%で有意差あり |
肉料理に砂糖を加えるとなぜ軟らかくなるのか
食品を口の中に入れて噛んだ時、この食品は、軟らかい、硬いと感じるのは、食品の持つ様々な性質を一緒に感じて総合的に判断しているのである。すなわち、1つの機械で測定できる性質は、1種類か、2〜3種類であり、食品には、硬い、軟らかい、汁気が多い、脆もろい、砕けやすい、さけやすい、歯切れが良い、つるつる、ざらざら、さくさく、ぱさぱさ、等々の様々な性質がある。機械ではこれらの性質は一緒に測定できないが、人の口の中では食品の異なった何種類もの性質をたちどころに感じて、総合しておいしいかどうかを判断している。牛肉の薄切り肉を加熱して歯触りに関連する性質を調べたのが以下の通りである。
1 噛みやすさ
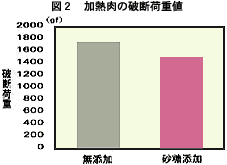
食べ物を口の中で噛んだ時に感じる性質を比較的良く表現するとされている機械であるレオメーターを用い、これにカッターの刃をつけて加熱薄切り牛肉の硬さを測ってみると、図2のようになった。この加熱肉の硬さは、醤油だけで煮た肉よりも砂糖を加えて煮た方が、軟らかい。肉の由来によって性質がかなり異なるが、薄く切った肉では、砂糖を加えると軟らかくなる場合が多い。
2 肉の砕けやすさ
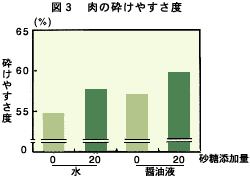
煮た肉を細かくブレンダーで砕いて、その細かくなりやすさを測ったものである。図3のように、水よりも砂糖液中で加熱した肉が、また醤油液よりも砂糖を加えた混合液で加熱した肉が、細かくなる率が高かった。砂糖を加えて加熱するとわずかであるが砕けやすくなっていることが示されている。これが、口の中で肉を噛んだとき歯切れが良いと感じられるのであろう。すなわち、牛肉の時雨しぐれ煮になど保存性を向上させるために砂糖と醤油を高濃度に加えて加熱しても水分の減少が大きい割には、歯切れが良く、硬くならないことになる。
肉の水分は、表3に示したように、砂糖を加えると4〜5%少なくなっている。一般には、食品の水分が少なくなると硬くなるが、砂糖を加えた肉では水分が少なくなっても硬くはならず、むしろ軟らかくなることもあると言える。おそらく肉から水分が出て、代わりに砂糖液が浸透するので、筋肉の凝集を砂糖が抑制するのではないかと予想している。
| 表3 加熱による肉の重量と水分率の変化及びpH |
| 加熱液 |
水 |
砂糖 |
醤油 |
砂糖・醤油 |
煮汁の水分(%)
肉の重量(%対生肉)
肉の水分(%) |
100
64
56 |
83.3
65
52 |
89.9
66
55 |
74.9
67
50 |
|
|
注:肉と汁の全重量の2.5%塩分になるよう醤油を加え、砂糖は肉の20%添加 |
3 コラーゲンの溶出
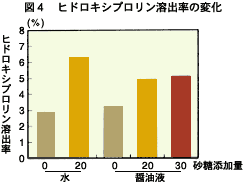
肉の主成分はタンパク質で、肉を加熱するとタンパク質の保水性が低下し、肉に含まれていた汁が浸み出て、肉の水分は減少する。この時、肉のタンパク質も溶出してくる。肉のコラーゲンは一般には長時間加熱しないと溶出しないと言われているが、図4のように、10分間の加熱でも数パーセントが溶出していた。コラーゲンの溶出は、水煮よりも砂糖を加えて加熱した方が、また醤油だけよりも砂糖と醤油を一緒にした液で加熱した方が、さらに砂糖の多い方が溶出量が多くなった。ヒドロキシプロリンは、コラーゲンに含まれているアミノ酸で、ヒドロキシプロリンの溶出はコラーゲンの溶出を意味している。こうしたコラーゲンの溶出によってシチューにこくが出て旨みが増すのであろう。
肉のにおいを改良する作用
砂糖を加えて肉を煮た時、表2に示したように肉のにおいがやや減少し、歯切れが良くなり、汁っぽくなり、総合的に好まれるようになる。砂糖などの糖類は、水を吸着しやすく、食品から発するにおい成分を保持して揮発させない性質があることは前から知られている。砂糖を加えるとにおい成分が出てくるのを押さえることで、肉のにおいが少なくなる。肉は旨味は強いが、においは良い香りとは言えないもので、ヨーロッパで胡椒などの香辛料が強く求められたのも肉のにおいを消すためであった。肉を焦がすとおいしそうなにおいになるが、これは焦げによって発する香りである。
一方、照り焼きや蒲焼きのにおいは食欲をそそるが、これは醤油とみりんまたは砂糖を混合して動物性の食品を高温で加熱するときに生じる香りである。糖類とタンパク質が一緒に加熱されるとメイラード反応が起こって、そこから生じてくるもので、これに動物の脂肪酸の分解成分が加わって、それぞれの動物性食品の特徴的な香りを形成している。肉類を醤油と砂糖で加熱すると、複雑な、しかも多種類の成分が生成して肉のにおいをカバーするので、香りが良くなるのである。ハンバーグを照り焼き風にして、これをハンバーガーにした照り焼きバーガーは国の内外を問わず若い人々の人気メニューである。また、北京ダックの皮の香ばしさ、おいしさも砂糖液や蜜を塗って焼くことによって形成されるものである。
保存性の向上
食品を保存するには、有害な微生物が繁殖しないようにすることが必要である。微生物は成育するのに水分が必要で、微生物が利用できるような水分を減らすことによって、細菌、カビの成育を防ぐことができる。魚の干物、干し椎茸やかんぴょうなどは、乾燥によって水分を減らし保存性を高めている。しかし、水分を減らすと食品が硬くなる、テクスチャー(歯触りや舌触りなど)が変化するなどおいしさに影響するところが大きい。水分のうちでも、細菌やカビが利用できる水分(自由水)を減らすことで保存性が向上する。砂糖やアミノ酸などを食品に添加するとこれらが食品中の水分を強く束縛して、動かない水(結合水)になり、細菌などが利用できなくなってくる。ジャムやようかんなどの保存性が高いのは、加えた砂糖が水を束縛していて、細菌が成育に使う自由水が少ないからである。牛肉の時雨煮、ふなの甘露煮、そぼろ、果物の砂糖漬けなどは味が濃いだけでなく、それに高濃度の砂糖が入っていることで保存性が高められている食品である。これらは水分がかなり少なくても、その割に硬くなっていない。
肉を加熱する場合も砂糖を加えると、肉の水分が出たところに砂糖が入り込んでいることによって、硬くはならないのである。
また、中国や台湾などで作られているものに肉乾という乾燥肉がある。これは軟らかな燻製品で、製造の際に砂糖を加えるので、水分が少なくても硬くならないと言われる。西洋に比べて湿度の高い東南アジアでは、食品を乾燥して保存するよりも、漬けるという加工法や佃煮にして保存することが行われている。
したがって、肉を加熱する際、あるいは肉製品を製造する際に砂糖を加えることは、味をまろやかにするとともに、水分を減らして保存性を向上し、においを減らし、水分が少なくても製品を硬くせず、歯切れを良くしていると言える。


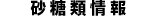


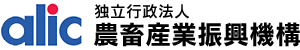

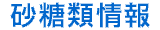
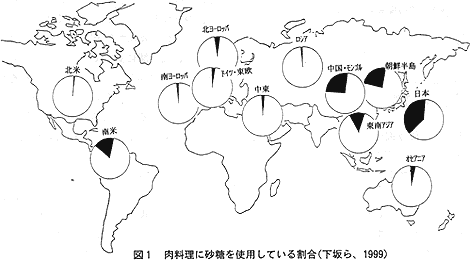
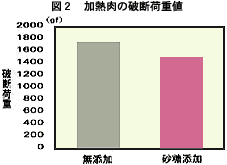 食べ物を口の中で噛んだ時に感じる性質を比較的良く表現するとされている機械であるレオメーターを用い、これにカッターの刃をつけて加熱薄切り牛肉の硬さを測ってみると、図2のようになった。この加熱肉の硬さは、醤油だけで煮た肉よりも砂糖を加えて煮た方が、軟らかい。肉の由来によって性質がかなり異なるが、薄く切った肉では、砂糖を加えると軟らかくなる場合が多い。
食べ物を口の中で噛んだ時に感じる性質を比較的良く表現するとされている機械であるレオメーターを用い、これにカッターの刃をつけて加熱薄切り牛肉の硬さを測ってみると、図2のようになった。この加熱肉の硬さは、醤油だけで煮た肉よりも砂糖を加えて煮た方が、軟らかい。肉の由来によって性質がかなり異なるが、薄く切った肉では、砂糖を加えると軟らかくなる場合が多い。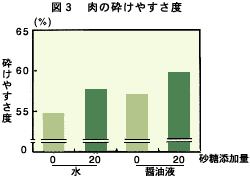 煮た肉を細かくブレンダーで砕いて、その細かくなりやすさを測ったものである。図3のように、水よりも砂糖液中で加熱した肉が、また醤油液よりも砂糖を加えた混合液で加熱した肉が、細かくなる率が高かった。砂糖を加えて加熱するとわずかであるが砕けやすくなっていることが示されている。これが、口の中で肉を噛んだとき歯切れが良いと感じられるのであろう。すなわち、牛肉の時雨しぐれ煮になど保存性を向上させるために砂糖と醤油を高濃度に加えて加熱しても水分の減少が大きい割には、歯切れが良く、硬くならないことになる。
煮た肉を細かくブレンダーで砕いて、その細かくなりやすさを測ったものである。図3のように、水よりも砂糖液中で加熱した肉が、また醤油液よりも砂糖を加えた混合液で加熱した肉が、細かくなる率が高かった。砂糖を加えて加熱するとわずかであるが砕けやすくなっていることが示されている。これが、口の中で肉を噛んだとき歯切れが良いと感じられるのであろう。すなわち、牛肉の時雨しぐれ煮になど保存性を向上させるために砂糖と醤油を高濃度に加えて加熱しても水分の減少が大きい割には、歯切れが良く、硬くならないことになる。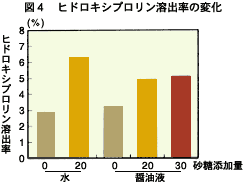 肉の主成分はタンパク質で、肉を加熱するとタンパク質の保水性が低下し、肉に含まれていた汁が浸み出て、肉の水分は減少する。この時、肉のタンパク質も溶出してくる。肉のコラーゲンは一般には長時間加熱しないと溶出しないと言われているが、図4のように、10分間の加熱でも数パーセントが溶出していた。コラーゲンの溶出は、水煮よりも砂糖を加えて加熱した方が、また醤油だけよりも砂糖と醤油を一緒にした液で加熱した方が、さらに砂糖の多い方が溶出量が多くなった。ヒドロキシプロリンは、コラーゲンに含まれているアミノ酸で、ヒドロキシプロリンの溶出はコラーゲンの溶出を意味している。こうしたコラーゲンの溶出によってシチューにこくが出て旨みが増すのであろう。
肉の主成分はタンパク質で、肉を加熱するとタンパク質の保水性が低下し、肉に含まれていた汁が浸み出て、肉の水分は減少する。この時、肉のタンパク質も溶出してくる。肉のコラーゲンは一般には長時間加熱しないと溶出しないと言われているが、図4のように、10分間の加熱でも数パーセントが溶出していた。コラーゲンの溶出は、水煮よりも砂糖を加えて加熱した方が、また醤油だけよりも砂糖と醤油を一緒にした液で加熱した方が、さらに砂糖の多い方が溶出量が多くなった。ヒドロキシプロリンは、コラーゲンに含まれているアミノ酸で、ヒドロキシプロリンの溶出はコラーゲンの溶出を意味している。こうしたコラーゲンの溶出によってシチューにこくが出て旨みが増すのであろう。








