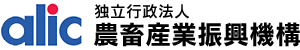ホーム > 砂糖 > 視点 > 食と文化 > フランス料理の歴史とデザートの役割
最終更新日:2010年3月6日
 |
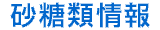 |
 |
フランス薬膳・文化研究家、エッセイストの須藤春子氏にフランス料理の歴史やデザートの役割、砂糖の役割を執筆していただきました。
| フランス薬膳・文化研究家、エッセイスト 須藤 春子 |
| 1.フランス料理の歴史 |
| 2.デザートの役割 |
| 3.デザートにおける砂糖の役割 |
フランス・ルネサンスの幕明けとも言える15世紀末から16世紀初めにかけて、フランス国王は三代に亘り、イタリアを手に入れるようと侵略した。3人の王様はシャルル8世、ルイ12世、フランソワ1世である。このイタリア戦争は失敗に終わったが、当時の輝かしいイタリア・ルネサンスの文化に心を奪われ、以後それを積極的に取り入れるようになった。
ロワール河沿いのシャンボール城を始め、お城や家具にイタリアの影響を受けた、装飾が多くて優美なルネサンス様式が生まれた。
フランソワ1世は先見の明のあった王様で、イタリア遠征の際、レオナルド・ダ・ヴィンチを連れて帰り、レオナルドは王様に「モナリザ」を献上した。これが、壮大なルーヴル美術館の蒐集の契機となった。また、フランス王室とイタリアのメディチ家との縁組を実現させ、以後、フランス料理は、大いなる恩恵を受けながら発達してゆくことになる。
中世の12世紀迄は、フランスの食事はローストした肉と茹でた野菜のみであった。料理法の点でイタリア人に後れを取っていたが、14〜15世紀になると、シチューに近いものが登場する。14世紀に、シャルル5世に仕えたタイユヴァンは、新しい料理法を考案するなど、フランス料理の基礎を築いた。
当時は、フォークも食事のマナーもなく、肉類をナイフで切っては手掴(づか)みで食べていた。肉類の保存に必要な香辛料は、金と等価で取引されるほど高価で、手に入りにくかった。また、砂糖は十分になく、蜂蜜を専ら代用していた。飲み物のお茶やコーヒーがなかったのは言うに及ばない。
ところで、フィレンツェは、内乱の収まった15世紀以降、全ヨーロッパ相手の商業と銀行業務によって益々栄え、イタリア中部を治める共和国となった。特にメディチ家が活躍し、大ロレンツォの時代は絶頂期に当たり、政治・経済活動のみならず、文芸の復興に努めるなどした。
1533年、フランソワ1世の子供アンリ2世は、父王の思惑通り、メディチ家のカトリーヌ (大ロレンツォの曾孫) と結婚した。また、1600年には、アンリ4世の許へ同じくメディチ家のマリーが嫁いだ。
メディチ家のお姫様達のお輿入れの際には彼女達の料理人も含めて、多くの従者を同行してきた。全てが新しく、華やかであり、かくしてイタリア料理に対する熱が高まるにつれて、その流行が生まれた。
当時、イタリアは料理の先進国で、料理技術の最先端がフランスへ伝えられた。伝わった料理法は、スープとソース類、野菜のトリュフ、グリンピース、アーテチョーク (朝鮮あざみ) 、ブロッコリーとその料理法、デザート類、リキュール (薬用酒) などである。トリュフは珍味の高価な「きのこ」だが、フランス人はこの味を覚えて病みつきになったという。グリンピースやアーテチョークは栄養学上大切な野菜となった。ケーキやクリームのデザート名もイタリア語が起源のものが多く、リキュールも以後フランスで数多く作られるようになった。
当時のフランスの貴族は、婦人でもマナーが悪かったので、カトリーヌは食事のマナーも教えた。
メディチ家は、東方との香辛料の取引で財をなした家柄である。カトリーヌやマリーは莫大な富を背景に贅を尽くした食事や生活を楽しんでいた。ガラス製品や銀製品、釉薬(ゆうやく)をかけた陶器、調理器具、食卓に至るまで全てイタリアから輸入されていた。
ルネサンス時代の料理は、洗練されて豪華になった。食事の主体であった肉が減り (牛肉などはあまり食べる機会はなく、大方は豚肉を食べていたであろうと思われる)、魚や野鳥、鹿肉がメニューに登場してくる。イタリアの影響が明確に表われ、ソースを添えた料理や菓子類など内容も豊かになる。メディチ家との縁組では、金と等価の香辛料並びに貴重な砂糖、この2つの宝物が容易に手に入るようになり、料理技術の発展に拍車をかける契機となった。
香辛料と言えば、胡椒、丁字、ナツメグ、シナモンなどが代表的だが、大半は熱帯植物で、東洋が原産である。その中でも胡椒は最も需要が多く、古代から南インド西側のマラバール海岸一帯で栽培されていた。エジプトもインドから輸入し、中国では、胃や腸の良薬として大切に扱っていた。ギリシア・ローマ時代には、インド洋からの南西風「キッパロスの風」に乗って、一獲千金を夢見た商人が、命懸けでギリシア・ローマからインドまで胡椒の買い付けにやってきた。ローマ皇帝もインドの胡椒が帝国になき唯一物と嘆いたという。
この時代から16世紀まで、胡椒は最も需要が多くて香辛料貿易の中心を占め、金と同じ価で取引されていた。
中世末に至るまで、ヨーロッパ人は狩猟による肉類を主食としていた。生肉は3日もすれば臭くなるので、長く保存するには塩漬け以外に方法はなかった。香辛料の中でも特に胡椒は、傷みかかった肉の臭みを消して味を良くすると同時に、防腐剤として殺菌力があるため引っ張り凧で、供給が間に合わなかった。香辛料さえあれば、冬を越すのに十分な食料、肉を貯蔵できた。ハムやソーセージも肉の保存用に発達したものである。香辛料は欠くことの出来ないものであり、最も利益の上がった交易品であった。このように高価で貴重な商品を売買する様は、扉や窓を念入りに閉め切って、黄金の秤で量っていたという。
香辛料で地代や税金、結婚の持参金も賄われただけでなく、婦人の虚栄心を満たす芳香類や教会で香炉に使う香としての消費量も莫大であった。かくして香辛料に対する西洋世界の情熱は、十字軍の遠征と共に高まってゆく。その取引を独占していたヴェニスの商人以外に安く香辛料を手に入れようと、多くの探検家がマルコ・ポーロの「東方見聞録」を道標(みちしるべ)として海に出て、大航海時代が幕を開けた。1498年、バスコ・ダ・ガマの航路発見以後、3世紀に亘り、ヨーロッパの列強国の間で、香辛料を生産する植民地の獲得と、その貿易の独占を求めて戦いが繰り返されたのである。大航海時代の動きは、同時に貴重な副産物をヨーロッパに齎もたらしたが、それに付いては、後段で述べることにする。
17世紀のルイ王朝の時代には、摂政のマザランや音楽家のリュリなど多くのイタリア人が宮廷に仕えた (尚、この2人は後にフランスに帰化した)。「太陽王」ルイ14世は、当代切っての建築・装飾・造園の3大芸術家を使ってヴェルサイユに壮大な宮殿を建て、絶対王制を敷いた。大蔵大臣コルベールは重商主義を唱えて東・西インド会社を設立し、アメリカやカナダの植民地政策をとる一方、文芸の推進役も務めたが、この時代にフランスの領土も広がり、国力が高まっていった。フランス文化に花が咲くに伴い、料理も発達していった。
この時代には「大食」が支配的で、大きい物が好きなルイ14世のお抱え料理人は324人もいた。大食漢の筆頭で、一度の食事で信じ難い量を平らげたと義妹が記している。この時代にイタリア伝来のフォークが普及し、新しい食卓作法が生まれ、ブリキ製調理器具が作られた。料理は見世物的であったが、近代フランス料理の礎が築かれた。
ルイ王朝の社交界では「サロン」が開かれて女性が活躍し、社交術も発達するにつれてパリは、ヨーロッパ最初の芸術の都となった。この傾向はルイ15世の時代へと引き継がれてゆく。
この時代には、サロンや宴会が盛んに開かれ、才色兼備のポンパドール夫人らが文芸の擁護者となり、絢爛豪華なフランス文化の華が咲いた。曲線を生かしたロココ様式は、家具や食器にもその特徴が表われ、セーヴル焼 (磁器) が誕生した。国民にも愛されたルイ15世は洗練された味を求め、王妃や貴族は、自分の名前が新しい創作料理に付けられる事を好んだ。料理書が多く書かれ、料理の目的が材料の味を引き出して肉や魚の出し汁を使うように変わっていった。
18世紀後半にルイ15世の孫ルイ16世が王位に就いたが、その旺盛な食欲は人間離れしており、ギロチンにかけられる前に、牢獄で鱈腹食べて昼寝をしたという。
この時代に料理技術は著しく進歩し、食料品関係の職業が仕出し屋、菓子屋など分業になり、史上初の「レストラン」が誕生した。
新しい傾向として、キャビアやビーフステーキ、カレー等の外国料理がフランス料理の中に登場し、コーヒーが普及した。園芸では、温室が出来て熱帯原産の果物も作られるようになった。
また、新大陸原産の新しい材料が登場した。唐辛子、アボカド、南瓜、トウモロコシ、豆類、トマト、じゃが芋、さつま芋、落花生、ココア、バニラである。トウモロコシは家畜の大切な飼料となり、豆類は栄養学上大切な野菜として、またトマトは地中海沿岸の国では欠かせない材料になった。ピーナツ油はフランスの植物性油の代表格で、ココアとバニラはお菓子の発達を促した。じゃが芋は、ルイ16世の時代に栽培に成功してから飢饉を救うことになった。新しい材料が新しい料理法を生み、フランス料理が広がりを見せた。
1789年のフランス革命は、料理の面でも革命的な出来事であった。ルイ王朝の宮廷に支えられてきたフランス料理は大きな変化を受けることになる。革命後、料理人が宮廷や貴族の館で働けなくなり、町に出てレストランを開いた。その数が増えるにつれて、「美食」が大衆化してゆく。
ナポレオンの時代に、料理は一層上品で洗練度を増したが、優秀な料理人が多く出た。特に、カレームとエスコフィエは通算150年間その光芒を放った。また、19世紀にはタレーランやブリア・サヴァラン、アレクサンドル・デュマ、キュルノンスキー等美食家がたくさん現れた。タレーランは外務大臣で、外交手段として宴会を催し、サヴァランは「美味礼讃」を著わした。
このようにあまたの美食家が出たと同時に、それに応えられる優秀な料理人が輩出した。そして、アメリカやイギリス、ロシア、ドイツ、オーストリアへ渡ってフランス料理を広める一方、外国の料理も積極的に取り入れ、一段と範囲が広がった。最近では、中国や日本の影響を受けた料理も考案されている。
フランス料理は、イタリアの影響を受けながら香料の島の発見、新大陸伝来の材料の導入という二つの歴史的な大事件が契機となり、発展してきた。料理の歴史を振り返ってみると、肉の冷蔵、パンの発酵、パスツールの殺菌法、缶詰などフランス人の発明法はたくさんある。幾多の障壁を乗り越えながら、美食家サヴァランの名言「新しい料理の発見は新しい星の発見よりも人類の幸福に貢献した」のごとく、フランス料理は、世界の人類の幸福に貢献し、普遍的なものとなったのである。
日本の懐石料理には、食べる料理の順番が約束事として決まっている。フランス料理の場合も同じで、前菜、スープ、魚料理、肉料理、サラダ、チーズ、デザートの順に進んでゆく。これがいわゆるフルコースだが、よほど正式な宴会でない限り、この全部のコースを食べることは滅多にない。レストランへ食事に行った場合、普通は前菜 (温かいものか冷たいもの) かスープ、メインディッシュとして魚料理か肉料理、チーズ、そしてデザートを注文する。これなら日本人でも食べ切れるのではないだろうか。因に、家庭では前菜かスープ、魚か肉か卵料理、付け合わせとして温かい野菜料理、サラダ、チーズ、ヨーグルト、デザートとして果物をいただくのが一般的である。クリスマスや記念日、友人を家に招く時は、コースの数は同じでも主婦が腕に縒りをかけて作り、気の利いた料理が食卓を飾り、果物の代わりに一手間かけたデザートが登場する。
ところで、フランス料理を食べた後の感想として、メインディッシュ迄の料理の美味しさとは別に、デザートの印象が残るような気がする。家庭に招かれた時など、その家伝来の秘密のレシピーがあり、こちらが褒めるとマダムは嬉しそうに「メルシ」と言いながら微笑み返してくれる。レストランで食事をした際も、デザートのコースになると、ワゴンサービスで見せてくれる。大きな店では10種類以上も用意してあり、どれも美味しそうで選ぶのに迷ってしまう。
この「選ぶのに迷う」というのは、それだけ変化に富んでいるからであろう。実際、和菓子に比べると、形といい、材料といい、多様性に満ちている。
 皇后風お米のババロア |
材料の点から注目してみると、砂糖以外に使うものは、卵、乳製品ではバター、牛乳、生クリーム、チーズ、澱粉類では小麦粉、お米、そば粉、パン等が使われる。果物もよく用いるが、苺やりんご、オレンジなどその季節の旬のもの以外に、干したレーズンやプルン、缶詰の洋梨やパイナップルも珍しくはない。ナッツ類ではアーモンドやくるみ、特にアーモンドは、丸のままや粉末、薄切り、粗切りと形を変えて頻繁に登場する。この他に、冷たいデザートのつなぎとしてゼラチン、香り付けには、バニラ、シナモン等のスパイス、チョコレートやコーヒー、紅茶、ワイン、ブランデーやリキュールのアルコール類、カラメルが脇役となる。
更に、食べる時の温度を考えた場合、常温、温かい状態のもの、冷たいものとに分類できる。常温でいただくものはビスケットやタルト、スポンジケーキ等。スフレAは、泡立てた卵白が熱で膨らむのを利用したもので、オーブンで表面が最も盛り上がったら間髪を入れずに供するとよい。また、冷やしておくものでは、アイスクリーム、シャーベット、ババロワやムースがある。
今迄述べてきたように、一口にデザートと言っても、複数の材料を組み合わせることによって幾多のバリエーションをもたらす。形は立体形な物から平たい物、丸や四角い形、味に付いては甘いものや果物の酸味、チョコレートの苦味があり、色合も鮮やかな赤い色や淡いパステル調の色彩、渋い茶色と広範囲である。更に、いただく時の温度も考え合わせれば、身近にある材料が千変万化する。「この身近な材料を何十倍にも変化させて楽しむ事」こそフランス文化の真髄である。
このように、見た目も美しく、食べて美味しく、中に入っている材料の香りや食べた時の触感といい、五感を駆使して味わえるデザート。デザートもそれなりの役目を果たしている。
デザートには、3つの役割があると言えよう。1つ目は、心の緊張を解すことである。本当に美味しいデザートに出会った時、人はどのような表情をするであろう。一口食べて美味しいと解ってから、二口目を口に運ぶのと同時に目を閉じて味わい、喉元を過ぎる頃から顔が綻びてくる。苦いものや酸っぱいものを食べた時は対照的で、表情が強張る。この顔付きが甘い物を食べている人の心理状態をよく表している。
2番目に、デザートに使う材料に付いては前に述べたが、食材を幅広く取ることができる。最も簡単なものでも3〜4種類は使うので、旬の果物を生かすなどして、変化を付けて食べていれば、より良い健康状態が保てる。
3番目の役目として、アルコールの解毒作用がある。食事の初めに甘い物を食べると、満腹感が早く起きて食欲がなくなるが、デザートは食事を締め括るばかりか、こちらの意義は大きい。ところでフランスでのお酒の飲み方は、食前酒、食事中のワイン、少量の食後酒と使い分けており、理に適っている。食前酒の代表格は、ペルノーやアブサン (ベルモット) だが、アルコール度数は低く、茴香(ういきょう)や蓬(よもぎ)など薬草入りで胃腸の働きを高める。食事中はワインで通し、食後には、アルコール度数の高い食後酒を飲む。食後酒には、ブランデー類の甘くないものと、甘味の強いリキュールとがある。リキュールとしては、コワントローとグランマルニエ (共にオレンジ入り)、シャルトリューズ (修道僧が作っており、甘草など50種類以上の薬草が入る) や郷土色豊かなジェネピ (アルプス蓬入り) などがある。食後酒は、アルコールが体内で食物を燃焼させ、消化を促進する働きをする。食後酒を表すフランス語の digestif (ディジェスティフ) には、文字通り、「消化を助ける」の意味がある。
このように、食事の最後にデザートを食べ、リキュールを飲むのは、薬に頼らずに自然な食べ物の組み合わせから体調を整える「医食同源」の現れである。
 小タルト (タルトレット) |
ご馳走を食べる時は、最低2時間ぐらいはかけてゆっくりしたペースで食べる事、更に食事中に楽しい話をし、笑うことも消化に良い。フランス料理はヘルシーでない、というイメージが日本にはある。が、実際には、フランク王国を統一した王シャルルマーニュが法令集に定めたハーブの使い方は千年を越える伝統があり、栄養面から見た野菜や果物の摂り方、先に記した食習慣など学ぶべき医食同源の考え方は多くあると言えよう。
デザートを作る時に、砂糖は欠かせない材料だが、その過程で大切な働きをしている。
先ず、材料に砂糖を加えれば、甘味を出し、杏など酸味の強い果物やカカオのように苦味の強いものに使うと、味が和らいで食べ易くなる。
苺やりんごなど果物のジュースをそのまま置くと空気に触れて色が悪くなるが、砂糖を加えて湯煎にかけるだけで、砂糖が溶け出すと同時に、果物本来の色が蘇える。つまり、色止めをして、ツヤを出す。
 桑の実入りスポンジケーキ |
フィンガービスケットやメレンゲを焼く前に表面に粉砂糖をふるが、これは粉砂糖が材料の水分を吸収し、表面を乾かすためである。別の場合で、砂糖を表面にふって上火を利かせると、砂糖が溶けてツヤが出、更にはカラメル化して焼き色が付く。
ジャムを作る時に砂糖を入れるのは、煮つめて水分を飛ばしながら保存力を与えている。
終わりに、砂糖の歴史を振り返ってみると、大昔は薬と考えられていたほどで、砂糖が手に入り易くなったのは、最近の200〜300年のことである。他の調味料と比べれば、その科学的性質から利用範囲が広く、使い方次第では健康にも良いのが砂糖である。その「砂糖」を活用してフランス料理のデザートのような多彩で甘くておいしいデザートを作り、毎日の生活に彩りを添えてはいかがでしょうか。
|
「今月の視点」 2001年2月 |
●新しい砂糖制度と行政体制の発足に当たって 農林水産省生産局特産振興課長 小山信温 ●日本の風土に合った食文化 〜食生活は未来の家族への投資です〜 料理研究家、おいしいもの研究所代表 土井善晴 ●フランス料理の歴史とデザートの役割 フランス薬膳・文化研究家、エッセイスト 須藤春子 |