

最終更新日:2010年3月6日
 |
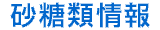 |
 |
|
北海道大学 教授 |
| はじめに |
| 自然食品は健康食品か? |
| 青酸配糖体 毒か毒でないかは量で決まる カラシ油配糖体 食べるということ |
| 快適な味、甘味について |
| 砂糖を食べると肥満になるか? 砂糖は血糖値を高めるか? 砂糖はカルシウムを奪うのか? 砂糖は脳のエネルギー源 |
食品には第1次機能 (栄養特性)、第2次機能 (嗜好特性)、第3次機能 (生理調整機能) があるとされている。これは食品に求められてきたことの変化を示している。すなわち、食品にまず求められたのは栄養、健康の維持であり (第1次機能)、それが満たされた時、食に楽しみが期待されるようになった (第2次機能)。そして現在は 「食にホルモン、神経、内分泌等生理機能の調節を求めるようになってきている (第3次機能)」 ということが機能性食品に関するほとんどの論文に記載されている。 しかし、ある食品の1次機能である栄養価が高いということは、その食品が正常な成長を促すということであり、正常な成長はその食品が第3次機能である正常な生理調整機能を有していて初めて可能になるものである。第3次機能は第1次機能に含まれる、あるいは第3次機能は第1次機能のある部分を特に強調したもの、ということもできる。
本論では、第3次機能を発現する物質の多くは不快な味を有しており第2次機能の嗜好特性の上では好ましくなく、第2次機能と第3次機能は矛盾する場合が多いという、従来ほとんど指摘されていない点について記述し、次いで快適な味としての甘味の意義について考えたい。
本論のサブタイトル、「食うものと食われるものと世にありて」 は、「食われてしまえばそれまでのこと」 と続く、大岡博 (歌人) が詠まれた私の好きな歌である。しかし、この歌には、「生物には食う生物と食われる生物という役割分担がある」 というように誤解される恐れがある。
生物を定義するのは難しいが、1つ言えるのは、生物は動的恒常性を有しているということである。その動的恒常性を維持する材料は他の生物であり、その食われる生物もまた他の生物を食って自分を維持している。食われるために存在している生物はなく、生物とは自分は食われずに相手を食おうとしているものであるということができる。自ら食われないためのバリアーと相手のバリアーを打ち破るための武器の両方の進化を怠った生物は食われ尽くし、あるいは食うものがなくなって絶滅することになる。
では、自ら動くことができない植物は、食われないためにどのような努力をしているか。多くの場合、捕食者に有害な物質を蓄積して自分を防御している。
青酸配糖体
植物が蓄積している有害物質の1つとして青酸があるが、それが2千種類以上の植物に含まれていることは意外に知られていない。また、植物中では青酸は糖と結合して必要な時まで不活性な形で蓄積されており、反応性の高い物質を必要時まで不活性な形で保存しておく方法は種々あるが、糖と結合する方法が最も一般的であり、そのような化合物を配糖体とよぶ。青酸配糖体を含む植物が攻撃されると細胞が傷つけられ、配糖体とは別の場所に貯蔵されていた分解酵素と配糖体が混じり合い、反応して青酸を発生し、捕食者に害を与えるという見事な機構を持っている。
例えば、梅やアンズなどバラ科植物の核にはアミグダリンという青酸配糖体が、そして果実にはその分解酵素が含まれている場合が多い。特に未熟な果実では核が柔らかく容易に噛み砕かれてしまうため、現在でも未熟なアンズによる中毒事故が報告されている。かつては日本でも未熟な梅による青酸事故が発生していた。熱帯・亜熱帯の主要エネルギー源であるキャッサバにも、リナマリンという青酸配糖体が含まれており、不充分な処理による中毒が現在でも報告されている。
ではそのような有害物質を摂取しても直ちに障害を起こさないのは何故なのか。
毒か毒でないかは量で決まる
ある物質は体に良い物、ある物質は体に毒である物と明快に分けられると誤解されている場合が多いが、完全に良い物とか完全に毒物とかいうものはなく、「毒か毒でないかは量で決まる」 のである。どのような有効な物質でもある量以上摂取すると何らかの害作用が現れるが、その害作用が現れる量をその物質の閾値という。
どのような物質が体内に入っても、それが閾値以下の量であれば、そのままあるいは形を変えて体外へ排出することができ、害作用は現れない。そのような機構を有していなければ、自分と物質的に異なる他の生物を取り入れて自己を再構成し続けて生きていくことはできない。
カラシ油配糖体
青酸ほどの猛毒ではないが、植物が蓄積している興味ある他の防御物質にカラシ油配糖体がある。
カラシ油配糖体はアブラナ科植物に含まれており、青酸配糖体の場合と同様に植物が傷付けられると別の場所に貯蔵されていた分解酵素が混じり合い、反応して、種々の成分が生成する。このうち特にイソチオシアネートというものが捕食者の嫌う辛味、苦味等を有する。ワサビ粉を水とよく練って辛いワサビを調製するが、それはこの反応によるものである。ダイコンおろしの辛みも、すりおろしている時にこの反応が起こることによる。
「夫婦喧嘩の後のダイコンおろしは辛い」 というのも、妻が喧嘩の後激怒した状態で力任せにダイコンをすりおろすのでこの反応が強く進行するためとされているが、これは、たとえ喧嘩の後でも妻が食事の用意をしたという遠い過去の物語であろう。
このダイコンの辛味物質の2重結合が飽和されたものがスルフォラファンという物質で、これはブロッコリーのガン予防物質として注目されている。この物質は苦味を持つことで従来消費者に嫌われてきたが、育種加工の過程で含量を低下させてきた。
イソチオシアネートに限らず、食品の第3次機能として注目されている活性酸素消去作用 (抗酸化性)、性ホルモン様作用等による生活習慣病の予防、発症遅延に有効とされ注目されている物質群がある。その中でメディアでも頻繁に登場する、フラボノイド、イソフラボノイド、アントシアン、カテキン等のポリフェノール、その他、テルペン、カラシ油配糖体等の生理活性物質のほとんどは消費者に嫌われる苦味、辛味、渋味を有しており、そのあるものは植物由来の有毒物質とされ、味、安全性の両面から、育種、加工の段階で低下、除去しようとしてきたものである。本論の初めに、第2次機能と第3次機能は相容れない場合が多いと記した理由である。
食べるということ
これらの多くは植物の防御物質と考えられるものであり、食べる側は不快味と感ずることでこれを避けることができ、害作用の発現を免れてきた。植物側としても食べられなければそれで良し、特に相手を殺す必要はない。
このようにヒトの脳の旧皮質である大脳辺縁系で自分の不利になる物質を不快味として認識し、いわば本能的にこれを避けてきたが、進化によりその上に積み上げた新皮質で科学という方法により、今まで避けてきたそれら物質に生理機能調節 (第3次機能) という重要な作用がある、ということを明らかにしてきた。
第3次機能を有する物質を摂取しようとする時、その物質を不快味として避けようとする大脳辺縁系の反応に、新皮質からの 「体に良いのだから食べろ」 という指令が勝たなければならないことになるが、そのようないわば本能のコントロールは可能なのだろうか。
私は可能であると考える。というのは、大脳辺縁系には食欲以外の多くの欲望も刷り込まれているが、ヒトは新皮質が作り上げた倫理、法等によりそれ等が剥き出しになることをコントロールしているのであり、食行動についても新皮質が見い出した食品の新たな機能性に基づいた食を楽しむことができるようになる。食べるということが優れて知性的かつ楽しい行為になると考えるからである。
| ページのトップへ |
味はそのものの属性ではなく、食べる側のそのものへの認識による、とされている。自分にとって不利な物質は不快味として認識してそれを避ける。では自分にとって有利なものはどのような味として認識するか、それが快感としての甘味であり、エネルギー、栄養素の存在を示すものである。そして自然界でその甘味を与える物質が砂糖であるが、その砂糖は現在、科学的根拠のない非難の対象となっている。それら誤解のいくつかを紹介する。
砂糖を食べると肥満になるか?
まず、砂糖は肥満を引き起こすという誤解である。肥満が危険なのは、それが動脈硬化を引き起こすためであり、日本でも動脈硬化による心臓病、脳卒中が増加している。肥満は糖尿病、高脂血症、高血圧の引き金になるものであり、肥満が危険とされる理由である。
肥満はあくまでも摂取エネルギーが消費するエネルギーを越えた結果であり、特に砂糖が肥満を引き起こしやすい、砂糖のエネルギーが消費されず蓄積されやすいということはない、どのようなエネルギー源であっても過剰摂取すれば肥満に結び付くものである。
砂糖は血糖値を高めるか?
次に、米国発の俗説として、砂糖は血糖値を高め、それを下げるためにインスリンが多量分泌され、その結果反応性低血糖といわれる血糖値の急激な低下が起こり、それが不安、精神分裂、現代の不登校、校内暴力、家庭内暴力の原因になっているという主張がある。しかし、砂糖が特に血糖値を高めるということはなく、砂糖が特に血糖値を高めるに違いないという思い込みから作り上げたと考えられる上述の主張には根拠がない (図1)。
また、砂糖は血糖値を上げ糖尿病を引き起こすということも強く主張されている。確かに、糖尿病は動脈硬化の非常に強い引き金になる疾病であり日本で急増している大きな問題だが、砂糖との相関は事実であろうか。まず、上述のように砂糖が特に血糖値を高めるということはない。さらに、糖尿病は急増しているが、砂糖消費量は減少しており (図2)、少なくとも正の相関は認められない。
| 図1 血糖上昇反応指数 | 図2 糖尿病患者数の推移と砂糖消費量 | |
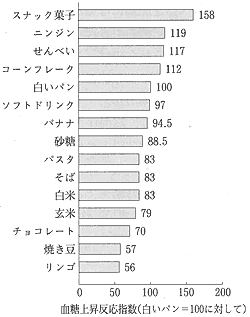 |
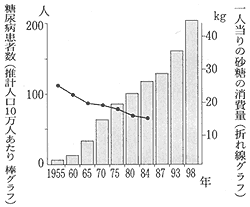 |
|
| (高田明和著『「砂糖は太る」の誤解』 講談社、2001年、より引用) |
砂糖はカルシウムを奪うのか?
先に米国発の俗説を紹介したが、日本の俗説として、砂糖はカルシウムを奪うというものがある。すなわち、砂糖は酸性食品であり体が酸性になるので、それを中和するために骨からカルシウムを溶かし出す、という説である。この酸性食品、アルカリ性食品という分け方は栄養学では100年も前に意味がなくなった概念であるが、未だに 「白砂糖は酸性食品なのでアルカリ性食品である黒砂糖を食べましょう」 等と言う評論家がいる。
では、酸性食品、アルカリ性食品とはどのように定義されるものか、そして何故それが意味を失ったか。
ある食品を完全燃焼させ、残った灰を水に溶解してpHを測定し、それが酸性なら酸性食品、アルカリ性ならアルカリ性食品とするのが定義である。しかし食品を摂取した時はもちろんそのように体内で炎を出して燃えるわけではなく、代謝されて種々の中間体を経て最終的に酸化 (燃焼) される訳で、この途中段階の各代謝産物が生体に種々の影響を与えることになるのだが、酸性食品、アルカリ性食品の定義ではこの酸化途中の代謝物の影響が全く考慮されていない。さらに、食品中のある栄養素がどの程度体内に吸収されるかについても全く考えられていない、等の理由で現在では栄養学的に意味のない概念なのである。たとえその定義に従っても白砂糖はいわゆる酸性食品なのであろうか。砂糖は炭素、水素、酸素からできており、燃やすと完全に水と炭酸ガスになっていしまい何も残らない。したがって、砂糖は酸性食品云々には始めから何の根拠もない。
さらに、酸性食品を食べたら血液が酸性になり、体に悪い、という主張についてであるが、血液のpHは食事に関係なく7.4に保たれており、動いたとしても7.35〜7.45の狭い範囲内である。
砂糖がカルシウムを奪う、という説は2重3重の誤解曲解の上に作り上げられた誤説と言える。
砂糖は脳のエネルギー源
先に血糖値について記したが、食後一時的に上昇した血糖値は直ぐに下がり、糖が消費されると臓器から糖が補給されて血糖値は常に一定に保たれている。血液中の糖はブドウ糖であり、これは神経細胞のエネルギー源なので、常に一定の濃度に保たれていなければならない。砂糖はブドウ糖と果糖が結合したもので、小腸でこの結合が切れながら吸収され、果糖はブドウ糖に変わる。このブドウ糖が神経細胞のエネルギー源なのであり、複雑な神経細胞のネットワークである大脳はその不断の活動のために大量のブドウ糖を消費しなければならない。極端な言い方をすれば、大脳の旧皮質に容量の大きな新皮質を積み上げ、多量の糖を消費して極めて複雑な神経活動を行っているヒトという生物種は、より多量の糖を必要とする方向に進化していると言うことができるのではないだろうか。
|
「今月の視点」 2002年2月 |
●機能性食品 〜 食うものと食われるものと世にありて 〜 北海道大学教授 葛西隆則 |










