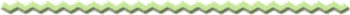���߂Ă̍��Y�r�[�g��
�m���N�ڂ̐��Y�̓t���R���ɔ����n
�@�����ŏ��߂ăr�[�g�̎���������͖̂���4�N�i1971�N�j�ł����A���̓����̉ۂ��߂����ẮA�J��g�_�ƌږ�̂��ق��O���l���m�ŁA�ӌ��̐H�Ⴂ���������̂͐捆�̂Ƃ���ł��B
�@�O�l���������_�̍Œ����A�J��g�͓Ǝ��Ƀt�����X�A�A�����J�A���V�A����r�[�g�̎�q��A�����A�엿�����Ȃǂ��s���Ă��܂����B11�N�i1878�N�j�ɂ�2�N�O�ɊJ�Z��������̎D�y�_�w�Z�i���E�k�C����w�j�ɂ�������˗����A�����ܗʍō�11���A�Œ�6���Ƃ����������ʂ��o�Ă���܂��B���̔N���߂ē��v���Ƀr�[�g�̑����n�ʂ�5,390�сi��20�g���j�Əo�Ă��܂����A13�N�i1880�N�j�ɂ͍�t�ʐς�121.7���i��121ha�j�ƋL�^����Ă���܂��B
�@���āA�����H��ł����A�k�C���͊C�ݐ����珙�X�ɓ������Ɍ����ĊJ�i�߂��A�J��g�͐V�������n��������̍앨��͍����Ă��܂������A�ېV��̖������{�́A�x�������E�B�Y���Ƃ�2�����Ƃ��Čf���Ă��܂����B����n�K�앨�Ƃ��Ẵr�[�g�͔̍|�����ƁA�B�Y���Ƃ̋ߑ�I�����ƈ琬��Ƃ����ѕt���āA�N���[�N�̍��ǂ���{�c�̐����H�ꂪ��ꈁi����ׂj�ɐݒu�����^�тƂȂ�܂����B
�@������ꈁi����ׂj�́A�����ōł��J�i�ݍL���k�n�����������ƁA���i�A���������`�ɋ߂��֗��A�Ȃǂ̗��n������w�i�ɁA13�N�i1880�N�j�Ɍ�����������1���сi��38�g���j�̍H�ꂪ�W�҂̊��҂��W�߂ăX�^�[�g���܂����B�������A�t�����X����A�������r�[�g�𐠂肨�낵�č�`����Ƃ��������̋@�B�́A�̏Ⴊ���o���āA���N�ڂ̑��ƊJ�n�͗��N2���ɂ��ꍞ�݁A�����͓����E�Z���̌J�Ԃ��ŕ��s���܂������A�����Z�p���̂��̂����n�������̂ŁA���ʂ͎U�X�ł����B�r�[�g�̎��n�ʂ�2,500�g�����ł�������A�����̌����i���Ɛ����Z�p�ł����450�g���߂��������ł���v�Z�ɂȂ�܂��B�������A���̔N�͂�������450kg�A1�g���̃t���V�L�u���R���e�i������Ɣ����ɂ������Ȃ��Ƃ����U�X�Ȍ��ʂł����B
�@���̂��߁A��������3���Ɗ����I�������_�ōH����x�~���A���`�����t�����X�̋@�B����A�r�[�g���ׂ����ݎϏo���`���獻�����Ƃ�h�C�c�̍ŐV�s�@�B�ɓ���ւ��Ă��܂��B�܂��N��������T�C�h�����ȂǂƂ������h�C�c�l�Z�p�҂������Ɍق�����Đ��������̌����}�����A��������͏Ē������A�p���v��r��̉a�ɂ���ȂǁA���Y����p�������p�o�c�ɂ����o���܂����B
�@���������̌���ƕ��Y�����p�ŁA��ƂƂ��Ă̌��ʂ������邭�Ȃ�ƁA�L��Ɏ����ōk�n���J���Ă����D�y�ߍx�ł��H��V�@�^�ɉ��t���A23�N�i1890�N�j�ɂ͎D�y�������̕c��H��i���D�y�s����j�����Ƃ��J�n���܂����B�c��H��͌����s�����������ׂ��A���ˁi���Ɓj�i�����`���j�č��̎��l���J����m�n���̍k�n������Ē��c�_��Ƃ�����A�k�ӎ���ƊJ�������˂ĎD�y�ߍx�ɓ��A�������ԓc���i�Ƃ�ł�ւ��j�̊J��n�ɍ͔|�����シ��ȂǁA�����̊m�ۂɖz�����܂����B
�@�R�����b�p�����}�ɁA�N�����R���P�����_��ƊJ�n���s���ԓc�����ł́A�r�[�g�̎�������������ɔz�z������Ȃǂ��܂������A�ԓc���̒��ɂ͐Ⴊ��������ł̖x����A�D�^�i�ł��˂��j�̈��H���^������̂���ɂŁA��������钆�ɂ�������t���C�p�����u��A���b�p�̍��}�ƂƂ��ɑ����̖ڑO�Ŏ�d�������ăA���o�C���������҂������Ƃ����܂��B
�@���ǁA�����̑e���I�Ȕ_�ƌo�c�ł͍��x�W��I�ȃr�[�g�͔|���v���ɔC���Ȃ��������ƂƁA���J�ŏd�ʍ앨�̊��ɂ͉��i�����͂ɖR�����������ƂȂǂ���A��t�ʐς͔���I�ȐL�т͌����܂���ł����B�t�ɁA25�N�i1892�N�j�ɂ͗A����q�̓����x��������Ėʐς͌������A�H�ꑀ�Ɨ����������āA�_���̉�ژ^�̂Ƃ���H����Ɍ������̂ł����A���Ƃ����Ă��A�����푈�I���ɂ���p�̗L�ŁA�l�X�̖ڂ��r�[�g�������Ɉڂ������Ƃ��j�]�̈�ԑ傫�ȗv���ƌ����܂��B
�@�s�[�N�̔N�A��t�ʐς�800ha�A���ʂ�12,000�g���A�Y���ʂ�580�g�����L�^�����r�[�g�́A28�N�i1895�N�j���Ȃē�������p�������A���Y���ĊJ���ꂽ�̂͑吳9�N�i1920�N�j�Ǝl�����I��̂��Ƃł����B
((��)�k�C���Ă�؋���k���@�`�@���A�j
�b�y�[�W�̃g�b�v�ցb
�����̐��Y
�@���Ƃ����тɂ�鍻�����Y�́A12������4������܂ł����̎�Ȑ��Y���Ԃł��B�H��ɔ������ꂽ���Ƃ����т́A�܂��i���������ꂽ��A�d�ʑ��肳��܂��B���̌�ׂ����ӂ���A�~���i���[���[�ݔ��j���f�B�t���[�U�[�ݔ��ŁA���t�ƃo�K�X�ɕ�������܂��B���t�͍X�ɉ��M�A����A�Z�k�A�����i�������j�A�����̍H�����o�đe���i�������j�Ɠ��������Y����܂��B
�o�K�X
�@���Ƃ����т̍i�肩�����o�K�X�ibagasse�j�ƌĂт܂��B���K�X�imegasse�j�ƌĂԒn�������܂��B���Ƃ����т�@�ۏ�ɂȂ�܂ōӂ��ă~���ō�邩�A�܂��̓f�B�t���[�U�[�ŐZ�o���ē��t�����o�����c����o�K�X�ƌĂт܂��B����͂��Ƃ����т̏d�ʂ�25���ʂɂȂ�܂��B
�@���̃o�K�X�͋͂��̓�����45���ʂ̐������܂�ł��܂��B����ꂽ�o�K�X�̓{�C���[�̔R���Ƃ��Ďg���ΐ����H��̂قƂ�ǂ̓d�͂�d�����Ƃ��ł��܂��B�o�K�X�͂��̑��Ɏ��p�C�v�A�ƒ{�̎����A�͔�̌����ɂ��g���܂��
�t�B���^�[�P�[�L
�@�O�r�̓��t�ɔM���������{�����a������Ɛ���ȓ��t�ƒ��a�c��ɕ�����܂��B����ȓ��t����͍����Ɠ����������܂��B���a�c����t�B���^�[�ɂ����A����ɓ��t�����o�����c����t�B���^�[�P�[�L�ƌĂт܂��B���̒��ɂ́A�����₽��ς������܂܂�Ă��܂����A�قƂ�ǂ������Ƃ��т̑@�ە��₫�тɕt�����čH��ɓ����Ă����y���ł��B�����₽��ς����܂܂�Ă��邽�ߔ��y�����ɂ��Ȃ�܂����A���y�͔�ɂ��Ă��Ƃ����є��ɊҌ�������@���ł��L���ȗ��p�@�Ƃ��čs���Ă��܂��
���@��
�@����ȓ��t��Z�k������A���������o�����������Ƃ����܂��B�������H��ł͓��t��3��������č�����������܂��B����ȏ�J��Ԃ����Ƃ̓R�X�g�Ƃ̌��ˍ����ł��B�����̓x�ɍ����Ɠ����������܂����A�Ō�̐����ɂ���ē���ꂽ�����͔p�����Ƃ����܂��B�d�ʔ�ł��Ƃ����т�3���߂��ʂƂȂ�܂��B�����̓A���R�[�����y�̌����A�����A���̑��ꕔ�H�i�ɗ��p����܂��B�����������H��͓s�s�����痣��Ă��邱�Ƃ������A���i���Ǝ��v�E���ʂ̊W����H��P�Ƃł̎��g�݂͂قƂ�Ǖs�\�ȏꍇ�������̂ŁA���n�̑傫�ȍH��ɏW�ς��ꂽ��A���i�����s�Ȃ��Ă���悤�ł��B
������
�@�@���Ƃ����ђ���t�߂̓������قƂ�NJ܂܂Ȃ������̏������icane top�j�ƌĂт܂��B���Ƃ����т̎��n�ɂ͓��͂ɂ����@�Ƌ@�B�ɂ����@������܂��B�䂪���ł��D�G�Ȏ��n�@�B���J�����y���A�@�B���n���ǂ�ǂ��Ă��Ă��܂��B
�@���Ƃ����э�n�т͑䕗��P�n�тł�����A�ЂƂ��ё䕗�ɑ����A���Ƃ��b�݂̉J�������炵���Ƃ��Ă��߂���߂���ɓ|�����Ă��܂��̂ŁA���Ƃ����т̓��̕��͕s�����ɂȂ�܂��B�������܂܂������ɂ͕s�K�v�Ȃ��̕��������ꂢ�ɋ@�B�Ŏ�菜�����Ƃ͕s�\�ł��B����Ȃ��Ƃ����шȊO�́A�g���b�V���ƌĂ�܂����A���������g���b�V���ł��B�@�B���n��������ɏ]���āA�H��ɂ̓g���b�V�����ǂ�ǂ��������āA�����H��ɂ͑傫�ȃ}�C�i�X�v���ƂȂ��Ă��Ă��܂��B���̂��ƌ����܂��ƁA�������܂�ł��Ȃ��g���b�V�����~���i����@�j���o�ăo�K�X�ƂȂ������ɂ́A3���߂��������܂�ł���A����ΓD�_�݂����ȑ��݂Ȃ̂ł��B������́A���̏������ɑ����܂܂�铜���ȊO�̕�������������̎ז������č����̉����W���Ă��邩��Ȃ̂ł��B���n�̋@�B����i�߂邱�Ƃƃg���b�V������菜���ݔ�������邱�ƂƂ͓����ɐi�s���Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�����A�ƒ{�ɂƂ��Ă͑�ς悢�����ɂȂ�܂�����A�{�Y�_�ƂƂ̘A�g���Ƃ��A�L�����p����Ă��鎖�������܂��B
�i�쐼����(��)�@���P�@�N��j
�b�y�[�W�̃g�b�v�ցb
�@�������ł́A�䂪���ɂ����鍻���̗��j�ɂ��ĐG��Ă݂����Ǝv���܂��B
�@�l�ނ��ŏ��ɏo������Ö��́A�Ñ�G�W�v�g�̕lj悩������炩�Ȃ悤�ɖI���Ƃ���Ă��܂��B�lj�ł��`����邮�炢�Ȃ̂ł�����A�����ɏd�v�ł����������f���܂��B���̂悤�ɊÖ��̗��j�͌Â��A�l�ނ̗��j�Ƃ͖��ڂȊW�ɂ���A����̉�X�̐H��������Ö���������Ƃ������Ƃ͂܂��z���ł��Ȃ����Ƃł��B
�@���āA�ŋ߂ł̓X�e�r�A�A�L�V���g�[���������ޗ��Ƃ���َq������������ȂǁA�ߋ��Ɣ�ׂ�A�Ȋw�̐i���ɂƂ��Ȃ��ĊÖ��̎�ނ͐�����Ȃ��قǑ������Ǝv���܂��B�������A���̒��ł������قǐl�ނ̗��j�Ɛ[���ւ�荇���Ă������̂͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�䂪���ɂ����鍻���̗��j�͌Â��A�������㏉���i825�N�j�A�`����t��������A�������Ƃ��̌����ژ^�̒��ɍ������������Ă��܂��B�����A�����͑�ςȋM�d�i�ł��������߁A�����ꕔ�̏㗬�K�����p���A������H�p�ł͂Ȃ��ނ����p�ł����B���̌�A���q���㖖������嗤�f�Ղ�����ɂȂ�A�����̗A�����������܂����B�܂��A���y����R����i1523�N�j�ɂ̓|���g�K���l����q���ɏ㗤���A�����������Ƃ����J�X�e���A�R���y�C�g�E�Ȃǂ̓�؉َq�������炵���̂ł����A�����̑嗤�f�Ղ̕i�ڂ̒��ł͐����A���D���A�ȐD���Ɏ����d�v�A���i�������ł����B
�@�]�ˎ���ɓ���ƁA�����͍�����Ԃł��������߁A����̏o�������ɖf�Ղ̑��������肳��Ă����̂ŁA��������肷��̂�����ł����B����f���Ă�������܂��A1610�N�ɉ����哇�ɂ����č������̐����ɐ��������ƋL�^����Ă��܂��B���̌�A�����哇�A��E���A���V���y�ї����i���Ƃ����э͔|�͉����哇���Â����A�F���˂̊NJ����ɒu���ꂽ�̂�1609�N�ȍ~�j�ɂ����Ă��Ƃ����т͑��Y����A�NJ����Ă����F���˂ɔ���Ȏ��v�������炵�܂����B�]�ˎ���̒����ȍ~�A���Ƃ����э͔|�́A������{�̋C�g�Ȓn��ɂ����ĐϋɓI�ɂƂ肢����Ă����܂����B
�@��������ɓ��荽�����x�͉�����A�s�������̉��ŗA�������������ɗ��ꍞ�݁A���Y���͉��ꥉ��������������ȃ_���[�W����ł��܂����B���̌�A�����푈�Ő폟���ƂȂ����䂪���́A��������p������A��p�o�c�̒��Ƃ��Đ����Ƃ��ʒu�t������ƂƂ��ɁA�����E�Ȃǂ���̏o���ɂ��@�B�����ꂽ��H��ɂ��ߑ㐻���Ƃ��m������܂��B�����č����ɂ��������̋ߑ�H�ꂪ���݂���A�䂪���̍����̐��Y�̐�����������Ă������ƂƂȂ�܂����B
�@�������A�����m�푈�ɓ˓�����ƁA��p�Ő��Y���ꂽ�e���������ɗA�����邱�Ƃ�����ƂȂ�A�����̍����s���͐[���Ȃ��̂ƂȂ�܂����B
�@�푈���I�����A�s�퍑�ƂȂ����䂪���ɂ͋͂��ȍ��������Ȃ��A1952�N�i���a27�N�j��3���܂Ŕz�����ƂȂ�܂����B�H����̏ɂ����������ɂƂ��ĊÖ��͔��ɋM�d�ȑ��݂ł���A���̎��v�ɑ��Ĕz������鍻�������ł͕₦�Ȃ��ł��������߁A�ꎞ���Y���`���i���a44�N���K���̋^��������Ƃ��Ďg�p�֎~�j��T�b�J�����i���a48�N���K���̋^��������Ƃ��Ďg�p�֎~�j�Ȃǂ̐l�H�Ö��������Ă͂₳��܂����B�₪�Đ��̕����ƂƂ��ɍ����̏���ʂ͔���I�ɐL�сA�����Ɏ����Ă��܂��B
�@���̂悤�ɁA�䂪���̗��j�ƍ����Ƃ͖��ڂȊW�ɂ���܂��B���̂悤�Ȋϓ_���獻���Ƃ������̂����ߒ����Ă͂������ł��傤���B
�i�_�ѐ��Y�ȍ����މہj
�b�y�[�W�̃g�b�v�ցb
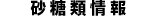
�u���������m���v�C���f�b�N�X��