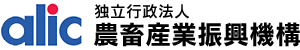ホーム > 砂糖 > 各国の砂糖制度 > インドの砂糖産業及び砂糖政策の概要
最終更新日:2010年3月6日

 |
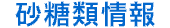 |
 |
こうしたインドの砂糖産業及び政策について、英国の調査会社LMC International Ltd.からの報告をもとに企画情報部で取りまとめたのでその概要を紹介する。
| 企画情報部 |
| 【砂糖産業に関する全般的な情報】 |
| ●国内需給バランス ●生産実績等 |
| ●生産量及び消費量 ●異性化糖の位置付け |
| 【砂糖制度の主要な特徴】 |
| ●生産規制 ●国内の価格支持 ●販売方法 |
| ●栽培者と製糖業者の関係 |
| 【砂糖産業の現状】 |
| ●さとうきびの圧搾と精製産業の構造 ●砂糖の流通 |
【砂糖産業に関する全般的な情報】
国内需給バランス
インドは、ブラジルと並び世界最大の砂糖生産国の1つである。インドの分みつ糖(centrifugal sugar)生産量は、過去40年間で急速に増加している(グラフ1)が、1995/96年に1,775万トンのピークに達した後、1997/98年には、1,386万トンまで減少した。また、消費量は、生産量とほぼ同じ水準で推移しているが、恒常的な輸出国となっていない点でブラジルと異なっている。
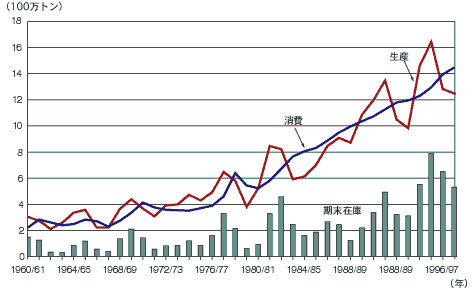
また、分みつ糖に加えて、インドでは、グル(gur)とカンサリ(khandsari)というさとうきびを原料としたオープン・パン・シュガー(open-pan sugar)といわれる伝統的な含みつ糖を大量に生産している。これらの砂糖は、何百年もの歴史があるが、分みつ糖は、1920年代に初めて確立された比較的新しいものである。グルは、さとうきびのジュースをオープン・パンで沸騰させることによって製造され、ケーキまたはスラブという板状の形のものであり、従来、砂糖生産量のほとんどを占めていた。もう1つのカンサリは、清浄化したさとうきびシロップをオープン・パンで煮詰めることによって生産されている。
1997/98年のグル及びカンサリの生産量、約1,068万トンと分みつ糖の生産量を加えるとインドのさとうきびを原料とする甘味料の総生産量は、2,454万トンという膨大な量となる。
分みつ糖の消費量は、1993/94年〜1997/98年の期間中に徐々に増加しているが、生産量は、1996/97年には対前年21%減少し、1997/98年にはほぼ前年並みであったが、1998/99年度には、1,600万トン(粗糖換算)に達する見込みである(表1)。
1997/98年のグル及びカンサリの生産量、約1,068万トンと分みつ糖の生産量を加えるとインドのさとうきびを原料とする甘味料の総生産量は、2,454万トンという膨大な量となる。
分みつ糖の消費量は、1993/94年〜1997/98年の期間中に徐々に増加しているが、生産量は、1996/97年には対前年21%減少し、1997/98年にはほぼ前年並みであったが、1998/99年度には、1,600万トン(粗糖換算)に達する見込みである(表1)。
| 表1:分みつ糖の需給バランス | ||||||||||||
| (単位:1,000トン、粗糖換算) | ||||||||||||
|
| ページのトップへ |
生産実績等
1994/95年〜1997/98年の平均収穫面積は、約400万haで、全農地の2%を占め、さとうきびの生産総額は農業生産総額の6%を占めている。また、さとうきび栽培者は、約500万人であり、平均収穫面積は1ha弱である。1996/97年の分みつ糖生産量は、さとうきび収穫面積及び単収の減少にともなって大きく減少した(表2)。
| 表2:生産量等の実績 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 注・1 さとうきびの生産総額は、さとうきび生産量に農場経営者のさとうきび1トン当たり手取額をかけたもの。 n.a.= データなし。 |
さとうきびの栽培地域は、インド全域にまたがるが、主に2つの地域に集中している。最大の栽培地域は、北部亜熱帯地域であり、インド最大の生産地ウタル・プラデシュ州を含む。この地域は、全栽培面積の70%を占めている。栽培面積のほぼ30%を占める第2の栽培地域は、西部のマハラシュトラ州から南下して、カルナタカ州とアンドラ・プラデシュ州を経て、南部のタミルナドゥ州にいたる熱帯地域である。
ウタル・プラデシュ州は、インドの全栽培面積の約45%を占めているが、その生産量の約半分は、グル及びカンサリ製造に使用されるため、分みつ糖の生産量ではインド全体の約30%を占めるにすぎない。マハラシュトラ州は、栽培面積ではウタル・プラデシュ州の4分の1にすぎないが、単収が高く、そのさとうきびのほとんどを分みつ糖製造用としていることから、国内分みつ糖生産量の約30%を占める。
マハラシュトラ州は、灌漑用水の充実及び集中的な化学肥料の投与などのため、ウタル・プラデシュ州より単収及びショ糖含有率がはるかに高い。1994/95年〜1997/98年のマハラシュトラ州の平均単収は81トン/ha、ウタル・プラデシュ州は59トン/haである。同期間中のマハラシュトラ州の平均ショ糖含有率は12.8%、ウタル・プラデシュ州は11.7%であった。タミルナドゥ州などの南部地域のさとうきび平均単収は高く、1994/95年〜1997/98年の平均では106トン/haであった。しかし、この地域においては、寒暖の差が少ないため、ショ糖含有率は低く、平均10.5%となっている。
ウタル・プラデシュ州は、インドの全栽培面積の約45%を占めているが、その生産量の約半分は、グル及びカンサリ製造に使用されるため、分みつ糖の生産量ではインド全体の約30%を占めるにすぎない。マハラシュトラ州は、栽培面積ではウタル・プラデシュ州の4分の1にすぎないが、単収が高く、そのさとうきびのほとんどを分みつ糖製造用としていることから、国内分みつ糖生産量の約30%を占める。
マハラシュトラ州は、灌漑用水の充実及び集中的な化学肥料の投与などのため、ウタル・プラデシュ州より単収及びショ糖含有率がはるかに高い。1994/95年〜1997/98年のマハラシュトラ州の平均単収は81トン/ha、ウタル・プラデシュ州は59トン/haである。同期間中のマハラシュトラ州の平均ショ糖含有率は12.8%、ウタル・プラデシュ州は11.7%であった。タミルナドゥ州などの南部地域のさとうきび平均単収は高く、1994/95年〜1997/98年の平均では106トン/haであった。しかし、この地域においては、寒暖の差が少ないため、ショ糖含有率は低く、平均10.5%となっている。
| ページのトップへ |
生産量及び消費量
表3は、分みつ糖並びにグル及びカンサリの生産実績を示している。
| 表3:砂糖生産量の内訳 | ||||||||||||
|
インドで生産されている分みつ糖のほとんどは、耕地白糖(原料産地で搾汁から直接つくられる白糖)である。粗糖の生産は、ごく僅かですべてが輸出されている。日本でいう精製糖の生産も、ごく僅かで5つ星ホテルや航空会社によって利用されるにすぎない。しかし、需要の高まりからシロップ清浄システム(syrup clarification system)を導入し、精製糖に近い白糖を生産するようになっている。
インドの分みつ糖生産量のほとんどを占める白糖は、3つの品質等級(29、30及び31)と3つのサイズ等級(小、中及び大)に分類されている。等級29は最低品質で、150ICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)単位を超える色価をもち、等級30はインドにおいて最も一般的に生産されている等級であり、100〜150ICUMSA単位の色価をもっている。等級31は色価約50ICUMSA単位の砂糖で、高品質砂糖の需要の高まりに対応するために、1997年に導入された。ほとんどの白糖は小さなサイズの粒子である。
表4は、1994/95年〜1997/98年の砂糖消費量の内訳を示している。1997/98年においては、家庭消費が総消費量の約26%を占めているが、そのシェアは低下し工業用消費が増大する傾向にある。
インドの食品加工業には、国内販売のための製品を製造する極めて小規模な家内工業が含まれている。これらは、砂糖の工業用部門に分類されている。
工業部門でのインドで最大の白糖ユーザーは、飲料製造部門であり、1997/98年には総消費量の約24%を占めている。この部門には、小規模な茶の販売業者によって使用される大量の白糖が含まれている。2番目に大きなユーザーは、菓子製造部門であり、1997/98年には総消費量の17%を占めており、伝統的な砂糖菓子やチューイング・パアン(chewing paan)(消化を助けるため、インドにおいて一般的に食されるもので、砂糖、ビンロウ、スパイスを葉でまいたもの)に加えられる大量の白糖が含まれている。この両部門での消費量は増加傾向にある。
1997/98年の白糖の1人当たり年間消費量は15.8kgで、グル及びカンサリの1人当たり消費量は11.1kgである。1960年には、グル及びカンサリの1人当たり消費量は15.4kg、白糖の1人当たりの消費量は4.8kgであったが、白糖は徐々にそのシェアを増大しつつある。
インドの分みつ糖生産量のほとんどを占める白糖は、3つの品質等級(29、30及び31)と3つのサイズ等級(小、中及び大)に分類されている。等級29は最低品質で、150ICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)単位を超える色価をもち、等級30はインドにおいて最も一般的に生産されている等級であり、100〜150ICUMSA単位の色価をもっている。等級31は色価約50ICUMSA単位の砂糖で、高品質砂糖の需要の高まりに対応するために、1997年に導入された。ほとんどの白糖は小さなサイズの粒子である。
表4は、1994/95年〜1997/98年の砂糖消費量の内訳を示している。1997/98年においては、家庭消費が総消費量の約26%を占めているが、そのシェアは低下し工業用消費が増大する傾向にある。
インドの食品加工業には、国内販売のための製品を製造する極めて小規模な家内工業が含まれている。これらは、砂糖の工業用部門に分類されている。
工業部門でのインドで最大の白糖ユーザーは、飲料製造部門であり、1997/98年には総消費量の約24%を占めている。この部門には、小規模な茶の販売業者によって使用される大量の白糖が含まれている。2番目に大きなユーザーは、菓子製造部門であり、1997/98年には総消費量の17%を占めており、伝統的な砂糖菓子やチューイング・パアン(chewing paan)(消化を助けるため、インドにおいて一般的に食されるもので、砂糖、ビンロウ、スパイスを葉でまいたもの)に加えられる大量の白糖が含まれている。この両部門での消費量は増加傾向にある。
1997/98年の白糖の1人当たり年間消費量は15.8kgで、グル及びカンサリの1人当たり消費量は11.1kgである。1960年には、グル及びカンサリの1人当たり消費量は15.4kg、白糖の1人当たりの消費量は4.8kgであったが、白糖は徐々にそのシェアを増大しつつある。
| 表4:砂糖消費量の内訳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:1,000トン、粗糖換算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページのトップへ |
異性化糖の位置付け
インドにおいては、異性化糖は生産されておらず、また消費もされていない。
| ページのトップへ |
【砂糖制度の主要な特徴】
インドの砂糖政策は、極めて複雑である。中央政府と州政府は、生産、販売及び消費のすべての段階で介入している。中央政府は、消費者への安価な供給を目標とし、州政府は、農場経営者側のロビー活動に対応するため、さとうきび価格を高く維持することを目指していることから、両者はしばしば相対立する。
さとうきび生産は、化学肥料、水資源及び電気などに対する補助金、並びにさとうきび価格を高めに維持することによって支持されている。中央政府が、農場経営者の所得維持のために定める「法定最低価格(SMP:Statutory Minimum Price)」は、州政府によって定められる州勧告価格(SAP:State Advised Price)がSMPより高いために有名無実な存在となっている。
製糖工場には、民間、公共及び協同組合経営の3種類の形態があり、協同組合経営の製糖工場は、その経営収支に基づいて原料代を支払うが、他の2形態(民間、公共)の製糖工場は、実質SAPにより原料代を支払うこととなっている。
一方、中央政府は、一部の白糖(白糖生産量の40%)を「徴収砂糖(levy sugar)」として国内自由市場価格より安価に流通させるため、公共流通制度(PDS:Public Distribution System)を導入している。残りの60%は、自由市場に販売することができるが、これについても毎月の割当によって厳しく規制されている。
白糖生産量は、過去4年間、周期的に増減した。製糖工場は、その地域のすべてのさとうきびを高い固定価格で購入しなければならない。したがって、収穫量が多い年には白糖の供給過剰が国内価格を押し下げ、製糖工場の栽培者への原料代の支払いを困難とさせ、多額の未払金を生じさせる。このことが、栽培面積の減少を招き、生産量の減少につながる。その結果、白糖の市場価格が高くなり、製糖工場の原料代の支払いを可能とし、再び栽培者をさとうきび栽培に引き戻すことになる。
砂糖政策の改革への圧力は、徐々に大きくなっている。中央政府は、1998年9月製糖工場の創業または設備拡張に対する許可制度を廃止した。また、インドの砂糖政策の有効性を分析するために高級委員会(high-level committee)が創設され、「徴収砂糖」販売の撤廃、砂糖販売に対する入札制度の導入、流通段階における規制の撤廃等の勧告を行っている。政府は、現在実施に向けて検討している。
さとうきび生産は、化学肥料、水資源及び電気などに対する補助金、並びにさとうきび価格を高めに維持することによって支持されている。中央政府が、農場経営者の所得維持のために定める「法定最低価格(SMP:Statutory Minimum Price)」は、州政府によって定められる州勧告価格(SAP:State Advised Price)がSMPより高いために有名無実な存在となっている。
製糖工場には、民間、公共及び協同組合経営の3種類の形態があり、協同組合経営の製糖工場は、その経営収支に基づいて原料代を支払うが、他の2形態(民間、公共)の製糖工場は、実質SAPにより原料代を支払うこととなっている。
一方、中央政府は、一部の白糖(白糖生産量の40%)を「徴収砂糖(levy sugar)」として国内自由市場価格より安価に流通させるため、公共流通制度(PDS:Public Distribution System)を導入している。残りの60%は、自由市場に販売することができるが、これについても毎月の割当によって厳しく規制されている。
白糖生産量は、過去4年間、周期的に増減した。製糖工場は、その地域のすべてのさとうきびを高い固定価格で購入しなければならない。したがって、収穫量が多い年には白糖の供給過剰が国内価格を押し下げ、製糖工場の栽培者への原料代の支払いを困難とさせ、多額の未払金を生じさせる。このことが、栽培面積の減少を招き、生産量の減少につながる。その結果、白糖の市場価格が高くなり、製糖工場の原料代の支払いを可能とし、再び栽培者をさとうきび栽培に引き戻すことになる。
砂糖政策の改革への圧力は、徐々に大きくなっている。中央政府は、1998年9月製糖工場の創業または設備拡張に対する許可制度を廃止した。また、インドの砂糖政策の有効性を分析するために高級委員会(high-level committee)が創設され、「徴収砂糖」販売の撤廃、砂糖販売に対する入札制度の導入、流通段階における規制の撤廃等の勧告を行っている。政府は、現在実施に向けて検討している。
| ページのトップへ |
生産規制
製糖工場の拡張を制限し多数の比較的小規模な製糖工場の開発を奨励していた許可制度の廃止以降、新しい製糖工場が操業する際の唯一の制限は、その所在距離(既存の製糖工場から少なくとも15km離れたところに所在しなければならない)のみである。
各製糖工場は、州政府によってさとうきび栽培区域を割り当てられているが、区域の拡大を出願する権利を持っている。
グルとカンサリの生産者は、比較的自由に操業することを許可されている。原料価格及び販売価格に対する制限はなく、分みつ糖の製糖工場から5 離れていれば、自由に新しい工場を開業することができる。
各製糖工場は、州政府によってさとうきび栽培区域を割り当てられているが、区域の拡大を出願する権利を持っている。
グルとカンサリの生産者は、比較的自由に操業することを許可されている。原料価格及び販売価格に対する制限はなく、分みつ糖の製糖工場から5 離れていれば、自由に新しい工場を開業することができる。
| ページのトップへ |
国内の価格支持
さとうきび価格は、中央政府及び州政府によって決定される。中央政府は、適正な原料供給を保証することを目的とし、さとうきび及び他農作物の生産コスト推定値に基づいて、法定最低価格(SMP)を定めている。一方、州政府は、政策的な理由によって(強力な農場経営者側のロビー活動の支持を得るため)、州勧告価格(SAP)をSMPより高い水準に定めている。
白糖の販売は、自由市場販売と徴収砂糖販売に分けられている。製糖工場が受け取る徴収砂糖価格は、中央政府によって定められており、自由市場価格より低く設定されている(国内自由市場砂糖価格の約75%)。中央政府は、製糖工場がさとうきびに対してSMPを支払うことを想定して、徴収砂糖価格を定めている。しかし、協同組合形態の経営を除き、製糖工場は、SMPよりはるかに高いSAPを原料代として支払っているため、徴収砂糖価格は、しばしば製糖工場の生産コストを下回り、製糖工場の経営を圧迫している。
市場価格は、自由に決定されるが、政府は毎月の販売割当を通して、消費者価格が急激に上昇しないよう配慮している。
表5は、1994/95年〜1997/98年のさとうきびと砂糖の平均価格を示している。国内自由市場価格は、輸出平価の水準を上回っていることから、製糖業者は世界自由市場に白糖を輸出することに積極的ではない。インドは、EUへの特恵白糖輸出(年間20,000トン)についてのみ、高い価格を受け取っている。
さとうきびと砂糖の価格への規制に加えて、州政府と中央政府は、製糖工場のさとうきびの購入及び徴収砂糖と自由市場砂糖の販売に異なる水準の課税額を定めている(中央政府による税率は徴収砂糖520ルピー/トン、自由市場砂糖850ルピー/トンであり、これ以外に州によって異なるか?概ね1%の地方税が課せられる。)。
グル及びカンサリに対しては価格規制はなく、購入価格と販売価格を自由に交渉することができる。さとうきびの収穫量が多い場合には、製造業者は市場価格を反映し原料代を下げることができる。収穫量が少ない場合には、製造業者は分みつ糖製糖工場によって支払われているSAPに極めて近い価格を提示することとなる。グルの価格は、一般に徴収砂糖の価格に近く、カンサリの価格は、自由市場砂糖価格に近い。また、グルとカンサリには中央政府による課税はない。
白糖の販売は、自由市場販売と徴収砂糖販売に分けられている。製糖工場が受け取る徴収砂糖価格は、中央政府によって定められており、自由市場価格より低く設定されている(国内自由市場砂糖価格の約75%)。中央政府は、製糖工場がさとうきびに対してSMPを支払うことを想定して、徴収砂糖価格を定めている。しかし、協同組合形態の経営を除き、製糖工場は、SMPよりはるかに高いSAPを原料代として支払っているため、徴収砂糖価格は、しばしば製糖工場の生産コストを下回り、製糖工場の経営を圧迫している。
| 表5:さとうきびと白糖の平均価格 〔1994/95〜1997/98年平均〕 | ||||||||
| (US$/トン) | ||||||||
| ||||||||
| 注)さとうきび価格は、各地域のSAPの加重平均である。 |
表5は、1994/95年〜1997/98年のさとうきびと砂糖の平均価格を示している。国内自由市場価格は、輸出平価の水準を上回っていることから、製糖業者は世界自由市場に白糖を輸出することに積極的ではない。インドは、EUへの特恵白糖輸出(年間20,000トン)についてのみ、高い価格を受け取っている。
さとうきびと砂糖の価格への規制に加えて、州政府と中央政府は、製糖工場のさとうきびの購入及び徴収砂糖と自由市場砂糖の販売に異なる水準の課税額を定めている(中央政府による税率は徴収砂糖520ルピー/トン、自由市場砂糖850ルピー/トンであり、これ以外に州によって異なるか?概ね1%の地方税が課せられる。)。
グル及びカンサリに対しては価格規制はなく、購入価格と販売価格を自由に交渉することができる。さとうきびの収穫量が多い場合には、製造業者は市場価格を反映し原料代を下げることができる。収穫量が少ない場合には、製造業者は分みつ糖製糖工場によって支払われているSAPに極めて近い価格を提示することとなる。グルの価格は、一般に徴収砂糖の価格に近く、カンサリの価格は、自由市場砂糖価格に近い。また、グルとカンサリには中央政府による課税はない。
| ページのトップへ |
販売方法
白糖の販売についても詳細な規則がある。各製糖工場の徴収砂糖は、PDSに基づき販売されなければならない。そして、低所得消費者が安価な白糖を入手できるようにするための配給カード制度(ration card system)を通して、低価格で販売される。残りの白糖は、国内自由市場に販売することができる。
1970年代末以降、徴収砂糖の総販売量に占める割合は、徐々に低下し、1992/93年に徴収砂糖の割合が引き下げられて以来40%となっている。製糖工場は、最低の品質及びサイズの白糖を徴収砂糖として販売し、より良質の白糖はプレミアムをつけて自由市場向けに販売している。新たに許可された製糖工場は、最初の数年間は全て自由市場に販売することを許可されている。
自由市場への白糖の販売もまた規制されている。中央政府は、国内の需給推定に基づいて毎月の割当を定め、製糖工場に分配する。製糖工場は、定められた月内に割当のすべてを販売しなければならず、さもないとその白糖は徴収砂糖として取り扱われることとなる。さらに、製糖工場は、定められた月の前半の2週間と後半の2週間で、割当の販売を等分に分割しなければならない(若干の調整は許可されており、いずれかの2週間に、最大52.5%まで、最低47.5%まで販売することができる)。
製糖工場は、エンド・ユーザーまたは許可されている取引業者に自由市場砂糖を販売することができる。取引業者は、常時保有できる白糖を最大50トンと制限されているほか、15日以内にエンド・ユーザーに白糖の在庫を販売しなければならない。これは、市場価格が投機的活動によって損なわれないようにすることを目的としている。
1997年1月以降、輸出の許可は、政府機関「農業加工食品輸出開発協会(APEDA:the Agricultural and Processed Food Export Development Association)」の規制下に置かれている。政府がその年の輸出割当を発表すると、製糖工場はAPEDAから許可を得て、砂糖を輸出することができる。しかし、(表5に示されているとおり)国内自由市場価格が輸出平価を上回っているため、製糖工場は輸出することによって不利益を被る。
砂糖の輸入は、1991年以前には厳しく規制されていた。政府による一元輸入であり、高い関税が国内の砂糖業界を保護していた。1991年に、国内の砂糖不足により輸入関税をゼロにし、民間部門に貿易を開放した。輸入された砂糖は、国内市場で自由に販売することができ、課税されることはない。1998年4月に、政府は、砂糖の輸入に対して、5%の関税と850ルピー/トンの相殺関税を導入した。
インドは、GATTウルグアイ・ラウンド合意によって、2004/5年までに砂糖関税を150%とするよう約束しているが、現在の関税は、この水準をはるかに下回っている。
1970年代末以降、徴収砂糖の総販売量に占める割合は、徐々に低下し、1992/93年に徴収砂糖の割合が引き下げられて以来40%となっている。製糖工場は、最低の品質及びサイズの白糖を徴収砂糖として販売し、より良質の白糖はプレミアムをつけて自由市場向けに販売している。新たに許可された製糖工場は、最初の数年間は全て自由市場に販売することを許可されている。
自由市場への白糖の販売もまた規制されている。中央政府は、国内の需給推定に基づいて毎月の割当を定め、製糖工場に分配する。製糖工場は、定められた月内に割当のすべてを販売しなければならず、さもないとその白糖は徴収砂糖として取り扱われることとなる。さらに、製糖工場は、定められた月の前半の2週間と後半の2週間で、割当の販売を等分に分割しなければならない(若干の調整は許可されており、いずれかの2週間に、最大52.5%まで、最低47.5%まで販売することができる)。
製糖工場は、エンド・ユーザーまたは許可されている取引業者に自由市場砂糖を販売することができる。取引業者は、常時保有できる白糖を最大50トンと制限されているほか、15日以内にエンド・ユーザーに白糖の在庫を販売しなければならない。これは、市場価格が投機的活動によって損なわれないようにすることを目的としている。
1997年1月以降、輸出の許可は、政府機関「農業加工食品輸出開発協会(APEDA:the Agricultural and Processed Food Export Development Association)」の規制下に置かれている。政府がその年の輸出割当を発表すると、製糖工場はAPEDAから許可を得て、砂糖を輸出することができる。しかし、(表5に示されているとおり)国内自由市場価格が輸出平価を上回っているため、製糖工場は輸出することによって不利益を被る。
砂糖の輸入は、1991年以前には厳しく規制されていた。政府による一元輸入であり、高い関税が国内の砂糖業界を保護していた。1991年に、国内の砂糖不足により輸入関税をゼロにし、民間部門に貿易を開放した。輸入された砂糖は、国内市場で自由に販売することができ、課税されることはない。1998年4月に、政府は、砂糖の輸入に対して、5%の関税と850ルピー/トンの相殺関税を導入した。
インドは、GATTウルグアイ・ラウンド合意によって、2004/5年までに砂糖関税を150%とするよう約束しているが、現在の関税は、この水準をはるかに下回っている。
| 表6:現在のインドにおける貿易政策 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 出典:LMC、WTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ページのトップへ |
栽培者と製糖業者の関係
さとうきび価格の決定プロセスは、製糖工場の経営形態によって異なっている。協同組合の経営ではない製糖工場は、中央政府または州政府によって定められるSMPまたはSAPにおいて原料を購入することを義務付けられている。協同組合である製糖工場は、その製糖工場の経営収支に基づいて、さとうきび価格を決定することができる。
中央政府によって定められているSMPは、歩留り8.5%という前提に基づいて決定されており、生産地域内の平均歩留りに応じて調整される。
州政府が定めるSAPは、SMPより高い水準に定められているため、実際にはSAPが採用される。ウタル・プラデシュ州を含むほとんどの北部の州におけるSAPは、同一価格である。タミルナドゥ州やアンドラ・プラデッシュ州などの南部の州では、SAPは、基本さとうきび価格(8.5%の歩留り)をその実績に応じて、調整し決定されている。
各製糖工場は、通常さとうきび監督官(Cane Commissioner)によってさとうきび栽培区域を割り当てられているが、区域の拡大を出願する権利を持っている。過去には、栽培者は定められた区域内の製糖工場に納入しなければならなかったが、最近の判例では、どの製糖工場にさとうきびを納入しても良いとしている。これは、特に協同組合経営の非能率的な製糖工場には脅威となっている。協同組合経営の製糖工場は、その経営収支に基づいてさとうきび価格を支払っているからである。
ウタル・プラデシュ州においては、製糖工場と栽培者間の関係は、さとうきび協同組合(Cane Co-operative Societies)の存在によって複雑になっている。同組合は、栽培者と製糖工場の間の仲介者としての役割を果たしており、原料さとうきびの納入に介入し、原料代の一部(約3%)を留保し、残りを栽培者に引き渡している。また、政治的には力を持っているが、さとうきび納入量等の調整をすることができないため、製糖工場からも不満が多い。製糖工場に納入される前に集積場に何日も保管されるため、品質面で問題となるからである。
他の州では、製糖工場と栽培者の間の関係は緊密であるため、さとうきびの品質を考慮し、製糖工場への原料の納入量は調整されている。
中央政府によって定められているSMPは、歩留り8.5%という前提に基づいて決定されており、生産地域内の平均歩留りに応じて調整される。
州政府が定めるSAPは、SMPより高い水準に定められているため、実際にはSAPが採用される。ウタル・プラデシュ州を含むほとんどの北部の州におけるSAPは、同一価格である。タミルナドゥ州やアンドラ・プラデッシュ州などの南部の州では、SAPは、基本さとうきび価格(8.5%の歩留り)をその実績に応じて、調整し決定されている。
各製糖工場は、通常さとうきび監督官(Cane Commissioner)によってさとうきび栽培区域を割り当てられているが、区域の拡大を出願する権利を持っている。過去には、栽培者は定められた区域内の製糖工場に納入しなければならなかったが、最近の判例では、どの製糖工場にさとうきびを納入しても良いとしている。これは、特に協同組合経営の非能率的な製糖工場には脅威となっている。協同組合経営の製糖工場は、その経営収支に基づいてさとうきび価格を支払っているからである。
ウタル・プラデシュ州においては、製糖工場と栽培者間の関係は、さとうきび協同組合(Cane Co-operative Societies)の存在によって複雑になっている。同組合は、栽培者と製糖工場の間の仲介者としての役割を果たしており、原料さとうきびの納入に介入し、原料代の一部(約3%)を留保し、残りを栽培者に引き渡している。また、政治的には力を持っているが、さとうきび納入量等の調整をすることができないため、製糖工場からも不満が多い。製糖工場に納入される前に集積場に何日も保管されるため、品質面で問題となるからである。
他の州では、製糖工場と栽培者の間の関係は緊密であるため、さとうきびの品質を考慮し、製糖工場への原料の納入量は調整されている。
| ページのトップへ |
【砂糖産業の現状】
さとうきびの圧搾と精製産業の構造
インドの製糖工場には、前述のように3種類の所有形態(民間、協同組合及び公共機関)がある。協同組合形態の製糖工場は、特にマハラシュトラ州に多く、栽培者は、製糖工場の組合員として、各年の製糖工場の経営収支に基づいて原料代金を受け、製糖工場は、収穫作業の手配を行うとともに原料輸送を手配し、栽培者にそれらの料金を請求する。製糖工場はまた、収益の一部をその地域の社会的便益(学校、医療施設など)に提供している。
民間の製糖工場は、ウタル・プラデシュ州及びカルナタカ州やタミルナドゥ州などの南部の諸州に多く、複数の工場を所有するグループもある。
公共の製糖工場は、ウタル・プラデシュ州やビハール州では最も一般的である。非営利の製糖工場であり、州政府が民間から引き継いだ製糖工場も存在している。
インドでは、精製糖はほとんど生産されていない(表3)。付属精製工場を持つ唯一の製糖工場は、ウタル・プラデシュ州のダウルラである。この工場は、イオン交換樹脂を利用して、5つ星ホテルや航空会社に利用される僅かな量の精製糖を製造している。他のいくつかの製糖工場は、シロップ清浄システムを用いて、精製糖に近い品質の白糖を生産しており、製品の色価をほぼ50ICUMSA単位まで下げている。この白糖は、高品質の白糖を要求する清涼飲料製造業者などに利用されている。インドには、単独の精製糖工場は存在しない。
民間の製糖工場は、ウタル・プラデシュ州及びカルナタカ州やタミルナドゥ州などの南部の諸州に多く、複数の工場を所有するグループもある。
公共の製糖工場は、ウタル・プラデシュ州やビハール州では最も一般的である。非営利の製糖工場であり、州政府が民間から引き継いだ製糖工場も存在している。
インドでは、精製糖はほとんど生産されていない(表3)。付属精製工場を持つ唯一の製糖工場は、ウタル・プラデシュ州のダウルラである。この工場は、イオン交換樹脂を利用して、5つ星ホテルや航空会社に利用される僅かな量の精製糖を製造している。他のいくつかの製糖工場は、シロップ清浄システムを用いて、精製糖に近い品質の白糖を生産しており、製品の色価をほぼ50ICUMSA単位まで下げている。この白糖は、高品質の白糖を要求する清涼飲料製造業者などに利用されている。インドには、単独の精製糖工場は存在しない。
| ページのトップへ |
砂糖の流通
徴収砂糖の販売は、ほとんどの州においてインド食糧公社(Food Corporation of India)によって行われている。同公社は、製糖工場からの徴収砂糖の購入と製糖工場から販売店への輸送を手配している。しかし、マハラシュトラ州では、州政府が徴収砂糖の販売を手配する代理人を任命しており、これらの代理人は、ほとんどが協同組合団体であり、購入先と販売地域を割り当てられている。
政府は、投機的要素を除外するため、自由市場砂糖の取引業者に対し多くの規制を設けている。
(1) すべての取引業者は、砂糖取引保管許可証(Sugar Dealers and Storage License)を所持しなければならない。
(2) 取引業者が保有することができる数量は、最大50トンである。
(3) 在庫は、最大15日間以内に販売されなければならない。
(4) 取引業者は、エンド・ユーザーに販売することはできるが、他の会社に販売することはできない。エンド・ユーザーは、砂糖の保有量に対する規制はない。
また、販売に際しては、100kgのジュート製の袋に詰めなければならない。この政策は、西ベンガル地方に集中しているインドのジュート産業を援助することを目的としている。しかし、国際貿易については、50kgの袋で実施されているため、政府は輸出販売については、この小さな袋に詰めることを許可している。
政府は、投機的要素を除外するため、自由市場砂糖の取引業者に対し多くの規制を設けている。
(1) すべての取引業者は、砂糖取引保管許可証(Sugar Dealers and Storage License)を所持しなければならない。
(2) 取引業者が保有することができる数量は、最大50トンである。
(3) 在庫は、最大15日間以内に販売されなければならない。
(4) 取引業者は、エンド・ユーザーに販売することはできるが、他の会社に販売することはできない。エンド・ユーザーは、砂糖の保有量に対する規制はない。
また、販売に際しては、100kgのジュート製の袋に詰めなければならない。この政策は、西ベンガル地方に集中しているインドのジュート産業を援助することを目的としている。しかし、国際貿易については、50kgの袋で実施されているため、政府は輸出販売については、この小さな袋に詰めることを許可している。
| ページのトップへ |