

ホーム > 砂糖 > 調査報告 > さとうきび > さとうきびのバイオマス利用による産業構造の強化と環境保全
最終更新日:2010年3月6日
[2004年11月]
【環境/資源保全】
| 琉球大学農学部生物生産学科 教授 上野 正実 |
さとうきび再生の大きなチャンスが巡ってきた。地球温暖化対策「バイオマス・ニッポン総合戦略」である。さとうきびは、バガス炭、アルコール、バイオガス、堆肥等としてバイオマス利用の核となり得る。ここでは炭化によるCO2の永久固定化を軸とする温暖化対策と、そこから派生する様々な用途について述べる。これは地域の産業構造にも大きな変革をもたらす可能性を持つが、それに向けて糖業の構造改革が求められる。これらを具体化し、元気で美しい地域社会を構築するために、生産と環境の調和を図るバイオ・エコシステムを提案する。
バイオマス利用による地球温暖化対策
1.バイオマスが熱い
いま、「バイオマス(biomass)」が注目されている。限られた紙面ではあるが、しばらくさとうきびを離れてこの話題に触れてみたい。バイオマスは、生物を意味する“bio”と、量を表す“mass”の合成語で、「生物量」と訳され、ある場所に存在する生物体の質量やエネルギー量を表す。生物体をエネルギー資源として利用する場合に用いられることが多い。一般には、「生物に由来する資源」を表す用語として受け入れられている。すなわち、生物体はもとより、そこから造られた様々な物質も資源として見る場合にはバイオマスとなる。中には下水汚泥のような意外なものもバイオマスに含まれる。バイオマスはつまるところ「光合成」の産物であり、炭素を媒体とする太陽エネルギーの一形態である。光合成を基点とする炭素循環の過程で、様々な形態に変化する。言い換えると、バイオマスは「太陽エネルギーの缶詰」とも表現できる。
第二次大戦後、バイオマスが注目されるのはこれが2回目である。記憶されている方も多いと思われるが、1970年代に中東情勢に端を発する原油の禁輸措置や価格の高騰によって、世界規模の混乱の原因となった石油危機(オイルショック)が発生した。加えて、ローマクラブの警告などによって、石油エネルギー資源の埋蔵量の有限性が強く認識されるようになり、代替エネルギーが模索されるようになった。特に、再生可能なエネルギーのひとつとしてバイオマスが注目され、産官学の多くの技術者や研究者が大挙して研究開発に取り組んだ経緯も記憶に新しい。このバイオマスブームは原油価格の低下とともに淡雪のように消滅してしまった。
| ページのトップへ |
2.地球温暖化
それでは何ゆえに今またバイオマスなのだろうか?その背景となっているのが、地球温暖化現象、より正確にはそれを引き起こすであろう大気中の二酸化炭素(CO2)濃度の上昇である。化石燃料よりエネルギーを自在に引き出す変換技術が開発された産業革命以来、化石燃料の消費量は増加の一途をたどっている。特に第二次大戦後はこの傾向が顕著になり、これに比例してCO2の発生量が増えつづけている。大気中の濃度は現在では370ppm程度であるが、1年で2ppmもの割合で上昇を続けている。大気中のCO2は太陽光線中の熱線である赤外線を捕捉して気温を上昇させるので、濃度が高いほどこの効果は顕著になる。温室の中で気温が上がる現象に似ているので「温室効果」と呼ばれている。温暖化の影響は、今年の台風の発生状況や世界的な異常気象の頻発などでその片鱗がうかがえるようになってきた。しかしながら、多くの人々にとっては遠い未来の出来事としか認識されていないのも事実である。
化石燃料の消費量が増加する中で、温暖化現象は現在の予測以上に深刻な影響をもたらすことも懸念され、「20世紀はアラームの世紀、21世紀はアクションの世紀」と呼ばれるほど事態は切迫している。しかしながら、これが現実味を帯びてきたのは、先進国を中心に排出量の削減量を具体的に定めた「京都議定書」の制定(1997年)後である。このとりあえずの目標値を達成するのでさえ、エネルギーシステム全体のあり方を見直す必要があり、産業だけでなくライフスタイルの変更が要求される。すなわち、温暖化の警告より、現実的な法的規制や増税、ビジネスの発生などに幅広い関心を呼ぶようになったのが実情であろう。とは言え、地球規模のスケールをもつ現象は極めて大きな慣性をもち、10年や20年程度の対策では修正不能である。それでも対策が早いほど効果を挙げやすいことを踏まえて取り組む必要がある。
| ページのトップへ |
3.「バイオマス・ニッポン総合戦略」とさとうきび
京都議定書ならびにそれを実施する仕組みである「京都メカニズム」を具体化するための政策策定は遅々として進まなかったが、平成14年12月に「バイオマス・ニッポン総合戦略」が閣議決定され、バイオマスを利用した温暖化対策が打ち出された。これは、地球温暖化対策の一環として排出削減にバイオマスの利活用を推進することを骨子としている。植物が吸収・固定したCO2がバイオマスの利用によって大気に還流し、全体的な増減には関与しない「カーボンニュートラル」という特性を利活用すれば、化石資源由来のエネルギーや製品の代替につながり、化石燃料由来のCO2の発生を抑制できる。2002年ヨハネスブルグ「持続可能な開発に関する世界首脳会議」の「実施計画」には、バイオマスを含めた再生可能エネルギーに係る技術開発、産業化の推進などが位置付けられ、バイオマスの総合的な利活用は国際的な合意事項となった。各種バイオマスを効果的に利用するために、国をあげて社会基盤の整備、産業構造の転換、ライフスタイルの変更を目指す総合的な対策を推進するのがバイオマス・ニッポン総合戦略である。これらを受けて各種の事業がスタートし、様々な技術開発が推進されるようになった。長期化する不況や経済構造の変化の中で、新しいビジネス源としてゼネコンを始めとする大手企業までもがこの分野に参入するようになった。これが昨今のバイオマスブームの原因となっている。
最初のバイオマスブームは、石油不足あるいはそれへの懸念が引き起こしたものであった。今回は温暖化現象というより深く大きな潮流が背景になっている。トイレットペーパーがなくなるような切迫感はないが、事態は比較にならないほど深刻である。したがって、先のITブームのように単なるビジネス上のブームに終わらせてはならない。「総合戦略」といういささか仰々しい位置付けは、国家としてのその決意表明であると理解したい。このような潮流の中で「さとうきび」はどのように位置付けられ、どのような可能性をもつのであろうか?
| ページのトップへ |
バガスの炭化によるCO2の永久固定化と低減
1.さとうきびの現状と島嶼農業
昨年(平成15年)9月に沖縄県宮古島地方を襲った超大型台風14号は、台風なれしたこの地域にも甚大な被害をもたらし、1000本以上の電柱が折損するなど、最近では類を見ない災害であった。さとうきびも例にもれず見るも無残な状態となり当初大幅な減産が懸念された(図1)。強固な鉄骨ハウスも倒壊し、内部の果樹などは大きな被害を受けた。しかしながら、さとうきびは驚嘆すべき回復力を発揮し、1ヶ月後には早くも被害の状態がほとんどわからなくなり、最終的には例年に近い状態となった。人口に膾炙したさとうきびの抵抗性が実証され、久々にその重要性が再認識された一幕であった。さとうきびはまさしく「琉球弧の宝」と言える。
|
図1 台風14号による被害状況と回復の様子 ハウス内のマンゴーの回復は非常に遅れた |
||
 |
 |
|
 |
 |
|
琉球弧の島々では、地域経済の第一次産業への依存度が極めて高く、地域経済から農業とりわけさとうきびを切り離すことはできない。土壌型に関係なく栽培でき、また、台風や干ばつなどの環境ストレスに対する耐性も高いので、島嶼環境に最も適した作物である。しかしながら、その実態はどうであろうか?ご存知のように平成に入ってから減産が続き、沖縄県では80万トン台にまで低下している。さとうきびの減産につられて最近では農業全体の生産性が低下する傾向が見られ、地域経済の冷え込みに拍車をかけている。経済が長期低迷する中で、地域経済の再生すなわち農業の振興が重要であることが認識されている。沖縄では好調な観光が牽引車の役割を果たしているが、本質的には農業の活性化が重要である。地域経済に対するさとうきびの波及効果は突出して高く4.3倍(家坂2001、沖縄甘蔗糖年報32)と評価されており、これが増産すれば地域経済も活性化する。
| ページのトップへ |
2.さとうきびの再生に向けた構造改革はバイオマスの利用から
離島経済および環境保全におけるさとうきびの重要性は誰もが認めるところであるが、残念ながらその再生に向けた有効な具対策は今ひとつ見えない状態であった。地域農業の置かれた厳しい状況を踏まえるとその実現は決して容易ではなく、とりわけ、さとうきびについては閉塞感を拭い得ず、新しい変革をもたらす「何か」が求められてきた。長い間、その模索が行われ、「さとうきびの総合利用」などが提案されてきた。その内容自体はすばらしいもので、絞りカスであるバガスの利用を中心に各種の研究開発が進められてきた。例えば、プラスティック、紙、ボード、飼料の製造などである。これらは試作の段階に止まるか、小規模な実用化に止まり、本格的な実用化にはほど遠い状態であった。
「バイオマス・ニッポン総合戦略」の策定によって、私達の前に糖業再生を含む問題解決の「何か」が見えてきた。風向きが逆風から順風に変わり、さとうきびをめぐる情勢が大きく変化することが期待できそうである。これをベースにさとうきびの再生に向けた「構造改革」を推進することが求められている。構造改革の根幹となるのがバイオマスの利用であり、さらにはITの活用である。製糖工場の経営が厳しい中で、ややもすると目先の利害が優先するのはやむを得ないとしても、長期展望を見据えた本質的な取り組みが必要である。これまでは時代の流れがなかったために、いずれの対策も大きな推進力となり得なかったのである。最大(にして最後?)のチャンスが訪れようとしている。
さとうきびの最大の利点はバイオマスの生産性すなわち光合成能力が極めて高いことである。平成11年度のさとうきび競作会(沖縄県)では夏植で24トン/10a(ジャーガル土壌)を記録しており、平成12年度は16トン/10aで甘蔗糖度は15.8%であった。これらの結果からも明らかなように、C4型光合成を行うさとうきびは、本来高いポテンシャルをもち、大気中CO2の吸収体として優れた能力を発揮する。しかしながら、九州沖縄農業研究センターの杉本明氏のレポート「琉球弧・南北大東島地域における砂糖安定生産のためのさとうきび栽培技術」(砂糖類情報、2004.7)に述べられているように、単収の低い地域が少なくないのが実情である。平均単収の低さはさとうきび本来の能力を活かしきれていないことに起因する。この観点から原因の究明と栽培技術の見直しを図り、本来のバイオマス生産性を発揮させる必要がある。
| ページのトップへ |
3.バイオマスとしてのさとうきび
さとうきびはこのような優れた光合成能力や多面的機能の他に、バイオマスとして理想的な特質をもっている(図2、3)。収穫されたさとうきびはすべてが製糖工場に集められ、砂糖に加工される。すなわち、バイオマスの利用で最大の問題となる収集システムはすでに確立されている。砂糖の製造過程において、バガス、フィルターケーキ、糖蜜など多様な副産物が大量に生成される。バガスは製糖工場の燃料として利用されているが、上述のようにその他にも多くの用途が知られている。これらの副産物をバイオマスとしてみると、その生産性と多用途性から、他の作物には類のない大きな利点をもっている。温暖化対策の一環としてバイオマスが注目されている中で、これらの副産物を活かすことがさとうきび再生の第一の方法である。
筆者のグループではこの点に着目して、バガスを炭化してCO2を永久的に固定して温暖化対策に利用するプロジェクトを平成11年度より推進してきた。沖縄県で生産されるさとうきび原料を約100万トン(実際はもっと少ない)としてCO2に換算すると約64万トンに相当する。世界では約12億トンのさとうきびが生産されているので8億トン近いCO2が固定されていることになる。毎年これだけの量が固定されるが、燃料利用や微生物による分解などでCO2は再び大気中へと戻ってしまう。製糖工場はバガスをボイラーで燃焼させて電気エネルギーと熱エネルギーを得て操業されている。このように糖業は早くから「コージェネレーション」を採用してきた環境に優しい産業である。
エネルギー利用によるCO2の循環はバイオマスの「カーボンニュートラル」の枠内にあって問題はないが、現状で満足するのはまことにもったいない。オーストラリアでは、製糖工場をエネルギープラントとして再編する国家的取り組みが推進されている。製糖工程をできるだけ省力化するとともに、高効率コージェネ化によって大量の余剰電力を生産しようとするもので、バガスだけでなくノコ屑などの利用も考えられている。バイオマスのカーボンニュートラル性と再生可能性を最大限に利用する試みで、産学官あげて動き出している。最近では、環境省の主導によって、糖蜜をエタノール化してガソリンに3%混合する「E3プロジェクト」もスタートした。また、ブラジルでは早くからさとうきびを利用したエタノール生産が行われており、バイオマスエネルギーの利用に関しては一日の長がある。E3プロジェクトはこの流れに沿ったものである。バイオマス生産性の高いさとうきびは、温暖化対策の切り札となりつつあると言っても過言ではない。「資源作物」と呼ばれるゆえんであろう。先ほどの杉本氏らが開発を進めているモンスターケーンは大きな威力を発揮するものと期待される。
| 図2 糖業におけるカーボンニュートラル |
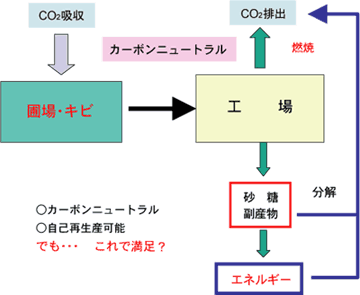 |
| 図3 さとうきびの収集と余剰バガス | ||
 |
 |
|
| ページのトップへ |
4.バガスの炭化によるCO2の永久固定化と低減
このようなさとうきびのエネルギー化路線に対して、バガスの炭化によるCO2の永久固定化はまったく新しいシステムである。カーボンニュートラル性を利用したバイオマスエネルギー化を含めて、現在取られている温暖化対策はあくまでも「排出量の削減」に限定されている。それ自体は有効かつ重要な対策であるが、大気中のCO2濃度の低減には、まずつながらないシステムである。これに対して、炭化はバイオマスを無酸素状態で熱分解して炭素の塊にするもので、燃焼させない限り、植物が固定したCO2を分解しない状態に転換するものである。この状態を維持すれば大気中CO2は減少する。すなわち「カーボンリダクション(炭素削減)」が実現できる。特に、バガス炭を土壌改良材として利用する、すなわち、固定した炭素を土中に貯蔵することがその基本となる。もちろん、燃料として使用しても支障はない。
土壌改良の効果によってさとうきびの増産が期待され、CO2の固定量もさらに増加する。すなわち土地からの一方的な収奪ではなく、還元も考慮した大気中CO2低減システムを構築することになる。これによってさとうきびの増産が地球環境の改善につながる図式ができあがる。無制限なバイオマスのエネルギー利用は吸収源の縮小を招き、結果として逆効果を招く危険性もはらんでいる。特に問題となるのが、一方向的なエネルギー利用を続けると、土地のバイオマスの再生能力が次第に低下することである。数十年後には不毛の大地を造りだす危険性もあることは常に念頭に入れて置かなければならない。その意味においてもバガス炭の土壌還元は大きな意味を持ってくる。
バガスは製糖副産物であるので主産物には何ら悪影響を及ぼさないこと、原料が自動的に集積されること、木を用いる木炭とは異なり毎年(短期間で)産出されることなど大きなメリットがある。すなわち1年あたりの固定量は限られていても、その量は年毎に累積され、他の排出量の削減システムと組み合わせて使えば大きな効果が期待できる。農家にとっては直接的な増収とともに環境税などに係るメリットを享受でき、何よりも地球環境への貢献が農家に大きな誇りをもたらす可能性がある。さとうきびが「厄介者」から「救世主」へ変貌する時がきた。さらに、このシステムは、稲・麦ワラ、籾殻、トウモロコシの残茎など、農林業に由来する残渣にもそのまま適用でき、莫大な量の炭素固定も決して夢ではない。排出量の削減技術、バイオマスのエネルギー利用と合わせて、バイオマス炭という「人造石炭」が温暖化対策に大きな効果をもたらすことが期待される。
このアイデアはなかなか理解してもらえないか、面白いほら話としてしか受け止められなかったが、最近では理解者も増えてきたように感じている。9月28日〜30日に東京国際フォーラムで開催された「イノベーション・ジャパン2004」に琉球大学を代表して出展する機会(島嶼型バイオマス循環システム)を得たが、多くの来場者に関心をもってもらうことができた。中には具体的なビジネスの話もあり、夢物語ではなくなりつつある。
| ページのトップへ |
5.バガスの炭化プロジェクト
この構想を実現する第一歩として、バガス炭化装置の開発とその生成物の利用に取り組み、平成11年より産学のプロジェクトによって研究を進めてきた。平成12年12月から宮古製糖株式会社伊良部工場に試作した炭化装置を設置してバガスの炭化試験を実施してきた。その成果が認められ、平成13年度沖縄県産学官共同研究推進事業に提案した「バガスの大量余剰化および炭化生成物の高度利用技術の開発」が採択され、研究の推進に大きな前進をみることができた。このプロジェクトは、製糖工程の省エネ化、効率的炭化技術の確立および炭化生成物の高度利用技術の開発を目的としたものである(図4)。本プロジェクトは、CO2の永久固定化だけに止まるものではなく、内部に微細孔を多く含み、表面積が極めて大きいバガス炭の特徴を活かすこともねらいとしている(図5)。大きな表面積があるためにガスや液体の吸着力が強く、脱臭作用では活性炭に比べて遜色のない効果があることが確認できた。
| 図4 産学官によるバガス炭化プロジェクト |
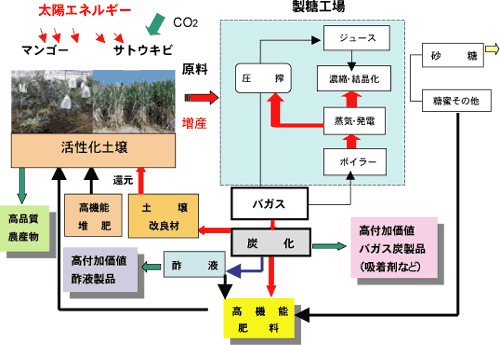 |
| 図5 バガス炭は大きな表面積をもっている | ||
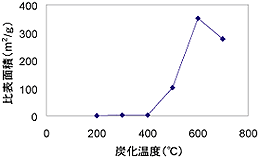 |
 |
|
とりわけ注目されるのは1gのバガス炭で約5gの水分を保持できる能力である(図6)。吸着された水の大半は植物が利用できる有効な水であり、他の炭にはみられない利点がある。このため、干ばつ常襲地である島や乾燥地域の逼迫した水事情の改善に大きな効果をもたらすことが期待される。このような能力によって地下に浸透する水分の浄化に利用できる可能性もある。炭の微細孔は微生物の住処となり、作物の増産につながるとともに様々な効果をもたらすことが期待される。さらに、土壌にバガス炭を混合すると、圧縮力に対して顕著な抵抗を示すことが明らかになった。これは機械による踏圧の軽減など大きな効果を引き出す可能性につながる。バガス炭による増収効果(表1)だけでなく、ウージ酢(酢液)による品質向上効果も得られている。さらにはこのように、温暖化対策とともに、様々な付加価値が生まれる点がバイオマス利用の魅力である(図7、8)。これらは新たな事業を創生する可能性をもっている。
| 表1 バガス炭(単独)施用によるさとうきび生育への影響 |
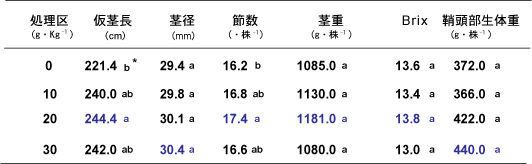 |
| 北大東島堆肥混合土壌 *縦に異なるアルファベット間にはダンカンの多重検定により5%水準で有意差あり |
| 図6 バガス炭の保水性と施用の様子 | ||
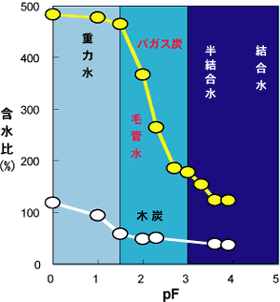 |
 *作物の根が吸収できるのは毛潅水と半結合水であり,バガス炭はこの範囲が広く非常に有効である。 |
|
| 図7 バガス炭とウージ酢、事業化に向けて準備中 | ||
 |
 |
|
| 図8 ウージ酢(酢液)を施用した時の土壌中リン等の溶融 |
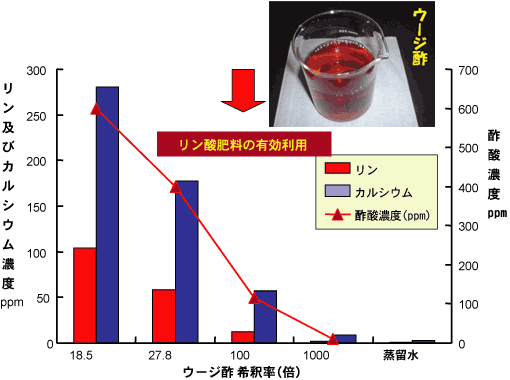 |
| *難溶性リンを溶融して可溶性リンとなるので糖度の上昇をもたらす |
| ページのトップへ |
バイオ・エコシステム
近年の大量消費文明は島嶼社会に多様な物資を流入させ、また、農業生産性を高めるために各種の生産資材を多投入させ、環境に深刻な影響を及ぼしている。生活物資などの島への輸送は、船舶と飛行機を利用して大量に運び込まれるが、島から外へ搬出されるのはわずかな農林水産物、加工生産物に限られている。従って、それらの差し引きが島に残り蓄積されていくことになり、その量も膨大なものになりつつある。「元気で美しい地域社会を造りたい」という願いは、どこの地域にも共通するものである。「生産と環境の調和」を実現するシステムとして提案したのが「バイオ・エコシステム」である。これはバガスの炭化を中心に各種のバイオマス利用を総合的に組み合わせた地域システムである。このシステムを成功させるには、燃料として使用されているバガスをいかに多く余剰化させ、低コストで効率的に炭化するかがポイントとなる。それにはまず製糖工場のボイラーの改善と工程全体のエネルギー効率の向上が課題となる。さらに、外部エネルギーを積極的に導入し、工場のバガスへの依存量を可能な限り縮減することも重要である。これには、廃棄物処理によって発生する熱エネルギーあるいは電気エネルギーの活用がもっとも合理的な方法と考えられる。ここで、ゴミ問題との関係がでてくるが、筆者らは小型還元溶融炉をその基幹設備として提案してきた。さらには生育の盛んなバイオマスの利用、太陽光や風力の利用も期待できる。このように、さとうきびの利用を中心に、その増産、CO2永久固定化と温暖化抑制、廃棄物管理・環境浄化さらには地域の活性化を同時に達成する総合的なシステムを「バイオ・エコシステム」と称している。生産と環境保全の調和を目指すバイオ・エコシステムは地域全体にかかわるシステムであることが特徴である(図9)。従って、まずモデルシステムを構築することが重要な課題である。モデルシステムの最小構成として、高効率省エネ化製糖プラント、バガス炭化装置、小型還元溶融炉およびエネルギー発生装置の組み合わせを考えている。このような一連の流れの中で、バイオ・エコシステムを島全体に展開した「バイオ・エコアイランド構想」がおのずとでてきた。地域システムとしてのバイオ・エコシステムは明瞭な境界をもつ島嶼において最も構築しやすいと言える。島嶼におけるエネルギーと物質の流れはすべて計量・把握できるため、今後の環境研究のモデルとなり得る面でも魅力的である。
| 図9 第一世代バイオ・エコシステムの構成 |
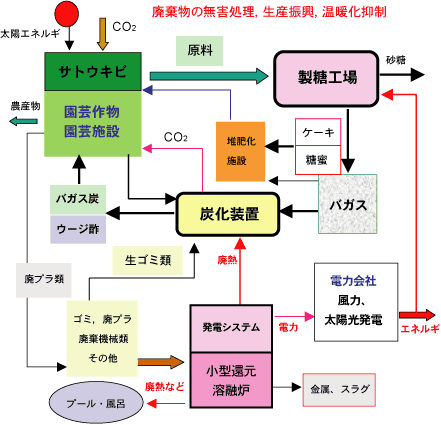 |
| ページのトップへ |
むすび
ここで、再認識しなければならないのが、「生産の重要性」である。ややもすると利用技術にのみ目が向きがちであるが、元がなければ何もできない。最後にこの点を強調しておきたい。さらに、バイオマスを効果的に活用し、本構想を実現するには情報が不可欠である。すなわち、広範囲に薄く散在しその状態が刻々と変化するバイオマスと、それが存在する環境およびそこにおける物質の循環を正確に把握し、効果的に対処する必要がある。著者らは、以前より、ITを活用した高度営農支援システムの構築を目指す「デージファーム」と称するプロジェクトを展開しており、両方のリンクを進めている。「太陽エネルギーの缶詰」であるさとうきびの活用では、研究面でも実利面でも楽しい夢が描けそうである。
| ページのトップへ |
|
「今月の視点」 2004年11月 |
●さとうきびのバイオマス利用による業構造の強化と環境保全 琉球大学農学部生物生産学科 教授 上野 正実 |
|
●WTOの枠組み合意とその意義 九州大学大学院 教授 鈴木 宣弘 | |
|
●砂糖摂取は骨格筋の有酸素代謝を亢進させるか (平成15年度砂糖に関する学術調査報告から) 日本女子大学 講師 佐古隆之 鹿屋体育大学 教授 浜岡隆文 北海道大学 助教授 新岡 正 東京医科大学 教授 勝村 俊仁 |
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03-3583-8713
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03-3583-8713










