

ホーム > 砂糖 > 視点 > 寿司と合わせ酢のいまむかし〜食酢業界における砂糖類の利用と動向〜
最終更新日:2010年3月6日
1.食酢の種類と生産量
食酢は、日本農林規格と品質表示基準により「醸造酢」と「合成酢」に大別され、「醸造酢」は「穀物酢」、「果実酢」、「その他の醸造酢」に分類される(表1)。「穀物酢」はさらに「米酢」、「黒酢」、それ以外の「穀物酢」に、また、果実酢は「りんご酢」、「ぶどう酢」、それ以外の「果実酢」に分類される。「その他の醸造酢」とは、「穀物酢・果実酢」に含まれないものを指し、原料には穀類・果実・野菜など(はちみつ、さとうきびを含む)・アルコールなどが使われる。
平成19年度の食酢生産実績は41万7300キロリットルで、対前年比96%となった。しかし平成元年度に対する比率は110%で、他の調味料市場が苦戦するなか、比較的堅調に市場を拡大させている(図1)。食酢の種類別の生産状況をみると、酢酸の希釈液に調味料などを加えて作る「合成酢」は極めてわずか(0.5%)で、ほとんどが醸造法で造った酢である。このうち、米などの穀類を原料とする「穀物酢」が全体の51%を占め、「果実酢」は6%程度である。
表1
食酢の分類
|
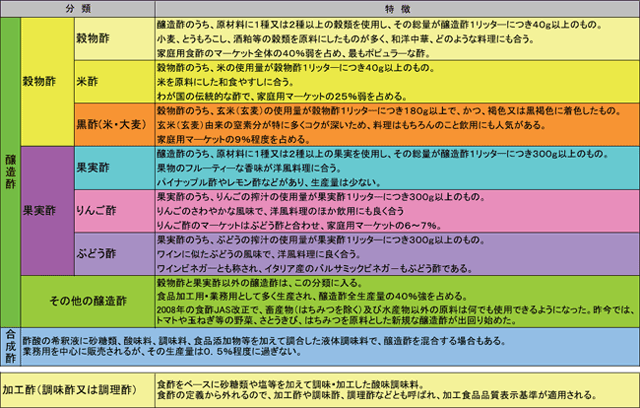 |
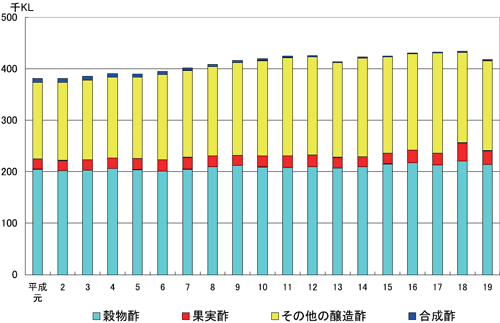 |
出典:農林水産省食品産業振興課調べ
|
図1
食酢の年度別生産量の推移
|
2.食酢の輸出入量
食酢の輸入量は、平成に入った頃は500〜600キロリットル程度であった。その後中国から香酢(もち米から作られる醸造酢)などの輸入量が急増した時期を経て、平成19年度には約3700キロリットルとなった。輸入相手国は、量的には中国が最も多い(40%)が、金額的にはバルサミックビネガーなどの高級酢が多いイタリアが第1位(50%)を占めた。
一方、日本からの輸出量は、平成の初めは1500キロリットル程度であったが、その後順調に増加し、平成19年度には1万キロリットルを超えた。この増加の要因としては、海外でのすしブームが考えられ、平成20年度の輸出相手国ではアメリカ合衆国が首位を占め、次いで中国、イギリス、香港、オーストラリアなどが続く(図2)。
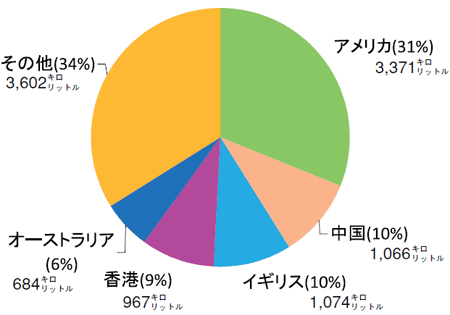 |
出典:財務省貿易統計より
|
図2
食酢の国別輸出量(平成20年度)
|
3.食酢の用途別消費量
食酢は基礎調味料として使われるほか、業務用や加工食品の原料(ソース、ケチャップ、マヨネーズ、すし、総菜など)にも多用され、家庭向けが34%であるのに対し業務・加工用は66%となっている。
4.すしとすし用合わせ酢
砂糖類を最も多く使用する食酢加工品や食酢メニューは、何と言ってもすしであろう。そこで「すし」と「すし用合わせ酢」について述べてみたい。
(1)昔のすし、今のすし
すしのルーツは、東南アジアの先住民が行っていた川魚の貯蔵法のひとつであったとされている。大量に取れた魚を塩と飯でかめに漬け込んでおくと、魚の自己消化と米の乳酸発酵によりさまざまなうま味成分のほか酸味が生じる。乳酸によって保存性がいっそう高まるとともに骨も柔らかくなり、酸味とうま味とが重なり特有の味に生まれ変わる。このような加工方法は、稲作とともに中国を経由してわが国に伝わったもので、「馴れずし」と呼ばれ、漬け込まれた魚だけを食べていた。わが国では滋賀県近江の「鮒(ふな)ずし」がこの系統にあたり、やはり飯を除いて魚だけを食べる。日本では「馴れずし」→「生成(なまなれ)ずし」→「早ずし」→「握りずし」へと発展し、今日では世界各地にSUSHIとして拡大している。
「すし」の記録がはじめて登場するのは、奈良時代の養老律令(718年)の中に「馴れずし」が現れる。室町時代に入ると、これが進化した「生成ずし」が登場するようになる。この「なまなれ」とは、発酵が浅いという意味で、単に発酵期間を短くしただけでなく、魚と飯に塩を加えて漬け込んで3、4日、遅くとも1〜2カ月間で消費するものであった。このようなすしの誕生には、食糧増産が進み、一日二食から三食へと変化した時代背景があり、すしが保存食というより嗜好的な食品へと変化していったものである。
江戸時代前期までは「生成」が主流であったが、その後、各地で食酢が生産されるようになると、飯を酢(酢酸の風味)で味付けし、乳酸発酵(乳酸の風味)を待たずに食べる「早ずし」が生まれた。上方では、酢と塩を合わせた飯の上に魚肉を貼り、押しをかけてから切って食べる「押しずし」が大評判となり、ほかの店もこれに倣ったとされる。このすし飯には、日本酒から造った米酢が使用され、砂糖も使用されたもようである。一方、江戸時代も後期の文化・文政年間になると、すしの高級化・多様化が進み、江戸で「握りずし」が考案された。当時、江戸で持てはやされた酢は、尾州(愛知県)半田で醸造された粕酢で、この原料には酒粕を3年間熟成させたものが用いられた。酒粕は密封し貯蔵する間に米粒が再分解し、さらに酒酵母の自己消化によってアミノ酸が大変豊富となる。この酢は、江戸前の魚をおいしく食べるには好適で、飯は粕酢と塩だけで味付けがなされ、上方の押しずしとは異なり砂糖を使用しなかった。サイズは小さなおにぎり程度(46グラム位)で、二口で食べたとされる。当時の「江戸前ずし」を再現したのが図3で、粕酢の色がついて飯がほんのり赤みを帯びる。
 |
図3
再現「江戸前ずし」
|
酢は、3年間熟成した酒粕を原料に使用した粕酢
すしネタも、当時の資料をもとに再現した
|
江戸時代とは異なり今日では、日本のどこに行っても「握りずし」が食べられるが、このような「握りずし」の広がりには、関東大震災(大正12年)の後、すし職人が地方に移り住み全国に広がったことのほか、第二次世界大戦後の食糧統制下のさなか、特別に許可された「持参米委託加工制度」(昭和22年)が貢献したとされる。この制度は、東京鮨組合の幹部が、当時の東京府やGHQと交渉し、客が米1合を持っていくと80匁(300グラム)のすしを受け取りその加工賃を支払うというもので、米1合で10個のすしを出したことから、これが1人前の基準となった。この制度は「江戸前ずし」に限られていたため、関西圏など「押しずし」が中心であった地域もこれに倣って「握りずし」を始めた。近代から今日までの「握りずし」の変遷を図4に示す。
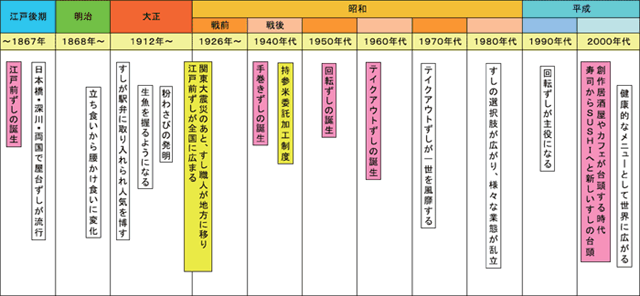 |
図4
握りずしの変遷
|
今や、寿司屋や回転ずしで食べる「すし」、家庭で作る「手巻きずし」、総菜の「持ち帰りずし」など、すしの種類はさまざまである。ミツカングループ本社が実施した首都圏および関西圏に居住する子供を持つ30〜49歳の主婦470名による「お寿司の認識と摂食実態に関する調査(平成20年)」によると、「おすし」と聞いてまず思い浮かべるのは「回転ずし」が最も多く、全体の64%を占めていた。特に関西では「回転ずし」の比率が高く75%にのぼったが、首都圏では3人に1人が「寿司屋で食べるおすし」と回答した。
(2)海外のすし
日本の食文化である「握りずし」は、米と魚と酢という食材からなるSUSHIとして、その国ならではの食べ方や具を使い世界各地に広まっている。
日本で誕生した「握りずし」は、アメリカ合衆国ではロサンゼルスからニューヨークに伝わり、ヨーロッパにおいてはニューヨークより遅く、イギリスからパリに伝わったとされている。
【ロサンゼルス】
明治39年、日本の寿司職人がリトル・トーキョーに日本人相手に握る寿司屋を開店した。その後、ハリウッドスターが好んで食べるSUSHIとして注目され、ヘルシー志向にマッチして拡大した。なお、西海岸には日系の食酢工場が2カ所あり、ここよりすし用合わせ酢がアメリカ全土に出荷されている。
【ニューヨーク】
ロサンゼルスの影響を受け、先進的なアメリカ人によって広められたもので、社交シーンの食として発展した。
【ロンドン】
ロサンゼルスと同様、日本人による日本食が現地に定着したパターンで、イギリス人にはあまり抵抗感がなく受け入れられ、回転ずしの人気が高い。すし用合わせ酢は、イギリス中部にある日系の食酢工場で生産され、イギリス国内とEUに出荷されている。
【パリ】
日本らしい正統派スタイルのSUSHIが定着している。
【香港】
1980年代の日本文化への興味・関心を発端にすしが注目され、日本文化の代表としてSUSHIが広まったもので、回転ずしの人気が高い。
【バンコク】
経済・情報・流通の発展にともない、健康意識の高まりもあってSUSHIはヘルシーな食事として人気が高い。
5.すし用合わせ酢の品質特性
すし用合わせ酢は、かつては店毎に寿司職人が食酢に砂糖、塩、調味料などを混ぜて作ってきたが、「回転ずし」や「持ち帰りずし」などの多店舗展開に伴い、合わせ酢のOEM(注)供給を食酢メーカーに委託したことから本格生産が始まった。さらに、家庭においても炊きたてのご飯に混ぜるだけという簡便性が受け、需要が拡大した。今日のすし用合わせ酢の生産量は推定10万キロリットル(販売額で153億円)とされ、このうち業務・加工用が70%以上を占めている。
すし用合わせ酢の原材料は、食酢に砂糖類、食塩、うま味付与の調味料からなり、極めてシンプルなため、食酢の特徴が直ちに香味に反映される。すしに相性の良い酢としては、米、小麦、コーンなどを使用した穀物酢が最もポピュラーで、現代人の嗜好にマッチしたさっぱりとした軽快な香味が好まれる。また、米酢のまろやかな香味は飯と大変よく合い、粕酢の重厚な風味とシャープな酸味は個性的な香味を醸し出す。このため、これらの酢を単独で使用したり、ブレンドして、すし飯の特徴付けをはかっている。
すし飯の味を構成する重要な要素に砂糖と塩のバランスがある。すし飯は酢合わせの後、時間の経過とともに全体に味が弱まり、塩味よりも甘味の方が弱く感じられるようになる。また、人の味覚は夏と冬で微妙に変化するもので、夏になると酸味と塩味への感受性が鈍く、冬場はこれらが鋭敏となる。このため、夏と冬では合わせ酢の処方を変更したり、飯に打つ量の調整が行われる。さらに興味深いことに、すし飯の味には地域性がある。川染らは、東京及び東京周辺、富山、滋賀および香川の各県では酸味、塩味、甘味の嗜好性が異なると報告している(調理科学会誌、20巻、p.142〜149、1987年)。ミツカングループがおこなった調査では、この傾向も時代と共に変化していることがわかったので紹介したい。
すし用合わせ酢の砂糖重量(砂糖類の重量を甘味度換算し、砂糖で表した)と塩重量のバランスの変化を図5に示す。1980年代までは地域に根付いた味づくりがなされてきたように思われる。その後、「持ち帰りずし」を中心とした全国チェ−ンの出現により、90年代には全国的に甘味の強い方向に動いたが、現在は以下の傾向となっている。
①関東・東北・甲越地域(第1グループ):甘味が比較的弱く、酸味の利いたすし飯が好まれる。
②関西・九州・山口・沖縄地域(第3グループ):甘味が強く、うま味の利いたすし飯が好まれる傾向がある。
③北海道・北陸・長野地域(第2グループ):第1と第3グループの中間にある。
④東海・中国・四国地域(第4グループ):関西地域よりもさらに甘味の強い味が好まれる。
これらの味の地域性をマップで示したのが図6である。
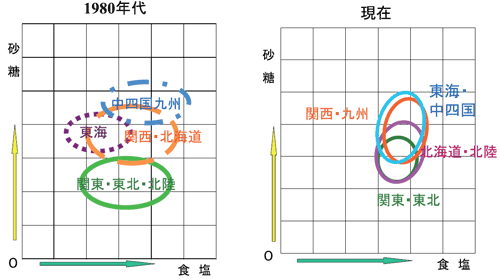 |
図5 すし用合わせ酢における砂糖重量・塩重量のバランス
|
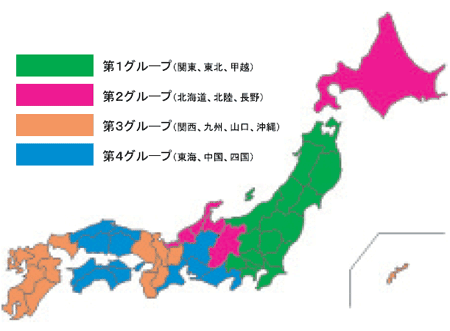 |
図6
すし用合わせ酢の味の地域性
|
6.砂糖類に望まれる機能
一人前の寿司職人になるためには「飯炊き三年握り八年」と言われるほど、すしには高度な調理技術が求められ、すしはかつて寿司専門店だけのものであったが今日では、デパート、スーパー、コンビニエンスストアなどで販売される手軽なすしが多くなった。このような「持ち帰りずし」は冷蔵ケースで保管されるため、「飯の老化」や前述したいわゆる「味ぼけ現象」のほか、乾燥しやすいという課題がある。これらを抑制するため、従来より各種の砂糖類などの利用研究がなされているが、なかなか満足できるものはない。また、職人が握ったすし飯は、すしロボットが作り出すすし飯とは異なり、飯粒同士が圧縮されずに口の中でパラッとほぐれる。このようなすし飯の食感改善に砂糖類は有効に機能すると思われるので、今後の砂糖類の機能の研究に期待したい。
(注)OEM・・・他社ブランドの製品を製造すること。
| ページのトップへ |










