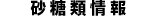最終更新日:2010年3月6日

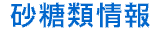

[2009年9月]
【視点】
日本ジャム工業組合
事務局長 川手 浩司
事務局長 川手 浩司
1.ジャムと砂糖の歴史
ヨーロッパでは日本の漬物のように、昔から地域の風土にあったジャムが生まれ、長い歴史を誇っています。温暖な地中海から寒さの厳しい北欧まで、いろいろな気候の土地があり、多くの果物や野菜が栽培されています。果物は生で食べてもおいしいのですが、はちみつや砂糖で煮込むと生とは違う風味がでて、別のおいしさになり、日持ちもするようになります。
はちみつや砂糖は紀元前から利用されてきました。スペインの旧石器時代の遺跡には木に登ってはちみつを採取している絵が残っています。紀元前334年、アレキサンダー大王のインド遠征に従軍した将軍ネアチャスは、「インドには蜂の力を借りずに葦から採る蜜がある」と語っています。「葦」とは、さとうきびのことで、その汁を煮詰めて砂糖を作る方法をインド人達は知っていました。
砂糖は、7世紀頃にはメソポタミアを経て、地中海沿岸部や島々に広がり、11〜13世紀にかけて、十字軍の騎士たちによって知られるようになりました。その頃は砂糖は貴重な薬として使われていて、料理や食べ物の保存のために使うことが出来たのは、王侯貴族など一部の人々だけだったようです。やがて15世紀になると砂糖の生産は西アフリカへ、そして16〜17世紀にはアメリカ大陸へと移っていきました。英国ではエリザベス1世の時代(16世紀後半)、海外の植民地から安い砂糖が入るようになり、家庭でもジャム作りが行われるようになりました。
ジャム加工は、一時的に大量に採れる果物を、よりおいしく食べたり保存したりする方法として発展してきました。そして販売を目的としたジャムが出回るようになったわけです。
はちみつや砂糖は紀元前から利用されてきました。スペインの旧石器時代の遺跡には木に登ってはちみつを採取している絵が残っています。紀元前334年、アレキサンダー大王のインド遠征に従軍した将軍ネアチャスは、「インドには蜂の力を借りずに葦から採る蜜がある」と語っています。「葦」とは、さとうきびのことで、その汁を煮詰めて砂糖を作る方法をインド人達は知っていました。
砂糖は、7世紀頃にはメソポタミアを経て、地中海沿岸部や島々に広がり、11〜13世紀にかけて、十字軍の騎士たちによって知られるようになりました。その頃は砂糖は貴重な薬として使われていて、料理や食べ物の保存のために使うことが出来たのは、王侯貴族など一部の人々だけだったようです。やがて15世紀になると砂糖の生産は西アフリカへ、そして16〜17世紀にはアメリカ大陸へと移っていきました。英国ではエリザベス1世の時代(16世紀後半)、海外の植民地から安い砂糖が入るようになり、家庭でもジャム作りが行われるようになりました。
ジャム加工は、一時的に大量に採れる果物を、よりおいしく食べたり保存したりする方法として発展してきました。そして販売を目的としたジャムが出回るようになったわけです。
2.砂糖がジャムに及ぼす効果
ジャムとは果物に砂糖を加え、加熱濃縮することによって果物の水分を砂糖に置き換え、酸とペクチン(注)の力によってゼリー化したものです。
ジャムは、現在では定義や規格がいろいろと決められていますが、もともとは砂糖漬けの保存食です。
戦前の日本では、ヨーロッパ文化の影響を強く受け、特に英国風のものが珍重されました。当時は缶詰がほとんどで、使用時に開缶しジャムつぼに移し替え、食卓に供されました。戦後はアメリカ文化の影響により、ビンも使用しやすくスマートになり、そのまま食卓で開封し使用するのが通常のパターンとなりました。
現在、一般にジャム類は、ジャム、マーマレード、ゼリーの3種類に分けられています(表1)。いずれもその保存性と素材の風味や色、香りを生かした身近な食品として高く評価され、広く世界中で作られています。
最近では、いちごやりんごのジャム、マーマレードは勿論のこと、ブルーベリー、ラズベリー、パッションフルーツなどの世界中のフルーツを始め、野菜や花弁を原料としたジャムも作られるようになりました。食生活の多様性から、甘さやカロリーを抑えたジャム、虫歯になりにくい糖を使ったジャムやフルーツソースなど、いろいろなタイプも出回り、毎日の食卓に彩りを添え、またお菓子やデザート、料理用と幅広い分野で使われるようになってきています。
ジャムは、適度にゼリー化した状態の中で織りなす酸味と甘味がおいしさのポイントです。ジャムに砂糖を加えるのは、甘味を付けるだけでなく、酸とともに砂糖がペクチンを編み目のようにつなぎ、その編み目の中に水を抱え込んでしまうことにより、ゼリー化を促進するからです。
また、ジャムは、保存性に優れた食品として知られていますが、この保存性は、砂糖には抱え込んだ水分をなかなか放さないという性質があるために、微生物が細胞の水分を奪われて活動できなくなることによるものです。砂糖をたっぷり使ったジャムや砂糖漬が腐りにくいのはこのためです。
人間は生まれつき、甘いものに引かれます。砂糖を上手に使ったジャムには心に楽しさと安らぎを与え、ストレスを取り除き、情緒を安定化させるという効果があります。
(注)ペクチン:果物や野菜などいろいろいな植物に含まれている炭水化物。ガラクトースという糖類の誘導体が長くつながった多糖類で、果物の中では細胞膜の強さを保ったり、細胞同士をつぎあわせる働きをしている。
ジャムは、現在では定義や規格がいろいろと決められていますが、もともとは砂糖漬けの保存食です。
戦前の日本では、ヨーロッパ文化の影響を強く受け、特に英国風のものが珍重されました。当時は缶詰がほとんどで、使用時に開缶しジャムつぼに移し替え、食卓に供されました。戦後はアメリカ文化の影響により、ビンも使用しやすくスマートになり、そのまま食卓で開封し使用するのが通常のパターンとなりました。
現在、一般にジャム類は、ジャム、マーマレード、ゼリーの3種類に分けられています(表1)。いずれもその保存性と素材の風味や色、香りを生かした身近な食品として高く評価され、広く世界中で作られています。
表1 日本農業規格(JAS)によるジャム類の定義
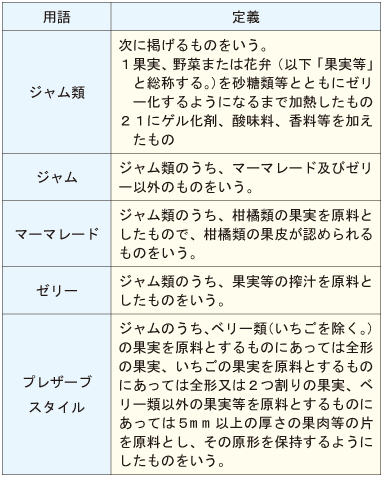
最近では、いちごやりんごのジャム、マーマレードは勿論のこと、ブルーベリー、ラズベリー、パッションフルーツなどの世界中のフルーツを始め、野菜や花弁を原料としたジャムも作られるようになりました。食生活の多様性から、甘さやカロリーを抑えたジャム、虫歯になりにくい糖を使ったジャムやフルーツソースなど、いろいろなタイプも出回り、毎日の食卓に彩りを添え、またお菓子やデザート、料理用と幅広い分野で使われるようになってきています。
ジャムは、適度にゼリー化した状態の中で織りなす酸味と甘味がおいしさのポイントです。ジャムに砂糖を加えるのは、甘味を付けるだけでなく、酸とともに砂糖がペクチンを編み目のようにつなぎ、その編み目の中に水を抱え込んでしまうことにより、ゼリー化を促進するからです。
また、ジャムは、保存性に優れた食品として知られていますが、この保存性は、砂糖には抱え込んだ水分をなかなか放さないという性質があるために、微生物が細胞の水分を奪われて活動できなくなることによるものです。砂糖をたっぷり使ったジャムや砂糖漬が腐りにくいのはこのためです。
人間は生まれつき、甘いものに引かれます。砂糖を上手に使ったジャムには心に楽しさと安らぎを与え、ストレスを取り除き、情緒を安定化させるという効果があります。
(注)ペクチン:果物や野菜などいろいろいな植物に含まれている炭水化物。ガラクトースという糖類の誘導体が長くつながった多糖類で、果物の中では細胞膜の強さを保ったり、細胞同士をつぎあわせる働きをしている。
3.ジャムで使用する砂糖
一般的にペクチンがゼリー化するための条件は、糖度が60〜65%であることです。これに対し果実中に含まれる糖分は10%前後であるため、ゼリー化するために糖を加える必要があります。このとき砂糖(ショ糖)ばかりでなく、ブドウ糖、水あめ、キシロース、オリゴ糖、糖アルコールなどの糖質でも同様なゼリー化を促進しますので、いろいろな糖質を原料として使用することができます。
ジャムの原料としてふさわしいものを選ばなければ、良いジャムは出来ません。原料の個性、特に香りを活かすため、ジャムに使用する砂糖は、精製度の高いグラニュー糖を使用することが基本になります。グラニュー糖がないときは上白糖でもよいのですが、ジャムの品質を比べると、グラニュー糖を原料としたジャムのほうが後味のすっきりとしたものになります。
ジャムの原料としてふさわしいものを選ばなければ、良いジャムは出来ません。原料の個性、特に香りを活かすため、ジャムに使用する砂糖は、精製度の高いグラニュー糖を使用することが基本になります。グラニュー糖がないときは上白糖でもよいのですが、ジャムの品質を比べると、グラニュー糖を原料としたジャムのほうが後味のすっきりとしたものになります。
4.ジャムのお国ぶり
1) ヨーロッパ
北欧では、果実の採れる短い期間に、お母さん方が、越冬食品として、野生いちご、ラズベリー、カーラント(スグリ)類のジャムを一生懸命につくり、つぼに蓄えます。我が国の漬け物と同じように、保存食品として愛用されているわけです。家族は、冬の間この「母の味」を感謝して食べているのでしょう。
ジャムの先進国は、英国、フランスです。英国では、いちごが古くから豊富に自生していました。ストロベリーの名は、10世紀の植物誌にありますが、いちごに宗教的な「徳性」を見つけて尊重し、中世紀からエリザベス王朝にかけて、野生のいちごを庭に移植・栽培することが流行しました。シェイクスピアの「ヘンリー8世」にも出てきます。マーマレードになるオレンジは、15世紀に、バスコ・ダ・ガマが、インド周航から持ち帰り、その後大量に輸入するようになりました。また、英国は砂糖の貿易を独占していましたので、ジャムづくりの伝統を誇ることができたわけです。
18世紀から19世紀にかけて、産業革命が一応達成され、国民の生活レベルは向上しましたが、ジャムは当時まだまだ高級で貴重な食品だったのです。英王室御用達であるオックスフォード・オレンジマーマレードは、「英国人の真心」「マーマレードの芸術品」といわれています。英国人は黄金色のマーマレードを朝食に欠かさず、そして深い満足を得てエネルギーの源泉としています。
フランスのジャムは、「小瓶に詰められた太陽の輝き」「天使の唇」と詩人がたたえています。さすがに芸術の国です。ジャムのフランス語は「コンフィチュール」(果実の砂糖煮)です。王様の正式な晩さんメニューには、必ずデザートとしてジャムがありました。現在でも、本当のフランス料理の朝食というと、各種のジャムがでて、クロワッサンにつけて食べるのです。
パリには、ジャムなどのギフト専門店があるほか、街角で売っているいろいろなジャムを包んだクレープや、指の間を流れるほどのアンズジャムをたっぷりかけたドーナッツを楽しく食べるアベックの姿などは、寒い季節の風物詩といえましょう。
2) 米国
ヨーロッパ人が移り住んだ国ですから、ジャムは好まれ、有名なメーカーが多く、ヨーロッパに劣らない製品を出しています。アメリカで最も好まれているのは、プレザーブスタイル(果実の原形が保持されたもの)のいちごジャムです。
3)ロシア
ロシア人は、パンに塗るだけではなく、ほかの形でもジャムやマーマレードを楽しみます。ロシア風ジャムティーがそれです。独特の煮だした紅茶の中に入れて飲むのですが、苦味や渋味が和らげられて、おいしくなります。雄大なロシアの風土が生んだ飲み方といえるでしょう。ロシアの風土が酪農に適さず、ミルクやクリームが豊富に手に入らなかったので、英国のようにミルクティーにならなかったのです。
北欧では、果実の採れる短い期間に、お母さん方が、越冬食品として、野生いちご、ラズベリー、カーラント(スグリ)類のジャムを一生懸命につくり、つぼに蓄えます。我が国の漬け物と同じように、保存食品として愛用されているわけです。家族は、冬の間この「母の味」を感謝して食べているのでしょう。
ジャムの先進国は、英国、フランスです。英国では、いちごが古くから豊富に自生していました。ストロベリーの名は、10世紀の植物誌にありますが、いちごに宗教的な「徳性」を見つけて尊重し、中世紀からエリザベス王朝にかけて、野生のいちごを庭に移植・栽培することが流行しました。シェイクスピアの「ヘンリー8世」にも出てきます。マーマレードになるオレンジは、15世紀に、バスコ・ダ・ガマが、インド周航から持ち帰り、その後大量に輸入するようになりました。また、英国は砂糖の貿易を独占していましたので、ジャムづくりの伝統を誇ることができたわけです。
18世紀から19世紀にかけて、産業革命が一応達成され、国民の生活レベルは向上しましたが、ジャムは当時まだまだ高級で貴重な食品だったのです。英王室御用達であるオックスフォード・オレンジマーマレードは、「英国人の真心」「マーマレードの芸術品」といわれています。英国人は黄金色のマーマレードを朝食に欠かさず、そして深い満足を得てエネルギーの源泉としています。
フランスのジャムは、「小瓶に詰められた太陽の輝き」「天使の唇」と詩人がたたえています。さすがに芸術の国です。ジャムのフランス語は「コンフィチュール」(果実の砂糖煮)です。王様の正式な晩さんメニューには、必ずデザートとしてジャムがありました。現在でも、本当のフランス料理の朝食というと、各種のジャムがでて、クロワッサンにつけて食べるのです。
パリには、ジャムなどのギフト専門店があるほか、街角で売っているいろいろなジャムを包んだクレープや、指の間を流れるほどのアンズジャムをたっぷりかけたドーナッツを楽しく食べるアベックの姿などは、寒い季節の風物詩といえましょう。
2) 米国
ヨーロッパ人が移り住んだ国ですから、ジャムは好まれ、有名なメーカーが多く、ヨーロッパに劣らない製品を出しています。アメリカで最も好まれているのは、プレザーブスタイル(果実の原形が保持されたもの)のいちごジャムです。
3)ロシア
ロシア人は、パンに塗るだけではなく、ほかの形でもジャムやマーマレードを楽しみます。ロシア風ジャムティーがそれです。独特の煮だした紅茶の中に入れて飲むのですが、苦味や渋味が和らげられて、おいしくなります。雄大なロシアの風土が生んだ飲み方といえるでしょう。ロシアの風土が酪農に適さず、ミルクやクリームが豊富に手に入らなかったので、英国のようにミルクティーにならなかったのです。
5.我が国のジャム
1) 国産ジャム第1号はいちごジャム
日本で初めてジャムをつくったのは、明治10年、東京の新橋にあった勧農局(明治時代の内務省の内省)で、そのいちごジャムを試売したそうです。企業としての始まりは、その4年後、1881年(明治14年)のことで、長野県人により缶詰のいちごジャムがつくられました。以来、長野県はジャムづくりが盛んになりました。
日本には、いちごが5種類ほど自生していて、清少納言が「枕草子」の中で「あてなるもの」(上品なもの)としてとりあげていますが、鑑賞用の植木としてあったにすぎません。開国後オレンダ人がいちごをもたらし、明治に入ると輸入されるようにもなり、国内で広く栽培されるようになったため、いちご=オランダいちごといわれています。
2)あんず
あんずは、1620年頃(元和年間)、伊予宇和島(愛媛県)の伊達家からお輿入れした信濃松代(長野県)藩主真田幸道夫人が、故郷の春を懐かしんで宇和島から取り寄せた苗木を、更埴(現在の千曲市)の森村に植えたのに始まるといわれています。
3)夏みかん
マーマレードの原料となる夏みかんの起源は、江戸時代中期、山口県青海島の海岸に漂着したものを、娘さんが拾い種子をまいて育てたもので、原木は天然記念物に指定されています。
4)パン食の普及とともに需要拡大
ジャムの普及発達に欠かせないパンは、西南戦争の軍用食として登場し、その後大正時代にパンとジャムが国民に普及していきました。夏目漱石の「吾輩は猫である」の中で、苦沙弥先生が、「俺はジャムは毎日舐めるが…」と言っていますが、漱石は、パンには砂糖を塗っていたということです。森鴎外も好きだったようで、ヨーロッパに留学した学者たちは、そのおいしさにヨーロッパ文化を投影して味わっていたのでしょう。
戦後、学校給食のパン食で、学童がジャムに親しんで成長してきたこと、洋風化志向となったことに加え、ジャムメーカーのたゆまざる努力によって価格と品質が消費者に受け入れられるようになりました。今日ではジャムの需要は大幅に増えるとともに、国産ジャムの供給割合が90%前後を占めています。
日本で初めてジャムをつくったのは、明治10年、東京の新橋にあった勧農局(明治時代の内務省の内省)で、そのいちごジャムを試売したそうです。企業としての始まりは、その4年後、1881年(明治14年)のことで、長野県人により缶詰のいちごジャムがつくられました。以来、長野県はジャムづくりが盛んになりました。
日本には、いちごが5種類ほど自生していて、清少納言が「枕草子」の中で「あてなるもの」(上品なもの)としてとりあげていますが、鑑賞用の植木としてあったにすぎません。開国後オレンダ人がいちごをもたらし、明治に入ると輸入されるようにもなり、国内で広く栽培されるようになったため、いちご=オランダいちごといわれています。
2)あんず
あんずは、1620年頃(元和年間)、伊予宇和島(愛媛県)の伊達家からお輿入れした信濃松代(長野県)藩主真田幸道夫人が、故郷の春を懐かしんで宇和島から取り寄せた苗木を、更埴(現在の千曲市)の森村に植えたのに始まるといわれています。
3)夏みかん
マーマレードの原料となる夏みかんの起源は、江戸時代中期、山口県青海島の海岸に漂着したものを、娘さんが拾い種子をまいて育てたもので、原木は天然記念物に指定されています。
4)パン食の普及とともに需要拡大
ジャムの普及発達に欠かせないパンは、西南戦争の軍用食として登場し、その後大正時代にパンとジャムが国民に普及していきました。夏目漱石の「吾輩は猫である」の中で、苦沙弥先生が、「俺はジャムは毎日舐めるが…」と言っていますが、漱石は、パンには砂糖を塗っていたということです。森鴎外も好きだったようで、ヨーロッパに留学した学者たちは、そのおいしさにヨーロッパ文化を投影して味わっていたのでしょう。
戦後、学校給食のパン食で、学童がジャムに親しんで成長してきたこと、洋風化志向となったことに加え、ジャムメーカーのたゆまざる努力によって価格と品質が消費者に受け入れられるようになりました。今日ではジャムの需要は大幅に増えるとともに、国産ジャムの供給割合が90%前後を占めています。
6.日本のジャムと世界のジャムの違い
日本農林規格(JAS)ではジャム類として一つの規格になっていますが、国際食品規格(CODEX)では「ジャム及びゼリー」と、「マーマレード」の二つの規格からなっています。どちらも「原料に水と糖類を混合し、適当な 粘稠 (ねんちゅう)(粘りけがあって密度の濃い状態)度まで加工されたもの」としています。
特に違いがあるのは、糖度の違いです。JASが40%以上としているのに対し、CODEXでは65%以上と規定し、低糖度を認めていません。
もともとヨーロッパでは、ジャムは果物の保存食品として家庭で作られ、食べられてきましたが、日本では販売用製品として製造され、普及しています。ヨーロッパではジャムを、「果実や果汁と炭水化物系甘味料を混合し、適当な粘稠度まで加工されたもの」と規定しており、日本より甘いものが主流です。
果実に砂糖類などを加えて煮込んでいくと、糖度が60〜65%以上にならなければ粘稠になっていきません。日本でも、以前は糖度65%のジャムが一般的でした。現在でも昔ながらの糖度60〜65%のジャムは現在も作られていますが、表−2(糖度別生産量)に示しているように、小売用製品の生産量では、糖度40〜55%のジャムが全体の約45%を占めています。
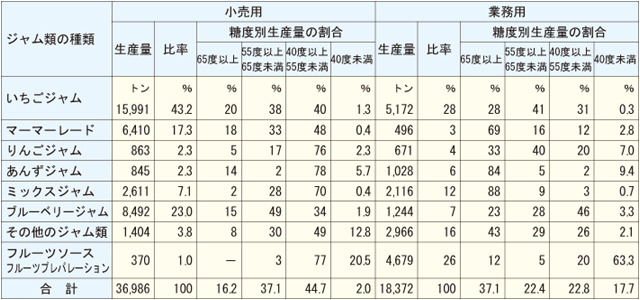
特に違いがあるのは、糖度の違いです。JASが40%以上としているのに対し、CODEXでは65%以上と規定し、低糖度を認めていません。
もともとヨーロッパでは、ジャムは果物の保存食品として家庭で作られ、食べられてきましたが、日本では販売用製品として製造され、普及しています。ヨーロッパではジャムを、「果実や果汁と炭水化物系甘味料を混合し、適当な粘稠度まで加工されたもの」と規定しており、日本より甘いものが主流です。
果実に砂糖類などを加えて煮込んでいくと、糖度が60〜65%以上にならなければ粘稠になっていきません。日本でも、以前は糖度65%のジャムが一般的でした。現在でも昔ながらの糖度60〜65%のジャムは現在も作られていますが、表−2(糖度別生産量)に示しているように、小売用製品の生産量では、糖度40〜55%のジャムが全体の約45%を占めています。
表2 平成20年度品種・糖度別生産数量
日本ジャム工業組合
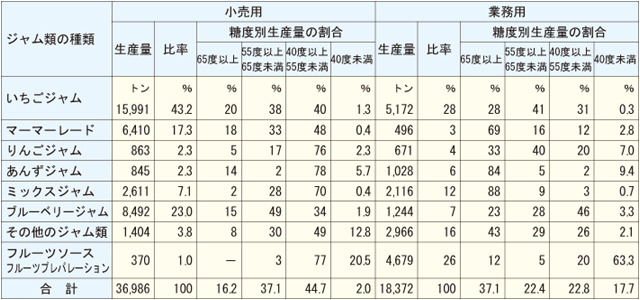
※生産量は1月〜12月
資料:日本ジャム工業組合
日本では、技術的にペクチンをうまく利用することによって、欧米メーカーでは真似することができない低糖度のジャムを製造することができるようになりました。これは日本のジャムメーカーの努力もさることながら、味に厳しい消費者の存在があったからと言えます。
資料:日本ジャム工業組合
日本では、技術的にペクチンをうまく利用することによって、欧米メーカーでは真似することができない低糖度のジャムを製造することができるようになりました。これは日本のジャムメーカーの努力もさることながら、味に厳しい消費者の存在があったからと言えます。
7.日本のジャム生産量
平成20年度のジャム類の国内生産量は、表−3のとおり5万5358トンで前年実績の5万4347トンに対して1.8%増となっています。一方、輸入数量(柑橘類以外・加糖)は、6990トンで前年の8528トンに対して18%減少しました。これは消費者の中国産食品に対する警戒感により、同国産製品の輸入量が落ち込んだことなどによります(表−4参照)。
表3 ジャム類の国内供給量の推移
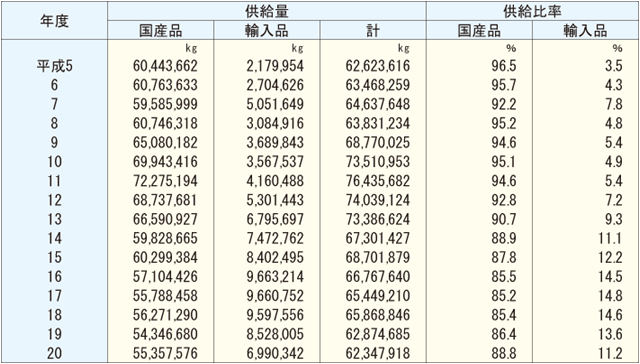
表4 最近5ヵ年のジャム類製品輸入数量(かんきつ類以外・加糖)

資料:財務省通関統計
国内生産数量と輸入数量を合わせた国内供給量は、6万2348トンで前年の6万2875トンに対して0.8%減少しました。国産品と輸入品の供給比率は、国産品が88.8%(前年86.4%)に対して輸入品が11.2%(同13.6%)と昨年に続き国産比率が上昇しています。
国産品の生産数量のピークは、表−3に示したように平成11年度で、その後は年々漸減傾向となり、最近は横這いの生産量となっております。11年度までの増加はブルーベリージャムの人気によるものです。ブルーベリーが国内で店頭に並んだのは1970年代の後半からで当時は文字通り新鮮な果物でした。
成熟した果実は、アントシアニン色素と呼ばれる濃い青紫色の水溶性色素を含みますが、このアントシアニン色素は、眼によい効果があると同時に強力な抗酸化作用があることから一躍注目を浴び、ブルーベリージャムの生産増加につながった訳です。
表−5は、平成20年度の用途別生産量を示しています。小売用は3万6521トンで前年の3万5058トンに対して増産しています。総生産量に占める割合は66%(前年64.5%)で前年より1.5ポイント上昇しています。
表5 平成20年度ジャム類生産量

業務用は1万4408トンで前年の1万5119トンに対して4.7%減産となっています。総生産量に占める割合は、26%(前年27.8%)と前年より1.8ポイント減少しています。
8.現状と今後の動向
ここ数年原材料特にブルーベリーは高値が続き、各メーカーは、ブルーベリーと他のベリー類とのミックス製品作りを戦略的に展開しています。また、今話題となっているコンフィチュール(果物に砂糖を加えて煮詰めたものというラテン語から転じたものだと言われ、14世紀中頃にはフランス全土に広がった)ブームもあり、ミックスジャムの生産増加傾向が目立っています。
ブルーベリーも最近の円高が手伝ってようやく下落傾向となり、原料調達コストの減少につながっている状況となっています。
ジャムの商品トレンドは、消費者の支持が高く、国産果実を使ったフルーツ感あふれるシリーズもの、安全・安心志向を背景に有機原料など原料にこだわった製品が着実に伸長し、また、アントシアニンの含有量が多いとされるカシスへの注目が高まりつつあります。更にコンフィチュールブームの定着で、その良さが消費者に認知されたミックスジャムも新商品の発売が相次いでいます。
中国産冷凍ギョウザ事件の発生以降、消費者の国産志向が高まっており、ジャムにおいても超低価格の輸入品が店頭から姿を消しつつあります。ジャム業界にとってこの状況は追い風と考えられ、今後なブルーベリーに次ぐ新たな果実の台頭が待ち望まれるところです。
「ジャムの絵本」小清水正美著 農文協
JAM STORY 日本ジャム工業組合
ブルーベリーも最近の円高が手伝ってようやく下落傾向となり、原料調達コストの減少につながっている状況となっています。
ジャムの商品トレンドは、消費者の支持が高く、国産果実を使ったフルーツ感あふれるシリーズもの、安全・安心志向を背景に有機原料など原料にこだわった製品が着実に伸長し、また、アントシアニンの含有量が多いとされるカシスへの注目が高まりつつあります。更にコンフィチュールブームの定着で、その良さが消費者に認知されたミックスジャムも新商品の発売が相次いでいます。
中国産冷凍ギョウザ事件の発生以降、消費者の国産志向が高まっており、ジャムにおいても超低価格の輸入品が店頭から姿を消しつつあります。ジャム業界にとってこの状況は追い風と考えられ、今後なブルーベリーに次ぐ新たな果実の台頭が待ち望まれるところです。

「ジャムの絵本」小清水正美著 農文協
JAM STORY 日本ジャム工業組合
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03-3583-8678
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03-3583-8678