

ホーム > 砂糖 > 調査報告 > さとうきび > サトウキビ供給力の将来展望
最終更新日:2010年3月6日
[2005年6月]
【調査報告〔農家経営〕〜奄美群島南部離島の担い手調査〜】
| 拓殖大学国際開発学部 | 教授 叶 芳和 |
| はじめに─合理的選択か「合成の誤謬」か |
| 1.奄美農業の価格弾力性 |
| 2.サトウキビ農業の情勢概観 |
| 3.地域ごとの条件に合わせた研究開発を |
| おわりに |
はじめに─合理的選択か「合成の誤謬」か
サトウキビ供給力の低下は、農家の合理的選択か「合成の誤謬」※か。サトウキビ栽培面積の減少はこのまま続くか、近い将来均衡点に達するか。ハーベスタ導入などの技術革新はサトウキビの供給力にどう影響するか。こうした論点が本稿の問題意識である。
鹿児島県南西諸島(奄美群島)は、サトウキビ産業が基幹作物であるが、サトウキビの収穫面積の減少で原料の確保ができず、厳しい経営状況になっている製糖会社が多く、工場によっては、稼動率は50〜60%台と低い。このまま損益分岐点以下の操業が続けば、工場の存続が危ぶまれる。もしも工場撤退となれば、その島からサトウキビ農業が消えることになる。サトウキビの波及効果の大きさから、「もしサトウキビが消えると、地域の人口は半減する」という見方もあり(もちろん、これは検証されるべき命題である)、関係者は農家を回って「1本でも、1アールでもサトウキビを植え付けて欲しい」と呼びかけている。相当な危機感である。
一方、サトウキビ栽培面積が減少してきたのは、高齢化による要因もあるが、畜産(和牛繁殖)のための牧草、花卉、野菜(バレイショ)など収益性の高い競合作物が伸びているためであり、農家にとっては合理的選択である。しかし、それによってサトウキビの栽培面積が大きく侵食されすぎると、製糖工場の撤退となり、その島のサトウキビ栽培は消滅する。その跡地を集約的作物が伸びて穴埋めできない場合、土地利用が十分でなく、農家および地域の総所得が減る可能性もある。
個々の農家の選択は合理的でも、地域全体としてみれば「合成の誤謬」が発生することになる。逆に、サトウキビから高収益作物への転換で土地利用が満たされるならば、製糖会社には厳しい事態であるが、合理的選択ということになる。
ただ、ハーベスタの導入によって規模拡大が実現し、サトウキビも粗収入2千万、3千万円という高所得農家が出現しているように、サトウキビ農業の比較生産性が回復してきた(表3参照)。こうした動きを評価すると、土地利用の競合も均衡点に近づいたという見方も出来る。
サトウキビの供給力維持(製糖会社の原料確保)と花卉・野菜など高収益作物の両立には、技術革新と経営形態の革新による比較生産性の向上、さらに単収を高めるため、農家の栽培管理技術の向上と島ごとの地域条件にあった品種の開発など、研究開発のあり方の転換が求められる。栽培管理と新品種で単収が向上すれば土地節約になり、共存共栄が図れる。サトウキビだけではなく、牧草の単収向上も必要だ。実際、双方とも研究開発の余地は大きい。
鹿児島県南西諸島(奄美群島)は、サトウキビ産業が基幹作物であるが、サトウキビの収穫面積の減少で原料の確保ができず、厳しい経営状況になっている製糖会社が多く、工場によっては、稼動率は50〜60%台と低い。このまま損益分岐点以下の操業が続けば、工場の存続が危ぶまれる。もしも工場撤退となれば、その島からサトウキビ農業が消えることになる。サトウキビの波及効果の大きさから、「もしサトウキビが消えると、地域の人口は半減する」という見方もあり(もちろん、これは検証されるべき命題である)、関係者は農家を回って「1本でも、1アールでもサトウキビを植え付けて欲しい」と呼びかけている。相当な危機感である。
一方、サトウキビ栽培面積が減少してきたのは、高齢化による要因もあるが、畜産(和牛繁殖)のための牧草、花卉、野菜(バレイショ)など収益性の高い競合作物が伸びているためであり、農家にとっては合理的選択である。しかし、それによってサトウキビの栽培面積が大きく侵食されすぎると、製糖工場の撤退となり、その島のサトウキビ栽培は消滅する。その跡地を集約的作物が伸びて穴埋めできない場合、土地利用が十分でなく、農家および地域の総所得が減る可能性もある。
個々の農家の選択は合理的でも、地域全体としてみれば「合成の誤謬」が発生することになる。逆に、サトウキビから高収益作物への転換で土地利用が満たされるならば、製糖会社には厳しい事態であるが、合理的選択ということになる。
ただ、ハーベスタの導入によって規模拡大が実現し、サトウキビも粗収入2千万、3千万円という高所得農家が出現しているように、サトウキビ農業の比較生産性が回復してきた(表3参照)。こうした動きを評価すると、土地利用の競合も均衡点に近づいたという見方も出来る。
サトウキビの供給力維持(製糖会社の原料確保)と花卉・野菜など高収益作物の両立には、技術革新と経営形態の革新による比較生産性の向上、さらに単収を高めるため、農家の栽培管理技術の向上と島ごとの地域条件にあった品種の開発など、研究開発のあり方の転換が求められる。栽培管理と新品種で単収が向上すれば土地節約になり、共存共栄が図れる。サトウキビだけではなく、牧草の単収向上も必要だ。実際、双方とも研究開発の余地は大きい。
| ページのトップへ |
1.奄美農業の価格弾力性
奄美群島は温暖な気候のため、色々な作物の栽培が可能であり、農家の作付選択は価格弾力性が高い。奄美群島の農業も市場の変化、技術進歩を背景に、ダイナミックに動いている。
(1) インターネット販売の効果
奄美群島においても、高度経済成長以降、農家戸数の減少、人口の過疎化というトレンドが支配してきた。しかし、近年、一部に農家数の増加という動きが見られる。IT技術の進歩を背景としたインターネット販売が、農家価格を引き上げたことにより、農家の供給意欲を高めている。技術進歩による歴史の逆転だ。外海離島奄美も決して停滞社会ではない。価格メカニズムで動いている。
奄美大島名瀬市金久町に、「合資会社アットマークやっちゃば」という奄美のくだもの専門店がある(「やっちゃば」は関東地方で「青果市場」のこと)。タンカン、ビワ、スモモ、パッシヨンフルーツ、マンゴー、グアバ、メロンなど、亜熱帯奄美特産の果実をインターネット通信販売している。間口6間、奥行き4間(25坪)の小さな八百屋で、まだ創業10年目であるが(創業1995年)、売上げは1億円を超える。その半分はインターネット販売である。
@やっちゃば(以下、「やっちゃば」という。)は全国に顧客を開拓することにより(インターネット顧客は1万2,000人)、奄美の特産物(とくに果実)を高値で販売することに成功している。例えば、島バナナはやっちゃばが買い付ける以前は、農協が1キロ当たり500円で買っていた。やっちゃばは全国販売力を生かして、農家から1キロ1,500円で買い付けた。1本で7キロあるので、農家は1本のバナナの木で1万500円の収入になる。栽培の手間がかかるものではないので、1本1万円以上にもなると、農家の栽培意欲を刺激し、台風被害の少ない畑の隅に10本、20本と植えつける農家が増え始めた。最近の一番の主力商品はミカンの王様といわれる奄美完熟タンカンである(2〜3月出荷)。品質格差が大きいので、優良農家と契約栽培し、良質なものばかりを販売している。
従来のような収益性の低い農業であれば、農家の高齢化と共に農家の離農が増えたが、やっちゃばの販売力と経営力で高値販売・高値買い付けが実現しているため、農家の供給力が維持されている。やっちゃばは価格効果を通して、奄美農業の供給力を高めたといえよう。農業分野は相当な財政資金が投入されてきたが、農家戸数は減少一途だった。これに対し、やっちゃばの事例は民間の経営力が農家戸数を増やすことを証明した。注目に値する現象だ。これらは、サトウキビに由来する関連商品の販売についても同様である。
(2) 瀬戸内町の農家戸数の増加現象
大島南部の瀬戸内町でも、一部で農家が増える現象がみられる。瀬戸内町は奄美群島内でも一番遊休農地が多かった。1971年(昭和46年)に拓南製糖(株)が撤収した後、サトウキビ栽培に使われていた畑は40年近くにわたって不耕作地となり荒れていた。町の耕地面積の半分が遊休農地だ。ところが、ここにきて、事情が変わってきた。畜産(和牛繁殖)が伸び始めた。米国のBSE問題で子牛価格が1頭40万円と高値なので、50頭規模で粗収入2,000万円の高所得農業になる。草地に対する需要が高まった。県営の基盤整備事業を導入して、遊休地を再開拓して、このニーズに応えた。新規参入者は建設業からの転換組が多い。多くの農家が規模拡大で100頭規模を目指している。(この畜産農家の発展は、米国産牛肉輸入再開の影響がどう現れるか注目される)。
サトウキビ農家も増え始めた。自然食ブームで、黒糖へのニーズが急増しているが、これは付加価値が高い(注:黒糖づくりは自由な市場経済下にある)。サトウキビの用途は、大型製糖工場の原料用、黒糖焼酎の原料、きび酢の原料、黒糖(含みつ糖)の4分野であるが、一番利益率の高い用途はきび酢向け、次いで黒糖であり、大型製糖工場への原料供給は一番利益率が低い(なお、図2参照)。瀬戸内町は製糖工場が無いので、サトウキビ栽培は付加価値の高い黒糖ときび酢用がほとんどである。サトウキビ生産から製品販売までの一環経営の黒糖(含みつ糖)は100グラム100円であり、1haで黒糖が7.2トン製造できるから(サトウキビ単収6トン/10a
、歩留まり12%)、収穫面積1haで粗収入720万円になる。黒糖製造は家内工業で通常、サトウキビから黒糖までの一貫経営であるから、1haで粗収入720万円、2haで1,440万円になる。これに対し、大型製糖工場への原料キビ供給は1haで粗収入120万円程度である。つまり、黒糖づくりは粗収入ベースで6倍も高い。そのため、瀬戸内町でも、サトウキビ農家が増えている。平成14年62戸、15年70戸、16年89戸である。
瀬戸内町では、拓南製糖の撤退後、畑は放棄され、遊休地化した。その後、40年近くも遊休農地となったのである。しかし、現在は畜産や黒糖が伸びており、そのための農地の供給である。ソフト先行型であることが成功の秘訣である。
ところで、牧草やサトウキビの栽培農地は、町役場がユンボ(中型、700万円)を購入し、役場農林課の職員がオペレータとして遊休農地を再開拓したものもある。こうした取り組みを背景に、サトウキビ栽培面積は平成16年29haから、17年41ha、18年50haに増える見込みである。こうした再開拓農地を利用してサトウキビ栽培が復活し、今年、同町篠川集落で小型黒糖工場が操業を開始した(工場投資1,000万円)。現在は栽培面積1.5haであるが、2〜3年後、3haを目指している。3haになれば、粗収入2,100万円の経営体の誕生となる。農林課の目標は各集落で小型黒糖工場を復活させることであり、そのために農地再開拓を進めている。遊休農地はさらに減少しよう。
遅れていた瀬戸内町でも、高収益の畜産農業が普及し始めている。サトウキビも高収益農業になった。その結果、遊休農地が急速に減少している。2,000万、3,000万円の経営体の出現は、その元を作ったのは役場による農地再開拓であり、お役所型インキュベーションといえよう。こうした施策を遂行しているのは農林課の豊永伸弥氏である。行政も人材が勝負であるということを如実に示した好例である。町長は農地からススキを追い出そうと「ノー・ススキ」運動を提唱してきたが、それが実ってきたといえよう。
| ページのトップへ |
2.サトウキビ農業の情勢概観
(1) 集約的作物との競合
サトウキビは土地利用上、花卉、野菜、牧草地と競合している。1960年代前半までは、南西諸島ではサトウキビが独占的で土地利用の8割前後を占めていたのであるが、2000年には沖永良部島では4割、徳之島、与論島でも7割に低下した(図1参照)。とくに沖永良部島でのサトウキビ栽培面積の減少が激しいが、これは1960年代から70年代にかけては花卉産業の発展、70年代後半からは野菜(とくにバレイショ)の影響が大きい。徳之島と与論島では80年代まではサトウキビの土地利用割合が高いが、ここでも沖永良部島に10年遅れて低下傾向が明瞭になった。
徳之島は花卉は少なく、1970年代から野菜(バレイショ)の成長、90年代には畜産の発展に伴う牧草地需要の伸びで、サトウキビ栽培が後退した。与論は90年代に入って畜産が成長し、牧草地がサトウキビ栽培に代替した。
ただし、注目すべきは、沖永良部島と徳之島ではサトウキビの土地利用割合が下げ止まり(1990年代後半)、近年は上昇傾向にある。これは、ひとつには競合作物側の変化がある。相対的に土地利用型のユリ球根生産から土地節約型の切花への転換、輸入野菜との競合などがその背景にある。しかし、こうした他律的要因だけではなく、サトウキビ側にも競争力向上の要因が出てきた。ハーベスタの導入・普及に伴い、高齢化に伴うサトウキビ作離れに歯止めがかかったこと、規模拡大による比較生産性の回復という要因もある。こうした諸要素を考えると、土地利用の競合も均衡点に近づいたのではないか。
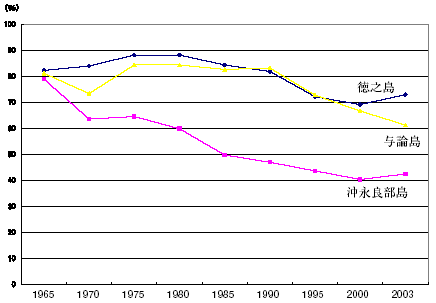
図1 土地利用におけるさとうきび栽培の占める割合の変化
表1 南西諸島におけるさとうきび栽培面積の占める割合の推移
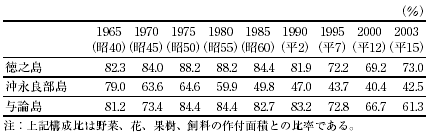
表2 奄美群島の土地利用(作付面積)の推移
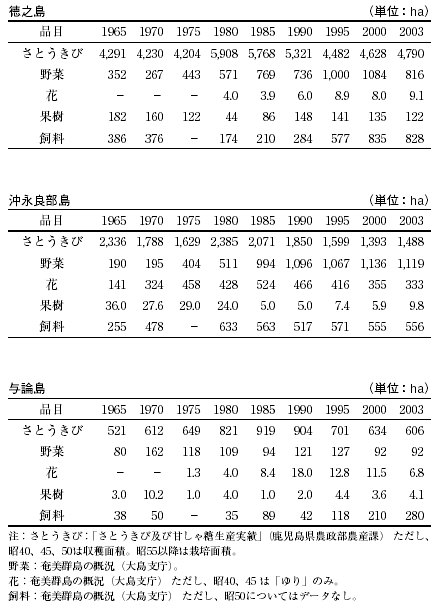
サトウキビは土地利用上、花卉、野菜、牧草地と競合している。1960年代前半までは、南西諸島ではサトウキビが独占的で土地利用の8割前後を占めていたのであるが、2000年には沖永良部島では4割、徳之島、与論島でも7割に低下した(図1参照)。とくに沖永良部島でのサトウキビ栽培面積の減少が激しいが、これは1960年代から70年代にかけては花卉産業の発展、70年代後半からは野菜(とくにバレイショ)の影響が大きい。徳之島と与論島では80年代まではサトウキビの土地利用割合が高いが、ここでも沖永良部島に10年遅れて低下傾向が明瞭になった。
徳之島は花卉は少なく、1970年代から野菜(バレイショ)の成長、90年代には畜産の発展に伴う牧草地需要の伸びで、サトウキビ栽培が後退した。与論は90年代に入って畜産が成長し、牧草地がサトウキビ栽培に代替した。
ただし、注目すべきは、沖永良部島と徳之島ではサトウキビの土地利用割合が下げ止まり(1990年代後半)、近年は上昇傾向にある。これは、ひとつには競合作物側の変化がある。相対的に土地利用型のユリ球根生産から土地節約型の切花への転換、輸入野菜との競合などがその背景にある。しかし、こうした他律的要因だけではなく、サトウキビ側にも競争力向上の要因が出てきた。ハーベスタの導入・普及に伴い、高齢化に伴うサトウキビ作離れに歯止めがかかったこと、規模拡大による比較生産性の回復という要因もある。こうした諸要素を考えると、土地利用の競合も均衡点に近づいたのではないか。
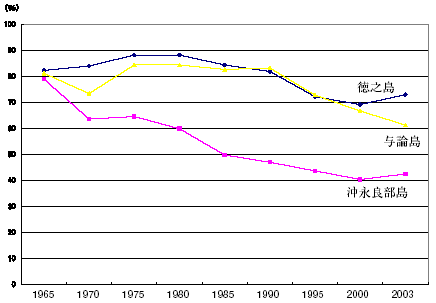
図1 土地利用におけるさとうきび栽培の占める割合の変化
表1 南西諸島におけるさとうきび栽培面積の占める割合の推移
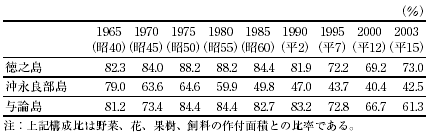
表2 奄美群島の土地利用(作付面積)の推移
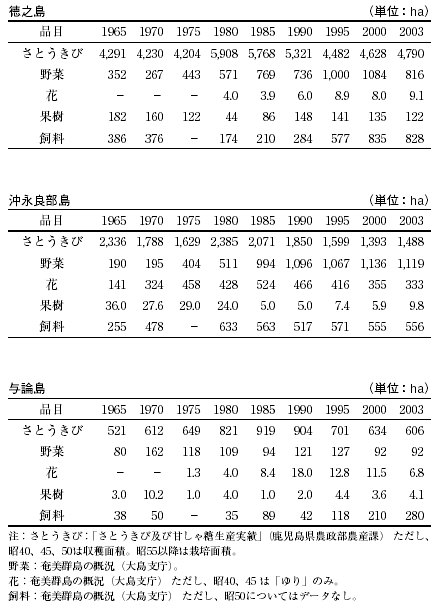
(2) ハーベスタ導入に伴う比較生産性の向上
ハーベスタの導入・普及に伴い、サトウキビは高所得農業に変貌し始めた。ハーベスタの導入で生産性が飛躍的に向上し、経営耕地の拡大、受託作業の拡大で規模拡大が実現している。通常、ハーベスタ導入農家は経営耕地10ha(借地を含む)、収穫作業請負20haが一般的な規模である。この場合、粗収入は1,800万円になる(筆者試算。サトウキビ価格2万円/トン、単収6トン/10a、収穫作業請負5,000円/トンを前提)。かつて、サトウキビは平均的に見ると、栽培規模1ha未満、粗収入50万円程度という零細・低所得農業の典型であったが、いま、かなりの高所得農家が出現している。
実際、種子島では粗収入4,000万円の農家も出現している。奄美群島でも喜界島では2,000万円農家が出てきた(『砂糖類情報』2002年3月号拙稿参照)。今回調査対象の離島でもいくつか事例が見られる。徳之島では、天城町三京地区の若山光秀氏(畜産とキビの複合経営)は収穫面積16ha(うち自作8ha)である。伊仙町阿三地区の大竹勝人氏は経営耕地の収穫21ha(自作2ha)のほか作業受託が7haある。与論島では、那間地区の林俊一氏(建設業から転換)は経営耕地7ha(すべて借地)のほか収穫作業受託が40haある。このように、収穫作業の集約化が起きており、作業受託による規模拡大が進んでいる(収穫作業受託費は1トン5,000円、1ha30万円)。ほとんどが高齢農家からの受託作業である。
いまやサトウキビで粗収入1,000万円達成はそう難しいことではなく、粗収入2,000万円以上の農家も見られるようになった。この経営発展は、ハーベスタ導入による生産性向上と高齢で引退する農家からの借地で、規模拡大が可能になったことが要因である。
こうした技術革新により、サトウキビの比較生産性は著しく向上した。表3は諸々の前提の下での試算であるが、労働生産性ベースでみると、サトウキビ(ハーベスタ導入農家)の比較生産性は1990年頃の0.20から、最近は2.25に大きく上昇した。ハーベスタ導入農家の生産性は花卉よりは低いが、畜産に匹敵し、野菜より高い。ちなみに、1戸当たり粗収入はモデル的農家のケースで、花卉2,000〜3,000万円、野菜1,000万円、畜産2,000万円、これに対しサトウキビ農家(ハーベスタ導入)は1,800万円である。まったく遜色がない。
なお、黒糖(小型工場の含みつ糖)はサトウキビから黒糖作りの一貫経営の場合、3ha規模で粗収入2,100万円であり、労働生産性ベースでも、土地生産性ベースでも、比較生産性が高い。
(3) 未来型の経営類型
表3 比較生産性(試算)
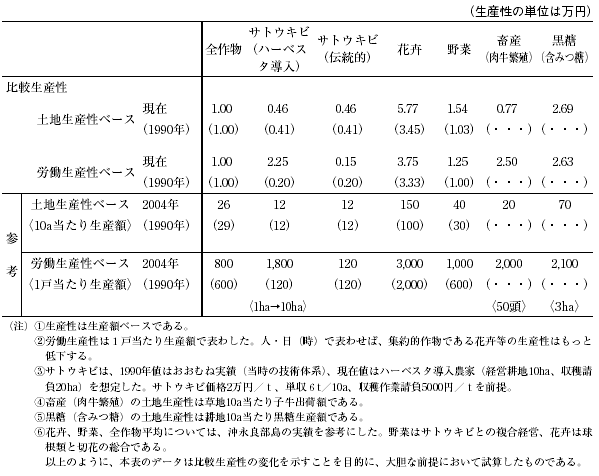
サトウキビ農業がサバイバルするためには、用途別に考える必要がある。先述したように、用途別に付加価値が5〜6倍の格差があるからだ。図2に示すように、大型製糖工場(分みつ糖)の原料用はハーベスタ導入と借地などによる規模拡大で対応する。これで高所得農業を実現する。経営規模10ha(借地を含む)、収穫作業請負20haの規模で粗収入1,800万円になる。これらの経営体を中心に地域のサトウキビ生産が行われなければ未来はない。これに対して、付加価値の高い黒糖やきび酢用は小規模ではあるが一貫経営で所得を高める。3ha規模で粗収入2,100万円になる。このように、用途別に新しい経営形態を実現すれば、比較生産性が向上し、競合作物と競争できる。
このような経営形態はすでに各島に散見できるようになったが、今後はもっと一般的な姿になろう。
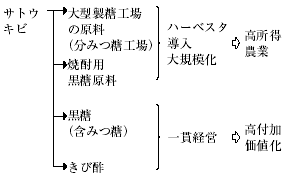
図2 サトウキビ農業の用途別・経営類型
高所得農業が可能になったことで、サトウキビは若者の農業になった。従来、サトウキビは高齢者農業であった。サトウキビは経営サイズが1〜2ha、粗収入100万円以下、作業も3K労働的で、若者はサトウキビ作を忌避した。しかし、ハーベスタの出現により、過酷な収穫作業から解放され、しかも高齢農家の作業請負や引退農家からの借地で規模拡大できるようになったので、若者の新規参入が見られる。ハーベスタの運転は青壮年が主体であり、サトウキビで規模拡大、高所得農業を実現しているのは青壮年が中心である。担い手は若者にシフトしつつある。
また、サトウキビ栽培面積が下げ止まる要因も出てきた。従来、過酷な収穫作業の制約から高齢農家の中にはサトウキビ作から撤退する傾向もあったが、自分は比較的軽労働の植え付け、栽培管理だけを行い、収穫はハーベスタ集団に任せることで、サトウキビ栽培を続ける農家も多くなった。こうして、ハーベスタの普及に伴って、サトウキビ栽培の減少を抑制する効果が出てきた。実際、徳之島、沖永良部島では1998年以降、サトウキビの栽培面積が拡大に転じている。技術革新が歴史の逆転をもたらした。下げ止まりの可能性が出てきたといえよう。
図式的に言えば、土地利用は次のように言えよう(図3参照)。南西諸島では、1950年代まではサトウキビ栽培が独占的であったが、60年代にユリ球根栽培が盛んになり、サトウキビ栽培面積は減少に転じた。70年代後半からは野菜の高成長がサトウキビと競合し、その後90年代には農家の高齢化で担い手も減り、サトウキビの土地利用は半分以下になった。しかし、他方、90年代に入ると、サトウキビに有利な要因が出てきた。第1に、花卉分野で、相対的に土地利用型であるユリ球根栽培から切花生産へという花卉産業の内容変化で土地需要が減少し(沖永良部のユリ球根栽培は1992年の94haから2003年の17haに減少)、サトウキビの急激な後退がスローダウンする。そして、90年代後半からはハーベスタの普及で下げ止まる。2000年代に入ると、切花も野菜も、輸入品との競合で、土地需要は減少傾向に転じた。このような動きに加えて、サトウキビの比較生産性の回復から、サトウキビの土地利用が下げ止まり、上昇傾向さえ見られるようになった。
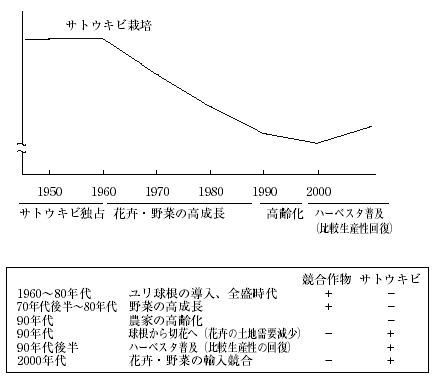
図3 土地利用の変化(模式図) ― 沖永良部島ケース―
(4) 製糖工場の稼働率
奄美群島のサトウキビ栽培は、1960年代後半(昭和40年代前半)まではかなりの速度と規模で発展したが、その後は停滞ないし減少傾向になった。製糖工場は原料(サトウキビ)の不足により、操業停止に追い込まれた工場もある。サトウキビ栽培面積のピークは1980年代前半で、各島とも近年の生産量はピーク比半減している(付表参照)。
こうした原料供給の後退で、製糖会社は工場を集約化したところもある。徳之島の南西糖業(株)はかつては3工場体制であったが、1992年頃から収穫面積が急減し始めたので、1995年に1工場を休止し、2工場体制になった。しかし、その後もサトウキビの供給力は後退を続け、生産量はピーク時の36万トンから(各工場12万トン)、現在は20万トンに減った。2工場の操業を維持することも容易ではない状況である。徳之島は耕地面積が多く、奄美群島の中ではサトウキビ生産が一番盛んな地域であるにもかかわらず、製糖会社はこのような厳しい状況にある。
各島の製糖工場の最近の稼働率を見ると、種子島は91%と高い。奄美群島では徳之島82%、喜界島72%は比較的に高いが、沖永良部島は50%、奄美大島(笠利)58%、与論島69%と低い(注:いずれも1997/98から2003/04年度の7年間のうち最大、最小を除く5ヵ年の平均。稼働率=原料処理量÷1日当たりの処理能力÷120日(適正稼動日数)×100)。稼働率50%台は損益分岐点以下での操業であり、経営は赤字になる。このままでは工場撤退に追い込まれる危険もある。原料のサトウキビ確保が最大の課題である。
沖永良部島の原料不足は、収益性の高い花卉や野菜(特にバレイショ)との土地利用の競合、与論島の原料不足は畜産(牧草地)との競合の結果である。個々の農家にとっては収益性の高い作物を作付するのは合理的な選択である。しかし、先述したように、それによってサトウキビの栽培面積が大きく侵食されると、製糖工場の撤退、その島のサトウキビ栽培の消滅につながり、農家および地域の総所得が減る可能性もある。地域全体としてみれば「合成の誤謬」が発生することになる。このリスクを緩和する政策は何か。われわれなりの政策提言を出さなければならない。
先述したように、サトウキビ栽培の一方的な減少の局面はもう過ぎた。サトウキビも競合作物も成長できる体系を考えなければならない。
| ページのトップへ |
徳之島、沖永良部島、与論島の土地利用状況は、99%、82%、91%(平成14年度)であるが、島によって遊休農地はほとんどない。耕地利用率も100%を超えている(沖永良部は130%、全国平均は94%)。こうした状況の下では、サトウキビ作付面積を増やす場合、他作物の作付面積を削減することになるので、サトウキビの作付拡大はなかなか困難を極める。一方、製糖工場は原料不足で危機に直面している。
サトウキビと他作物の土地利用上の競合を緩和する術を開発することが喫緊の課題である。それには、サトウキビだけではなく、各作物の土地生産性を向上させることが課題である。
サトウキビの単収(土地生産性)が高まれば、サトウキビの作付面積を拡大しなくてもサトウキビ生産量が増えて、製糖工場の原料確保を可能ならしめる。逆に、牧草の土地生産性が高まれば、草地需要が抑制され、サトウキビ畑との競合が緩和され、畜産の成長とサトウキビが共存できる。世界的に牧草は寒冷地で発達してきたが、暖地の牧草は研究開発が遅れている。現在、南西諸島ではローズグラスを中心に飼料作物が栽培されているが、新品種の導入をはじめ研究開発の余地は大きいと思われる。
サトウキビと他作物の土地利用上の競合を緩和する術を開発することが喫緊の課題である。それには、サトウキビだけではなく、各作物の土地生産性を向上させることが課題である。
サトウキビの単収(土地生産性)が高まれば、サトウキビの作付面積を拡大しなくてもサトウキビ生産量が増えて、製糖工場の原料確保を可能ならしめる。逆に、牧草の土地生産性が高まれば、草地需要が抑制され、サトウキビ畑との競合が緩和され、畜産の成長とサトウキビが共存できる。世界的に牧草は寒冷地で発達してきたが、暖地の牧草は研究開発が遅れている。現在、南西諸島ではローズグラスを中心に飼料作物が栽培されているが、新品種の導入をはじめ研究開発の余地は大きいと思われる。
(1) 栽培管理の向上
サトウキビは、品種改良と栽培管理による単収向上が期待される。単収は品種より栽培管理の効果が大きいといわれる。従って、農家の取り組みに依存する部分が大きい。
注目すべきは、近年、サトウキビの土地生産性が低下してきている。これはハーベスタ比率が高まったこととの関連が指摘されている。ハーベスタ導入による踏圧・飛散ロスが10%近くあるとの見解もある。収穫ロスは5%以上あると見られている。畑の踏圧は株出しの生産性低下をもたらしているので、収穫直後(1週間以内)の管理が大切であるが、最近の農家は、管理作業に熱心だとは言い難いようだ。株出し管理機の改良とその普及があれば、この問題はある程度解消しよう。(注:徳之島では株出し管理機の普及は昨年から始まったばかりである)。
株揃え機の導入も選択肢であろう。日当たりを良くするため、根の上に被さった収穫後の残渣と土壌を取り除く作業機である。これで発芽がよくなる。株出し管理機は1台110万円と高いが、株揃え機は30〜40万円と安い。加えて、生産性が高い。株出し管理機は「株揃え+根切り+施肥+除草剤」の4作業を同時に行う機械なのでスピードが遅い。これに対して、株揃え機は単能機なのでスピードが速く、発芽率を高める目的で面積をこなすにはこの方がよい。
(2) 島ごとの条件に合わせた研究開発を
品種改良については、近年、次つぎと新しい品種が開発されているが、問題は地域によって適応性が異なることである。
南西諸島では、現在、品種はNiF8とNi17が多い。8号は収量性が高く、17号は台風に強いということで選好されている。しかし、17号は干ばつに弱く、かん水対策が必要である。Ni9は17号より干ばつに強いが、黒穂病に弱いという欠点がある。黒穂病が発生していない地域には適する。このように、品種別に特性があり、適性品種は地域ごとに異なる。現場の農家の人たちは「キビは島ごとに品種を選ぶ」という(注:牧草はどの島もローズグラス)。従って、各島ごとに、島の条件に合った品種の開発が望ましい。
従来、鹿児島県のサトウキビ品種は全県一本で適性品種を開発してきたが、10年位前から、熊毛地方(種子島)と奄美群島を分けて開発目標を設定、さらに5年位前からは奄美群島の北部と南部を分けて考えるようになった。良い方向である。今後はこの考えをさらに進めて、奄美群島の中でも島ごとに条件が異なるので、島ごとの条件に合った品種開発のR&D(研究開発)努力が望まれる。また、島の中でも場所によって地域条件が異なるので、リスクを軽減するためには島ごとに3品種位は必要であろう。ハーベスタ適性品種、梢頭部の飼料利用に適した品種の開発も課題である。
また、南西諸島として地域の持つ条件の類似性を考えるならば、品種開発においては県を超えて沖縄県とのさらなる連携も考えるべきであろう。
(3) 総合的生産性概念からのR&D努力
限られた研究開発資源をサトウキビ産業に投入するのは疑問という考え方があるのではないか。しかし、この考え方は必ずしも正しくはない。サトウキビの土地生産性を向上させることが、集約的作物の発展に寄与する。
サトウキビの単収が向上すれば、製糖工場の稼働率を一定水準に維持するための栽培面積は少なくて済む。その分、草地や野菜畑に使える。つまり、サトウキビの土地生産性を高めるための研究開発は、畜産や花卉、野菜の発展に寄与する。逆に、牧草の土地生産性が高まれば草地需要が抑制され、サトウキビの生産が増える。このように、土地利用が競合している場合、どの作物についてであれ生産性を高める研究開発を行えば、全体の発展につながる。部分均衡ではなく、一般均衡の視点で考えるべきである。
現在、鹿児島県のサトウキビ対策は「離島対策」が中心であって、集約的作物については研究資源を投入しているものの、サトウキビについては比較的少ない。一般均衡的発想から、サトウキビの研究開発投資を検討してはどうか。
研究開発の成果でサトウキビ生産が増え、製糖工場の稼働率が上昇すれば、工場のコストダウンになり、消費者・納税者負担の軽減にもつながる。国民負担の軽減という視点からも、サトウキビの単収向上による供給増大は大切である。
| ページのトップへ |
サトウキビは輪作体系におけるクリーニング作物という重要な役割がある。野菜や花卉のあとにサトウキビを植えると、連作障害を防ぎ、その後の野菜や花卉はいいものが取れる。クリーニング作物として、サトウキビは野菜や花卉と共存してきた。また、梢頭部の粗飼料活用で畜産とも共存してきた。
しかし、ハーベスタの普及と経営形態の進歩による比較生産性向上という積極的要因で、サバイバルの道が開けてきた。しかも、2,000万、3,000万円の高所得農業が可能だ。この展望の実現を追及すべきである。
もうひとつ見逃せないのは、バイオマスエネルギーという視点だ。原油価格は1バーレル50ドル台に高騰している。これはイラク情勢などの短期的要因もあるが、中国の経済発展に伴う石油需要の増大など長期すう勢的要因が背景にある。
経済的要因だけでも、WTI原油(米国産)40ドル台、中東原油30ドル台という見通しが多い。そのため、世界的に代替エネルギー開発の研究開発努力がなされており、バイオマスエネルギーも有力視されている。原油価格が40ドルになれば、サトウキビ(エタノール計画)は石油と競争できるといわれる。アメリカ政府の研究によると(1999年、クリントン大統領時代)、将来石油代替が進み、2050年には化石燃料とバイオマスエネルギーが半々になるという予測ケースもある(ただし、将来も石油・石炭がエネルギー需要の主流という見方のほうが多い)。
石油高価格時代が展望されるのであれば、サトウキビはバイオマスエネルギーとして新たな用途が生れる。しかも、膨大な需要が発生する。南栄糖業(株)の川口義洋社長によると、「サトウキビの新しい用途の拡大で、食糧としての砂糖価格は上昇する。砂糖が奄美を救うときがまた来る」。夢のような世界である。サトウキビの新しい位置づけである。また、バイオマスエネルギーになれば、燃料が循環型になるだけではなく、CO2吸収にもなり、地球環境保全に貢献する。この夢を生かすためにも、サトウキビの研究開発努力が望まれる。
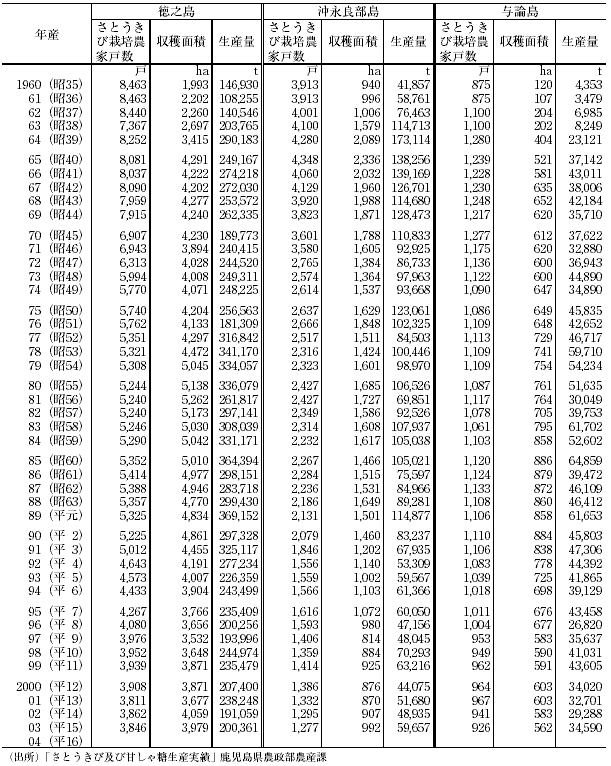
しかし、ハーベスタの普及と経営形態の進歩による比較生産性向上という積極的要因で、サバイバルの道が開けてきた。しかも、2,000万、3,000万円の高所得農業が可能だ。この展望の実現を追及すべきである。
もうひとつ見逃せないのは、バイオマスエネルギーという視点だ。原油価格は1バーレル50ドル台に高騰している。これはイラク情勢などの短期的要因もあるが、中国の経済発展に伴う石油需要の増大など長期すう勢的要因が背景にある。
経済的要因だけでも、WTI原油(米国産)40ドル台、中東原油30ドル台という見通しが多い。そのため、世界的に代替エネルギー開発の研究開発努力がなされており、バイオマスエネルギーも有力視されている。原油価格が40ドルになれば、サトウキビ(エタノール計画)は石油と競争できるといわれる。アメリカ政府の研究によると(1999年、クリントン大統領時代)、将来石油代替が進み、2050年には化石燃料とバイオマスエネルギーが半々になるという予測ケースもある(ただし、将来も石油・石炭がエネルギー需要の主流という見方のほうが多い)。
石油高価格時代が展望されるのであれば、サトウキビはバイオマスエネルギーとして新たな用途が生れる。しかも、膨大な需要が発生する。南栄糖業(株)の川口義洋社長によると、「サトウキビの新しい用途の拡大で、食糧としての砂糖価格は上昇する。砂糖が奄美を救うときがまた来る」。夢のような世界である。サトウキビの新しい位置づけである。また、バイオマスエネルギーになれば、燃料が循環型になるだけではなく、CO2吸収にもなり、地球環境保全に貢献する。この夢を生かすためにも、サトウキビの研究開発努力が望まれる。
(参考)叶芳和『農業ルネッサンス』講談社、1990年(第27章「奄美農業のルネッサンス」)参照。ここでは花卉など高付加価値作物の発展と同時に、サトウキビをクリーニング作物と評価して将来を展望した。なお、本論分の初出は毎日新聞社刊『農業富民』1987年12月号である。当時と現在では筆者の見方に若干の変化があるが、ハーベスタの出現・普及がその背景である。
〈追記〉南西諸島のサトウキビ農業に関する筆者の既発表論文は、『砂糖類情報』2002年3月号(種子島・喜界島)、同2002年4月号(沖縄本島・宮古島・伊良部島)、同2002年11月号(奄美大島)がある。
付表 さとうきびの生産推移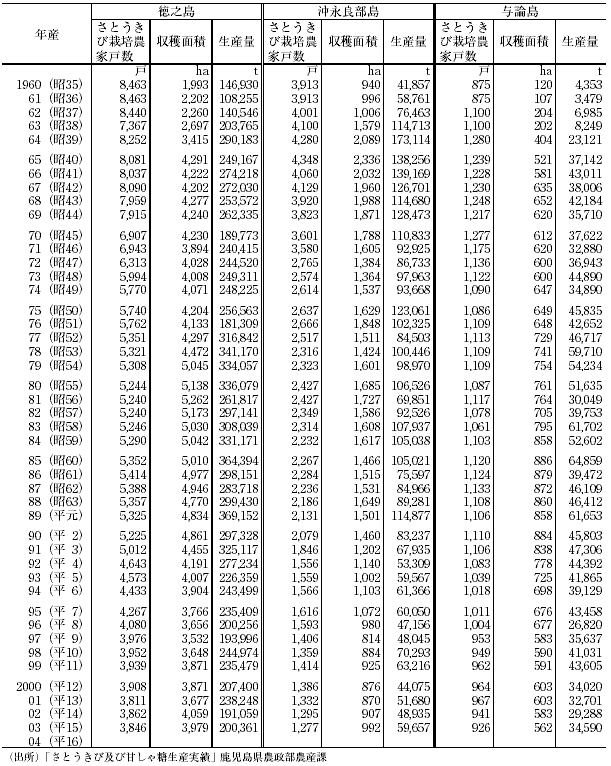
| ページのトップへ |
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03-3583-8678
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03-3583-8678










