しかも、こうした純白の砂糖を好む傾向は、日本だけのことでもない。ヨーロッパ人はむろんそうだし、ヨーロッパ人に砂糖を教えたイスラームの世界でも同様であるようだ。純白の砂糖の方が、味が良いのか。より甘いのか。好みということになると、黒糖の方が好きという人も少なくはないだろう。精製糖は、精製の過程を繰り返していて、コストがかかっているし、化学的に純粋だから、保存料としての効果などは優れていることは間違いない。しかし、どうもそういうことが原因でもなさそうである。いったいこの感覚は、どこからきたのだろうか。
イスラームの医学や中世ヨーロッパの医学では、砂糖は万能の薬品とみなされていたが、医療用に用いる場合は、いずれもミルクなどの白い食品との併用が勧められていた。
そもそも白という色には、神秘的な力があるとみなされることが多い。日本の神道における神主や巫女の衣装から、清めの塩に至るまで、万事そういうことになっている。反対に「腹黒い」などという場合の黒は、何やらよこしまな色である。こうして、純白の精製糖には、神秘的な力を感じる人が、世界中で多かったようなのである。
純白の砂糖が、そのシンボリックな意味を最もよく発揮できたのは、砂糖の細工物においてであった。今日、日本の結婚式では、「ウェディング・ケーキ」がつきものになっている。芸能人の場合などは、そのケーキの大きさが、結婚式の豪華さの基準にされたりするほどである。しかし、いったいなぜ結婚式にケーキなのだろうか。実は、「ウェディング・ケーキ」の源流は、砂糖細工の菓子にあるといわれている。
砂糖細工の起源は、これも明らかにイスラーム世界にあった。11世紀には、折から飢饉と疫病が蔓延していたにもかかわらず、ときのカリフ、ザヒールは、祭日に「157人の人間のいる、7つのテーブル大の宮殿」を砂糖でつくらせたといわれている。砂糖でモスクの模型をつくった支配者もあり、最後に貧民がそれを分け与えられて食べたともいわれている。
おそらくこの影響であろうが、ヨーロッパでも中世には、各国の王室で、同様の習慣が広がっていたことが知られている。一般に、こうした細工ものをつくるには、砂糖と油、粉末のアーモンド、植物性ガムなどでつくったマジパンとよばれる生地が使われた。この生地を焼き固めたものが、ここでいう「砂糖細工」である(図1、図2)。
「砂糖細工」は、繊細な表現ができ、メッセージや献辞を書き込むこともできたから、上流階級の間では、たちまち大流行となった。今日でも、さまざまな機会に、じつに繊細で多様な砂糖細工を見ることができる。
中世の王族の宴会にあっては、料理の合間に、このような細工ものが提供されて鑑賞するのが普通であった。例えば、イギリス国王ヘンリ4世の結婚式では、3コースの肉料理と、3コースの魚料理が供されたが、それぞれの最後は、いずれも「砂糖細工」によって、締めくくられた。
「砂糖細工」には、家紋や城郭、乗馬、塔、熊、猿などをかたどった簡単なものから、戦場の風景を壮大なパノラマとして再現するものや、大砲の弾が飛び出したり、本物の蛙などが現れる、からくり風のものもあった。
メッセージ性の強い「砂糖細工」もあった。むろん、実際に献辞がそえられることもあった。ヘンリ6世の戴冠式に供された「砂糖細工」は、二人の聖人がそれぞれの家紋のついた武具に身を固めた姿が再現されており、その真ん中に、国王ヘンリとおぼしき人物が、これも家紋付きの武具に身を固めており、二人の聖人は、聖書の中の次の一句を口にしている。いわく、「同じ家紋をもつ二人の完璧な王を見習え」と。こうして、「砂糖細工」は、食べる前に「鑑賞する」芸術品、といっていい過ぎなら、工芸品であった。しかし、同時にそれはまた、「食べる前に読む」こともできたのである。
こうした動きの背景にあったのは、権威の象徴として「宴会」の重要性が、歴史の進行とともに、高まっていったという事実である。中世末以来、ステイタスの高い者、権力や権威を誇示したい者にとって、派手な宴会は不可欠なシンボルとなった。当時、頻発された身分ごとに着用を許される衣服を規制した「ぜいたく禁止法」(詳しくは、拙著『洒落者たちのイギリス史―騎士の国から紳士の国へ』を参照)が、しばしば宴会にも言及しているのは、このためである。「砂糖細工」は、宴会の象徴でもあったから、人びとがこの法の網をくぐってでも、競って派手なものを出そうとしたのは当然である。
ところで、中でも面白いもののひとつに、1503年にオックスフォード大学の総長がその就任の際の祝宴に供した「砂糖細工」がある。記録によると、それは次のような趣向になっていた。すなわち、「オックスフォード大学の8つの塔をかたどってあり、そのひとつひとつに総長を先導する式典係がいた。塔の下には、ときの国王の人形も置かれており、その国王に、正装した大勢の博士たちに囲まれた総長が、ラテン語の詩4編を捧げ、国王がこれに応えている」ものであった。
この総長は、イギリスで第一級の聖職者でもあったから、砂糖に何か神秘的な魔力を感じるのは、世俗の権力者ばかりではなく、聖職者でも学者でも、選ぶところはなかったようなのである。
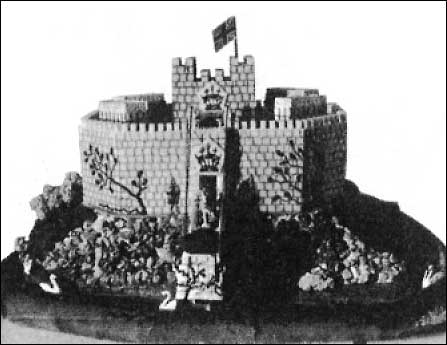
図1 砂糖でつくった中世の城の模型
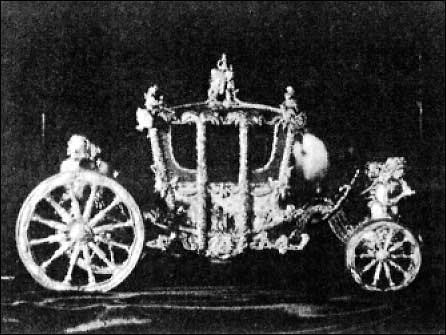
図2 砂糖でつくったイギリス王室公式馬車の縮尺模型(80分の1)












