

ホーム > 砂糖 > 視点 > 食と文化 > “クスリ”としての砂糖
最終更新日:2010年3月6日
[2005年11月]
【今月の視点〔医学/健康〕】
| 千葉大学大学院薬学研究院 教授 戸井田 敏彦 |
| 1.はじめに |
| 2.医薬品としての砂糖 |
| 3.分析試薬としての砂糖 |
| 4.工業製品としての砂糖 |
| 5.おわりに |
1.はじめに
“砂糖”をキーワードにしてインターネットの検索エンジンで調べてみると、砂糖の先物取引など相場に関する情報から、砂糖を使わないお菓子の作り方、砂糖を用いた化学実験など、そのヒット数の多さに驚く。中には「砂糖は体も心も狂わせる―学校・家庭内暴力も砂糖のとりすぎが関係」と題された宗教関係者が著した本の宣伝広告まである1)。この本の著者の主張する根拠は未確認であるが、砂糖が健康を指向する一般人から目の敵にされ、健康維持・増進に反する大敵の一つにリストアップされているとは噂では聞いていたが、それを目の当たりにしてさらに驚いた。砂糖の栄養学的な価値、製糖の産業としての重要性を思い、また生体内糖鎖の機能研究に携わるものの一人として、砂糖がいわれのない誹謗中傷を受けているようで胸が痛む思いである。幸い世界保健機構(World
Health Organization, WHO)および国連食糧農業機関(Food Agriculture Organization、FAO)による砂糖の健康への影響を調べた結果が1997年4月に報告されており、糖尿病、肥満などのいわゆる成人病と砂糖の消費には因果関係がないことが疫学的に証明されていると知り、甘い菓子類に目のない著者としては、ひとまず安心した次第である。少し冷静になって考えれば、世の中に出回るいずれの食物も弊害があるとすれば摂取法が問題なのであり、適量を食している限り食物それ自体が有害・有毒などとは科学者でなくとも容易に気が付く。しかし虫歯だけは砂糖を含めた糖質の摂取量に関係するようであり、食事後の口腔内の洗浄は怠らないようにしたい。
一方砂糖の歴史を紐解いてみると、既に紀元前2000年頃にはインドで砂糖が使われていたようで、サトウキビから砂糖を作ったのはインドが最古といわれている。インドの砂糖やサトウキビは、アラビア人によってペルシャ・エジプト・中国などへと伝えられたようである。日本には奈良時代に鑑真和尚によって伝えられたといわれているが史実と一致しない点もあり、定かではない。江戸時代の将軍徳川吉宗が琉球(現在の沖縄県)からサトウキビをとりよせ、サトウキビの栽培を奨励したとの記録がある2)。
また、ヨーロッパには11世紀に十字軍が持ち帰り、地中海周辺でサトウキビが栽培されるようになったといわれている。1747年にドイツの化学者がテンサイから砂糖と同じ成分、すなわちショ糖を取り出すことに成功した。またこれを機にフランスやドイツでテンサイが栽培されるようになったといわれ、ナポレオンがこのテンサイに注目し、製糖業が発達した。その後の砂糖に関わる歴史を調べてみると、奴隷制、産業革命などさまざまな歴史上の出来事と深く関わっているようで、興味深い2)。
一方、筆者が専門とする薬学領域における砂糖に着目すると、最近改訂された日本薬局方14局にも砂糖は“白糖”、“精製白糖”としてほかの医薬品とともに収載されており、正真正銘の医薬品である。繰り返しになるが、肥満、糖尿病などの原因物質の一つとして砂糖が言われなき迫害を受けているようにも思え、今回砂糖に関して薬学的な観点からできるだけ客観的に、その有効性を含めた性質について紹介してみたい。
一方砂糖の歴史を紐解いてみると、既に紀元前2000年頃にはインドで砂糖が使われていたようで、サトウキビから砂糖を作ったのはインドが最古といわれている。インドの砂糖やサトウキビは、アラビア人によってペルシャ・エジプト・中国などへと伝えられたようである。日本には奈良時代に鑑真和尚によって伝えられたといわれているが史実と一致しない点もあり、定かではない。江戸時代の将軍徳川吉宗が琉球(現在の沖縄県)からサトウキビをとりよせ、サトウキビの栽培を奨励したとの記録がある2)。
また、ヨーロッパには11世紀に十字軍が持ち帰り、地中海周辺でサトウキビが栽培されるようになったといわれている。1747年にドイツの化学者がテンサイから砂糖と同じ成分、すなわちショ糖を取り出すことに成功した。またこれを機にフランスやドイツでテンサイが栽培されるようになったといわれ、ナポレオンがこのテンサイに注目し、製糖業が発達した。その後の砂糖に関わる歴史を調べてみると、奴隷制、産業革命などさまざまな歴史上の出来事と深く関わっているようで、興味深い2)。
一方、筆者が専門とする薬学領域における砂糖に着目すると、最近改訂された日本薬局方14局にも砂糖は“白糖”、“精製白糖”としてほかの医薬品とともに収載されており、正真正銘の医薬品である。繰り返しになるが、肥満、糖尿病などの原因物質の一つとして砂糖が言われなき迫害を受けているようにも思え、今回砂糖に関して薬学的な観点からできるだけ客観的に、その有効性を含めた性質について紹介してみたい。
| ページのトップへ |
2.医薬品としての砂糖
砂糖(以下ショ糖)は植物界に広く存在し、サトウキビからショ糖を作ることは東洋で古くから行われていた。1747年Andreas S. Marggrafがサトウダイコン中にショ糖を発見し、1798年彼の門人Franz
Achardはドイツでショ糖製造工場を設立した。ショ糖は当初大変な貴重品で、精製したショ糖の白く輝くその外観の美しさから想像される神秘性と、その耽美な味覚から万能薬として珍重されたようである。その後ヨーロッパでは中南米におけるショ糖栽培の拡大を基盤としてショ糖が日用品となり、現在に至っている。ショ糖の化学構造については、1920〜1935年ごろにWalter
N. HaworthやClaude S. Hudsonらによって研究・確定された。Pictetらは化学的に合成したと報告したが結局天然品とは異なり、Raymond
U. Lemieuxらの報告(出発原料の5%の収率)まで待たねばならなかった。酵素的にはWilliam Z. Hassidらにより細菌由来の酵素を用いて合成されたが3)、現在もなおサトウキビ、サトウダイコンなどの植物から精製するのが最も効率がよく、工業的にも世界中で製糖が行われているようである。
ショ糖の物理的・化学的性質としては、白色、甘味のある単斜晶系結晶。融点185℃、約200℃で褐色の非結晶質で構造不明のカラメルになる。水に対する溶解度は200g/100mL(20℃)以上で、ほとんど自由に溶ける。アルコールの一種であるメタノールにはよく溶けるが、95%エタノールにはほとんど溶けない。しかしアルコールを含むリキュール類(エタノール濃度15〜25%)にはよく溶けるため、カクテル飲料に広く用いられている。果糖とブドウ糖からなる二糖類であるが、加水分解して単糖にしないと還元性を示さない。この加水分解に伴い、旋光度が右旋性から左旋性に変化するため、これを転化と称し、生成物を転化糖と呼ぶ。清涼飲料、調味料などに添加物としてこの名称が使用されており、なじみの深い読者も多くあるに違いない。ショ糖は用途としてはいうまでもなく、史上最も重要な甘味料である。さまざまな砂糖製品として栄養料、調味料、嗜好品および保存料として広く多量に用いられている。医薬品としては日本薬局方6局から白糖および精製白糖として収載され、内服薬の矯味剤(味の改善・調節)、糖衣、内外用薬の賦形および希釈剤として用いられている。また、血糖値を下げる膵臓ホルモンのインシュリンショック療法の際の血糖低下防止用に用いられている。いずれにしても、ショ糖の医薬品としての重要性は高く、今後も日本薬局方から消えることはないものと考えられる。
一方、中性のショ糖分子に含まれる8個の水酸基(−OH基)を、化学合成によりすべて硫酸エステル(−OSO3H)として酸性の分子に変換した硫酸化ショ糖(スークロースオクタサルフェート、8個の硫酸エステルを含むため与えられた英語表記による名称。Sucrose octasulfate.)の金属アルミニウム塩(硫酸化ショ糖アルミニウム、硫酸エステルに含まれる水素Hが金属であるアルミニウムで置換された中性の化合物)は“スクラルファート”(商品名:アルサルミン、中外製薬株式会社より製造・発売されている)と呼ばれる消化性潰瘍治療剤として用いられている(図1)。薬理作用としては胃液に含まれる消化酵素ペプシンに対する阻害作用や、胃酸に対する抑制作用、胃粘膜保護作用、再生胃粘膜発育促進作用、潰瘍治癒効果などが認められており、胃潰瘍、十二指腸潰瘍の初期治療に用いられている。さらに医薬品の場合はいずれも多かれ少なかれ副作用が問題となるが、スークロースオクタサルフェートの場合は基剤となるショ糖の安全性も含めて、体内に吸収されることもないといわれており、安全性の高い医薬品であるといえよう。蛇足になるが、筆者らは最近このスークロースオクタサルフェートを硫酸化糖類のモデル化合物として用い、それまで困難といわれていた硫酸化糖類の質量分析法を模索し(図2)、大きな成果を挙げた4)。すなわち田中耕一氏のノーベル賞で有名になった”質量分析法“の分野で、それまで実施が不可能であった、分子中に数多くの硫酸エステルをもつ糖鎖(ここではスークロースオクタサルフェート)の質量分析に、世界で初めて成功したのである。これは生体内にも多数存在する他の硫酸化糖鎖の生物学的機能を研究する上で、大きな第一歩を踏み出すきっかけとなった4)。
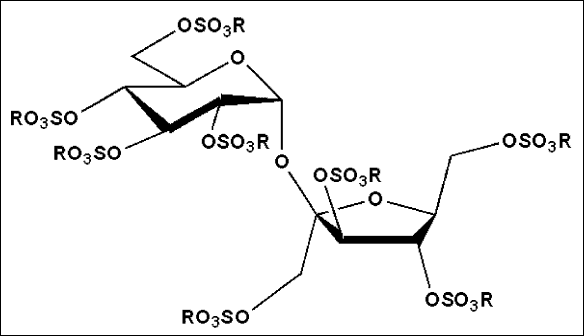
図1 スクラルファートの構造
R、対金属
また、ショ糖を構成するブドウ糖は脳が唯一消費可能なエネルギー源として知られ、1日に健康な成人の脳は約120〜150グラムのブドウ糖を消費するといわれている。単糖であるブドウ糖をヒトが意識して摂取することはまれで、ほとんど穀類に含まれるデンプンおよびショ糖から体内で酵素分解によって生じたブドウ糖である。脳は唯一このブドウ糖をエネルギー源としているのであり、本を読んだり、思考して脳を使うと、脳のブドウ糖の消費も当然ながら増加する。私事で恐縮だが、ダイエットに夢中になるわが家の住人たちに対して筆者は、常日頃から本を読み思索に励むことが効率の良いダイエット法であるとことあるごとに進言し、煙たがられている毎日を送っている。
ショ糖の物理的・化学的性質としては、白色、甘味のある単斜晶系結晶。融点185℃、約200℃で褐色の非結晶質で構造不明のカラメルになる。水に対する溶解度は200g/100mL(20℃)以上で、ほとんど自由に溶ける。アルコールの一種であるメタノールにはよく溶けるが、95%エタノールにはほとんど溶けない。しかしアルコールを含むリキュール類(エタノール濃度15〜25%)にはよく溶けるため、カクテル飲料に広く用いられている。果糖とブドウ糖からなる二糖類であるが、加水分解して単糖にしないと還元性を示さない。この加水分解に伴い、旋光度が右旋性から左旋性に変化するため、これを転化と称し、生成物を転化糖と呼ぶ。清涼飲料、調味料などに添加物としてこの名称が使用されており、なじみの深い読者も多くあるに違いない。ショ糖は用途としてはいうまでもなく、史上最も重要な甘味料である。さまざまな砂糖製品として栄養料、調味料、嗜好品および保存料として広く多量に用いられている。医薬品としては日本薬局方6局から白糖および精製白糖として収載され、内服薬の矯味剤(味の改善・調節)、糖衣、内外用薬の賦形および希釈剤として用いられている。また、血糖値を下げる膵臓ホルモンのインシュリンショック療法の際の血糖低下防止用に用いられている。いずれにしても、ショ糖の医薬品としての重要性は高く、今後も日本薬局方から消えることはないものと考えられる。
一方、中性のショ糖分子に含まれる8個の水酸基(−OH基)を、化学合成によりすべて硫酸エステル(−OSO3H)として酸性の分子に変換した硫酸化ショ糖(スークロースオクタサルフェート、8個の硫酸エステルを含むため与えられた英語表記による名称。Sucrose octasulfate.)の金属アルミニウム塩(硫酸化ショ糖アルミニウム、硫酸エステルに含まれる水素Hが金属であるアルミニウムで置換された中性の化合物)は“スクラルファート”(商品名:アルサルミン、中外製薬株式会社より製造・発売されている)と呼ばれる消化性潰瘍治療剤として用いられている(図1)。薬理作用としては胃液に含まれる消化酵素ペプシンに対する阻害作用や、胃酸に対する抑制作用、胃粘膜保護作用、再生胃粘膜発育促進作用、潰瘍治癒効果などが認められており、胃潰瘍、十二指腸潰瘍の初期治療に用いられている。さらに医薬品の場合はいずれも多かれ少なかれ副作用が問題となるが、スークロースオクタサルフェートの場合は基剤となるショ糖の安全性も含めて、体内に吸収されることもないといわれており、安全性の高い医薬品であるといえよう。蛇足になるが、筆者らは最近このスークロースオクタサルフェートを硫酸化糖類のモデル化合物として用い、それまで困難といわれていた硫酸化糖類の質量分析法を模索し(図2)、大きな成果を挙げた4)。すなわち田中耕一氏のノーベル賞で有名になった”質量分析法“の分野で、それまで実施が不可能であった、分子中に数多くの硫酸エステルをもつ糖鎖(ここではスークロースオクタサルフェート)の質量分析に、世界で初めて成功したのである。これは生体内にも多数存在する他の硫酸化糖鎖の生物学的機能を研究する上で、大きな第一歩を踏み出すきっかけとなった4)。
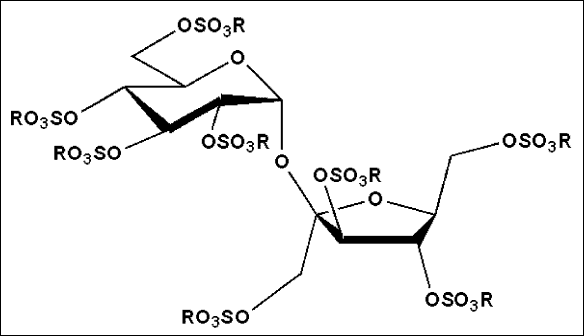
図1 スクラルファートの構造
R、対金属
また、ショ糖を構成するブドウ糖は脳が唯一消費可能なエネルギー源として知られ、1日に健康な成人の脳は約120〜150グラムのブドウ糖を消費するといわれている。単糖であるブドウ糖をヒトが意識して摂取することはまれで、ほとんど穀類に含まれるデンプンおよびショ糖から体内で酵素分解によって生じたブドウ糖である。脳は唯一このブドウ糖をエネルギー源としているのであり、本を読んだり、思考して脳を使うと、脳のブドウ糖の消費も当然ながら増加する。私事で恐縮だが、ダイエットに夢中になるわが家の住人たちに対して筆者は、常日頃から本を読み思索に励むことが効率の良いダイエット法であるとことあるごとに進言し、煙たがられている毎日を送っている。
筆者の専門の一つである分析化学的観点から砂糖を眺めると、カルシウムとマグネシウムの分離にショ糖溶液が用いられている。すなわち酸化カルシウムは30%ショ糖溶液には溶けるが、酸化マグネシウムは溶けないため、効率よく両金属塩を含む試料から片方を精製するのに用いられている。また、少量の水酸化ナトリウムの存在で、銀塩を含む溶液と加熱すれば黄色あるいは褐色に着色するので、銀を比色定量することができる。また、バナジウムと反応し当量の酸を遊離するので、定量分析に用いることができる。
また、ショ糖密度勾配法として知られる生体高分子の分離法は、生化学実験に欠かすことのできない方法の一つとして薬学生に知られている。すなわち、水に対してほとんど自由に溶けるショ糖の性質を利用し、ショ糖濃度の異なる溶液を濃度の高いものを下から順に重層し、生体高分子の混合物を上に乗せスイングローターで遠心分離機に掛けると、重さの違いで効率よく分離することができるのである。この原理はまた、ショ糖密度と色の異なるリキュールを重層したカクテル“レインボー”(呼称は定かでない)にも利用され、大人たちを楽しませている。
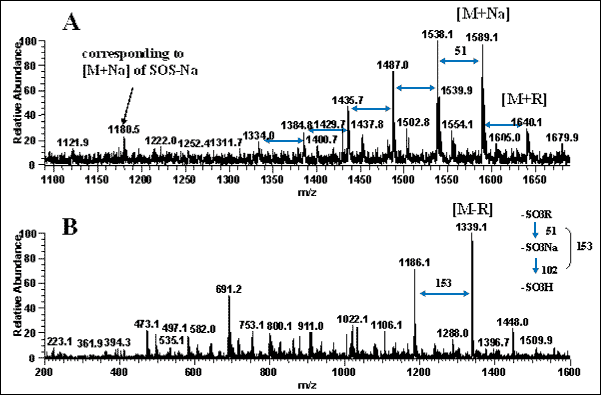
図2 スクラルファートの質量スペクトル
A、陽イオン検出;B、陰イオン検出
また、ショ糖密度勾配法として知られる生体高分子の分離法は、生化学実験に欠かすことのできない方法の一つとして薬学生に知られている。すなわち、水に対してほとんど自由に溶けるショ糖の性質を利用し、ショ糖濃度の異なる溶液を濃度の高いものを下から順に重層し、生体高分子の混合物を上に乗せスイングローターで遠心分離機に掛けると、重さの違いで効率よく分離することができるのである。この原理はまた、ショ糖密度と色の異なるリキュールを重層したカクテル“レインボー”(呼称は定かでない)にも利用され、大人たちを楽しませている。
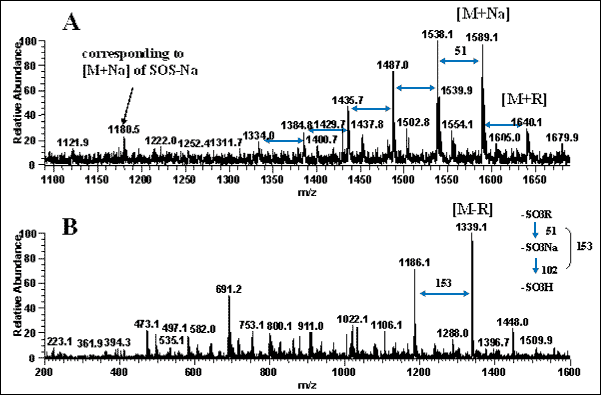
図2 スクラルファートの質量スペクトル
A、陽イオン検出;B、陰イオン検出
| ページのトップへ |
医薬品に限らず一般工業製品としてのショ糖の利用について目を転じると、ショ糖脂肪酸エステルが挙げられよう。用途はショ糖部分を水に親和性のある親水基、炭化水素からなる脂肪酸部分を親油基とする非イオン性界面活性剤として利用されている。脂肪酸の部分が長い炭化水素鎖(アルキル基)は化粧品などに安全性の高い乳化剤として、また洗浄力はほかのイオン性界面活性剤とは異なるものの皮膚への刺激の少ない洗浄剤として用いられている。一方、アルキル基が短い脂肪酸は、香料を清涼飲料水に添加する際の比重調節剤として用いられており、その用途は広い。万が一河川に流れ込んでも、自然界に存在する細菌群がショ糖も脂肪酸も容易に分解できるものと思われ、環境にやさしい工業製品として利用価値も高いものと考えられる。
一方、砂糖の消費に対するある種の抵抗感が、思いもよらない科学的な進歩をもたらしたことにも触れておきたい。合成甘味料の開発である。かつては高価で希少な砂糖の代用品として開発された合成甘味料が、今ではショ糖の摂取を避ける一部の消費者に受け入れられ、ショ糖に比べて数百倍の甘味をもつ甘味料が天然から見出され、あるいは化学的に合成され市場に出回っている。一部の欧米人のように、すべての食べ物を日本人には想像できないほど多量に消費する場合には、合成甘味料の有用性を否定しないでもないが、ヒトの身体に取り込むための代謝系が備わっているショ糖の代わりに、“外来異物”である合成甘味料を摂取する気にならないのは筆者ひとりであろうか。
一方、砂糖の消費に対するある種の抵抗感が、思いもよらない科学的な進歩をもたらしたことにも触れておきたい。合成甘味料の開発である。かつては高価で希少な砂糖の代用品として開発された合成甘味料が、今ではショ糖の摂取を避ける一部の消費者に受け入れられ、ショ糖に比べて数百倍の甘味をもつ甘味料が天然から見出され、あるいは化学的に合成され市場に出回っている。一部の欧米人のように、すべての食べ物を日本人には想像できないほど多量に消費する場合には、合成甘味料の有用性を否定しないでもないが、ヒトの身体に取り込むための代謝系が備わっているショ糖の代わりに、“外来異物”である合成甘味料を摂取する気にならないのは筆者ひとりであろうか。
| ページのトップへ |
現在筆者らは平成15年から独立行政法人農畜産業振興機構の砂糖調査研究助成を受けて、砂糖の腸管免疫系、全身性免疫系に対する効果を調査している。細菌などの外敵から健康を守るために重要な役割を担っている免疫系に対するショ糖の効果について、特にT細胞の分化誘導を、T細胞が産生するサイトカイン類を分析することによって調査している。免疫系に対する効果を評価するための方法を確立することから手掛けなければならないなど、その前途は厳しく長いものとなるものと予想されるが、ショ糖が脾臓細胞由来のナイーブなT細胞を分化誘導する効果が観察されるなど少しずつではあるが成果は挙がっている5)。糖鎖に対する受容体を、T細胞やB細胞など免疫を担当する細胞群がその細胞表面に発現していることは確実で、これら糖鎖に対する受容体がショ糖に対して親和性を持つかどうか、また親和性をもち結合した場合、その相互作用がいかなる情報として伝達されるのかなど、興味は尽きない。私たち日本人の生活環境の変化や食物嗜好の変化が、最近の免疫性疾患、特にアトピー性皮膚炎、喘息、花粉症など免疫系疾患の罹患率の上昇に繋がっていると指摘する研究者もいることから、ヒトの免疫系と食物は密接に関与している可能性は大きいものと思われる。
いずれにしろ、ショ糖のヒトの免疫系に関する研究は緒についたばかりであり、実際に効果があるのかないのか暗中模索の状態といっても過言ではない。しかしながらヒトの健康増進へのショ糖摂取の効果を信じて、今後も検討を続けていきたい。
参考文献
1.高尾利数、“砂糖は体も心も狂わせる 学校・家庭内暴力も砂糖のとりすぎ”出版元ペガサス ISBN:4−89332−005−X(1982)
2.川北稔、“砂糖の世界史”出版元岩波書店 ISBN:4−00−500276−5(1996)
3.Hassid, W.Z., Doudoroff, M., Adv. Carbohydr. Chem., 5:29−48(1950).
4.Gunay, N.S., Tadano−Aritomi, K., Toida, T., Ishizuka, I., Linhardt, R.J., Anal. Chem.,. 75(13):3226−3231(2003).
5.戸井田敏彦、酒井信夫、「平成15年度砂糖に関する学術調査報告」(2004)。
いずれにしろ、ショ糖のヒトの免疫系に関する研究は緒についたばかりであり、実際に効果があるのかないのか暗中模索の状態といっても過言ではない。しかしながらヒトの健康増進へのショ糖摂取の効果を信じて、今後も検討を続けていきたい。
参考文献
1.高尾利数、“砂糖は体も心も狂わせる 学校・家庭内暴力も砂糖のとりすぎ”出版元ペガサス ISBN:4−89332−005−X(1982)
2.川北稔、“砂糖の世界史”出版元岩波書店 ISBN:4−00−500276−5(1996)
3.Hassid, W.Z., Doudoroff, M., Adv. Carbohydr. Chem., 5:29−48(1950).
4.Gunay, N.S., Tadano−Aritomi, K., Toida, T., Ishizuka, I., Linhardt, R.J., Anal. Chem.,. 75(13):3226−3231(2003).
5.戸井田敏彦、酒井信夫、「平成15年度砂糖に関する学術調査報告」(2004)。
| ページのトップへ |










