

ホーム > 砂糖 > 視点 > 社会 > 甘味嗜好の成立過程の検討(平成16年度砂糖に関する学術調査報告から)
最終更新日:2010年3月6日
[2006年4月]
【調査・報告〔砂糖/健康〕】
| 安田女子短期大学保育科 広島修道大学人文学部 広島大学教育学研究科 |
非常勤講師 加藤 佳子 教授 今田 純雄 教授 森 敏昭 |
| 1.はじめに |
| 2.方法 |
| 3.結果と考察 |
| 4.要約 |
| 5.引用文献 |
本研究は、甘味に対する態度がどのように形成されていくのかを明らかにすることを目的としたものである。
実験では、4歳から17歳の園児、児童、生徒ならびにその保護者に対して、甘味に対する態度などに関する複数の質問項目について回答させ、それについて回帰分析を行った。
その結果、(1)甘味に対する肯定的な態度は養育態度を介して間接的に影響し、否定的な態度は保護者の甘味に対する態度が直接影響すること、(2)甘味に対する肯定的・否定的な感情を同時に持つこと(アンビバレント)が過食などの異常傾向と関連していること、(3)子どもの食行動には養育態度が影響していること、などが明らかになった。
健康な食行動を身につけるには、甘味に対するアンビバレントな態度を回避することが必要であり、本研究の結果を啓蒙することによって、国民の健康な食生活が営まれる一助となることが期待される。
実験では、4歳から17歳の園児、児童、生徒ならびにその保護者に対して、甘味に対する態度などに関する複数の質問項目について回答させ、それについて回帰分析を行った。
その結果、(1)甘味に対する肯定的な態度は養育態度を介して間接的に影響し、否定的な態度は保護者の甘味に対する態度が直接影響すること、(2)甘味に対する肯定的・否定的な感情を同時に持つこと(アンビバレント)が過食などの異常傾向と関連していること、(3)子どもの食行動には養育態度が影響していること、などが明らかになった。
健康な食行動を身につけるには、甘味に対するアンビバレントな態度を回避することが必要であり、本研究の結果を啓蒙することによって、国民の健康な食生活が営まれる一助となることが期待される。
1.はじめに
甘味に対する態度は生理的な要因によって規定されるとともに,社会・文化的な影響を受け形成されると考えられる。本調査では,幼児から高校生の子どもとその保護者を対象として甘味に対する態度の形成要因を探ることとした。
人は生来甘味に対して受容的であるが,発達過程において,甘味に対する態度が形成されていく過程では家庭での食生活のあり方が影響を及ぼしていると考えた。そこで甘味に対する態度の形成に関わると考えられる次の二つの要因について検討した。一つ目は,甘いものと養育環境に関する要因である。「アメと鞭」といった言葉にも代表されるように子どもを育てる上で甘いものが利用されたり,甘いものが制限される場面を目にする。したがってこのような甘いものと関連した養育環境が子どもの甘味に対する態度に影響すると考えた。二つ目は,保護者の甘味に対する態度の影響である。様々な地域の食文化にみられるように,食行動は,学習によって習得される側面を持つ。よって,食行動のモデル(手本)となる保護者の甘味に対する態度は,子どもの甘味に対する態度に反映されると考えた。
はじめに,本調査で使用した尺度の検討を行った。次に甘味に対する態度の発達的な特徴を見るために,各学年,男女差の比較を行った。そして各変数間での相関を検討したうえで,幼児期の甘いものに関連した養育態度や保護者の甘味に対する態度が子どもの甘味に対する態度や食行動の問題にどのように関係しているかを分析した。最後にきょうだいの有無,親の養育態度との関係についても調べた。こうして養育環境など,子どもを取り巻く環境と甘味に対する態度との関係を分析することを計画した。
調査内容と関連分析のための枠組みを示したものがFigure 1である。
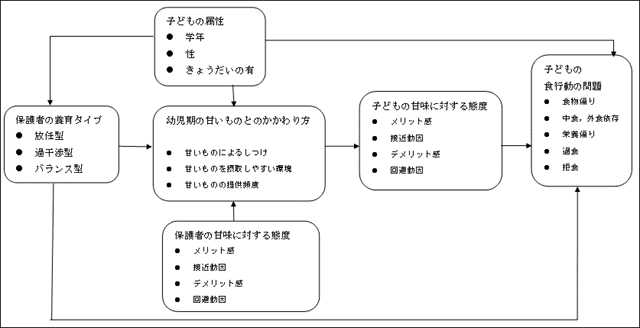 Figure 1 調査内容と関連分析のための枠組み
Figure 1 調査内容と関連分析のための枠組み
人は生来甘味に対して受容的であるが,発達過程において,甘味に対する態度が形成されていく過程では家庭での食生活のあり方が影響を及ぼしていると考えた。そこで甘味に対する態度の形成に関わると考えられる次の二つの要因について検討した。一つ目は,甘いものと養育環境に関する要因である。「アメと鞭」といった言葉にも代表されるように子どもを育てる上で甘いものが利用されたり,甘いものが制限される場面を目にする。したがってこのような甘いものと関連した養育環境が子どもの甘味に対する態度に影響すると考えた。二つ目は,保護者の甘味に対する態度の影響である。様々な地域の食文化にみられるように,食行動は,学習によって習得される側面を持つ。よって,食行動のモデル(手本)となる保護者の甘味に対する態度は,子どもの甘味に対する態度に反映されると考えた。
はじめに,本調査で使用した尺度の検討を行った。次に甘味に対する態度の発達的な特徴を見るために,各学年,男女差の比較を行った。そして各変数間での相関を検討したうえで,幼児期の甘いものに関連した養育態度や保護者の甘味に対する態度が子どもの甘味に対する態度や食行動の問題にどのように関係しているかを分析した。最後にきょうだいの有無,親の養育態度との関係についても調べた。こうして養育環境など,子どもを取り巻く環境と甘味に対する態度との関係を分析することを計画した。
調査内容と関連分析のための枠組みを示したものがFigure 1である。
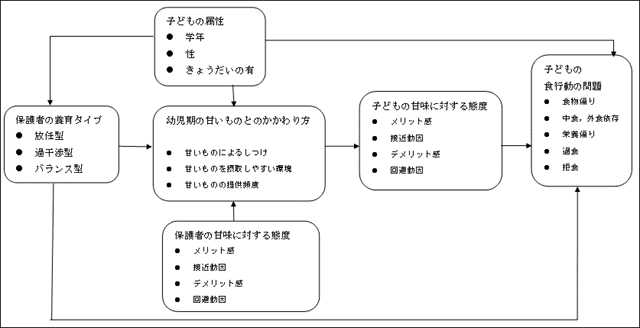 Figure 1 調査内容と関連分析のための枠組み
Figure 1 調査内容と関連分析のための枠組み | ページのトップへ |
2.方法
4歳から17歳の園児,児童,生徒(男子313名,女子320名,性別無記名3名,合計636名)ならびにその保護者(男性16名,女性594名,合計610名)であった。学年と性別の人数分布の詳細を,Table
1に示す。
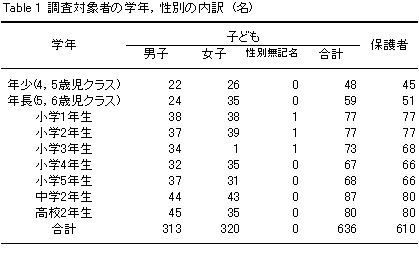
2.調査方法
小学生,中学生,高校生には教師を通じて質問を配布し,集団調査法もしくは留め置き法により回答を求めた。幼児には一人ずつ個別に面接を行い,○,×のカードを補助的に使用しながら,回答方法の練習を行い,甘いものにはどのようなものがあるかを確認した上で回答を求めた。面接時間は一人当たり15分から20分であった。保護者には留め置き法により回答を求めた。
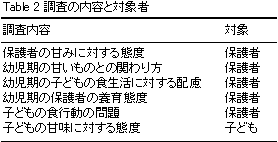
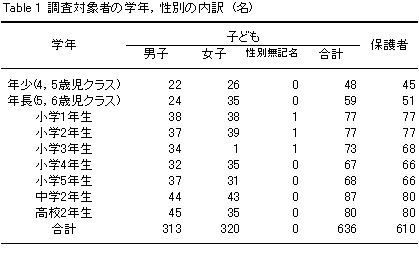
2.調査方法
小学生,中学生,高校生には教師を通じて質問を配布し,集団調査法もしくは留め置き法により回答を求めた。幼児には一人ずつ個別に面接を行い,○,×のカードを補助的に使用しながら,回答方法の練習を行い,甘いものにはどのようなものがあるかを確認した上で回答を求めた。面接時間は一人当たり15分から20分であった。保護者には留め置き法により回答を求めた。
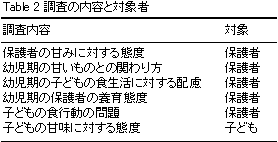
| ページのトップへ |
3.結果と考察
性別,年齢横断的甘味に対する態度の特徴
子どもの甘味に対する態度を性別,年齢横断的に検討した。年少(4,5歳児クラス),年長(5,6歳児クラス)を幼児,小学校1,2年生を低学年,小学校3,4年生を中学年,小学校5年生を高学年とした。各学年,性別の平均値と分散分析結果をTable 3に示した。
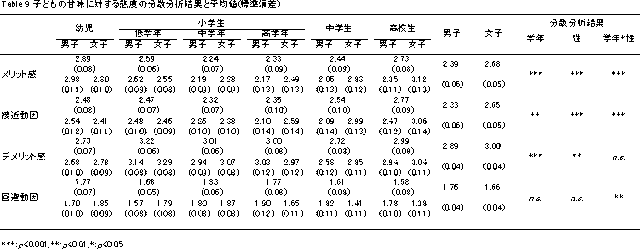
学年ごとの甘味に対する態度を比較すると,甘味に対するメリット感は,学年があがるにつれて低下し,小学校中学年をターニング・ポイントとして,再び上昇していた(Figure 2)。
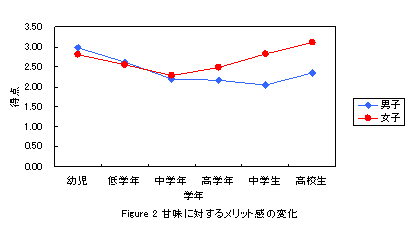
甘味に対する接近動因もメリット感に平行して,幼児期から次第に減少し,小学校中学年をターニング・ポイントに上昇していた(Figure 3)。
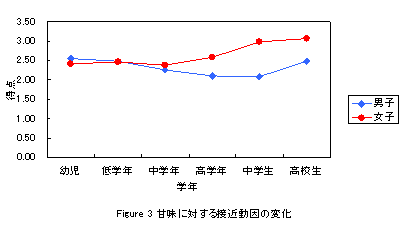
これに相反してデメリット感は幼児期から上昇し小学校低学年をターニング・ポイントに減少していた。
学校教育の始まりとともに,甘味に対する警戒感が定着するが,その後学年があがるにつれて,このような警戒感は減少していくことが示唆された。中学生に比較して,成人の甘味に対する否定的な認知の程度が低いことが明らかにされおり,甘味に対するデメリット感は年齢の増加とともに次第に低くなっていると考えられる。ヒトは生来,甘味を好むことから,結局,否定的な認知や感情はその後持続しないのかもしれない。しかし,好きな食べ物を嫌いになることよりも,嫌いな食べ物を好きになるほうが困難であることを示しており,いったん獲得された甘味に対する否定感を意識の中から完全になくすことは難しいと考えられる。女子大学生の甘味に対するアンビバレントな態度が食行動の異常傾向を説明していることを考慮すると,健康的な食行動を獲得するためには甘味に対する認知,感情,行動傾向の形成過程に注意を払わなくてはならない。
女子は男子に比較して,甘味に対するメリット感が強く,甘味に対する接近動因が強いが,同時に甘味に対するデメリット感も強い。しかし,甘味に対する回避動因には男女の差はみられなかった。
甘味に対する回避動因は,小学校低学年で女子のほうが強い回避動因を示したが,その後中学生,高校生では男子のほうが強い回避動因を示した。大学生を対象とした研究では,女性は男性に比較して甘味に対してメリット感,デメリット感の両方が強く甘味に対して接近的であり,男性は回避的であると報告されている。この報告とあわせて考察すると,男性が女性に比較して,甘味に対して回避的になるのは中学生以降であると考えられる。また,女性は甘味に対してメリット感もデメリット感も強く甘味に対してアンビバレントな態度を持っていると考察されている。性別による主効果をみると,このようなアンビバレントな態度が観察されるものの,学年と性別による交互作用から検討してみると高校生までの段階では,女子の甘味に対するアンビバレントな態度は観察できない。つまり発達段階として甘味に対するアンビバレントな態度が決定的となるのは大学生以降であることが示唆された。このようなアンビバレントな態度は,痩せ願望やストレスを背景として食行動の異常傾向と関連していることが明らかにされている。今後高校生から大学生への移行期に痩せ願望やストレスがどのように食行動の問題を発展させているかを探ることで,青年期の食行動の問題解決の糸口を明らかにすることができると考えられる。
子どもの甘味に対する態度と幼児期の甘いものとのかかわり方,保護者の甘味に対する態度との関係
子どもの甘味に対する態度と幼児期の甘いものとのかかわり方,保護者の甘味に対する態度との関係を検討するために各尺度の下位尺度間の相関係数(ピアソンの積率相関係数)を求めた。その結果をTable 4に示した。相関係数が有意であった項目がみられたが,全体的に低い値であった。食糧供給の豊かとなった今日では,食行動は今回あげたような項目のみではなく生理的,心理的な様々な要因からの影響を受け,複雑に構成されている。したがって相関係数は低いもののその相関係数が有意であることは,複雑に構成される食行動を見ていく上で,考慮すべき要因であると考え,考察を進めることとする。
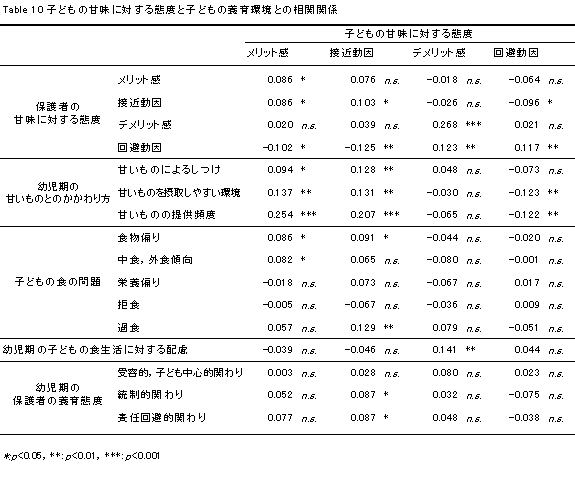
保護者の甘味に対する態度は子どもの甘味に対する態度と有意に関連していた。相関の程度は全体的に弱いものの,その中でもっとも高い数値を示したのは,保護者と子どもの甘味に対するデメリット感の間の相関であった。甘味に対する肯定的な認知,感情,行動傾向の獲得よりも,甘味に対する否定的な認知,感情,行動傾向の獲得に際し,モデリング2)が重要な要因として働いていると推測できる。甘味は生来,受容される味であることを考慮すると,甘味に対する否定的な態度がモデリングによって形成されることは妥当な結果であるといえる。
幼児期の甘いものとのかかわり方のうち,甘いものによるしつけ,甘いものを摂取しやすい環境,甘いものの提供頻度のいずれも甘味に対するメリット感,接近動因と正の相関関係にあり,甘いものを摂取しやすい環境と甘いものの提供頻度は回避動因とは負の相関関係にあった。「いつもおやつに出されるから甘いものが好き」,といったように甘い物に触れる頻度の高い生活環境であるほど甘いものに対して肯定となりやすいことが示された。
子どもの食の問題の中では,甘味に対するメリット感は,食物の偏り,中食・外食依存と正の相関関係にあった。そして接近動因は,食物の偏り,過食と正の相関関係にあった。しかしいずれもその相関係数は0.1前後ときわめて弱い相関であった。青年期後期の大学生を対象とした調査では甘味に対するメリット感,デメリット感,接近動因は,摂食障害に類似した行動傾向を示す食行動の異常傾向や過食と関連していた。そしてその相関係数は,0.2から0.4であった。このように相関の強さに差が出た原因として,今回実施した質問紙の内容と大学生を対象として行った質問紙の内容が多少異なるためであるとも考えられるが,発達段階の違いによるとも考えられる。青年期は自立への移行期であり,食生活も保護者による外的制御中心の食生活から,自己制御中心の食生活へと移行する時期である。青年期の甘味に対する態度も,保護者による外的制御の影響よりも,自己制御による影響が大きいと考えられる。それゆえ自己制御によって形成される甘味に対する態度のあり方は,食行動の自己制御不全状態としてとらえられている食行動の異常傾向と関連性がみられたと推測できる。
幼児期の子どもの食生活に対する配慮は,子どもの甘味に対する態度のデメリット感と正の相関があった。また幼児期の保護者の養育態度では,統制的関わり,責任回避的関わりは甘味に対する接近動因と正の相関関係があったが,その相関は大変弱いものであった。
今回観察した保護者の甘味に対する態度,幼児期の甘いものとの関わり方,子どもの食の問題,幼児期の保護者の養育態度と子どもの甘味に対する態度との相関係数はいずれも低いものであった。しかし食行動はさまざまな要因の影響を受けて確立するものであることを考慮すると,甘味に対する態度の形成過程について検討する上で,その一つ一つの内容に注目する必要があると考える。そこでさらにこの関係を深く検討するために,これらの相関係数と,Figure 1で示したような調査内容と関連分析のための枠組みをもとにパス解析を行った。なお幼児期の保護者の養育態度の下位尺度との相関係数は,0.10未満で極めて低い相関であったので,この変数はパス解析による分析対象から外すこととした。パス解析を行った結果,適合度はχ2=80.41,p=0.08,GFI=0.98,AGFI=0.96,CFI=0.99,RMSEA=0.02でありモデルはデータに適合していた。
保護者の甘味に対する態度は,幼児期の子どもの甘いものに関する養育態度の予測因子となっていた。保護者は自分の甘いものに対するメリット感や接近動因が高いほど子どもに対して甘いものをしつけに使用したり,甘いものを摂取しやすい環境を設定したりしていた。甘いものによるしつけの頻度が高く,甘いものを摂取しやすい環境であるほど結果的に甘いものを提供する頻度も高くなり,甘いものを提供する頻度の高さは,子どもの甘味に対する態度のうちメリット感を高める要因となっていた。甘味に対するメリット感は栄養の偏りに対して負の標準化係数を示していた。子どもが甘味に対してメリット感を持つことは,栄養の偏りのない食行動を導く予測因子となっている。また甘味に対する接近動因とデメリット感は過食を説明する要因として影響していた。この関係を示す標準化係数の値は大変小さいものの,甘味に対する肯定的な態度と否定的な態度が食行動の問題を説明する過程は,女子大学生の甘味に対する態度で,接近動因と回避動因が食行動の異常傾向を説明している過程と一致している。つまり甘味に対するアンビバレントな態度が食行動の異常傾向を説明する傾向は今回対象とした幼児期から青年期にもみられることが示唆された。
今回の調査では,保護者の甘味に対する態度と甘いものに関する養育態度が子どもの甘味に対する態度の形成に影響をおよぼしていると仮定して分析を進めた。しかし甘味に対するメリット感や接近動因のように甘味に対する肯定的な態度は,保護者の甘味に対する肯定的な態度の影響を直接受けるのではなく,保護者が甘いものに対して肯定的であることにより,甘いものに関する養育態度が寛容となり,保護者の甘味に対する肯定的な態度が間接的に影響して子どもの甘味に対するメリット感や接近動因が高まることが示唆された。一方甘味に対するデメリット感は,保護者の甘味に対するデメリット感や回避動因の影響を直接受けることが示された。よって保護者の甘味に対する態度が,アンビバレントであれば,子どもの甘味に対する態度もアンビバレントとなる可能性が高くなるであろう。女子大学生にみられたアンビバレントな態度は,社会的な風潮から生まれてきた痩せ願望やその背景にある強いストレスによるものであると加藤(2005b)は考察した。しかしアンビバレントな態度を形成しないためには,甘味に対する態度が形成される青年期以前の保護者の甘味に対する態度,甘いものに関する養育態度にも注目する必要がある。子どもを養育する上で,甘いものの利用のしかたには充分注意を払うべきであるとともに,保護者の甘味に対する高すぎる否定感も子どもの甘味に対する態度を形成する上でよい影響を与えないことにも留意すべきである。
保護者の養育態度と子どもの甘味に対する態度,食行動の問題との関係
保護者の養育態度の代表的な特徴である受容的・子ども中心的関わり,統制的関わり,責任回避的関わりについて検討をすることとしたが,一般的に保護者の態度は受容的・子ども中心的関わり,統制的関わり,責任回避的といった単一的な特徴ではなく,これらの三つの基本的な養育態度が組み合わさった複合的な特徴によってタイプ分けすることができると考えられる。そこで受容的・子ども中心的関わり,統制的関わり,責任回避的かかわりの得点を標準化し標準化得点を用いてクラスター分析を行った。その結果,3つのクラスターが得られた。第1クラスターは子どものことをある程度受け入れ,統制的関わりも責任回避的関わりも低い得点を示したので「バランス型」,第2クラスターはある程度子どもを統制しながらも責任は回避し,子どもを受容しないので「放任型」,第3クラスターは責任を回避せず,子どもを統制し,強く受容していたので「過干渉型」と命名した。
「バランス型」,「放任型」,「過干渉型」の3タイプを独立変数とする1要因の分散分析を行い,3タイプの養育タイプ間の子どもの甘味に対する態度,甘いものに関する養育態度,子どもの食生活への配慮,食行動の問題について比較した。分散分析の結果,主効果のみられた変数についてボンフェローニィの下位検定を行った。
子どもの甘味に対する態度は,「バランス型」,「放任型」,「過干渉型」のどのタイプ間にも有意な差はみられなかった。
Figure 5 に養育態度と子どもの食環境として,各養育タイプ別の甘いものに関する養育態度および子どもの食生活への配慮の平均得点を示した。
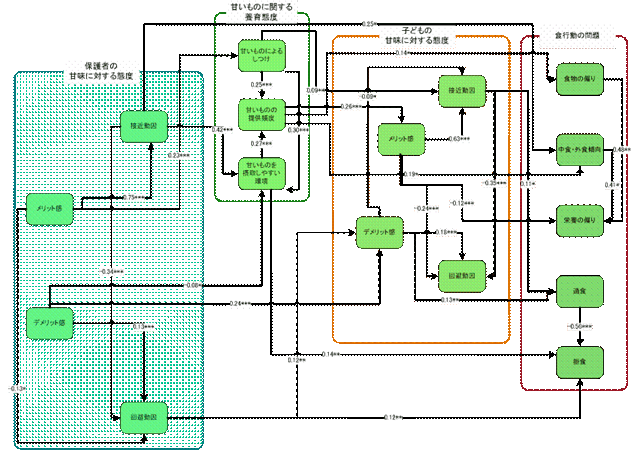
Figure 5 甘味に対する態度に影響する環境要因と食行動の問題との関係
注)***:p<0.001,**:p<0.01,*p<0.05
甘いものによるしつけでは,放任型,過干渉型,バランス型の順で甘いものをしつけに利用する程度が高かった。つまり子どもと適度な距離をとりながら養育する上では,甘いものをしつけに利用することはあまりない。
子どもの食への配慮は,どの養育のタイプも平均値が高く,全体的に子どもの食生活への配慮がよくなされていることが傾向としてみられたものの養育タイプ間には有意な差がみられた。バランス型,過干渉型は放任型に比較して子どもの食生活への配慮がよくなされていた。
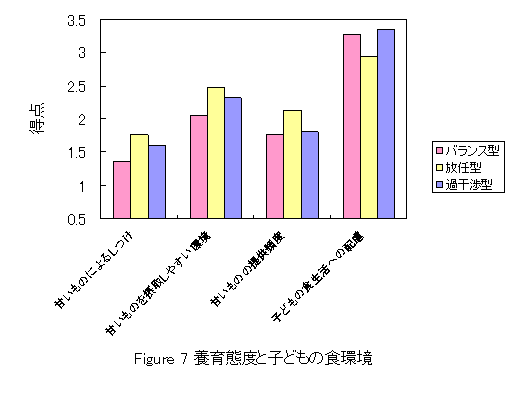
甘いものを摂取しやすい環境は,バランス型は,放任型,過干渉型に比較して甘いものを摂取しやすい環境の程度が有意に低かった。放任型と過干渉型との間には,有意な差がみられなかった。甘いものの提供頻度は,放任型がバランス型,過干渉型に比較して有意に高い値を示した。放任型は,甘いものをいつも準備し摂取しやすい環境を設定し,実際甘いものを提供する頻度が高く,過干渉型は,甘いものを準備するものの甘いものの提供頻度は放任型ほど高くない。一方バランス型は,甘いものを習慣的に準備している程度も低く,よってその提供頻度も低い。放任型は甘いものをしつけに利用する頻度が高く,子どもの食に対する配慮も他の養育タイプに比較して低い。このような放任型の特徴が,甘いものを習慣的に準備し,子どもに甘いものをよく提供する要因となっていると考えられる。また過干渉型は甘いものをしつけに利用するものの,放任型とは異なり子どもに対する受容の程度が高く,子どもの食に対する配慮が強い。そのため過干渉型は甘いものを習慣的に準備しながらも,甘いものを提供する頻度はバランス型と差がない結果となったのかもしれない。つまり甘いものをしつけに利用する背景が放任型と過干渉型とは本質的に異なっていると考えられる。
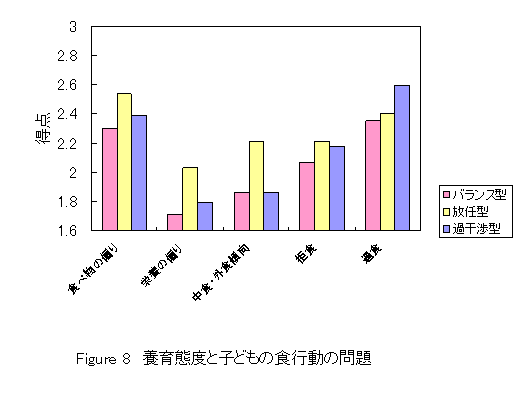
Figure 6 に養育態度と子どもの食行動の問題の平均得点を示した。放任型はバランス型,過干渉型に比較して食べ物の偏り,栄養の偏りが強く,中食・外食依存も強かった。バランス型と過干渉型の間には有意な差がみられなかった。子どもに対する受容の程度が低いことが,子どもの食生活に対する配慮の程度を低め,子どもの中食や外食の頻度をあげ,食べ物の偏り,栄養の偏りを生じさせていると考えられる。
拒食については,3つの養育タイプ間に有意な差がみられなかった。
過食については,過干渉型が有意に高い値を示した。養育態度のアンバランスが子どもの過食に反映されていると考えられる。
きょうだいの数による影響
きょうだいの数による影響を調べるためにきょうだい無し,きょうだい一人,きょうだい二人以上の3群を独立変数とし,保護者の養育態度,甘いものとの関わり方,食行動の問題を従属変数として分散分析を行い,有意な差のみられた変数についてボンフェローニィの下位検定を行った。
Table 5に調査対象となった子どものきょうだいの人数別群の分布を示した。
またきょうだいの人数別養育態度のタイプの分布をみてみると,一人っ子には過干渉型の養育タイプの割合が多く,バランス型,放任型はきょうだいの人数が多くなるほどその割合が増えていた(Table
6)。
Figure 7にきょうだいの数別甘いものとの関わり方の平均値を示した。きょうだいの数が多いほど甘いものによるしつけ,甘いものを摂取しやすい環境で高い平均値が示された。 甘いものの提供頻度では,有意な差はみられなかった。
またきょうだいの人数別養育態度のタイプの分布をみてみると,一人っ子には過干渉型の養育タイプの割合が多く,バランス型,放任型はきょうだいの人数が多くなるほどその割合が増えていた(Table 6)。
Figure 7にきょうだいの数別甘いものとの関わり方の平均値を示した。きょうだいの数が多いほど甘いものによるしつけ,甘いものを摂取しやすい環境で高い平均値が示された。 甘いものの提供頻度では,有意な差はみられなかった。
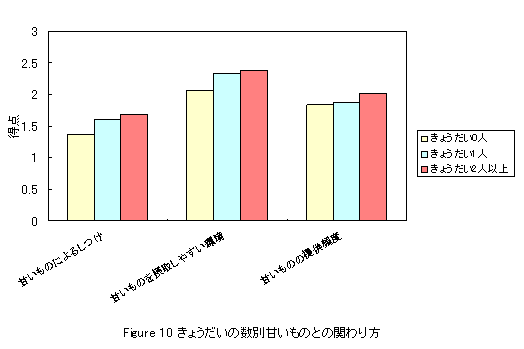
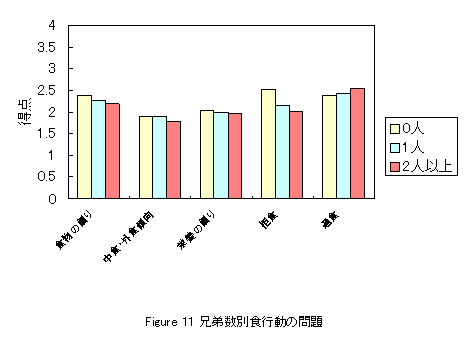
子どもの甘味に対する態度には,きょうだいの数の相違による効果はみられなかった。
以上の結果からきょうだいの数は,保護者の養育態度を決定する要因となり,このことは子どもの甘いものとの関わり,拒食に影響を与えていた。甘味に対する態度に影響する環境要因と食行動の問題との関係についておこなったパス解析の結果では,甘いものを摂取しやすい環境は拒食を予測する変数となっていた(Figure 4)。しかし一人っ子では,きょうだいを持つ子どもたちに比較して甘いものを摂取しやすい環境にない。そのため一人っ子の拒食は,甘味に対する態度とは関係ないと考えられる。
子どもの甘味に対する態度を性別,年齢横断的に検討した。年少(4,5歳児クラス),年長(5,6歳児クラス)を幼児,小学校1,2年生を低学年,小学校3,4年生を中学年,小学校5年生を高学年とした。各学年,性別の平均値と分散分析結果をTable 3に示した。
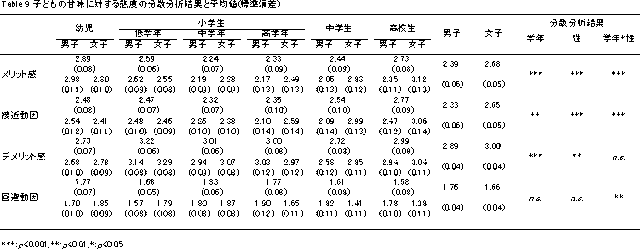
学年ごとの甘味に対する態度を比較すると,甘味に対するメリット感は,学年があがるにつれて低下し,小学校中学年をターニング・ポイントとして,再び上昇していた(Figure 2)。
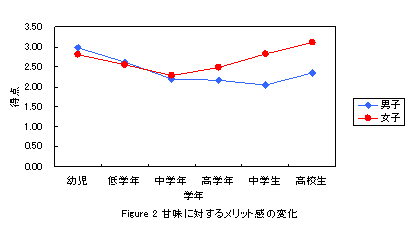
甘味に対する接近動因もメリット感に平行して,幼児期から次第に減少し,小学校中学年をターニング・ポイントに上昇していた(Figure 3)。
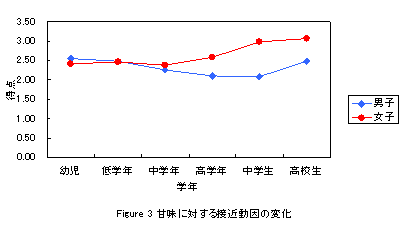
これに相反してデメリット感は幼児期から上昇し小学校低学年をターニング・ポイントに減少していた。
学校教育の始まりとともに,甘味に対する警戒感が定着するが,その後学年があがるにつれて,このような警戒感は減少していくことが示唆された。中学生に比較して,成人の甘味に対する否定的な認知の程度が低いことが明らかにされおり,甘味に対するデメリット感は年齢の増加とともに次第に低くなっていると考えられる。ヒトは生来,甘味を好むことから,結局,否定的な認知や感情はその後持続しないのかもしれない。しかし,好きな食べ物を嫌いになることよりも,嫌いな食べ物を好きになるほうが困難であることを示しており,いったん獲得された甘味に対する否定感を意識の中から完全になくすことは難しいと考えられる。女子大学生の甘味に対するアンビバレントな態度が食行動の異常傾向を説明していることを考慮すると,健康的な食行動を獲得するためには甘味に対する認知,感情,行動傾向の形成過程に注意を払わなくてはならない。
女子は男子に比較して,甘味に対するメリット感が強く,甘味に対する接近動因が強いが,同時に甘味に対するデメリット感も強い。しかし,甘味に対する回避動因には男女の差はみられなかった。
甘味に対する回避動因は,小学校低学年で女子のほうが強い回避動因を示したが,その後中学生,高校生では男子のほうが強い回避動因を示した。大学生を対象とした研究では,女性は男性に比較して甘味に対してメリット感,デメリット感の両方が強く甘味に対して接近的であり,男性は回避的であると報告されている。この報告とあわせて考察すると,男性が女性に比較して,甘味に対して回避的になるのは中学生以降であると考えられる。また,女性は甘味に対してメリット感もデメリット感も強く甘味に対してアンビバレントな態度を持っていると考察されている。性別による主効果をみると,このようなアンビバレントな態度が観察されるものの,学年と性別による交互作用から検討してみると高校生までの段階では,女子の甘味に対するアンビバレントな態度は観察できない。つまり発達段階として甘味に対するアンビバレントな態度が決定的となるのは大学生以降であることが示唆された。このようなアンビバレントな態度は,痩せ願望やストレスを背景として食行動の異常傾向と関連していることが明らかにされている。今後高校生から大学生への移行期に痩せ願望やストレスがどのように食行動の問題を発展させているかを探ることで,青年期の食行動の問題解決の糸口を明らかにすることができると考えられる。
子どもの甘味に対する態度と幼児期の甘いものとのかかわり方,保護者の甘味に対する態度との関係
子どもの甘味に対する態度と幼児期の甘いものとのかかわり方,保護者の甘味に対する態度との関係を検討するために各尺度の下位尺度間の相関係数(ピアソンの積率相関係数)を求めた。その結果をTable 4に示した。相関係数が有意であった項目がみられたが,全体的に低い値であった。食糧供給の豊かとなった今日では,食行動は今回あげたような項目のみではなく生理的,心理的な様々な要因からの影響を受け,複雑に構成されている。したがって相関係数は低いもののその相関係数が有意であることは,複雑に構成される食行動を見ていく上で,考慮すべき要因であると考え,考察を進めることとする。
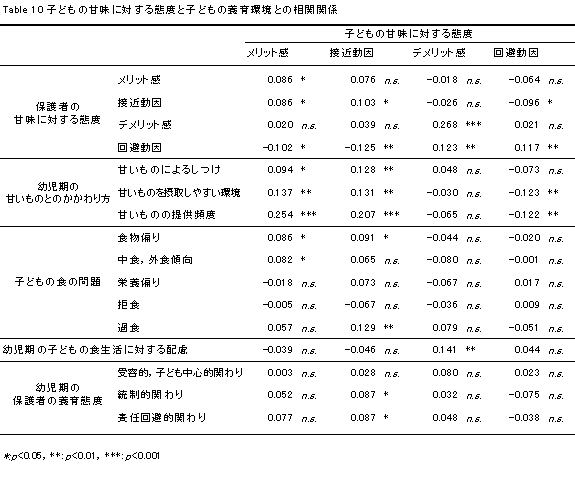
保護者の甘味に対する態度は子どもの甘味に対する態度と有意に関連していた。相関の程度は全体的に弱いものの,その中でもっとも高い数値を示したのは,保護者と子どもの甘味に対するデメリット感の間の相関であった。甘味に対する肯定的な認知,感情,行動傾向の獲得よりも,甘味に対する否定的な認知,感情,行動傾向の獲得に際し,モデリング2)が重要な要因として働いていると推測できる。甘味は生来,受容される味であることを考慮すると,甘味に対する否定的な態度がモデリングによって形成されることは妥当な結果であるといえる。
幼児期の甘いものとのかかわり方のうち,甘いものによるしつけ,甘いものを摂取しやすい環境,甘いものの提供頻度のいずれも甘味に対するメリット感,接近動因と正の相関関係にあり,甘いものを摂取しやすい環境と甘いものの提供頻度は回避動因とは負の相関関係にあった。「いつもおやつに出されるから甘いものが好き」,といったように甘い物に触れる頻度の高い生活環境であるほど甘いものに対して肯定となりやすいことが示された。
子どもの食の問題の中では,甘味に対するメリット感は,食物の偏り,中食・外食依存と正の相関関係にあった。そして接近動因は,食物の偏り,過食と正の相関関係にあった。しかしいずれもその相関係数は0.1前後ときわめて弱い相関であった。青年期後期の大学生を対象とした調査では甘味に対するメリット感,デメリット感,接近動因は,摂食障害に類似した行動傾向を示す食行動の異常傾向や過食と関連していた。そしてその相関係数は,0.2から0.4であった。このように相関の強さに差が出た原因として,今回実施した質問紙の内容と大学生を対象として行った質問紙の内容が多少異なるためであるとも考えられるが,発達段階の違いによるとも考えられる。青年期は自立への移行期であり,食生活も保護者による外的制御中心の食生活から,自己制御中心の食生活へと移行する時期である。青年期の甘味に対する態度も,保護者による外的制御の影響よりも,自己制御による影響が大きいと考えられる。それゆえ自己制御によって形成される甘味に対する態度のあり方は,食行動の自己制御不全状態としてとらえられている食行動の異常傾向と関連性がみられたと推測できる。
幼児期の子どもの食生活に対する配慮は,子どもの甘味に対する態度のデメリット感と正の相関があった。また幼児期の保護者の養育態度では,統制的関わり,責任回避的関わりは甘味に対する接近動因と正の相関関係があったが,その相関は大変弱いものであった。
今回観察した保護者の甘味に対する態度,幼児期の甘いものとの関わり方,子どもの食の問題,幼児期の保護者の養育態度と子どもの甘味に対する態度との相関係数はいずれも低いものであった。しかし食行動はさまざまな要因の影響を受けて確立するものであることを考慮すると,甘味に対する態度の形成過程について検討する上で,その一つ一つの内容に注目する必要があると考える。そこでさらにこの関係を深く検討するために,これらの相関係数と,Figure 1で示したような調査内容と関連分析のための枠組みをもとにパス解析を行った。なお幼児期の保護者の養育態度の下位尺度との相関係数は,0.10未満で極めて低い相関であったので,この変数はパス解析による分析対象から外すこととした。パス解析を行った結果,適合度はχ2=80.41,p=0.08,GFI=0.98,AGFI=0.96,CFI=0.99,RMSEA=0.02でありモデルはデータに適合していた。
保護者の甘味に対する態度は,幼児期の子どもの甘いものに関する養育態度の予測因子となっていた。保護者は自分の甘いものに対するメリット感や接近動因が高いほど子どもに対して甘いものをしつけに使用したり,甘いものを摂取しやすい環境を設定したりしていた。甘いものによるしつけの頻度が高く,甘いものを摂取しやすい環境であるほど結果的に甘いものを提供する頻度も高くなり,甘いものを提供する頻度の高さは,子どもの甘味に対する態度のうちメリット感を高める要因となっていた。甘味に対するメリット感は栄養の偏りに対して負の標準化係数を示していた。子どもが甘味に対してメリット感を持つことは,栄養の偏りのない食行動を導く予測因子となっている。また甘味に対する接近動因とデメリット感は過食を説明する要因として影響していた。この関係を示す標準化係数の値は大変小さいものの,甘味に対する肯定的な態度と否定的な態度が食行動の問題を説明する過程は,女子大学生の甘味に対する態度で,接近動因と回避動因が食行動の異常傾向を説明している過程と一致している。つまり甘味に対するアンビバレントな態度が食行動の異常傾向を説明する傾向は今回対象とした幼児期から青年期にもみられることが示唆された。
今回の調査では,保護者の甘味に対する態度と甘いものに関する養育態度が子どもの甘味に対する態度の形成に影響をおよぼしていると仮定して分析を進めた。しかし甘味に対するメリット感や接近動因のように甘味に対する肯定的な態度は,保護者の甘味に対する肯定的な態度の影響を直接受けるのではなく,保護者が甘いものに対して肯定的であることにより,甘いものに関する養育態度が寛容となり,保護者の甘味に対する肯定的な態度が間接的に影響して子どもの甘味に対するメリット感や接近動因が高まることが示唆された。一方甘味に対するデメリット感は,保護者の甘味に対するデメリット感や回避動因の影響を直接受けることが示された。よって保護者の甘味に対する態度が,アンビバレントであれば,子どもの甘味に対する態度もアンビバレントとなる可能性が高くなるであろう。女子大学生にみられたアンビバレントな態度は,社会的な風潮から生まれてきた痩せ願望やその背景にある強いストレスによるものであると加藤(2005b)は考察した。しかしアンビバレントな態度を形成しないためには,甘味に対する態度が形成される青年期以前の保護者の甘味に対する態度,甘いものに関する養育態度にも注目する必要がある。子どもを養育する上で,甘いものの利用のしかたには充分注意を払うべきであるとともに,保護者の甘味に対する高すぎる否定感も子どもの甘味に対する態度を形成する上でよい影響を与えないことにも留意すべきである。
保護者の養育態度と子どもの甘味に対する態度,食行動の問題との関係
保護者の養育態度の代表的な特徴である受容的・子ども中心的関わり,統制的関わり,責任回避的関わりについて検討をすることとしたが,一般的に保護者の態度は受容的・子ども中心的関わり,統制的関わり,責任回避的といった単一的な特徴ではなく,これらの三つの基本的な養育態度が組み合わさった複合的な特徴によってタイプ分けすることができると考えられる。そこで受容的・子ども中心的関わり,統制的関わり,責任回避的かかわりの得点を標準化し標準化得点を用いてクラスター分析を行った。その結果,3つのクラスターが得られた。第1クラスターは子どものことをある程度受け入れ,統制的関わりも責任回避的関わりも低い得点を示したので「バランス型」,第2クラスターはある程度子どもを統制しながらも責任は回避し,子どもを受容しないので「放任型」,第3クラスターは責任を回避せず,子どもを統制し,強く受容していたので「過干渉型」と命名した。
「バランス型」,「放任型」,「過干渉型」の3タイプを独立変数とする1要因の分散分析を行い,3タイプの養育タイプ間の子どもの甘味に対する態度,甘いものに関する養育態度,子どもの食生活への配慮,食行動の問題について比較した。分散分析の結果,主効果のみられた変数についてボンフェローニィの下位検定を行った。
子どもの甘味に対する態度は,「バランス型」,「放任型」,「過干渉型」のどのタイプ間にも有意な差はみられなかった。
Figure 5 に養育態度と子どもの食環境として,各養育タイプ別の甘いものに関する養育態度および子どもの食生活への配慮の平均得点を示した。
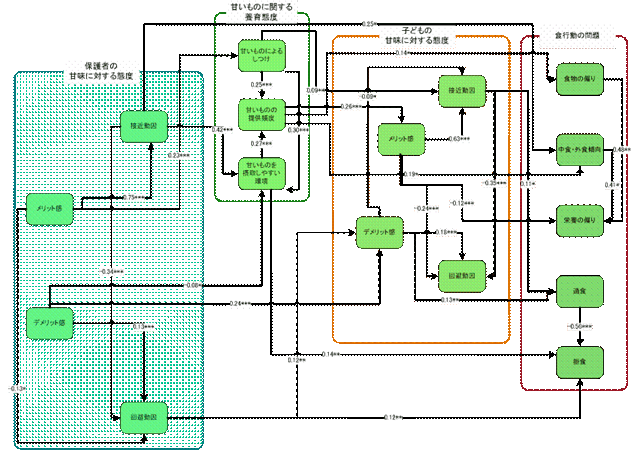
Figure 5 甘味に対する態度に影響する環境要因と食行動の問題との関係
注)***:p<0.001,**:p<0.01,*p<0.05
甘いものによるしつけでは,放任型,過干渉型,バランス型の順で甘いものをしつけに利用する程度が高かった。つまり子どもと適度な距離をとりながら養育する上では,甘いものをしつけに利用することはあまりない。
子どもの食への配慮は,どの養育のタイプも平均値が高く,全体的に子どもの食生活への配慮がよくなされていることが傾向としてみられたものの養育タイプ間には有意な差がみられた。バランス型,過干渉型は放任型に比較して子どもの食生活への配慮がよくなされていた。
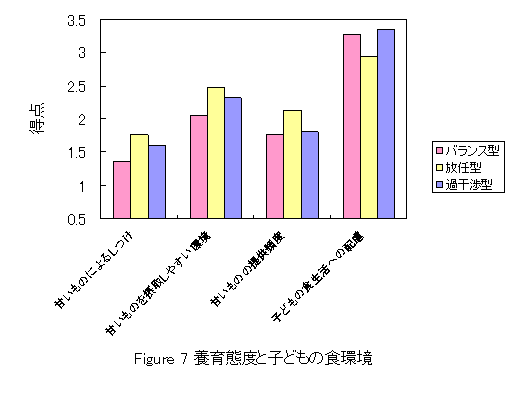
甘いものを摂取しやすい環境は,バランス型は,放任型,過干渉型に比較して甘いものを摂取しやすい環境の程度が有意に低かった。放任型と過干渉型との間には,有意な差がみられなかった。甘いものの提供頻度は,放任型がバランス型,過干渉型に比較して有意に高い値を示した。放任型は,甘いものをいつも準備し摂取しやすい環境を設定し,実際甘いものを提供する頻度が高く,過干渉型は,甘いものを準備するものの甘いものの提供頻度は放任型ほど高くない。一方バランス型は,甘いものを習慣的に準備している程度も低く,よってその提供頻度も低い。放任型は甘いものをしつけに利用する頻度が高く,子どもの食に対する配慮も他の養育タイプに比較して低い。このような放任型の特徴が,甘いものを習慣的に準備し,子どもに甘いものをよく提供する要因となっていると考えられる。また過干渉型は甘いものをしつけに利用するものの,放任型とは異なり子どもに対する受容の程度が高く,子どもの食に対する配慮が強い。そのため過干渉型は甘いものを習慣的に準備しながらも,甘いものを提供する頻度はバランス型と差がない結果となったのかもしれない。つまり甘いものをしつけに利用する背景が放任型と過干渉型とは本質的に異なっていると考えられる。
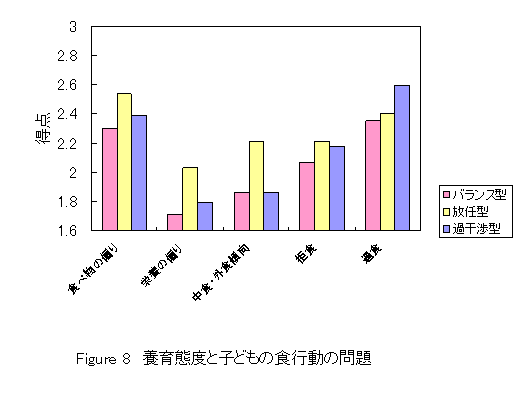
Figure 6 に養育態度と子どもの食行動の問題の平均得点を示した。放任型はバランス型,過干渉型に比較して食べ物の偏り,栄養の偏りが強く,中食・外食依存も強かった。バランス型と過干渉型の間には有意な差がみられなかった。子どもに対する受容の程度が低いことが,子どもの食生活に対する配慮の程度を低め,子どもの中食や外食の頻度をあげ,食べ物の偏り,栄養の偏りを生じさせていると考えられる。
拒食については,3つの養育タイプ間に有意な差がみられなかった。
過食については,過干渉型が有意に高い値を示した。養育態度のアンバランスが子どもの過食に反映されていると考えられる。
きょうだいの数による影響
きょうだいの数による影響を調べるためにきょうだい無し,きょうだい一人,きょうだい二人以上の3群を独立変数とし,保護者の養育態度,甘いものとの関わり方,食行動の問題を従属変数として分散分析を行い,有意な差のみられた変数についてボンフェローニィの下位検定を行った。
Table 5に調査対象となった子どものきょうだいの人数別群の分布を示した。
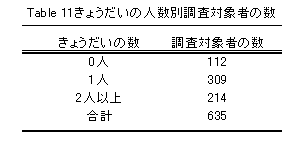 |
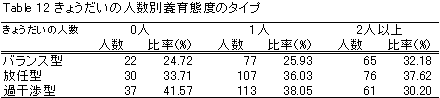 |
Figure 7にきょうだいの数別甘いものとの関わり方の平均値を示した。きょうだいの数が多いほど甘いものによるしつけ,甘いものを摂取しやすい環境で高い平均値が示された。 甘いものの提供頻度では,有意な差はみられなかった。
またきょうだいの人数別養育態度のタイプの分布をみてみると,一人っ子には過干渉型の養育タイプの割合が多く,バランス型,放任型はきょうだいの人数が多くなるほどその割合が増えていた(Table 6)。
Figure 7にきょうだいの数別甘いものとの関わり方の平均値を示した。きょうだいの数が多いほど甘いものによるしつけ,甘いものを摂取しやすい環境で高い平均値が示された。 甘いものの提供頻度では,有意な差はみられなかった。
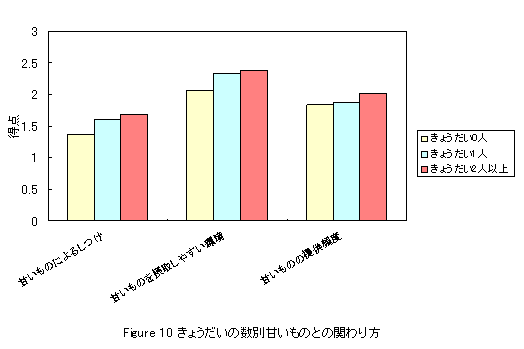
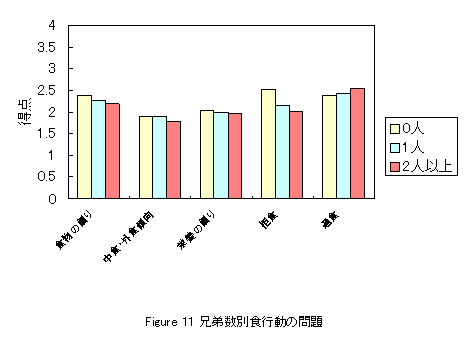
子どもの甘味に対する態度には,きょうだいの数の相違による効果はみられなかった。
以上の結果からきょうだいの数は,保護者の養育態度を決定する要因となり,このことは子どもの甘いものとの関わり,拒食に影響を与えていた。甘味に対する態度に影響する環境要因と食行動の問題との関係についておこなったパス解析の結果では,甘いものを摂取しやすい環境は拒食を予測する変数となっていた(Figure 4)。しかし一人っ子では,きょうだいを持つ子どもたちに比較して甘いものを摂取しやすい環境にない。そのため一人っ子の拒食は,甘味に対する態度とは関係ないと考えられる。
| ページのトップへ |
5.要約
1. 甘味に対する否定的な態度,肯定的な態度は,幼児期から青年期を通じて形成されていくことが明らかになった。子どもの甘味に対する肯定的な態度は,保護者の甘味に対する肯定的な態度が直接影響するのではなく,甘いものに関する養育態度を介して間接的に影響する。一方子どもの甘味に対する否定的な態度は,保護者の甘味に対する否定的な態度が直接関連していた。
2. また女子大学生にみられた食行動の異常傾向の予測変数である甘味に対するアンビバレントな態度は,幼児期から高校生の発達段階でも説明力は弱いものの過食と因果関係が認められた。
3. 子どもの食行動を形成する上で強い影響をもたらすと考えられる保護者の養育態度と子どもの甘味に対する態度,食行動の問題について検討した。その結果,子どもの食行動の問題の背景には,兄弟の数,一般的な養育態度のありかたが影響していることが示された。具体的には一般的な養育態度のあり方は,甘いものに関する養育態度や子どもの食生活への配慮をとおして子どもの食生活に反映され,結果的に子どもの食行動の問題へと結びついていると考えられる。保護者の養育態度を背景とした子どもの食生活を考える上で,甘いものをどのように位置づけるかが子どもの食行動の問題を考える上では重要な視点となる。
本研究で甘味に対する嗜好の形成過程を検討したことで,子どもを養育していく上で甘味物質の代表である砂糖をどのように位置づけるか,一定の示唆を得ることができたと考えられる。生来,人は生理的な理由から甘味に対して受容的である。それゆえ甘味に対してメリット感を持つ,そしてメリット感は,再び甘味に対する嗜好を導く要因となる。同時に現代人は,高栄養時代を背景として甘味に対する否定的な認知,感情,行動傾向を獲得する。しかし,甘味に対する肯定的な態度,否定的な態度の両方を強く持つことは食行動の異常をきたす要因となる。つまり健康な食行動を身につけるには,甘味に対するアンビバレントな態度の形成を回避することが必要である。本研究から甘味に対する肯定的な態度,否定的な態度がどのように形成されるか,その一端が明らかとなったので,今後食教育や保護者に対する啓蒙教育にこの内容が反映され,国民の砂糖に対する態度がバランスの取れたものとなり,健康な食生活が営まれることを期待する。
2. また女子大学生にみられた食行動の異常傾向の予測変数である甘味に対するアンビバレントな態度は,幼児期から高校生の発達段階でも説明力は弱いものの過食と因果関係が認められた。
3. 子どもの食行動を形成する上で強い影響をもたらすと考えられる保護者の養育態度と子どもの甘味に対する態度,食行動の問題について検討した。その結果,子どもの食行動の問題の背景には,兄弟の数,一般的な養育態度のありかたが影響していることが示された。具体的には一般的な養育態度のあり方は,甘いものに関する養育態度や子どもの食生活への配慮をとおして子どもの食生活に反映され,結果的に子どもの食行動の問題へと結びついていると考えられる。保護者の養育態度を背景とした子どもの食生活を考える上で,甘いものをどのように位置づけるかが子どもの食行動の問題を考える上では重要な視点となる。
本研究で甘味に対する嗜好の形成過程を検討したことで,子どもを養育していく上で甘味物質の代表である砂糖をどのように位置づけるか,一定の示唆を得ることができたと考えられる。生来,人は生理的な理由から甘味に対して受容的である。それゆえ甘味に対してメリット感を持つ,そしてメリット感は,再び甘味に対する嗜好を導く要因となる。同時に現代人は,高栄養時代を背景として甘味に対する否定的な認知,感情,行動傾向を獲得する。しかし,甘味に対する肯定的な態度,否定的な態度の両方を強く持つことは食行動の異常をきたす要因となる。つまり健康な食行動を身につけるには,甘味に対するアンビバレントな態度の形成を回避することが必要である。本研究から甘味に対する肯定的な態度,否定的な態度がどのように形成されるか,その一端が明らかとなったので,今後食教育や保護者に対する啓蒙教育にこの内容が反映され,国民の砂糖に対する態度がバランスの取れたものとなり,健康な食生活が営まれることを期待する。
| ページのトップへ |
5.引用文献
Bandura, A., Social Learning Theory, 1977(原野広太郎監訳『社会的学習理論』1979).
Dye, L., Warner, P. & Bancroft, J. 1995 Food craving during the menstrual cycle and its relationship to stress, happiness of relationship and depression; a preliminary enquiry. Affective Disorders. 34,157-164.
長谷川智子 2000 子どもの肥満と発達臨床心理学 川島書店
Holt, S.H.A., Cobiac, L., Beaumont-Smith, N.E., Easton, K., & Best, D.J. 2000 Dietary habits and the perception and liking of sweetness among Australian and Malaysian students: A cross-culture study. Food Quality and Preference , 11, 299-312.
今田純雄 1997 青年期の食行動 中島義明・今田純雄(編) たべる 食行動の心理学 朝倉書店
今田純雄 2005 好き嫌いはどうして生まれる? −食べることの学習− 今田純雄(編) 食べることの心理学−食べる,食べない,好き嫌い− 有斐閣社
加藤佳子,井川佳子 2002 糖溶液に対する中学生および成人の好みの分析 日本食生活学会,13,99-106.
加藤佳子 2005a 大学生の甘味に対する態度が食行動の異常傾向に及ぼす影響 健康心理学研究,18,(印刷中)
加藤佳子 2005b 甘味に対する態度を規定する心理的要因に関する研究 広島大学教育学研究科博士論文 (未刊行)
Katou, Y., Mori, T., & Ikawa, Y. 2005 Effect of age and gender on attitudes towards sweet foods among Japanese. Food Quality and Preference, 16,171-179.
健康・体力作り事業財団 2000 健康日本21 報告書 http://www.kenkounippon21.gr.jp/
松村康生 1995 ヒトはなぜ甘いものや脂肪分に富む食物を好むのか 日本調理学会誌,28,185-189.
宮下一博 1999 中島義明・安藤清志・子安増生・繁桝算男・坂野雄二・立花政夫・箱田祐司 心理学辞典 CD-ROM版
二宮克美 1999 中島義明・安藤清志・子安増生・繁桝算男・坂野雄二・立花政夫・箱田祐司 心理学辞典 CD-ROM版
向井隆代 1998 摂食障害 児童心理学の進歩 37,金子書房,Pp.225‐246.
高木州一郎 1991 摂食障害の発症誘発因子と準備因子の検討 臨床精神医学 20,319-327.
筒井末春,中野弘一,坪井康次,中島弘子:大学生の食習慣及び食行動異常に関する検討.厚生省特定疾患神経性食欲不振症調査研究班平成4年度報告書Pp. 87-90,1994
渋谷美里 1996 偏食に関する心理学的考察 広島修道大学人文学部卒業論文(未刊行)
鈴木眞雄,松田 惺,永田忠夫,植村勝彦 1985 子どものパーソナリティ発達に影響を及ぼす養育態度・家族環境・社会的ストレスに関する測定尺度構成 愛知教育大学研究報告 34,139−152.
若月秀夫2004,小学校と中学校の接続関係を考える
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/gijiroku/001/04080201/003.pdf
Dye, L., Warner, P. & Bancroft, J. 1995 Food craving during the menstrual cycle and its relationship to stress, happiness of relationship and depression; a preliminary enquiry. Affective Disorders. 34,157-164.
長谷川智子 2000 子どもの肥満と発達臨床心理学 川島書店
Holt, S.H.A., Cobiac, L., Beaumont-Smith, N.E., Easton, K., & Best, D.J. 2000 Dietary habits and the perception and liking of sweetness among Australian and Malaysian students: A cross-culture study. Food Quality and Preference , 11, 299-312.
今田純雄 1997 青年期の食行動 中島義明・今田純雄(編) たべる 食行動の心理学 朝倉書店
今田純雄 2005 好き嫌いはどうして生まれる? −食べることの学習− 今田純雄(編) 食べることの心理学−食べる,食べない,好き嫌い− 有斐閣社
加藤佳子,井川佳子 2002 糖溶液に対する中学生および成人の好みの分析 日本食生活学会,13,99-106.
加藤佳子 2005a 大学生の甘味に対する態度が食行動の異常傾向に及ぼす影響 健康心理学研究,18,(印刷中)
加藤佳子 2005b 甘味に対する態度を規定する心理的要因に関する研究 広島大学教育学研究科博士論文 (未刊行)
Katou, Y., Mori, T., & Ikawa, Y. 2005 Effect of age and gender on attitudes towards sweet foods among Japanese. Food Quality and Preference, 16,171-179.
健康・体力作り事業財団 2000 健康日本21 報告書 http://www.kenkounippon21.gr.jp/
松村康生 1995 ヒトはなぜ甘いものや脂肪分に富む食物を好むのか 日本調理学会誌,28,185-189.
宮下一博 1999 中島義明・安藤清志・子安増生・繁桝算男・坂野雄二・立花政夫・箱田祐司 心理学辞典 CD-ROM版
二宮克美 1999 中島義明・安藤清志・子安増生・繁桝算男・坂野雄二・立花政夫・箱田祐司 心理学辞典 CD-ROM版
向井隆代 1998 摂食障害 児童心理学の進歩 37,金子書房,Pp.225‐246.
高木州一郎 1991 摂食障害の発症誘発因子と準備因子の検討 臨床精神医学 20,319-327.
筒井末春,中野弘一,坪井康次,中島弘子:大学生の食習慣及び食行動異常に関する検討.厚生省特定疾患神経性食欲不振症調査研究班平成4年度報告書Pp. 87-90,1994
渋谷美里 1996 偏食に関する心理学的考察 広島修道大学人文学部卒業論文(未刊行)
鈴木眞雄,松田 惺,永田忠夫,植村勝彦 1985 子どものパーソナリティ発達に影響を及ぼす養育態度・家族環境・社会的ストレスに関する測定尺度構成 愛知教育大学研究報告 34,139−152.
若月秀夫2004,小学校と中学校の接続関係を考える
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/gijiroku/001/04080201/003.pdf
| ページのトップへ |










