

ホーム > 砂糖 > 視点 > 産業 > 世界のさとうきび育種について
最終更新日:2010年3月6日
[2006年9月]
【調査・報告〔生産/利用技術〕】
| 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター 研究リーダー |
永冨 成紀 | |
| 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター バイオマス・資源作物開発チーム |
主任研究員 伊禮 信 重点研究支援協力員 福原 誠司 |
| 1.はじめに |
| 2.第8回育種・遺伝資源分野ワークショップの概要 |
| 3.おわりに(今後のさとうきび研究) |
| 参考文献・URL |
1.はじめに
2006年5月1日からの5日までの5日間にわたり、エクアドル共和国のグアヤキル市において、エクアドル糖業研究所(CINCAE)が受入機関となり国際甘蔗糖技術者会議(ISSCT:International
Society of Sugar Cane Technologists)の第8回育種・遺伝資源ワークショップが開催された。ISSCTは、さとうきび農業から製糖業までのあらゆる技術に関する研究情報や意見交換を行うことを目的に1924年に発足し、80余年の歴史を持つ国際的な学会である。
5つの委員会(農業技術系、農学・生物学系、製糖技術関連、副産物等の関連、経営等の関連)が設置されており、約60カ国の1,300余名が会員となっている。各委員会の下には、さらに細分化された専門分野があり、1〜2年毎に、その専門分野ごとのワークショップが開催される。また、3年毎に、各分野すべてを含めた形で世界大会が開催される。
近年、さとうきびの研究戦略や生産技術は、さとうきびのバイオエネルギー源としての利用を目指す世界の潮流を受け、刻々と変化をしている。このような時期に国際的な学会に参加し、世界的な情報を得ることは、わが国にとって極めて重要である。
5つの委員会(農業技術系、農学・生物学系、製糖技術関連、副産物等の関連、経営等の関連)が設置されており、約60カ国の1,300余名が会員となっている。各委員会の下には、さらに細分化された専門分野があり、1〜2年毎に、その専門分野ごとのワークショップが開催される。また、3年毎に、各分野すべてを含めた形で世界大会が開催される。
近年、さとうきびの研究戦略や生産技術は、さとうきびのバイオエネルギー源としての利用を目指す世界の潮流を受け、刻々と変化をしている。このような時期に国際的な学会に参加し、世界的な情報を得ることは、わが国にとって極めて重要である。
| ページのトップへ |
2.第8回育種・遺伝資源分野ワークショップの概要
(1) ワークショップの参加者
育種・遺伝資源分野ワークショップは、グアヤキル市のヒルトンコロンホテルにおいて2006年5月1日から5日まで開催され、エクアドル、ブラジル、オーストラリア、南アフリカ共和国など15カ国から53人のさとうきびの育種・遺伝資源に関わる専門家が参加し、最新情報の発表と質疑が行われた。
なお、育種・遺伝資源ワークショップのプログラムの内容は次のウエブで閲覧できる。
http://issct.intnet.mu/breedprog06.htm
 |
写真 ワークショップの参加者CINCAEのエントランスにて |
(2) 日本からの参加者の研究発表
日本からの参加者は、永冨、伊禮、福原の3人で、各人の研究発表の概要は次のとおり。
(1) さとうきびの属間交雑種の選抜と特性について
福原は、さとうきびの属間交雑種の選抜と特性について発表を行った(図1参照)。
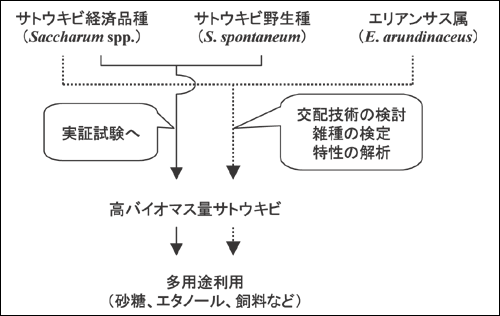 |
図1 種属間交雑を利用した品種開発の流れ(イメージ図)
|
さとうきびの経済品種(製糖用品種)の成立は、高貴種(Saccharum officinarum)と野生種(S. spontaneum)の種間交雑に端を発しているが、現在の品種はごく限られた交配組合せに由来することが多くなっており、品種の近縁化が進み、遺伝的脆弱性が指摘されている。
さとうきびは、長い間、製糖用として利用されてきたが、近年ではエタノール用や飼料用など、多用途の利用が進められている。多用途の利用に向けたさとうきびの育成には遺伝的変異を拡大する必要があり、その方法として種間交雑と属間交雑が挙げられる。
種間交雑では、経済品種と野生種との後代からエタノールや飼料用の高バイオマス量サトウキビが育成されており、現在実証試験の段階にある。
属間交雑では、さとうきびと近縁なエリアンサス属(genus Erianthus)が耐干性や旺盛な生育など有用な特性を具えているため、交配素材として有望視されてきた。しかしこれまでのところ、高貴種との交雑後代に関する報告がわずかにあるだけで、育種への利用は進んでいない。属間交雑は、作物を飛躍的に改善する可能性が期待される。
そこで、経済品種を母本に、E. arundinaceusを父本に用いて交雑種子を得た。DNAマーカーを用いたところ、雑種性が確認された。得られた雑種のDNA量と基礎的な特性を調査し、遺伝的解析の糸口を示した。
高貴種とE. arundinaceusとの雑種では不稔性や生育抑制などが知られているため、参加者からは開花特性や今後の利用についての質問やコメントがあり、現在得られている知見と今後の方針を紹介した。
(2) さとうきびへのガンマ線照射の突然変異誘発の効果について
永冨は、さとうきびへのガンマ線照射の突然変異誘発の効果について発表を行った。
ガンマ線の急照射と緩照射を行ったさとうきびの幼葉を無菌培養し、その誘導カルス(組織の一部から発生する未分化の細胞の塊)から再分化個体を獲得し、その栄養繁殖による系統を作成した(図2参照)。
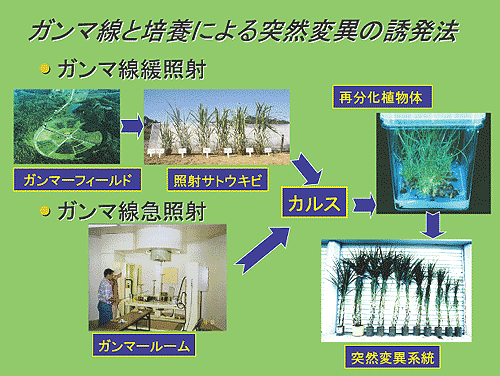 |
図2 ガンマ線と培養による突然変異の誘発法
|
各系統を試験ほ場に植え付け、茎長、1茎重、ブリックスなどの重要形質を調査し、併行してフローサイトメーターによる核DNA量の変動を基に解析を行なった。
その結果、再分化系統の生育量については、急照射と培養を組み合わせた方法では、線量の増加につれて減少し、負の方向に変異し、核DNA量も減少した(図3参照)。
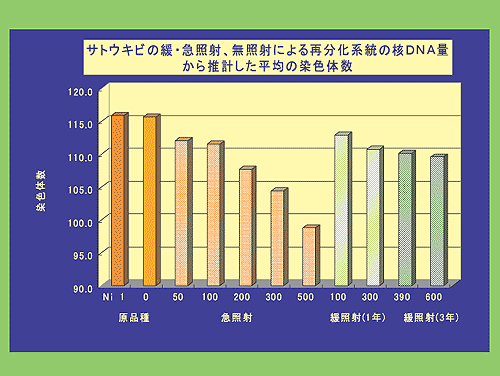 |
図3 サトウキビの急照射、緩照射による再分化系統の核DNA量から推計した平均の染色体数
|
つまり、急照射のように短時間であっても高い線量で照射した培養体から再分化した系統では、生育量が減少し、細胞核内の染色体(DNA)が失われて、放射線の影響が強く現れた。
これに対し、緩照射と培養を組み合わせた方法では、明瞭に正および負の方向に拡大し、核DNA量の減少は少なかった。 すなわち、急照射と同じ線量を照射するにしても、緩照射のように長期間に低い線量で照射した培養体から再生した系統では、生育量が減少のみらず増大する多収型が現れ、染色体の減少が少なく放射線の影響が軽減され、育種法としては優れている。
なお、無照射と培養を組み合わせた方法では、ほとんど有意な変化がなく、核DNA量は原品種と同じ値であった。
また、再分化系統の主要形質と核DNA量は有意な正の相関関係が認められ、ガンマ線の障害により主要形質が減少すれば、それに伴いDNA量も減少した。核DNA量は障害の程度を判定できる方法に利用できた。
ガンマ線照射と培養を組み合わせた変異誘発法では、緩照射の方が急照射よりも障害が少なく、変異が正の方にも拡大し、より生育の旺盛な系統が誘発される頻度が大きくなった。また、再分化系統の変異性は、栄養繁殖により次代にも伝わり、キメラ(1個体の生物に元の細胞と新たな細胞が混在する状態を示す。ギリシャ神話に登場する想像上の動物名に由来。)もなく安定しているので、従来のようにキメラを安定化する年月を省略することができ、短期間に優良系統を選抜することができる。
講演後、突然変異系統がキメラを生じることはないかとの質問があったが、細胞培養を用いた突然変異系統は、単一の変異細胞から誘発されるため、キメラを生じないことを説明した(これまで、栄養繁殖植物は、ガンマ線を照射することによりキメラが必ず生じて、真の突然変異体を得ることが難しく、突然変異育種の効率を著しく低下させてきた事情がある)。
(3) 日本のさとうきび育種における近縁属種利用の現状等について
伊禮は、日本のさとうきび育種における近縁属種利用の現状、利用に際しての問題点について発表を行った(図4参照)。
九州沖縄農業研究センターでは、干ばつや低地力等に代表される不良な栽培環境における安定的なさとうきび生産、また、さとうきびの多様な利用に向け、近縁種・属を交配に用いた育種を行っている。さとうきびの野生種Saccharum
spontaneumを用いた交配からは、高バイオマスの有望系統を多数得ており、それら有望系統の中から、飼料用のさとうきびとして「KRFo93-1」を今年度品種登録する。
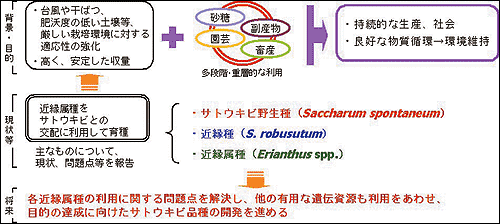 |
図4 伊禮らの発表の概略
|
野生種は、後代に黒穂病に罹病性の高いものが多いという問題を抱えている。そこで、現在、黒穂病の接種検定により、黒穂病抵抗性をもつ野生種の選定を進めているところである。
さとうきびの祖先種のひとつS. robustumを用いた交配からは、生育、繊維分、ブリックス等において幅広い変異のある107個体の後代が得られている。しかし、本種は、出穂がまれであり定常的な交配利用が難しいという問題がある。現在までに得られた107個体を“橋渡し”として次の交配に利用していく一方、本種の出穂対策として日長処理による開花誘導について検討する必要がある。
近縁属種であるErianthus spp.は、深い根系を持ち、不良な環境での栽培適性の強化に向けた有用な遺伝資源と考えられている。Erianthus
spp.の持つ有用形質の導入に向け、これまでに数多くの交配を行ってきたが、得られている実生(みしょう:さとうきびの種子から発生した植物)はわずかである。本種の利用では、効率的に交配実生、あるいは雑種を得るための条件を明らかにしていく必要があると考えており、開花特性の違い等に注目し、調査を進めているところである。
以上の内容で発表を行ったところ、「KRFo93-1」に関し、「飼料用としてどのような点に注目して選抜を行ったか」という質問があった。質問に対し、日本のさとうきび栽培地帯の自然環境等も踏まえたうえで、株出し萌芽の良さと持続性、旺盛な生育を重点に初期からの選抜を行ったことを述べた。
(3) 各国の参加者からの主な発表
ワークショップにおける今後の日本のさとうきび育種に参考となると思われる主な発表は、次のとおりである
(1) 世界の製糖業を支えたさとうきび育種の歴史
ブラジルのMachado氏(「世界のサトウキビ品種目録」の編集者)は、世界の製糖業を支えたさとうきび育種の歴史などについて基調講演を行った。
さとうきび育種開始の時期は、19世紀の後期にジャワとバルバドスにおける稔実種子の発見にさかのぼるとし、当時の経済品種であった原種UbaとBadilaはやがて交雑品種に置き替わり、それ以降、主要産糖国においてさとうきび品種が変遷してきた。
現在の品種を巡る問題点としては、知的財産権としての品種育成権が主張されるようになり、それまで導入品種に依存していた地域で自由に品種が使えなくなったことが挙げられる。この結果、新規の育種に挑戦せざるを得なくなっている。
また、さとうきびに新たな用途を求めた育種が進行している。新たな用途としては、繊維分、バイオエタノール、新種の病虫害抵抗性、機械化適性、気象変動に関連する生理形質、潅漑技術、糖分上昇技術などがある。
さとうきび育種では、いくつかの国で遺伝子組み換えが禁止されているが、ブラジルでは、200人を超す研究者が従事したサトウキビゲノム解析計画によって、さとうきびの総遺伝子数33,000のうち2,000の遺伝子が植物体内の糖代謝との関連性が認められるなど成果があり、今後の育種の生産性向上に遺伝子組み換えが期待されている。
(2) 多父交配の欠点を補足できる手法
ルイジアナのホウマ研究所のTew氏は、多父交配(1つの母本に対して複数の父本の花粉を混合して受粉させる交配法で、二親交配(父母本を1対1に交配)に比べ交雑種子数を増加できる利点がある)の欠点を補足できる手法について発表した。
さとうきびは、品種間で出穂性にばらつきがあり、選定した交配親間すべてで交配を行うことは困難である。最大数の組み合わせを実現するため、これまで多父交配が試みられてきたが、その結果、数世代にわたり父系の情報が得られないという矛盾に突き当たっている。博士は、父系を特定するため、マイクロサテライトマーカーを用いる方法を紹介した。
(3) 交配事業に大きな影響を持つ出穂促進の試験結果
オーストラリアのサトウキビ試験場事務局(BSES)のNils Berding氏は、交配事業に大きな影響を持つ出穂促進の試験結果を発表した。
さとうきびの日長時間の調整による出穂制御は、育種事業にとって、交配品種の出穂率を高め、開花時期を調整するため、亜熱帯のみならず交配条件に好まれた熱帯地域においても重要である。出穂促進施設の実績として、2003年出穂品種率は77−90%、出穂茎率は59−78%、450組み合わせを行い、通常であれば大成功の交配結果であるが、さらに出穂率を高めようとする改良試験を行った。
花成誘導と成長に関係する日長時間の漸減に焦点を当て、4月1,17,28日に日長時間12時間55分から開始し、1日で30,45、60秒ずつ日長時間を減少させていった。1日あたり45秒の漸減日長が最良の結果を得た。出穂時期の調整については現在も実施中である。
(4) 初期選抜法
モーリシャスの糖業研究所のRamdoyal氏は、初期選抜法について発表した。従来のポット育苗から苗は直接植え付け、さらに苗の間隔を狭め、二条植にすることで、選抜にかかる年数を一年短縮でき、従来の選抜と比較しても遜色は無いことも確認されたことが紹介された。
この選抜方法について、参加者からは特にコスト面でのメリット、デメリットに関する質問が多かった。今後は、日本でもより効率的な選抜法を取り入れていくことが必要であると思われた。
(5) 遺伝子型と環境の相互作用
オーストラリア・試験場事務局のJackson氏は、遺伝子型と環境の相互作用について発表した。オーストラリアの5カ所の主要栽培地域で選抜系統を調査したところ、遺伝子型×環境相互作用が茎収量と可製糖率(CCS)に及ぼす影響は少ないことが発表された。これにより、地域を跨いだ検定試験の実施や、将来的には広域向けの育種センターを設立して、選抜年数を短縮することが提案された。栽培地域の環境や栽培管理法は国により一様ではないため、今後は地域の実情を踏まえた検討が必要であると思われた。
(6) 植物病原細菌により引き起こされる矮化病(ratoon stunt disease、RSD)の抵抗性の検定
アメリカの農務省(USDA)のComstock氏は、植物病原細菌により引き起こされる矮化病(ratoon stunt disease、RSD)の抵抗性の検定について発表した。抵抗性品種の選抜の際に、Tissue
Blot Immunoassay法(免疫組織化学法の一種。抗原-抗体反応という特異的な結合反応を利用。病原菌のタンパク質の細胞内および組織内の局在を検出する方法)で罹病性を検定しており、ある程度の効果が得られたことや、土壌水分と発病の関係など栽培時の留意点が発表された。他の病害にも言えることだが、育種選抜過程では効率的で高精度に行える病害抵抗性検定法が求められる。今後展開されるであろう病害抵抗性の育種に期待が持たれる。
(7) さとうきびの多様な利用
バルバドスの西インドサトウキビ研究所のKennedy氏は、さとうきびの多様な利用の例として、高バイオマスを利用した燃料資源、バガスからの発電・売電、エタノール生産、ラム酒、地元消費に向けた砂糖、輸出に向けた高付加価値の砂糖などをあげ、これらに向けた育種、交配組み合わせを、具体的な目標数値を示して報告し、従来の製糖用のみに向けた育種操作を急速に変化させる必要があると強調した。西インド諸島、諸国の生産環境は、日本と通じるところも多いので、さとうきびを通して、物質の循環、社会経営等を含めた持続的な農業を維持、実現しようとする動きに共感を覚えた。
(8) 開花誘導
CINCAEの育種研究部門を統括するCastillo氏からは、開花誘導に関して発表があった。
現在エクアドルでは栽培される主要な品種は、1980年代頃にオーストラリアで育成されたRagnarである。Ragnarは他国でも栽培された経緯をもつ優れた品種であるが、エクアドルでは、さらなる多収、高糖を目標に、交配育種により新品種育成に取り組んでいる。
さとうきびは短日植物で、出穂には日長の短方向への変化が必要である。赤道直下に位置するエクアドルでは、年間を通した日長の変化が少なく、自然条件下では500余の遺伝資源のうち、25から30%しか出穂しないとのことであった。Castillo氏らは、徐々に日長を減じていくことで80%以上の高出穂率を確保できたと報告した。
(9) エクアドルの有する遺伝資源の多様性
CINCAEのCedeno氏らからは、エクアドルの有する遺伝資源の多様性についてポスター発表があった。
それによると、遺伝的類似度の平均は65%程度で、比較的高かった。両発表をあわせると、遺伝的類似度が比較的高かったために高率の開花誘導結果が得られた可能性もあると考えられる。将来の育成品種のさらなる強化に向け、より多様な遺伝資源を導入、収集する必要もあると考えられた。
(10) 生長点の長期低温保存
フランス(西インド諸島のグアドループ)の農業研究所のDaniele女史から、生長点の長期低温保存についてポスター発表があった。
多様な遺伝資源を収集し、利用していくことは、育種を行ううえで極めて重要である。栄養繁殖性であるさとうきびの保存、維持は常に植物体で行われる。そのため、種子保存できる作物と異なり高コストである。
Daniele女史は、幼葉鞘1枚を残した状態で生長点を切り出してアルギン酸カルシウムに包埋し、−196℃の液体窒素で凍結させ、以後−80℃の冷凍庫で長期間保存できると報告した。比較的簡易な手法により、従来に比べ小規模で大量の遺伝資源が保存できることは極めて意義深い。本手法で保存された遺伝資源を育種に利用するには、培養による植物体再生が必要である。さとうきびでは培養に伴い形質の変化がみられることが多く報告されているが、本手法適用後の遺伝資源について、植物体再生後に20の主要形質について調査した結果、変化は認められないとのことであった。詳細な意味では、遺伝的変異の出現を否定できないが、育種利用を目的とした遺伝資源保存法として有用であると考えられた。
(4) わが国と世界の糖業国との連携
日本では、海外に交配委託して導入した種子に、国内交配による種子をあわせ、育種を行っている。これまでに、台湾交配に由来する農林3号(NiF3)、農林8号(NiF8)、農林20号(NiTn20)といった品種、南アフリカ交配に由来する農林2号(NiN2)、新品種候補KN91-49といった品種あるいは系統を育成している。
ワークショップでは、南アフリカ糖業研究所からParfitt氏、Butterfield氏が参加しており、種子導入に関するお礼を述べることができた。台湾糖業研究所の閉鎖に伴い、昨年から新たに交配を委託しているブラジルの製糖企業(Cana
Vialis)からはMatsuoka氏が参加しており、同様に謝意を述べることができた。交配種子の導入は、日本にない遺伝資源の導入という観点からも意義は大きく、今後も導入を継続する必要があると考える。
各国の研究者と意見を交換する中で、日本の栽培品種や近縁属種に対する関心が高いことを知った。その理由として、日本から海外に向けた研究情報の発信が少ないことが挙げられるであろう。また、他の栽培地域に比べ高緯度、かつ、島しょのさまざまな環境で経済品種が栽培される、あるいは近縁属種が自生するという点が、有用な遺伝資源としての期待を大きくしているものと考えられる。
日本から他国の品種をみた場合、黒穂病等の重要病害に対する抵抗性等、遺伝資源として期待できる有用な形質は多い。経済品種では、限られた交配組合せに由来する遺伝的脆弱性も指摘されていることから、国を問わず、新たな遺伝資源を導入する意義は大きい。
各国の参加者は、講演で紹介される研究成果や提案の内容もさることながら、砂糖価格や試算されるコストに非常に敏感であった。また、基調講演後の質疑では、さとうきびの将来への方向性に対する質問があるなど、さとうきびと砂糖を取り巻く状況は大きく変化しており、今後の展開を見極める必要があると感じた。
現在、九州沖縄農業研究センターではさとうきびの多用途利用の研究を進めており、国内の風土に適応した品種育成のためにも、国内で収集された野生種の有効利用を検討する必要があると思われる。
ワークショップにおける発表全体を通し、世界的に、さとうきびに期待すること、さとうきびで可能なことが大きく変わりつつあることを実感できたことは、今後の研究を考えるうえで貴重な経験であった。
また、さとうきびの育種研究を取り巻く世界の状況は、研究成果を積み重ねてゆく普遍的な分野と大きく変化した分野が明瞭に感じ分けられた。特に後者の分野は、世界が地球環境の保全と農業の持続的発展を目指す上で、さとうきびに新たな価値を期待し始めていることの現われであり、その一つがバイオエネルギー源としての価値である。
さとうきびには将来に向けて期待される特性が多く、これらを生かした研究戦略を構築していくことが重要であろうと考えられた。
最後に、ワークショップは同分野の各国の研究に触れ、研究者を知り、情報交換し、情報のみでは実感しがたい生産現場の様子を知るうえで絶好の機会である。日本のさとうきび研究を推進するうえでも、自らを含め、日本からの積極的な参加を継続したい。
| ページのトップへ |
● 中南米におけるCDMの取り組み.ジェトロ(JETRO)海外調査部中南米課.(2005年)
● ポケット砂糖統計.株式会社精糖工業会館.(2004年)
● Informe Anual. CINCAE. (2005年)
● FAO(http://www.fao.org)
● SICA(The Agricultural Census and Information System Technical Assistance
Project, http://www.sica.gov.ec/ingles/)
● US Department of State(http://www.state.gov)
● 8th ISSCT Breeding and Germplasm Workshop Abstract Book, 44Pp. Guayaquil-Ecuador,
May1-5, 2006.
| ページのトップへ |










