

ホーム > 砂糖 > 視点 > 社会 > 歴史を踏まえたEU(欧州連合)砂糖政策の転換点〜改革の今後の動向に注目〜
最終更新日:2010年3月6日
もともとニューギニア原産といわれるさとうきびは、インドを経由し、8世紀頃アラビア人により初めてヨーロッパの南、地中海世界に持ち込まれたが、15世紀のコロンブスによる「新世界発見」により、主にカリブ海地域において、アフリカから連行してきた奴隷を強制労働させる、いわゆる「プランテーション農業」としてのさとうきび糖業が成立した。生産量の増加に伴い、砂糖は、王侯貴族が権力を誇示するための香料、薬品から、ヨーロッパの一般大衆がお茶、コーヒーなどに入れて楽しむ大衆的な食品に変身し、17−8世紀以降、その消費量も、裾野の広がりにより飛躍的に拡大した。
歴史は偶然のたまものである。1745年にドイツの化学者S. Marggrafが、ビート(てん菜=砂糖大根)から砂糖を分離することに成功していたが、ヨーロッパにビート糖業を根付かせることになったのは、ナポレオンの大陸封鎖であった。1806年から1813年における大陸封鎖による影響で、ヨーロッパへ新大陸から砂糖が供給されなくなった。そのため、砂糖の自給を目的とし、ヨーロッパ各地にビート糖業が広まった。歴史に「もし」は禁句であるが、もし、ナポレオンが現れなかったら、ヨーロッパにビート糖業が成立していなかったかもしれない。
ビート糖業は、温帯から亜寒帯にかけての比較的冷涼な地域で行なわれており、先進国に多い。EU25(欧州連合25カ国)、アメリカ、日本がその代表的な国・地域である。これらの国・地域は、いわゆる先進国であり、砂糖の1人当たり消費量の水準も概して高く、それぞれ、39Kg,30Kg,19Kg(OECDデータ、2005年)となっている。EU25の1人当たり消費量の水準は、キューバ、オーストラリア、ブラジルといった、年間50Kgを超える主要生産国には及ばない。しかし、EU25の人口が4億7千万人に達していることを勘案すると、EU25は世界の砂糖消費量の1割強を占める、世界の砂糖の主要市場となっている。
上記のような偶然で生まれたヨーロッパのビート糖業は、北アメリカ、日本(北海道)に伝播するとともに、その根をしっかりとヨーロッパの大地に降ろした。第二次世界大戦の惨渦を乗り越え、戦後、ヨーロッパ共同体と、CAP(共通農業政策)が発足した時、砂糖も穀物などの他の基幹作物と同様、可変課徴金−生産量割当および国内価格支持−輸出補助金の、いわば「緑のトライアングル(三角)」で守られた重要農産物として位置づけられた。ガット農業交渉において、可変課徴金制度は廃止され、関税化されたが、制度の基本的な枠組みには、1968年以来、手をつけられなかった。
しかし、保護一辺倒でないところが、ヨーロッパのしたたかさであり、懐の深さである。砂糖の国内保護と、旧植民地諸国への援助は、一体不可分である。すなわち、イギリスやフランスは、カリブ海やアフリカにかつて多くの植民地を持っており、そこでの基幹産業はさとうきび栽培であったため、これらの国々の砂糖の貿易は、いわゆる「特恵的」、すなわち、これらの旧植民地から優先的に砂糖を輸入するという協定を、CAP発足以前から取り交わしていたのである。戦後まもなくの時期は、EUは砂糖の純輸入地域であり、ビート糖だけでは域内の需要を充足できなかった。従って、このような旧植民地諸国(いわゆるACP諸国)からの特恵輸入は、一方では食料の安定供給、またもう一方では、大戦後新たに独立した旧植民地諸国から安定的にその基幹輸出商品である砂糖を輸入してやることにより、これらの国々の経済を支え、また同時に旧宗主国としての面目を保つという、いわば、援助と農業保護という二足のわらじを履く政策を推進した。
CAPの目的は、(1)農業生産性の向上、(2)農民の生活水準の確保、(3)農産物市場の安定、(4)消費者に対する食料の安定供給、などであるが、輸出入をコントロールすることにより、域内市場を安定させることを目標としたCAPにより、ビート糖業者は、国際市場とは隔離された安定的に支持された価格水準での生産が可能となった結果、1980年代には、潜在生産量が消費量を大幅に上回る状態になり、生産割当枠の厳しい運用と、余剰分の域外への輸出が必要となった。また、輸出は、ブラジルやオーストラリア等の砂糖輸出国との間に摩擦を引き起こした。同様の問題は、他の主要農産物でも生じており、補助金付輸出、国内支持、国境保護の3分野は、1986年にスタートしたガット ・ウルグアイ・ラウンド農業交渉の交渉対象となった。
ガット・ウルグアイ・ラウンド交渉の終結により、1995年1月に発効した、マラケシュ協定においても、乳製品、砂糖といったEUの基幹農産物の制度の枠組みは実質上変わらなかった。可変輸入課徴金を関税に置き換えたものの、その関税のレベルは、依然EU域内の市場を域外から隔離するに十分であった。
1992年のCAP改革と、直接支払の導入は、CAPの保護の形態を、価格支持から、生産者に対する直接支払に転換する大きな転機となった。これ以降、CAPは、生産を刺激しない直接支払いへと、大きく舵を切った。
改革への決定的な契機は、2001年に訪れた。2月26日、EU閣僚理事会は、EBAの原則を採択した。「EBA(Everything But Arms)の原則」とは、LDC(後発開発途上国)諸国からの商品の輸入について、武器を除き、全ての物資を原則、無関税、数量制限無しで輸入可能とすることである。2006年から2009年の移行期間中、段階的な関税の引き下げが行われ、2009年から自由な輸入が可能となるというものである。このような大胆な貿易政策の舵取りが行われた背景には、2001年11月に開始するWTO新多国間交渉(ドーハラウンド)に推進力をつけ、開発途上国に対するイニシアティブを握ろうとしたEUの意志の表れと見ることができるだろう。しかし、各論で見た場合、コメ、砂糖といった品目は、LDC諸国との競争に直接さらされることになり、現行の政策の枠組みがくずれるため、政策の見直しは必至となった。特に、砂糖の場合は、2005年4月に、WTOのパネルで、ブラジル、オーストラリア、タイの提訴により、EUの砂糖輸出が実質的には補助金付輸出でWTO規則に違反しているとの裁定が下ったことも、改革への機運を加速した。
こうして、2005年11月、EU農相理事会は、1968年以来続いてきた砂糖政策の抜本的改革に合意した。ここでは詳細には立ち入らないが、その改革のポイントは、(1)砂糖の生産割当制度は維持するものの、支持価格を段階的に36%引き下げる、(2)引下げ幅の64%を直接支払いにより補償する、(3)生産割当保有者に賦課金を課し、それを財源に、非効率な工場の生産縮小あるいは廃業に対して、環境保全措置や労働者の再教育等、市場から円滑に撤退するための補助を行う、(4)LDC諸国からの輸入が前年の25%を上回る速度で増加した場合、セーフガード措置をとる、(5)ACP諸国に対し、2006年度に4,000万ユーロの「多角化援助資金」を提供し、その後は利用状況を見ながら予算の増減を行う、といった、多岐にわたるものである。
EU委員会は、これらの保護削減措置により、現在の500万トン程度ある輸出を削減し、2009年には輸出量を50万トン程度まで劇的に減らすことをねらっている。一方、今後需要の増加が見込まれるバイオエタノール用ビートの生産量は生産割当から除外するとの意向である。貿易自由化の流れの中で、CAPの唱えるさまざまな目的を達成しつつ、旧植民地諸国にも目配りをしなければならない−過去の歴史を踏まえ、新たな未来を目指す−CAPの砂糖政策は、今大きな転換点にさしかかっており、改革は始まったばかりである。2006年7月1日に、改革に着手する新たな砂糖年度(2006砂糖年度)が開始した。この改革が砂糖の国際市場に与える影響も大きいとみられ、今後の動向が注目される。
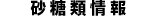

歴史は偶然のたまものである。1745年にドイツの化学者S. Marggrafが、ビート(てん菜=砂糖大根)から砂糖を分離することに成功していたが、ヨーロッパにビート糖業を根付かせることになったのは、ナポレオンの大陸封鎖であった。1806年から1813年における大陸封鎖による影響で、ヨーロッパへ新大陸から砂糖が供給されなくなった。そのため、砂糖の自給を目的とし、ヨーロッパ各地にビート糖業が広まった。歴史に「もし」は禁句であるが、もし、ナポレオンが現れなかったら、ヨーロッパにビート糖業が成立していなかったかもしれない。
ビート糖業は、温帯から亜寒帯にかけての比較的冷涼な地域で行なわれており、先進国に多い。EU25(欧州連合25カ国)、アメリカ、日本がその代表的な国・地域である。これらの国・地域は、いわゆる先進国であり、砂糖の1人当たり消費量の水準も概して高く、それぞれ、39Kg,30Kg,19Kg(OECDデータ、2005年)となっている。EU25の1人当たり消費量の水準は、キューバ、オーストラリア、ブラジルといった、年間50Kgを超える主要生産国には及ばない。しかし、EU25の人口が4億7千万人に達していることを勘案すると、EU25は世界の砂糖消費量の1割強を占める、世界の砂糖の主要市場となっている。
上記のような偶然で生まれたヨーロッパのビート糖業は、北アメリカ、日本(北海道)に伝播するとともに、その根をしっかりとヨーロッパの大地に降ろした。第二次世界大戦の惨渦を乗り越え、戦後、ヨーロッパ共同体と、CAP(共通農業政策)が発足した時、砂糖も穀物などの他の基幹作物と同様、可変課徴金−生産量割当および国内価格支持−輸出補助金の、いわば「緑のトライアングル(三角)」で守られた重要農産物として位置づけられた。ガット農業交渉において、可変課徴金制度は廃止され、関税化されたが、制度の基本的な枠組みには、1968年以来、手をつけられなかった。
しかし、保護一辺倒でないところが、ヨーロッパのしたたかさであり、懐の深さである。砂糖の国内保護と、旧植民地諸国への援助は、一体不可分である。すなわち、イギリスやフランスは、カリブ海やアフリカにかつて多くの植民地を持っており、そこでの基幹産業はさとうきび栽培であったため、これらの国々の砂糖の貿易は、いわゆる「特恵的」、すなわち、これらの旧植民地から優先的に砂糖を輸入するという協定を、CAP発足以前から取り交わしていたのである。戦後まもなくの時期は、EUは砂糖の純輸入地域であり、ビート糖だけでは域内の需要を充足できなかった。従って、このような旧植民地諸国(いわゆるACP諸国)からの特恵輸入は、一方では食料の安定供給、またもう一方では、大戦後新たに独立した旧植民地諸国から安定的にその基幹輸出商品である砂糖を輸入してやることにより、これらの国々の経済を支え、また同時に旧宗主国としての面目を保つという、いわば、援助と農業保護という二足のわらじを履く政策を推進した。
CAPの目的は、(1)農業生産性の向上、(2)農民の生活水準の確保、(3)農産物市場の安定、(4)消費者に対する食料の安定供給、などであるが、輸出入をコントロールすることにより、域内市場を安定させることを目標としたCAPにより、ビート糖業者は、国際市場とは隔離された安定的に支持された価格水準での生産が可能となった結果、1980年代には、潜在生産量が消費量を大幅に上回る状態になり、生産割当枠の厳しい運用と、余剰分の域外への輸出が必要となった。また、輸出は、ブラジルやオーストラリア等の砂糖輸出国との間に摩擦を引き起こした。同様の問題は、他の主要農産物でも生じており、補助金付輸出、国内支持、国境保護の3分野は、1986年にスタートしたガット ・ウルグアイ・ラウンド農業交渉の交渉対象となった。
ガット・ウルグアイ・ラウンド交渉の終結により、1995年1月に発効した、マラケシュ協定においても、乳製品、砂糖といったEUの基幹農産物の制度の枠組みは実質上変わらなかった。可変輸入課徴金を関税に置き換えたものの、その関税のレベルは、依然EU域内の市場を域外から隔離するに十分であった。
1992年のCAP改革と、直接支払の導入は、CAPの保護の形態を、価格支持から、生産者に対する直接支払に転換する大きな転機となった。これ以降、CAPは、生産を刺激しない直接支払いへと、大きく舵を切った。
改革への決定的な契機は、2001年に訪れた。2月26日、EU閣僚理事会は、EBAの原則を採択した。「EBA(Everything But Arms)の原則」とは、LDC(後発開発途上国)諸国からの商品の輸入について、武器を除き、全ての物資を原則、無関税、数量制限無しで輸入可能とすることである。2006年から2009年の移行期間中、段階的な関税の引き下げが行われ、2009年から自由な輸入が可能となるというものである。このような大胆な貿易政策の舵取りが行われた背景には、2001年11月に開始するWTO新多国間交渉(ドーハラウンド)に推進力をつけ、開発途上国に対するイニシアティブを握ろうとしたEUの意志の表れと見ることができるだろう。しかし、各論で見た場合、コメ、砂糖といった品目は、LDC諸国との競争に直接さらされることになり、現行の政策の枠組みがくずれるため、政策の見直しは必至となった。特に、砂糖の場合は、2005年4月に、WTOのパネルで、ブラジル、オーストラリア、タイの提訴により、EUの砂糖輸出が実質的には補助金付輸出でWTO規則に違反しているとの裁定が下ったことも、改革への機運を加速した。
こうして、2005年11月、EU農相理事会は、1968年以来続いてきた砂糖政策の抜本的改革に合意した。ここでは詳細には立ち入らないが、その改革のポイントは、(1)砂糖の生産割当制度は維持するものの、支持価格を段階的に36%引き下げる、(2)引下げ幅の64%を直接支払いにより補償する、(3)生産割当保有者に賦課金を課し、それを財源に、非効率な工場の生産縮小あるいは廃業に対して、環境保全措置や労働者の再教育等、市場から円滑に撤退するための補助を行う、(4)LDC諸国からの輸入が前年の25%を上回る速度で増加した場合、セーフガード措置をとる、(5)ACP諸国に対し、2006年度に4,000万ユーロの「多角化援助資金」を提供し、その後は利用状況を見ながら予算の増減を行う、といった、多岐にわたるものである。
EU委員会は、これらの保護削減措置により、現在の500万トン程度ある輸出を削減し、2009年には輸出量を50万トン程度まで劇的に減らすことをねらっている。一方、今後需要の増加が見込まれるバイオエタノール用ビートの生産量は生産割当から除外するとの意向である。貿易自由化の流れの中で、CAPの唱えるさまざまな目的を達成しつつ、旧植民地諸国にも目配りをしなければならない−過去の歴史を踏まえ、新たな未来を目指す−CAPの砂糖政策は、今大きな転換点にさしかかっており、改革は始まったばかりである。2006年7月1日に、改革に着手する新たな砂糖年度(2006砂糖年度)が開始した。この改革が砂糖の国際市場に与える影響も大きいとみられ、今後の動向が注目される。
| ページのトップへ |










