

�z�[�� > ���� > ���_ > �Y�� > �������H��ɂ�����ȃG�l�Ɠ�_���Y�f�̍팸�ɂ���
�ŏI�X�V���F2010�N3��6��
�m2007�N2���n
| �����H�Ɖ�@�����@�@�@�֓��@�ˎ� |
| �͂��߂� |
| 1�D���{�ɂ�����G�l���M�[�g�p�̏Ƃ��̌o�� |
| 2�D�������ʃK�X�Ƃ��̉e���ɂ��� |
| 3�D���{�ɂ����鉷�g���� |
| 4�D�������H��ɂ�����ȃG�l���Ɣr�o��_���Y�f |
| ������ |
| �Q�l���� |
�͂��߂�
�@1973�N�ɔ���������ꎟ�Ζ���@�A1978�N�̑�Ζ���@�����ɐ��E�e���́A�G�l���M�[����Ζ������Ɉˑ�����댯���Ƃ��̐Ǝ㐫�ɋC�t���Ɠ����ɁA�Ζ��ɑ���G�l���M�[�̊J����Љ�S�̂̏ȃG�l���M�[���i�ȃG�l���j�̂��߂̋�̓I�ȕ������A�d�v�ȉۑ�Ƃ��Ď��g�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɋC�Â����ꂽ�B�����āA1970�A1980�N��́A�Ζ������̌͊��A�Ζ��J���R�X�g�̍����A�Ζ������i�V���i���Y���̐�s���Ȃǂ��A��փG�l���M�[�̊J����G�l���M�[�g�p�̌������ȂǂɊS���������Ă�������ł������B
�@�������A���ꂪ1990�N��ɂȂ�ƁA���ΔR���̔R�Ăɂ��r�o������_���Y�f�Ȃǂ̉������ʃK�X�ɂ��n�����g�����d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă����B�n�����g���ɂ�鎩�R���ւ̉e���A���Ԍn�ւ̉e���A����ɂ͐l�ސ����ւ̉e���Ȃǂ����X�Ɩ��炩�ɂȂ�ɂ�āA�r�o���ꂽ��_���Y�f���n�����g���ɍł��e����^���邱�ƂɋC�Â����ꂽ���߁A���E�e���́A���͂��ĉ������ʃK�X�A���ɓ�_���Y�f�̔r�o�팸�ɐ��͂𒍂��ł���B
�@���{�����E�̗���ƋO����ɂ��āA1970�A1980�N��́A�Ζ���փG�l���M�[�̊J����G�l���M�[�g�p�̌������Ȃǂ̐�����d�v�ۑ�Ƃ��Đ��s���Ă����B1990�N��ɂȂ�ƁA�V���ȉۑ�Ƃ��ĉ������ʃK�X�̔r�o�팸�Ɏ��g�ޕK�v�������邱�Ƃ��F������A���݂ł͊���̐����s�Ɉڂ���Ă���B
�@�ȃG�l�Ɣr�o��_���Y�f�̍팸�́A�\����̂̊W�ł���A�ȃG�l�A���A�r�o��_���Y�f�̍팸�ƂȂ���������`�����̂ŁA�ȃG�l�ւ̓w�͔͂r�o��_���Y�f�̍팸�ւ̓w�͂Ƃ��Ȃ�B�����ŁA�����ł�1970�N�ォ��̓��{�̎Y�ƊE�̃G�l���M�[�g�p���Ԃ�ǂ��Ȃ���A1990�N��̒n�����g���ւ̊S�̍��܂�A����ɕ��s���āA�������H��ɂ�����ȃG�l���ւ̓w�͂Ɠ�_���Y�f�̍팸�ւ̑Ή������邱�Ƃɂ���B
| �y�[�W�̃g�b�v�� |
1�D���{�ɂ�����G�l���M�[�g�p�̏Ƃ��̌o��
�@�G�l���M�[�����́u���ΔR���v�Ɓu�ΔR���v�Ƃɕ�������B���ΔR���͐ΒY�A�Ζ��A�V�R�K�X�ALP�K�X�ł���A�Ζ���փG�l���M�[�Ƃ��Ă̔ΔR���ɂ́A���q�́A���́A�n�M�A�V�G�l���M�[�Ȃǂ�����B���z�����d�A���͔��d�A�p�������d�Ȃǂ́A�V�G�l���M�[�ɑ����A���݁A���p�����邢�͎��p���Ɍ����Č����E�J���̓r��ɂ���G�l���M�[�����ł���B����A���́A���́A�o�C�I�}�X�Ȃǂ̃G�l���M�[�����́A���X�ɍĐ������̂ŁA�u�Đ��\�G�l���M�[�v�Ƃ��Ă�Ă���B
�@���{�̃G�l���M�[�����̂قƂ�ǂ́A�C�O����̗A���ɗ���A�����Ŋm�ۂł���̂́A���́A�n�M�A���́A�V�R�K�X�̖�4���ŁA���̐����͎�v��i���iG7�j�̒��ōŒ�ł���B�܂��A���{�Ŏ����ł���G�l���M�[�́A���q�͂��܂߂Ă���20���ŁA��v��i���̒��ŃC�^���A�Ɏ����ŒႢ�����ł���B���{�ɂ����鋟�����G�l���M�[�A���Ȃ킿�ꎟ�G�l���M�[��2004�N�x�ł�5,509.1�~1012�L���J�����[�iKcal�A�������Z59,587��KL�j�ł��������A�ŏI�I�ɗ��p�����G�l���M�[�i�ŏI�G�l���M�[�j�́A3,828.2�~1012Kcal�i��41,406��KL�j�ŁA�c���29���A1,641.5�~1012Kcal�i��17,238��KL�j���Ζ��A�ΒY�A���邢�͓V�R�K�X�Ȃǂ���d�C�Ȃǂɕς���G�l���M�[�]������ȂǂŐ�����]�������A�A�����̑����A���Ə���Ȃǂł������B����ʂ̃G�l���M�[�g�p�̎��Ԃ�2004�N�x�Ō���ƁA�d�͂��܂߂čŏI�G�l���M�[��44.9�����Y�ƕ���ɁA17.9���������Ɩ�����ɁA������14.7�����^�A���q����ɁA13.1���������ƒ땔��ɁA�c�肪�^�A�ݕ�����Ɏg�p����Ă����B
�@�G�l���M�[�g�p�̍ő啔��ł���Y�ƕ���́A���̖�9���������Ƃł������B�����Ƃɂ�����G�l���M�[����̔N���I�o�܂������1965�`1973�N��8�N�Ԃ̕��ϐL�ї���11.8���A����1973�`1986�N��13�N�Ԃ̓}�C�i�X1.8���ƂȂ�A�����ɓ]�������A���̌�͂قډ����Ȃ����A�����ƂȂ��Ă���B�������A�����Ƃ̍H�Ɛ��Y�w���iIIP�j������̃G�l���M�[����P�ʂ�1973�N�x��100�Ƃ���ƁA�}1�Ɏ����悤�ɔN���o�邲�ƂɌ����𑱂��A1990�N�ɂ�55.6�ƂȂ������A���̌�̓G�l���M�[�g�p�ʂƓ��l�ɁA�����Ȃ�����̑����ɓ]���Ă���B
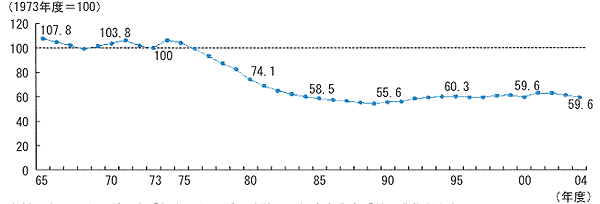 |
| �����F�����G�l���M�[���u�����G�l���M�[���v�v�A�o�ώY�Əȁu�z�H�Ǝw���N��v �i���j1�D���P�ʂ́A�����ƇUP�i�t�����l�E�F�C�g�j1�P�ʓ�����̍ŏI�G�l���M�[����ʂŁA1973�N�x��100�Ƃ����ꍇ�̎w���ł���B �@�@�@2�D�z�H�Ɛ��Y�w���͔��l�̉e�����邽�߁A�̔����i���ቺ���Ă���ꍇ�ɂ́A���Y�ʂ̌����ȏ�ɏ������Ȃ�_�ɗ��ӂ���K�v������B�܂��A���̃O���t�ł͕]������Ă��Ȃ����A�����Ƃł͔p�M������̏ȃG�l�w�͂��s���Ă���B �@�@�@3�D�u�����G�l���M�[���v�v�́A1990�N�x�ȍ~�̐��l�ɂ��ĎZ�o���@���ύX����Ă���B |
�}1�@�����Ƃ̃G�l���M�[�g�p�ʂ̐��� |
| �y�[�W�̃g�b�v�� |
2�D�������ʃK�X�Ƃ��̉e���ɂ���
(1)�n�����g���Ɖ������ʃK�X�̉e��
�@���݁A���ۓI�ɑ傫�ȊS�̓I�ƂȂ��Ă���n�����g���́A��C���ɑ��݂����_���Y�f��^���A���邢�̓t�����Ȃǂ̉������ʃK�X�Z�x�̏㏸�ɋN�����Ă���B�������ʃK�X�́A���z���̃G�l���M�[�ɂ���C���Ő��������ԊO����n���O�ɕ��o�������ɋz�����āA�Ăѕ��˂��Ēn�\�ʂ̕��ϋC���������̈ێ��ɓK�������x�ɕۂ���������B�������A�������ʃK�X�̔Z�x����������ƁA���̓���������ɋ��܂�A���ʂƂ��ĉ������ʂɂ��n���̕��ϋC���̏㏸�������炷�����ƂȂ�B���ꂪ�n�����g���̃��J�j�Y���Ƃ��Ēm���Ă��錻�ۂŁA�n�����g���̑��x�Ƀu���[�L���|����̂́A�������ʃK�X�ł����_���Y�f�A���^���A�t�����Ȃǂ̔r�o�ʂ̍팸�������܂Ŏ����ł��邩�Ɍ������Ă���B�������ʃK�X�́A��x��C���ɔr�o�����ƁA�������̂����ɍ���ł���A�����h���ɂ́A�������ʃK�X�̔r�o��}������ȊO�ɕ��@���Ȃ��B
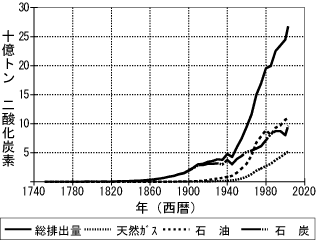 |
�}2�@�������ʃK�X�r�o�ʂ̐��� |
�@�������ʃK�X�̑�C���ւ̔r�o�́A�ߔN�Ɏn�܂������̂ł͂Ȃ��A�Â���18���I�㔼����n�܂����Y�Ɗv���̎���ɂ܂ők��B�Y�Ɗv�����猻��܂ł̑�C���̉������ʃK�X�i��_���Y�f�j�̔r�o�ʂ̐��ڂ�}2�Ɏ��������A�Y�Ɗv�������A1751�N����1850�N�܂ł̓�_���Y�f�r�o�ʂ́A����قǑ������̂ł͂Ȃ��A�S�ĐΒY�̔R�Ăɂ��r�o����A11�`198�S���g���Ő��ڂ����B�����āA35�N���1885�N�ɔr�o�ʂ��\���g����ƂȂ�����́A�}���ȑ����������A��ꎟ���E��풆�͈ꎞ�A���������B����1918�N�ɏI�����邪�A1923�N��3,557�S���g���ƂȂ�����́A���E�o�ϋ��Q�ɂ���_���Y�f�r�o�ʂ͔����ƂȂ�A����E��풼�O��1938�N�ł́A4,187�S���g���ł������B����E����A1946�N�������㕜���̒��ŔR���̎g�p�����債�A�r�o�ʂ�1945�N��4,253�S���g�����ɑ����ɓ]���A���{�Łu���͂���ł͂Ȃ��v�ƌ���ꂽ1956�N�ɂ�7,982�S���g���ƂȂ�A1968�N�ɂ́A�Ζ�����̔r�o�ʂ��ΒY�̔r�o�ʂ����߂ď������B�����āA��ꎟ�Ζ���@�̔�������1973�N�ɂ́A16,999�S���g���ƂȂ�A���̌���N���ŕ���1.97���A7.25�`�|3.11���͈̔͂ő������Ă���B
�@�C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���iIPCC�FIntergovernmental Panel on Climate Change�A�n�����g���̎��Ԕc���Ƃ��̐��x�̍����\���A�e���]���A��̍�����s�����Ƃ�ړI�Ƃ��āA���E�C�ۋ@�ցiWMO�j�ƍ��A���v��iUNEP�j�̋��͂̉���1988�N�ɐݗ����ꂽ���A�g�D�j��2000�N�̕��ɂ��ƁA��_���Y�f�̔r�o�����̂܂܂̏�Ԃő����ƁA2000�N�ɂ͑�C���̔Z�x����370ppm�i0.037���j�A2100�N�ɂ́A1,000ppm�i0.1���j���A�n���̕��ς̒n��C����1990�N����2100�N�܂ł̊Ԃ�1.4�`5.8���̏㏸������Ɨ\�����Ă���B�����āA���̕��ϋC���̏㏸�́A�C���ʂ̏㏸�������炷�ȊO�ɁA���Ԍn�A�H�Ɛ��Y�A�������Ȃǂɂ��[���ȉe���������炷�Ɨ\������Ă���B�Ⴆ�A���Ԍn�ւ̉e���́A�����̏㏸�ɂ�肨����X��ʂ̔����A�Ԃȗт̕��z��̌����̂悤�ȐA���̕ϓ��A�����̕��z�Ǝ�̕ϓ��A�~��ʂ̌����ƍ��W����ւ̍~��n��̈ړ��A���n�̌����ɂ�鎼�n�����̐�����̌����A���݈�ł́A�C���ʂ̏㏸�ɂ�鐅�v�ʐς̑����A�H�Ɛ��Y�ւ̉e���ł́A�������Y�ʂ̌����A�l�ւ̌��N�ʂ̉e���ł́A���ړI�ɂ͏��M��M�g�̑����ɂ��M���ǁA�ԐړI�ɂ̓}�������A�f���O�M�A���i�C���M�E�C���X�Ȃǂ�}��铮���Ȃǂ̐����n��̊g��A�`���a�̑����ȂǁA�n����ɐ�������l��A�����邢�͓����̑�������@�ɂ��炳��鎖�Ԃɑ�������ƍl���Ă����������Ȃ��̓������\������Ă���B
(2)�������ʃK�X�Ɓu���s�c�菑�v
�@�n�����g���̖h�~�ւ̓w�͂��n�܂����̂́A1992�N�ɍ��A�C��ϓ��g�g���iUNFCCC�FUnited Nations Framework Convention on Climate Change�j���̑����ꂽ�̂��ŏ��ł���B������1994�N�ɔ����������A���̏��̖ڕW�ɍ��킹�āA���g���h�~�̋�̓I�s�����������̂��A1997�N�ɋ��s�ŊJ�Â��ꂽUNFCCC��3�����c�œ��c����A�̑����ꂽ�u���s�c�菑�v�ł���B���́u���s�c�菑�v�ɂ́A��i���̉������ʃK�X�r�o�ʂɂ��āA�@�I�S���͂̂��鐔�l���e�����Ƃɐ݂��邱�Ƃ����荞�܂�Ă���B����ɂ��ƁA��i����|�[�����h�A���V�A�A�`�F�R�Ȃǂ̎s��o�ψڍs��41�J���́A�S�̂ő����Ԃ�2008�`2012�N�̊Ԃɓ�_���Y�f�A���^���A��_���f�iN2O�j�A�n�C�h���t���I�J�[�{���iHFCs�j�A�p�[�t���I�J�[�{���iPFCs�j�A�Z�t�b�������iSF6�j�Ȃǂ̉������ʃK�X��1990�N�̔r�o�ʁi�A���AHFCs�APFCs�ASF��1995�N����Ƃ���j���5���ȏ�팸���邱�ƂŁA���ӂ��Ȃ��ꂽ�B�������Ɋe���ɍ팸�ʂ����蓖�Ă��A���{��6���A�č���7���AEU�͑S�̂�8�������炷���ƂɂȂ����B�������A�����P�Ɋe�����Ǝ��ʼn������ʃK�X�̔r�o�ʂ��팸����ɂ͌��E������A���̂��߁A�u���s�c�菑�v�̒��ɁA�r�o������A��i�����m�Ŏ��{�����팸�v���W�F�N�g�œ����팸�ʂ�z�������A��i�����r�㍑�ōs�����r�o�ʃv���W�F�N�g��z���v���W�F�N�g�œ����팸�ʂ�z���ʂ������̍팸�ʂɑg�ݓ����d�g�݂Ȃǂ́g���s���J�j�Y���h�ƌĂ����@�����荞�܂ꂽ�B�܂��A2001�N�ɂ́A�X�ъǗ��ɂ��r�o��_���Y�f�̋z���ʂ̏���l����߂�ꂽ�B
�@����ɂ��A�n�����g���h�~�̂��߂̐��E�̍��X�̖ڕW�Ƌ`������߂��A���̖ڕW�Ɍ������Ď�X�̐���̎��s���e���ɉʂ�����A���{���ڕW��B�����邽�߂ɁA�����̐����s�Ɉڂ���Ă���B
(3)���E�̉������ʃK�X�̔r�o��
�@�n�����g���h�~�̂��߂̊�{�I����܂łɐ��E�e���̍��ӂ̉��Ɏ��s�Ɉڂ���ė��Ă��邪�A���ۂɂ����̑������ʃK�X�̔r�o�팸�ɗL���ɍ�p���Ă��邩�ۂ��͌��������ƁA���炩�łȂ��B���E�̔R������̓�_���Y�f�̔r�o�ʂ�����Ɛ}3�Ɏ����悤�ɁA���߂�2003�N��1990�N�̔�r�ł́A1.14�{�ƂȂ��Ă���B�������A���̓��������ƁA��i���́A2002�N��1990�N�ł́A0.98�{�ł������̂��A���̑��̒��i���┭�W�r�㍑�ł́A�G�l���M�[����̋}���ȑ�������A1.39�{���������Ă���B
�@�\1�ɂ́A��v���̓�_���Y�f�r�o�ʂ̐��ڂ����������A����ɂ��ƁA��v���̔r�o�ʂ�1990�N�����ꎞ�I�ɉ�������N�����������A2003�N�ł̓h�C�c�Ɖp���������A�����Ă���B���̂��Ƃ́A�����Ԃ�2008�`2012�N�̔N���ω������ʃK�X�r�o�ʂ�1990�N�̒l�ȉ��ɂ���Ƃ������ۓI�Ȗ��A�����ɍ���ȁg�h�ł��邩����Ă���B
�@��v����2002�N�̑S�Ẳ������ʃK�X�r�o�ʂ�1990�N�ɔ�r���āA�ǂ̒��x�A�B���ł�������}4�Ɏ��������A����ɂ��ƁA���E�ő�̔r�o�ʍ��ł���č��̓v���X13.1���A���l�ɃJ�i�_��20.1���A�X�y�C����40.5���ȂǁA���ɂ��������������́A�h�C�c��18.8���A���V�A��38.5���A�C�M���X��14.5���ł���A���̒��Łu���s�c�菑�v�̍팸�̒l����������̂́A��v���̒��ł̓C�M���X�݂̂ł������B
�i���F�č��́A�u���s�c�菑�v���y���Ă��Ȃ��B�j
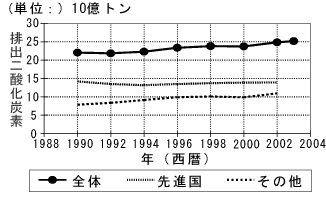 |
�}3�@���E�̔R������̔r�o��_���Y�f�̐���
|
�\1�@��v���̔R������̔r�o��_���Y�f�̐��� |
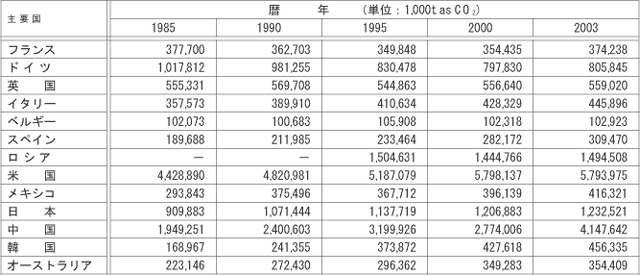 |
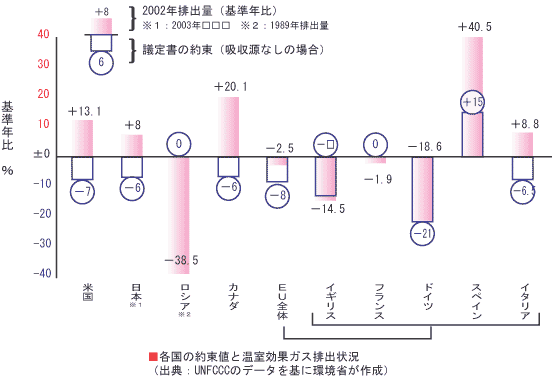 |
�}4�@�e���̖l�Ɣr�o�� |
| �y�[�W�̃g�b�v�� |
3�D���{�ɂ����鉷�g����
(1)���{�ɂ����鉷�����ʃK�X�̔r�o��
�@�u���s�c�菑�v�ɂ����āA1990�N�̓��{�̉������ʃK�X�̑��r�o�ʂ́A1,261,442��g���i1990�N����N�Ƃ����_���Y�f��1,144,130��g���A�����^����33,382��g���A��N2O��32,744��g���A1995�N����N�Ƃ���HFCs�Ȃǂ̃t������51,186��g���̍��v�j�Ƃ���A�������Ƃ��đ����Ԃł�5�N�Ԃ̊����ʂ����߂�ꂽ�B���̌��ʁA�����Ԃ̊����ʂ́A��_���Y�f���Z�ŁA���̊�̒l��6������5,928,770��g���ł���A2008�`2012�N�̊Ԃ�5�N�ԂŁA���̒l��B�����邱�Ƃ��ڕW�ƂȂ��Ă���i����́A�P�N�x�������Ԃ�5,928,770��g����1/5���I�[�o�[���Ă��A5�N�ԑS�̂ł��̐��l��B���ł���悢���ƂɂȂ�j�B
�@���̖ڕW��B�����邽�߂ɁA�����ɂ������Ƃ��āA���{��2002�N3���Ɂu�n�����g�������i��j�v�����肵�A�g���ƌo�ς̗����h�A�g�X�e�b�v�E�o�C�E�X�e�b�v�̃A�v���[�`�h�A�g�e�E�E�e�w����̂ƂȂ������g�݂̐��i�h�A�g�n�����g����̍��ۓI�A�g�̊m�ہh���x�[�X�Ƃ��āA�ȃG�l�@�̉����A�G�l���M�[���v�ʂ̑�A���q�͔��d�̐��i�A�V�G�l���M�[�̓������i�A�R���]���Ȃǂ̐�������s���Ă���B�܂��A���Ԃɂ����Ă��Y�ƊE�̎���I�Ȕr�o��_���Y�f�̍팸�w�͂��Вc�@�l���{�o�ϒc�̘A����𒆐S�Ƃ����u������s���v��v�g�t�H���[�A�b�v�h�Ƃ����`�Ō����s�����Ƃɂ��A�n�����g���������~�߂邽�߂̓w�͂��s���Ă���B
�@��̓I�ȍ팸�ڕW�Ƃ��Đ��{�́A�\2�Ɏ����悤�ɉ������ʃK�X�̂����A��9�������߂�G�l���M�[���p�ɔ�����_���Y�f�̔r�o�ʂ�1990�N���0.6�����Ƃ��A�������ʃK�X�̔r�o�ʂ�S�̂�0.5���팸���A�X�тȂǂ̓�_���Y�f�̋z�����̐����ɂ��3.9���̍팸���s���A����Ɏc���1.6���͔r�o������Ȃǂ́g���s���J�j�Y���h�𗘗p���ĒB�����邱�Ƃ�ڎw���Ă���B�Ƃ��낪���ۂ́A2004�N�̉������ʃK�X�̔r�o�ʂ������1,285.8�S���g���ł���A1990�N�x�ɔ�r����11.97�����ƂȂ��Ă���A��N�Ɣ�r���Ă�7.44�����ł���B�������ʃK�X�̒��ōő�̔r�o�ʂ��߂��_���Y�f�̑��r�o�ʂɐ�߂銄���́A1995�N�ł�91.4���ł��������A���̌�A���X�ɏ㏸���A94.9���ƂȂ��Ă���B���̏�A�r�o���ʂ����X�ɏ㏸���A1990�N�x��2004�N�x�ł́A12.36�����ƂȂ��Ă���B
�@��_���Y�f�̔r�o�ʂ̓��������ƁA�R������̓�_���Y�f�r�o�ʂ́A���r�o�ʂ�93.04���ł���A�H�ƃv���Z�X����̔䗦��4.14���ƂȂ��Ă���B
| �\2�@�������ʃK�X�̗}���E�z���ʂ̖ڕW |
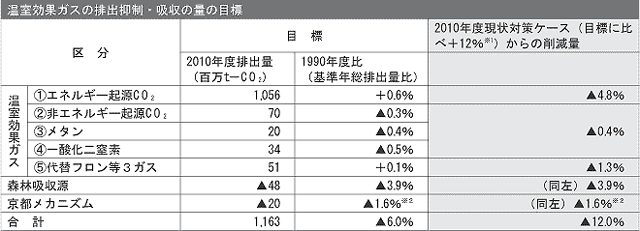 |
| ��1�F2002�N�x���сi�{13.6���j����o�ϐ������ɂ�鑝�A���s��̌p���ɂ��팸��������2010�N������ ��2�F�팸�ڕW�i��6���j�ƍ�����i�r�o�팸�A�z������j�̍��� |
(2)�r�o��_���Y�f�ƎY�ƕ���Ƃ̊W
�@�R���̏���ʂƓ��l�ɁA���ΔR���̔R�Ăɂ���_���Y�f�̔r�o�ʂ́A1990�N�ɂ́A�������ʃK�X��92.57�����߁A���̗ʂ�1,059,076��g���ŁA���̓��A�G�l���M�[�]���E�Y�ƕ��傪706,741��g���ƑS�ʂ�66.73���ł��������A���X�ɁA�����p�ł���ƒ�E�Ɩ����̑����傪���̊����𑝂��A2004�N�ł̓G�l���M�[�]���E�Y�ƕ��傪770,297��g���ŁA�S�́i1,196,376��g���j��64.39���ƂȂ��Ă���B�����āA�G�l���M�[�]���E�Y�ƕ���́A���̕��傾���̑������������8.99�����ƁA�ƒ�E�Ɩ����̑�����i21.64�����j�̂������12.65��������Ă���B�������A�r�o�ʂ̕ω����e����ł̕ω��ƔN���ʂ̕ω��𑍍����Č���ƁA�}5�Ɏ������悤�ɁA1990�N�̑��r�o�ʂ�100�Ƃ���ƁA�G�l���M�[�]���E�Y�ƕ����2004�N��1990�N��7.65������72.73���ł���A�ƒ�E�Ɩ����̑����傪2.73�����ŁA16.11���ł������B���̂��Ƃ���A�G�l���M�[�]���E�Y�ƕ���̓�_���Y�f�̔r�o�ʂւ̊�^�͔N���o�邲�Ƃɍ����Ȃ��Ă��Ă���̂�����ł���B
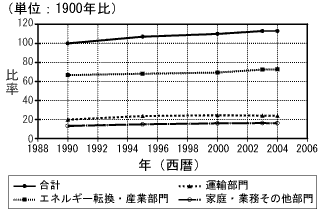 |
�}5�@�R������̓�_���Y�f�r�o�ʂ̕���ʁE�N���ʐ��� |
�@����A�u������s���v��v�ɎQ�����Ă���G�l���M�[�]���E�Y�ƕ����35�Ǝ�ƊE�ɂ������_���Y�f�r�o�ʂ̏́A2005�N�x�ɂ��Č���ƁA1990�N�x��Ń}�C�i�X0.6���ƂȂ��Ă���B���̂��Ƃ́A�u������s���v��v�̔r�o�ʂɊւ��Ă̗v�����͂ŁA�i�C�ɔ������Y�����̊���������ь��q�͔��d���̒�~�ɂ���_���Y�f�r�o�̑��������A�Q��35�ƊE�̓�_���Y�f�팸�ւ̓w�͂������Ă������Ƃɂ��Ƃ��Ă���B���Ȃ킿�A���̐��Y�����̕ω����v���X10.1���A���̓�_���Y�f�r�o�W���̕ω����v���X0.2���ł������̂ɑ��A���Y����������r�o�ʂ̕ω����}�C�i�X10.9���ł��������Ƃɂ��A1990�N�x��}�C�i�X0.6���������ł����̂ł���Ƃ��Ă���B�������A����̓�_���Y�f�̔r�o�ʂ̏��猩��ƁA�Y�ƊE�Ƃ��Ă͍���A���{����c�̂��狞�s�c�菑�̑����Ԃ̊����ʂ̒B���̂��߂ɁA�����Ƃ𒆐S�Ƃ��āA��_���Y�f�r�o�ʂ̂���Ȃ�팸�ɓw�͂���悤���߂��邱�Ƃ��\�������B
| �y�[�W�̃g�b�v�� |
4�D�������H��ɂ�����ȃG�l���Ɣr�o��_���Y�f
(1)�ȃG�l���ɂ���
�@1979�N�����̐������H��ɂ�����G�l���M�[�̎g�p�́A�}6�Ɏ����悤�Ɍ��P�ʃG�l���M�[�g�p�ʁi�n���ʓ�����̃G�l���M�[�g�p�ʁj�Ō���ƁA���ΔR����131.1���b�g��/�g��-�������iL/t-R�j�ł���A�d�͂�73.7�L�����b�g��/�g��-�������iKWh/t-R�j�ŁA���G�l���M�[�g�p�ʂ́A�������Z��148.5L/t-R�ł������B�����āA�������H��ɂ�����G�l���M�[�̎g�p�`�Ԃ́A���d�Ǝ��Ɣ��d�ɂ�苟�������d�͂Ə��C�ł���A���d�������A����������ΔR�����{�C���[�ŔR�Ă����ē�������C�����Ƃ��āA�Z�k������ɗ��p����A�d�͉͂��S�@��|���v�Ȃǂ̓��͌��ɑ����p�����Ă���B�G�l���M�[�̐������H��ł̕���ʂ̎g�p���Ԃ�����ƁA�\3�Ɏ����悤�ɁA1979�`1984�N�����̉��ΔR���œ���ꂽ���C�́A�Z�k�E��������őS�̂�65�`68�����߁A���ɑ����̂́A15�`16���̗n���E����ł������B�܂��A1979�`1984�N�����̌��P�ʎg�p�ʂ�����ƁA�Z�k�E���������72.5�`90.1L/t-R�A�ŁA�n���E�����15.8�`21.7L/t-R�ł������B����A1979�`1984�N�����̓d�͎g�p�ʂ͐��傪23���A���݂H����18�`20���A���P�ʎg�p�ʂł͐��傪24�`25KWh/t-R�A���݂H����18.3�`21.3KWh/t-R�ł������B
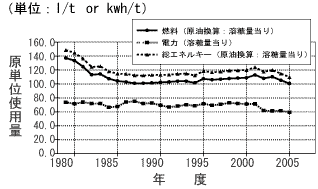 |
�}6�@�N���ʃG�l���L�[�g�p�ʁi���P�ʁj�̐���
|
| �\3�@�N���ʂ̕���ʃG�l���M�[�g�p�䗦�̎��� |
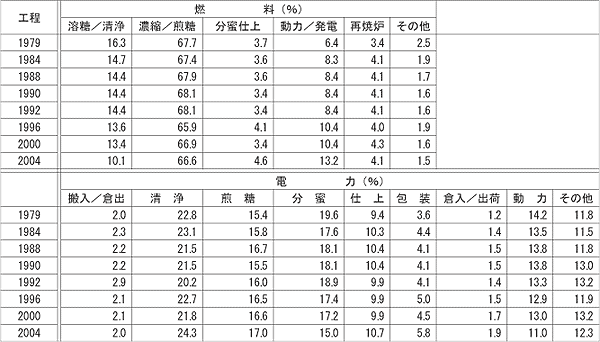 |
�@�Ƃ��낪�A��ꎟ�Ζ���@�A��Ζ���@�ɑ������A��r�I���P�ʃG�l���M�[�g�p�ʂ̑����������H��ł́A�R�����i�̍������琻���R�X�g���㏸���A���i���i�ւ̓]�ł��\���ɂł��Ȃ���Ԃɒu����Ă������߁A�ȃG�l�Z�p�̊J�����d�v�ȉۑ�ƂȂ����B�O�q�����悤�ɁA�G�l���M�[���������������ɂ́A�Z�k�E��������ł̏��C�̎g�p�ʂ����炷���ƁA���݂H���ł̓d�͎g�p�̕������ƌ��������s�����Ƃ��K�v�ł������B���̂��߁A�����ƊE�������ďȃG�l���ɑΉ����邱�ƂɂȂ�A1979�N12���̐����H�Ɖ�Z�p�ψ���ŁA�ȃG�l�^�����ʂ̊J���ƌ����ʂ̔p�M����Ɏ��g�ނ��Ƃ����肳�ꂽ�B��1980�N9���ɂ́A���c�@�l�H�i�Y�ƃZ���^�[���⏕������t���邱�Ƃ����߂����Ƃɔ����A�����͂�@�t�������ʂ̊J���ƌ����ʂ̔p�M����V�X�e���̊J�����X�^�[�g�����B����A�e��Ƃ̋Z�p�҂����͋����āA�ȃG�l���̋Z�p�J����ȃG�l�^�̂��߂̐ݔ��̓����A�ݔ��̍X�V������Ȃǂ��s���A�}6�̂悤�ɔN��ǂ����ɃG�l���M�[�̎g�p�ʂ́A���������B
�@�������H�ꂪ����܂łɓ�����X�V������ȏȃG�l���ݔ��ɂ��ĕ\4�Ɏ��������A1985�N�܂łɂقƂ�ǂ̍H��ł́A�����͂�@�t�������ʂ̓����A���ȏ����^�Z�k�ʂ̐ݒu�A�����ʂ̎������Ȃǂ��s���A���̂��߁A�G�l���M�[�g�p�ʂ�1985�N�ɂ�1979�N�ɔ�r���āA40.28������59.72���܂Ō������Ă��Ă���B���̌�A���̃y�[�X�͓݂��Ă͂��邪�A���������Ď��ȏ����^�Z�k�ʂ̐ݒu�A����ɂ̓{�C���[�p�̃G�R�m�}�C�U�[�̐ݒu�A�����@�ȂǂɎg�p����郂�[�^�[�̃C���o�[�^�[���Ȃǂ��s���A�G�l���M�[�g�p�ʂ͏��X�Ɍ������Ă��Ă���B���̌��ʁA���߂�2005�N�ɂ́A���G�l���M�[�g�p�ʂ�109.8L/t-R�ł���A�R���̎g�p�ʂ�100.6L/t-R�A�d�͂�59.3KWh/t-R�ł������B1979�N�Ƃ��̒l���r����ƁA���G�l���M�[�g�p�ʂł�26.06�����A�R���ł�26.62�����A�d�͂ł�19.54�����ƂȂ�A20�N�Ԃő��G�l���M�[�g�p�ʂ�3/4�ƂȂ������ƂɂȂ�B
�@�������H��́A����20�N�Ԃ̊Ԃɍl�����邠��Ƃ�����ȃG�l���Z�p�̂قƂ�ǂ����s�Ɉڂ������߁A����ȏ�̏ȃG�l���́A���݂̐����H������ՂƂ������A���ɍ���ȏɂ���B����́A�������H��ɂ����邳��Ȃ�G�l���M�[����̍팸�ɂ́A�����Z�p�̃u���[�N�X���[���K�v�ł��낤�B
| �\4�@��ȏȃG�l�ݔ��̍X�V�y�ѓ����̌o�� |
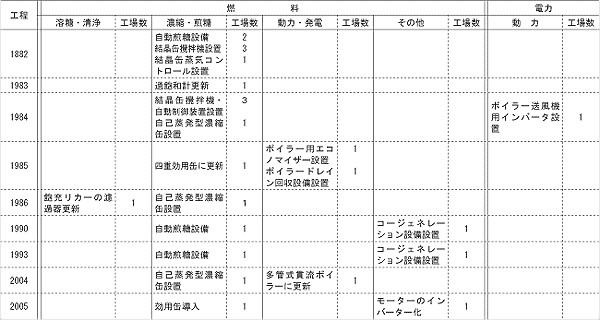 |
(2)�������H��ɂ�����r�o��_���Y�f�̌���
�@�ŏ��A�ȃG�l���Z�p�̊J���́A���A��_���Y�f�r�o�ʂ̍팸�ɂȂ���ƋL�����悤�ɁA20�N�Ԃ̏ȃG�l���̓w�͂́A�������H��ɂ������_���Y�f�r�o�ʂ̍팸�ɑ傫�ȍv�������邱�ƂɂȂ����B�������ƊE�́A1997�N����n�܂������{�o�c�A�́u������s���v��v�ɏ��N�x����Q�����A���N�A�������H��ɂ������_���Y�f�r�o�ʂ����j�^�[���A2008�N�x����n�܂�����Ԃ̊����ʂ�B���ł���悤�ɁA�w�߂Ă���B����ɂ��ƁA�������H��Ŕr�o�����_���Y�f�́A�}7�Ɏ������悤�ɁA2005�N��418��g���ŁA1990�N�x���72.08���ł���A�������H��̔r�o���ʂ́A���݂̂Ƃ���A�����Ԃ̊����ʂ�B���ł��錩���݂ł���B�������A���́A���̓�_���Y�f���r�o�ʂ̌������n���ʂ̌����ɂ��e���ł���ƍl�����A�Ăїn���ʂ����������ꍇ�A�Ăєr�o�ʂ̑�������������邱�Ƃł���B
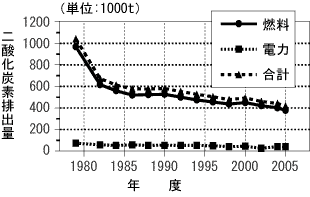 |
�}7�@�������H�ꂩ��̓�_���Y�f�̔r�o�ʂ̐���
|
�@���̂��߁A�������ƊE�Ƃ��ẮA�ȃG�l�����u��ݔ����邢�͐V���Ȑ����@�̋Z�p�J�����K�v�ɂȂ��Ă���B�����ŁA���܂łɍs��ꂽ�������H��ɂ�����Z�p�̓����E���P�̌��ʂ������邱�Ƃ��d�v�ł��邪�A�������ƊE���G�l���M�[�g�p�������n�߂�1979�N�ȗ��A�n���ʂ��N�X����������A��������A���̉e���ŃG�l���M�[�g�p�ʂ��������Ă���ɂ��邽�߂ɁA����t���܂Ƃ��B�������A�ȃG�l���Z�p�̓����E���P�̌��ʂ������邱�Ƃ́A����̏ȃG�l���Z�p�̋Z�p�̊J���ɗL�Ӌ`�Ȃ��ƂȂ̂ŁA�����āA���P�ʓ�����̓�_���Y�f�r�o�ʂ����߁A���̌��P�ʓ�_���Y�f�r�o�ʂ̌�������A�������H��ł̏ȃG�l���Z�p�̓����E���P�̌��ʂ������邱�Ƃɂ����B����ɂ��ƁA�}8�̂悤�ɂȂ�B�}�������悤��1979�N�x�́A��ꎟ�Ζ���@���u���������ŁA�ȃG�l���Z�p�̓����E���P�Ɍ������]���_�̔N�ł���B���̔N�̌��P�ʓ�_���Y�f�r�o�ʂ������0.391�g��/�g��-�������it/t-R�j�ŁA�H��̏ȃG�l����͂قƂ�Ǎs���Ă��炸�A�H����͔r�M�̂��߂ɁA�������C�̂悤�ȏ�Ԃł������B�Ƃ��낪���̊�@�ɂ��R�����i�̍����̂��߁A�e�ЂƂ��������H��̏ȃG�l����i�߂���Ȃ��Ȃ�A1985�N�܂łɂقƂ�ǂ̍H��ʼn��炩�̏ȃG�l���ݔ��̓�����ȃG�l���̂��߂̐������H���̉��P���s��ꂽ�B���̌��ʁA1986�N�x�ɂ́A�G�l���M�[����ʂ����I�Ɍ������A���P�ʓ�_���Y�f�r�o�ʂ�1979�N�x�ɔ��28.1������0.281t/t-R�ƂȂ����B�������A�ȃG�l���ݔ��̓�����ȃG�l���̂��߂̐������H���̉��P����i������ƁA���P�ʓ�_���Y�f�r�o�ʂ́A�قƂ�Ǖς��Ȃ��Ȃ����B
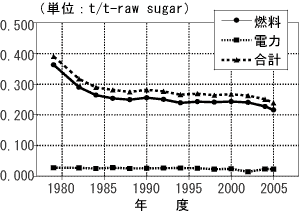 |
�}8�@�������H��ɂ������_���Y�f�r�o�ʁi���P�ʁj�̐���
|
�@����A�ȃG�l���ƕ���ŁA�������H�ꂪ���g�̂́A��C������̈�Ƃ��āAC�AB�d������A�d���ɁA�d������s�s�K�X�i�V�R�K�X�j�ւ̔R���]���ł������B���ɁA�d������s�s�K�X�ւ̓]���������ŁA�}9�̂悤��1990�N���܂ł͉��ΔR���̒��ŏd����65�����x�A�s�s�K�X��30�����x�ł������̂��A���ꂪ1992�N�x�ɂ́A�d����59�����x�A�s�s�K�X����37���ƁA�s�s�K�X�̊��������X�ɑ��������B�����āA���̌X���͂��̌���������A���̔R���]���́A��_���Y�f�r�o�ʂ̍팸�ɂ͌��ʓI�ł������B
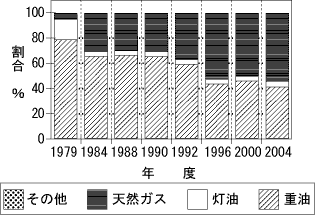 |
�}9�@�R����̕ϊ��̔N���I����
|
�@�R���]���Ɠ�_���Y�f�r�o�ʂ̒ቺ�Ƃ̊W�́A�R����ɂ�蔭�M�ʓ�����̓�_���Y�f�̔r�o�ʂ��قȂ邱�ƂŁA�R�����ς��邱�Ƃœ�_���Y�f�̔r�o�ʂ����炷���Ƃ��ł��邽�߂ł���B���M�ʓ�����̓s�s�K�X�̓�_���Y�f�r�o�ʂ�2.141�g��/107�L���J�����[�it/107kcal�j�ł��邪�AA�d����2.901t/107kcal�AB�d����2.951t/107kcal�AC�d����2.999t/107kcal�ł���̂ŁA�������M�ʂł́A�d�������s�s�K�X�̕�����_���Y�f�r�o�ʂ̍팸�Ɍ��ʂ�����B���̂��߁A�d������s�s�K�X�ւ̔R���]���������ɂȂ�1992�N�x�ȍ~�́A1992�N�x�̓�_���Y�f�r�o��0.277t/t-R��1998�N�x��0.267t/t-R�Ə��X�ɒቺ���邱�ƂɂȂ�B�������A�ꎞ�I�ɁA2000�`2001�N�x�ɂ����ē�_���Y�f�r�o�ʂ��㏸���邪�A���̌����́A�������H��̏W�ɂ�鍇�����̈ꎞ�I�ȉe���Ǝ��̂�g���u���ɂ�錴�q�͔��d���̒�~�ɂ��e���ł���B2000�N�̓�_���Y�f�r�o�ʂ�0.276t/t-R�ŁA�d�͂����0.024t/t-R�ł��邪�A����A���q�͔��d���̒�~�����Ȃ��A���d�ɂ������_���Y�f�̔r�o�ʂ����Ȃ�����1998�N�x�͓�_���Y�f�̔r�o�ʂ�0.264t/t-R�ŁA�d�͂����0.023t/t-R�ł������B�]���āA���G�l���M�[�g�p�ʂɑ���d�͎g�p�ʂ̊�����1998�N�x��9.412���A2000�N�x��9.182���ŁA�d�͎g�p�ʂ�1998�N�x�̕���0.23���قǏ����Ă���̂ɂ�����炸�A��_���Y�f�̑��r�o�ʂɑ���d�͂���̔r�o�ʂ̊�����1998�N�x��8.712���ł������̂ɑ��āA2000�N�x��8.989����2000�N�x��0.277���قǏ����Ă���B���̂��Ƃ́A2000�N�x�����q�͔��d���̒�~���Ԃ̒��������~�ӏ������������Ƃɂ��A�Η͔��d���̉ғ������オ�������߁A�P�ʓd�͓�����̓�_���Y�f�̔r�o�ʂ������������Ƃ��Ӗ����A����ɂ��A�������H��̓�_���Y�f�̔r�o�ʂ��ꎞ�I�ɁA�������������Ƃ����炩�ƂȂ����B
| �y�[�W�̃g�b�v�� |
������
�@�������H�ꂩ��̔r�o��_���Y�f�́A�N���ƂɌ������Ă��邪�A���̌����͗n���ʂ̌����ɂ����ʂ����ɑ傫���B�����ʼne����^�����̂��A1985�N�܂ł͏ȃG�l���ݔ��̓�������P�Ȃǂ̌��ʂɂ����̂ł���A�����͏d������V�R�K�X�ւ̔R����̓]���ł������B�������A2004�N�x�ɂ́A�������H��Ŏg�p�����R����54.2�����V�R�K�X�ł���A����ȏ�̓V�R�K�X�ւ̔R���]���͎�����A����ł���B���̂��߁A���܂ł̂悤�ɓ�_���Y�f�r�o�ʂ����炷���Ƃ��s�\�ɂȂ邱�Ƃ��\�z�����B�]���āA�������H��́A��_���Y�f�r�o�ʂ̍팸�̂��߂ɁA����Ȃ�ȃG�l���Z�p�̊J���ƏȃG�l�����V�X�e���̋Z�p�J�����K�v�ƂȂ��Ă��Ă���B
| �y�[�W�̃g�b�v�� |
�Q�l����
�i1�j�S�Ȏ��T�uWikipedia�v
�i2�j�o�ώY�ƏȁF���{�̃G�l���M�[2006
�i3�j�����G�l���M�[���F�G�l���M�[����2006
�i4�j�����G�l���M�[���F���{�̃G�l���M�[����
�i5�jCDLAC, Oak Ridge National Laboratory : Grobal, Regional, and National Fossil Fuel CO2 Emissions
�i6�j���ȁFSTOP THE ���g�� 2005 ����3��
�i7�jCDLAC, Oak Ridge National Laboratory : Kyoto-Related Fossil-fuel CO2 Emission Totals�i2006/12�j
�i8�j�S���n�����g���h�~�������i�Z���^�[�F���E�̓�_���Y�f�r�o�ʁ|���ʔr�o�����|�i2004�N�j
�i9�jCDLAC, Oak Ridge National Laboratory : National Fossil-fuel CO2 Emissions�i2006/12�j
�i10�j�Ɨ��s���@�l �������������n���������Z���^�[�F���{���������ʃK�X�C���x���g�����i2000/6�j
�i11�j���ȁF�u�C��ϓ��Ɋւ��鍑�ۘA���g�g���̋��s�c�菑��7��4�v�Ɋ�Â��g���s�c�菑��3��7�y��8�ɏ����������{���̊����ʂɊւ�����h�i���{��/2006/8�j
�i12�j���{�o�ϒc�̘A����F���g����@������s���v��2006�N�x�t�H���[�A�b�v���ʁ@�T�v�Łq2005�N�x���сr�i2006/12�j
�i13�j�O�䐻���F������20�������G�l���M�[, �M�Ǘ��ƌ��Q�i�G���j, Vol. 30. No. 2,�i1978�j
�i14�j�����H�Ɖ�F�Z�p�ψ���c���^
�i15�j�c���B�瑼�F���a�@�t�����ʂɂ�����ȃG�l���M�[�����@�̌����C�����Z�p�����,Vol.32�i1981�j
�i16�j�ꌳ���P�F�^�r�M������u ���̓����Ǝ��сC�����Z�p�����, Vol. 32�i1981�j
�i17�j�����H�Ɖ�Z�p�������F�G�l���M�[�W�����i1979�`2006�j
| �y�[�W�̃g�b�v�� |










