

ホーム > 砂糖 > 視点 > 社会 > 近世の砂糖を考える
最終更新日:2010年3月6日
 |
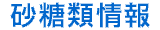 |
 |
ポルトガル人が種子島に上陸したいわゆる南蛮人の渡来とともに、カステラ、コンペイト等の南蛮菓子が日本にもたらされました。江戸時代に鎖国令が敷かれたとき、貿易の窓口は出島に限られており、当時輸入品であった砂糖はこの地から普及していったようです。
かつて長崎市立博物館館長等を務められ、長崎の食文化に詳しい越中哲也氏に執筆していただきました。
長崎純心大学 長崎学研究所主任 越中 哲也
| 1.ポルトガル貿易と長崎 | 2.南蛮料理 (菓子) と砂糖 | |
| 3.唐船来航と砂糖 | 4.江戸幕府と砂糖 | |
| 5.長崎貿易と砂糖 | おわりに |
ポルトガル船の入港は1543年のポルトガル人の種子島上陸により始まっている。続いてF・ザビエルがキリスト教布教のため1549年来航して以来、急速にヨーロッパの文化がわが国に伝えられているが、その中の1つに食の文化があった。
ザビエルはイエズス会に所属していたのでイエズス会関係の文書を見ると多くのことが記されている。その中より1、2の例を拾うと次のものが読まれる。
○1577年の P・フロイス (Padre Luis Frois) の書簡、日本人がよろこぶ進物用品は砂時計、眼鏡、ラシャのカッパ、……瓶入のコンペイト、上等の砂糖漬、蜂蜜、壷入の砂糖菓子、酢漬の唐辛子
また、P・フロイスが記した「日本人の食事と飲食の仕方」を読むと次のように記している。
○吾れ吾れは、甘い味を好むが日本人は塩辛い味を喜ぶ。
○吾れ吾れは、砂糖や卵やシナモンをつかって麺類を食べるが、日本人は芥子や唐辛子をつかって食べる。
○吾れ吾れは、牛を食べるが日本人は牛を食べないで犬を食べる。
○吾れ吾れは、砂糖や卵やシナモンをつかって麺類を食べるが、日本人は芥子や唐辛子をつかって食べる。
○吾れ吾れは、牛を食べるが日本人は牛を食べないで犬を食べる。
それは一般の日本人には砂糖は高価であり、広く普及していなかったからである。16世紀末の砂糖貿易のことについてセビリヤの文書館の貿易資料の中に、次のものがあると報告されていて、いかに砂糖は当時高価なものであったかが分かる。
○白砂糖は約6乃至7,000斤 (1斤は約600g) 日本に輸出されている。その仕入値は100斤につき15匁であるが、日本では、それを30匁乃至40匁で賣ることができた。然し其の需要は少なく日本人は黒砂糖を好んだ。黒砂糖は仕入値は100斤につき4、5匁であるのに40乃至60匁に賣れた (岩生成一著、江戸時代の砂糖貿易)。
日本人は最初のうちは黒砂糖を賞味していたが、17世紀に入ると白砂糖の輸入が急速に伸びている。
長崎の港が、わが国における唯一のポルトガル船の入港する場所として開港されたのは1571(元亀2)年のことであり、この港町はキリスト教信者のみの町であり、信者以外の者は貿易商であっても住むことはできなかった。
長崎の港が、わが国における唯一のポルトガル船の入港する場所として開港されたのは1571(元亀2)年のことであり、この港町はキリスト教信者のみの町であり、信者以外の者は貿易商であっても住むことはできなかった。
 長崎港図(蘭唐船入港) |
 オランダ人貿易図 |
長崎の町での神父たちの生活は「まったくヨーロッパ風であり、このような豊かな食事のできる処は他にみたことがない」(1614年メスキータ神父の書簡) と記している。その書簡の中より砂糖菓子の部分を引くと次のように記してある。
○巡察師ヴィレイラ神父は自分好みの砂糖煮の果物・パイ・ねじりパン及び大好物の果物を注文します……梨の時期には梨に穴をあけて其処に砂糖をつめ釜でやいたものを神父はデーザートにします。
この砂糖料理や菓子は間もなく全国にひろめられ、1603年、長崎イエズス会で編纂された Vocabvlario da Lingoa de Japom (日葡辞書) によると砂糖関係のものが集められている。
| Am Mochi | 豆をつぶしたものに Jagra を加えた米の餅 注)Jagra:黒砂糖。インド及びアフリカで椰子、甘蔗から製する粗糖 |
||
| Sato Mangiu | お湯でむした或る種の小さなパンで黒砂糖を入れて作った物 | ||
| Sato Mochi | 米で作った円い菓子 (Bollos) に白砂糖を入れて作った。 | ||
| Sato Uri | 砂糖でたいた瓜 | ||
| Sato Yocan | 豆と砂糖で作る甘い板菓子 | ||
| Cho-can | 豆と砂糖で作る甘い菓子 | ||
| An | 餅や饅頭の中の詰め物 | ||
| Amegata | 麦その他の物で作り、かたまりにした糖蜜 | ||
| Xiruame | 非常にやわらかな一種の飴 | ||
| Ame qimaqi | 糯米を葉に包み煮た甘い物 | ||
| Ame | 日本で麦その他のもので作る。 | ||
| (土井忠生・森田 武・長岡 実 編訳) | |||
1615年以来平戸に来航したイギリス人が残した「イギリス商館日記」(東京大学出版) にも砂糖関係資料が見いだせる。日記には長崎より砂糖漬の菓子が土産として贈られたことが記してある。
○1615年10月1日 午后私の船が長崎から帰ってきた。長崎のジョルジュと彼の妻から2壷の糖菓と糖菓1箱、梨1篭、無花果1篭。中国の船長にも糖菓の入った小箱を1つ持ってきた。
○1615年11月15日 私はトメ殿より course sugar (粗製の砂糖) 6ピコル95カティーを1ピコル当り20匁として126匁を支拂う。
○1616年 長崎から平戸に来られたスキアモン殿が私に金平糖と輕焼のビスケットを土産として持ってきた。
○1615年11月15日 私はトメ殿より course sugar (粗製の砂糖) 6ピコル95カティーを1ピコル当り20匁として126匁を支拂う。
○1616年 長崎から平戸に来られたスキアモン殿が私に金平糖と輕焼のビスケットを土産として持ってきた。
1618年1月6日の日記には現在イギリス商館に砂糖がないと次のように記してある。
○長崎の J・ドゥロンスに手紙を書いた。当地 (平戸) には砂糖がもう手に入らないと言った。
その返事は1月13日と1月22日に届いている。そして長崎の中国商人季旦からも砂糖菓子が贈られてきた。
○2人の中国人より糖でつくられた日本人が Yebygod (エビガネ−伊勢海老のこと) とよぶ菓子が贈られた。
この伊勢海老や鯛の砂糖菓子は有平細工とよばれ「長崎くんち」などの時、お祝いの品として長崎老舗の菓子屋松翁軒などに依頼し作ってもらっている。有平というのはポルトガル alfeloa (ポルトガルの飴菓子) を語源とし長崎砂糖菓子の代表的なもので中国菓子製法の影響も受け各種の花、菓物、柿・筍・蓮根など各種のものが客の注文により作られ、江戸時代の中期、砂糖が全国に普及するにつれ全国にその製法は伝えられている。「守貞漫稿」には次のように記してある。
○有平は諸国諸所にて製(こしら)え、白或は紅黄萌木等を加へ、種々の形を模造する。……専ら手造りにするも、近年は鎔製にするものあり、白砂糖を練り、鎔形を以て焼き、而後ちに筆刷毛などにて彩を施し鯛・野菜など其他を造る。真物の如し、号(なず)けて金花糖という。嘉永に亘り、江戸に至り製す。
長崎初期の洋学者西川如見 (1648〜1724) の著書の中に「長崎夜話草」というのがある。その中に土産物の章があり、その中に「蛮人 (ポルトガル人) 長崎にて教えて造り初めし物」があると記し、次の南蛮菓子の名をあげている。
○南蛮菓子の色々
ハルテ、ケジャド、カステラボウル、花ボウル、コンペイト、アルヘイ、タアゴソウメン、ビスコウト、パン其外猶有べし。
○ハルテの語源はポルトガル語の Farte で、砂糖アーモンドを材料として造るとある。
○ケジャトの語源はポルトガル語の gueijada でチーズケーキにあたると説明してある。
○カステラは通常 Castella という国名より伝来した菓子であるとしている。
ハルテ、ケジャド、カステラボウル、花ボウル、コンペイト、アルヘイ、タアゴソウメン、ビスコウト、パン其外猶有べし。
○ハルテの語源はポルトガル語の Farte で、砂糖アーモンドを材料として造るとある。
○ケジャトの語源はポルトガル語の gueijada でチーズケーキにあたると説明してある。
○カステラは通常 Castella という国名より伝来した菓子であるとしている。
その製法については正徳2(1712)年に寺島良安が記した「和漢三才図会」百五巻には次のようにその製法を説明している。
○清き小麦粉1升、白砂糖2斤、を玉子8個の肉汁でこねまぜ、銅鍋に入れ、炭火で焼いて黄色にする。竹針で穴を作って火気をよく中まで通らせる。取りだして切って食べる。最上級のものなり
明治時代以後、現代のカステラには、上述の3つの材料の他に水飴を加えて作られているが、これは明治時代、長崎に伝えられた中国の菓子、鶏蛋●(チィタンコ) の影響による。水飴を加えることによって菓子の乾燥がおくれ風味を増すからであるという。
コンペイトはポルトガル語の conpites である。1569年1月 P・フロイスが織田信長に初めて謁見したときの献上品の中にコンペイトウを献上したことは有名である。昔は長崎名物のお菓子の1つであった。コンペイトウは「金餅糖」、「金平糖」と書き、出世を祝う進物の1つであったと近松門左衛門の「大職冠」に記してある程めずらしいものであった。
タマゴそうめんはポルトガル語の Fios de Ovos という菓子を和訳したものである。Fios は糸であり、Ovos は玉子のことである。その故に長崎で「タマゴそうめん」と訳し長崎名物の1つであったが、現在その製法は福岡に伝えられ「鶏卵素麺」の名で全国に喧伝されている。その製法は「玉子の赤味を去り、布にてこし、砂糖とねり、其の上に小麦粉をたらしかけ、造るなり」と記してある。
当時の料理菓子のことを記したものとしては、東北大学狩野文庫に収蔵されている「和蘭陀菓子製法」は有名である。
コンペイトはポルトガル語の conpites である。1569年1月 P・フロイスが織田信長に初めて謁見したときの献上品の中にコンペイトウを献上したことは有名である。昔は長崎名物のお菓子の1つであった。コンペイトウは「金餅糖」、「金平糖」と書き、出世を祝う進物の1つであったと近松門左衛門の「大職冠」に記してある程めずらしいものであった。
タマゴそうめんはポルトガル語の Fios de Ovos という菓子を和訳したものである。Fios は糸であり、Ovos は玉子のことである。その故に長崎で「タマゴそうめん」と訳し長崎名物の1つであったが、現在その製法は福岡に伝えられ「鶏卵素麺」の名で全国に喧伝されている。その製法は「玉子の赤味を去り、布にてこし、砂糖とねり、其の上に小麦粉をたらしかけ、造るなり」と記してある。
当時の料理菓子のことを記したものとしては、東北大学狩野文庫に収蔵されている「和蘭陀菓子製法」は有名である。
 長崎菓子屋図(カステラ焼図) |
 コンペイト |
唐船と言えば私たちはすべて中国大陸より来航してきた船と考えるが、17世紀の人たちはジャンク型の船に乗って来航し、漢字で会話もできる人をすべて唐人といったので、ベトナム、カンボチヤ、タイ方面、福建省方面から来る人、近く杭州・南京方面から来航して来た人もすべて長崎の人たちは「唐人さん」とよんでいた。
その唐船の人たちが最初に長崎に来たのは、1600年頃であり、その人たちは皆ポルトガルの人と同様に長崎の街中に自由に住むことができ、その奥さんはすべて日本の女性であったので、町中には多くの混血の子供がいた。
唐船の人は長崎に自分たちより先に来航していたポルトガル人たちの貿易内容を見たとき、第一の貿易品は生糸・織物 (反物)、砂糖が主であることを知った。以来、唐船の人たちも多くの生糸・砂糖を積み、渡って来た。
1641年の長崎入港の唐船は大小97隻であった。その積荷の大半は砂糖であった。
○福州方面より89隻。黒砂糖・251,700斤、白砂糖・5,427斤
広南方面より3隻。黒砂糖・4,000斤、白砂糖・20,000斤
カンボチヤ、東京方面の唐船ともに砂糖なし。
○1648年の入港唐船数は17隻であった。その積荷は砂糖が主であった。
黒砂糖・91,000斤、白砂糖・12,000斤、氷砂糖・83斤、蜂蜜・6,600斤
広南方面より3隻。黒砂糖・4,000斤、白砂糖・20,000斤
カンボチヤ、東京方面の唐船ともに砂糖なし。
○1648年の入港唐船数は17隻であった。その積荷は砂糖が主であった。
黒砂糖・91,000斤、白砂糖・12,000斤、氷砂糖・83斤、蜂蜜・6,600斤
1640年、徳川幕府は平戸にいたオランダ人に対し長崎出島に移転することを命じたので、1641年オランダ人は出島内にオランダ商館を移し、以後オランダ船は安政の開国 (1859年) まで長崎港でのみ貿易を続けている。
オランダ船は長崎で目のあたりに唐船の砂糖貿易の実情を見たとき、オランダ船もまた船の底荷として砂糖を用いるようになった。
1641年台湾を経由して長崎に入港してきたオランダ船の積荷には黒砂糖・35,000斤、白砂糖・4,000斤があった。翌1642年のオランダ船の積荷の中にも白砂糖1,000斤が積まれている。
オランダ船の積荷砂糖のほとんどは台湾よりの積荷であった。1652年の出島オランダ商館の日記には次の記事があった。
オランダ船は長崎で目のあたりに唐船の砂糖貿易の実情を見たとき、オランダ船もまた船の底荷として砂糖を用いるようになった。
1641年台湾を経由して長崎に入港してきたオランダ船の積荷には黒砂糖・35,000斤、白砂糖・4,000斤があった。翌1642年のオランダ船の積荷の中にも白砂糖1,000斤が積まれている。
オランダ船の積荷砂糖のほとんどは台湾よりの積荷であった。1652年の出島オランダ商館の日記には次の記事があった。
○9月25日、ベルガル糸、トンキン・オランダの織物、ラーケンについては昨年より相当高く売れたが、ミルラと砂糖は殆ど利益がなかった。それは唐船で多くの砂糖が輸入されていたからである。
江戸幕府は初期の長崎貿易については比較的自由であったが、寛文12 (1672)年より輸入貨物をすべて評価させ適当の価格をきめ全国に販売させる制度をとり、全体の総額についても国内の生産需要に合わせて、その時代時代によって制限を加えている。
18世紀前半 (正徳年間) の輸入砂糖量は200万斤前後と推定されている。
正徳2(1712)年 寺島良安著の「和漢三才図会」には次のように記してある。
○思うに砂糖には氷糖 (こおりざとう)、糖霜 (しろざとう)、紫糖 (くろざとう) の三品がある。
・白砂糖はおよそ250万斤が諸外国より長崎に来る。潔で湿ってないものが良い。その中に円く扁(ひらた)く餅状になった大塊がある。これを盞 (さんぼん) という。砕くと大へん白い。すべて台湾のものを極上とす。
交趾 (ベトナム) の物は之に次ぐ。南京・福建・寧波などは又その次なり。ジャガタラ、オランダの物は下等品である。
・氷砂糖の輸入はおよそ30万斤、台湾のものがよい。
・黒砂糖 およそ7、80万斤輸入されている。
交趾のものを最上とし、台湾・福州・シャム (タイ) のものが之に次ぎ、カンボチヤの物は下等品である。琉球からも7〜80斤くるが最下等のものである。琉球ではまだ白・氷の製法を知らないのであろうか、ただ黒砂糖のみが有るだけである。
・白砂糖はおよそ250万斤が諸外国より長崎に来る。潔で湿ってないものが良い。その中に円く扁(ひらた)く餅状になった大塊がある。これを盞 (さんぼん) という。砕くと大へん白い。すべて台湾のものを極上とす。
交趾 (ベトナム) の物は之に次ぐ。南京・福建・寧波などは又その次なり。ジャガタラ、オランダの物は下等品である。
・氷砂糖の輸入はおよそ30万斤、台湾のものがよい。
・黒砂糖 およそ7、80万斤輸入されている。
交趾のものを最上とし、台湾・福州・シャム (タイ) のものが之に次ぎ、カンボチヤの物は下等品である。琉球からも7〜80斤くるが最下等のものである。琉球ではまだ白・氷の製法を知らないのであろうか、ただ黒砂糖のみが有るだけである。
このようにわが国では17世紀後半より18世紀にかけて主として白砂糖が多く使用されていることが分かる。
日本には「砂糖きび」はなかったし、黒砂糖より白糖にする製法は伝えられていなかった。寛文7(1667)年水戸光圀が●● (ジャガタラ) に砂糖きび3本を注文した記録が「長崎唐通事会所日録」に記してある。また黒砂糖より白砂糖を製する技法について廷宝4 (1676) 年長崎奉行牛込忠左衛門が来航した唐船のものにその技法を尋ねさせたところ、唐船の人たちの答は、
日本には「砂糖きび」はなかったし、黒砂糖より白糖にする製法は伝えられていなかった。寛文7(1667)年水戸光圀が●● (ジャガタラ) に砂糖きび3本を注文した記録が「長崎唐通事会所日録」に記してある。また黒砂糖より白砂糖を製する技法について廷宝4 (1676) 年長崎奉行牛込忠左衛門が来航した唐船のものにその技法を尋ねさせたところ、唐船の人たちの答は、
○左様の事一人も存じ申したる者ご座なく候、又長崎市中に在住している唐人たちも存知の者一人も御座なく候
といっている (長崎寛宝日記)。
享保5(1720)年将軍吉宗は洋書解禁を令し対外新知識の吸収に努めているが、その1つとして享保10 (1725)年には長崎に来航して来た南京船主沈玉国に「黒砂糖を作る法・白砂糖を作る法」を尋ねその回答を翌11年正月に受けている。これより吉宗は同年8月全国に甘蔗栽培を奨励する法令を出している。
これよりわが国では砂糖を外国よりの輸入のみに頼ることがなく、自分で生産することができるようになってきた。
全国的な砂糖の増産は今まで砂糖の輸入で利益を受けていた長崎奉行所 (長崎会所) では、幕府に天保8(1837)年次のように申しでている。
享保5(1720)年将軍吉宗は洋書解禁を令し対外新知識の吸収に努めているが、その1つとして享保10 (1725)年には長崎に来航して来た南京船主沈玉国に「黒砂糖を作る法・白砂糖を作る法」を尋ねその回答を翌11年正月に受けている。これより吉宗は同年8月全国に甘蔗栽培を奨励する法令を出している。
これよりわが国では砂糖を外国よりの輸入のみに頼ることがなく、自分で生産することができるようになってきた。
全国的な砂糖の増産は今まで砂糖の輸入で利益を受けていた長崎奉行所 (長崎会所) では、幕府に天保8(1837)年次のように申しでている。
◯享和・文化の間 (1801−1817) より 和製砂糖相増、右に付、外国持渡砂糖直段下落仕り……
困っているので和製の砂糖の生産量を制限していただかないと長崎の対外貿易は大変な損失を招くことになる、というのである。幕府はこれに応じて国産砂糖を年間1,197万7,900斤ときめ、価格は平均1斤に付2匁3分3毛6糸になると記してある。
1802年のオランダ商館日記を読むと砂糖は1斤につき7コンデリンと記してあるが、1815年には1斤につき3コンデリン5カッシィとなっている。
1802年のオランダ商館日記を読むと砂糖は1斤につき7コンデリンと記してあるが、1815年には1斤につき3コンデリン5カッシィとなっている。
以上のように砂糖貿易は、幕府すなわちその貿易の第一線にあってすべての貿易業務を行っていた長崎会所にあって砂糖の輸入販売は重要なことであった。
寛政3(1791)年幕府は国内の事情もあって来航して来る唐船数は年に10艘、取引額を銀2,740貫目としているが、そのうち、砂糖の取引額は39貫460目とし、その利益は19貫730目と記している。そして天保8(1837)年には砂糖取引額を銀49貫目と増している。
輸入砂糖については御用物砂糖と御漬物 (砂糖漬) のことがあった。この両者はすべて老中たちにより町年寄高木作右衛門 (後世の長崎代官高木氏) の差配により実施されていた。
御用砂糖を納めた御用物蔵も御菓子蜜漬屋敷も共に高木代官所内にあり、蜜漬屋敷は元禄7(1694)年に造られている。蜜漬製作のときは町年寄1人、高木家の家来が立ち合い砂糖漬物師がつけこんでいる。
その砂糖御用漬物師については長崎奉行所の記録明細分限帳に次のように記してある。
○元禄7年より7代相勤め、牛島家・受用高六百目。御漬物手伝原家・受用高三百目。同手伝渡辺家・受用高300目 以上三人。此の蜜漬に用る水は最精選す。麹屋町にあり常に一般の飲用を禁じ密封す。
蜜漬にされたものとしては果物の類で―ザボン、仏手柑、桃、橙子、金柑、柿、林檎、棗、くるみ、天門冬、竜眼。蔬菜の類――生姜、冬瓜など、であったと記してある。
毎年入港してくる唐蘭船は長崎の社寺に一定額の砂糖を寄進することを許されていた。寺社側も何に彼と縁故を求めて大いに砂糖の寄進を願い出ている。面白いのはオランダ人も社寺に砂糖を寄進している。その一例として正保元(1640)年よりは真言宗の寺院聖無動寺に毎年白砂糖12篭を、天台宗の威福寺には享保8(1722)年より白砂糖2篭を毎年寄進している。
これらの寄進砂糖は現物が直接その社寺に届けられるのではなく、一応長崎会所の蔵に納められ同会所よりこれに相当する代価が贈られるようになっていた。
これと同様に出島オランダ屋敷に在留していたオランダ人も屋敷内に呼び入れた丸山遊女に対して砂糖を贈ることが許されていた。この砂糖のことを貰(もらい)砂糖とよんだ。
この貰砂糖について天明2(1782)年以後は、唐蘭人共一定の規定がなされている。例えば唐船主 (船長)、財副 (副船長) のものは各1人・白砂糖1,000斤まで許されていた。
この他、輸入砂糖については「御菓子屋除砂糖」という条令があった (長崎会所五冊物より)。
このことは時代によって変遷しているが、これは1年間660両までを御菓子製造者に対する砂糖と認め、そのうち500両は幕府役人の大久保主人が、残り150両は菓子業虎屋織江に買い取りを許すということであった。しかし寛政3(1791)年以後はこの制度は改められ、さらに天保9(1838)年からは「御菓子砂糖一同調進」することができるようになったと記してある。これは前記のように国内産の砂糖も多く出回ってきたからである。
長崎の砂糖については以上の他に多く書き残されているものがある。その中より幾つかを次に拾ってみることにした。
1.こぼれ砂糖
これは唐船より砂糖荷上げの折に落ちこぼれた砂糖は人足共の収入にしてよろしい。また唐人屋敷内に居住していた唐人たちが帰国の際館内に残した砂糖は係役人が処分してよろしいということであったが、色々のことがあり天明5(1785)年以後は禁止となっている。
2.砂糖会所
長崎奉行所では前述のように「こぼれ砂糖」の取り扱いを禁止したので、以後は長崎大村町に砂糖会所を設け、「こぼれ砂糖」の類を取りまとめ、一般に売りに出すことになった。
3.八朔御礼と砂糖
(旧)8月1日になると唐蘭船より貿易終了の御礼として奉行所、代官、長崎会所、町年寄に礼金を差し出していたが、この添物として砂糖を贈られていた。文政9(1826)年の記録には次のように記してある。
毎年入港してくる唐蘭船は長崎の社寺に一定額の砂糖を寄進することを許されていた。寺社側も何に彼と縁故を求めて大いに砂糖の寄進を願い出ている。面白いのはオランダ人も社寺に砂糖を寄進している。その一例として正保元(1640)年よりは真言宗の寺院聖無動寺に毎年白砂糖12篭を、天台宗の威福寺には享保8(1722)年より白砂糖2篭を毎年寄進している。
これらの寄進砂糖は現物が直接その社寺に届けられるのではなく、一応長崎会所の蔵に納められ同会所よりこれに相当する代価が贈られるようになっていた。
これと同様に出島オランダ屋敷に在留していたオランダ人も屋敷内に呼び入れた丸山遊女に対して砂糖を贈ることが許されていた。この砂糖のことを貰(もらい)砂糖とよんだ。
この貰砂糖について天明2(1782)年以後は、唐蘭人共一定の規定がなされている。例えば唐船主 (船長)、財副 (副船長) のものは各1人・白砂糖1,000斤まで許されていた。
この他、輸入砂糖については「御菓子屋除砂糖」という条令があった (長崎会所五冊物より)。
このことは時代によって変遷しているが、これは1年間660両までを御菓子製造者に対する砂糖と認め、そのうち500両は幕府役人の大久保主人が、残り150両は菓子業虎屋織江に買い取りを許すということであった。しかし寛政3(1791)年以後はこの制度は改められ、さらに天保9(1838)年からは「御菓子砂糖一同調進」することができるようになったと記してある。これは前記のように国内産の砂糖も多く出回ってきたからである。
長崎の砂糖については以上の他に多く書き残されているものがある。その中より幾つかを次に拾ってみることにした。
1.こぼれ砂糖
これは唐船より砂糖荷上げの折に落ちこぼれた砂糖は人足共の収入にしてよろしい。また唐人屋敷内に居住していた唐人たちが帰国の際館内に残した砂糖は係役人が処分してよろしいということであったが、色々のことがあり天明5(1785)年以後は禁止となっている。
2.砂糖会所
長崎奉行所では前述のように「こぼれ砂糖」の取り扱いを禁止したので、以後は長崎大村町に砂糖会所を設け、「こぼれ砂糖」の類を取りまとめ、一般に売りに出すことになった。
3.八朔御礼と砂糖
(旧)8月1日になると唐蘭船より貿易終了の御礼として奉行所、代官、長崎会所、町年寄に礼金を差し出していたが、この添物として砂糖を贈られていた。文政9(1826)年の記録には次のように記してある。
○文政9戌年より御鉄炮方高木道之助殿え八朔御礼として1ヶ年白砂糖5,000斤宛差出度旨紅毛人共依願
4.混血児と砂糖
1815年12月、出島カピタン、ヘンドリック・ドーフは、在日18年で種々の功績を残し出島を離れることになった。この時ドーフには丸山遊女瓜生野との間に丈吉という子供がいた。ドーフは帰国に際しドーフはわが国の規則で子供をつれ帰ることが禁じられていたので、彼は子供の今後の生活のため白砂糖300篭 (代価2,180両) を長崎奉行遠山左衛門尉に托し帰国し、それに応えて奉行は丈吉が成人したとき町年寄支配役人として取りたてた話は美談として今に伝えられている。
長崎と砂糖の研究は色々の方向より今後も論考されてゆくのであろうが、昔の人は長崎と言えばまず砂糖を思いうかべていた。その故に、あまりおもてなしの馳走がない時の挨拶に「うちは、長崎が遠うございまして」という言葉が残っている。これは「充分に砂糖を使った料理ではありませんが」という挨拶の意が込められている。また俳諧の1つに「長崎で砂糖は砂のごとくなり」というのもある。
参考文献
江戸時代の砂糖貿易 (岩生成一著、日本学士院紀要)
本邦糖業史 (樋口 弘著、味燈社)
砂糖考(上・下) (越中哲也著、長崎純心大学博物館食の文化史、続・食の文化史)
|
「今月の視点」 2001年2月 |
●近世の砂糖を考える 長崎純心大学 長崎学研究所主任 越中哲也 ●さとうきびの生産振興に向けた取り組み 沖縄県農林水産部糖業農産課係長 大城 健 |










