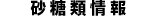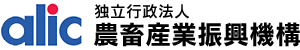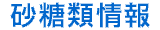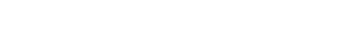
[2000年1月]
砂糖は単に甘いだけではなく、防腐効果、油の酸化防止、果物をゼリー状にする、泡立ちの保持など様々な使い方があります。また、砂糖を良いタイミングで使うことによって、十分な効果を上げることができます。おいしい料理を作るために、砂糖を上手に利用する方法を日本料理の献立を交え執筆していただきました。
なお、長島氏は「食は生い命のち」の認識を取り組みの原点とし、消費者と生産者の橋渡し、望ましい食生活の啓発等の役割を担って設立された「食と農の応援団」の構成メンバーとしても活躍なさっています。
(社)日本料理研究会師範 築地「紫水」料理長
長島 博 |
料理という言葉は、量はかりおさめるという意味であり、これは「素材に合った調味料の量と調理法を意味する」ということです。
料理の味というものについて、おいしいという味覚は、味のバランスが丁度良いということで、その食べ物にとって素材の持っている旨味を上手に引き出し、調味料の量が程良いことを言います。甘いものは甘く、バランスがとれていればおいしいのです。
きんとんや、芋の旨煮(甘煮)などは、薄味より、糖分が勝っている方がおいしく食べられます。それでは日本料理の代表的な献立を何点か紹介します。
一昔前までは、砂糖は貴重な調味料で、めったに口にすることができない時代もありました。それでも1年のうち数回は年中行事の中で、口にすることができる日がありました。代表的なものが、お彼岸のおはぎやぼたもちなどです。
戦後数十年の間に、日本の食生活は経済の高度成長とともに日本型食生活と言われる米、魚肉、野菜中心の食生活から、欧米型のパン、畜肉、乳製品中心の食生活へと変わってきました。これは日本人の体位の向上と栄養改善を目指したことによって、大きく変化したものでしょう。
近年における食生活の多様化によって、栄養の過剰摂取やアンバランスが肥満、虫歯、成人病など多くの疾病の原因とされ、運動不足や生活環境の変化などとともに、新しい健康問題として取り上げられています。
一部の女性によるダイエットなども、低カロリー食と称し遍った食事を摂ることより、いろいろな食品をバランスよく摂取し、適度な運動を心がけ、甘味も適量楽しむことが心身の健康を維持するためには大切であると思います。
また、特に発育途中の子供にとっては、脳の働きを良くするためにも、規則正しい3度の食事とおやつでの糖分補給を心がけることが大切であると思います。
里芋の旨煮(甘煮)
4〜5人分
材料:里芋1kg、上白糖360g、塩25cc、しょうゆ60cc |
(1) 里芋は皮を剥き、ざるに取り、振り洗いをしながら、ぬめりをとります。
(2) 鍋に(1)を入れ、水を張り泡をよくすくいとりながら串がスーと通るまで柔らかく茹ゆで水にさらします。
(3) 鍋に(2)を入れ、出し汁を若干少なめに張り、上白糖を全体量の3分の1入れ、紙蓋をし煮汁が3分の1程煮詰まったところで上白糖3分の1を入れ塩を加え煮ます。
(4) 残りの出し汁が3分の1程煮詰まったところに上白糖の残り3分の1を入れ、しょうゆを加え仕上げます。
|
現在、砂糖は、その製法によって実に多くの種類があります。調味料としての甘味だけではなく、その形態においてもバラエティーに富んでいます。完全な液状の液糖から、黒砂糖のように塊状のもの、粉糖、双目糖、グラニュー糖、上白糖、三温糖、角砂糖、氷砂糖の結晶状のものまで様々です。そして、甘味もそれぞれ微妙に異なります。三温糖は、上白糖と似た粒の細かいしっとりとした薄い褐色の砂糖です。佃煮や煮物などに使うとその独特の風味と、一味違ったコクのある甘さが料理の味を引き立てます。煮物に黒砂糖を使う時には、分量を加減して使わないと、しつこい味になります。すき焼きには、白いさっぱりした上白糖がよく合います。しつこさが少ないので、いくらでもすき焼きが食べられると言われます。
砂糖は、温度変化によって色や味などがいろいろ変化し、使う用途も広がります。砂糖液を鍋に入れ火にかけると、どんどん温度が高くなり、沸点も上がります。
温度の低い方から、シロップ、フォンダン、キャラメル、ドロップ、ベッコウ、カラメルソースなどができます。カラメルソースは、製菓用、しょうゆ、ソース、食酢、黒ビール、ブランデーなどの着色用に使われ、風味をつける上で、大切な役割を果たしています。
そして、砂糖は、おいしそうな焼き色をつけます。ホットケーキ、ビスケット、カステラ、クッキー、パンの外側のこんがりとした表面の焼き色は、卵や小麦粉に含まれるアミノ酸と砂糖とが反応してできる現象で、これをメイラード反応と言います。魚の照り焼きやうなぎのかば焼きなど、どちらのタレにも砂糖としょうゆが使われています。これを煮詰めると、しょうゆに含まれているアミノ酸と砂糖のブドウ糖や果糖とが反応して、褐色になりおいしいにおいが生まれます。
砂糖が料理に使われる時は、しょうゆも一緒に使われることが多くあります。この時、砂糖の量が多すぎても、少なすぎても料理の味のバランスは悪くなります。一般的には、しょうゆの量に対して砂糖は10〜20%位とされていますが、魚や肉などの強い臭みを消すには砂糖を多めに加えて煮るとにおいが消えます。逆に、素材の香りや持ち味を生かす必要がある料理では、砂糖はなるべく少なめに使う方が良いと思います。
料理の中での砂糖の働きはたくさんあります。老化抑制、防腐作用、醗酵促進、粘性付与、光沢付与、水分の保持、コロイド形成、ペクチンのゲル形成、結晶化、カラメル化などです。
すじの多い肉に砂糖をもみ込んで煮ると肉が柔らかくなります。これはすじの筋肉中のコラーゲンが砂糖を加えることにより保水性が高まるからです。豆の場合は、砂糖を一度に入れると豆の中の水分が一気に外へ出てしまうので、どうしても固くなり、しなびてしまい煮えにくくなり、味も染み込み難くなってしまいます。煮豆を作る時は、砂糖を何回かに分けて入れると浸透圧が徐々に上がるため、砂糖の粒子が豆の中にゆっくり入り込み保水性が保たれたまま豆を柔らかく煮上げることができます。干ぴょうや乾物、干ししいたけを水で戻す時、ひとつまみの砂糖を加えるのもこの砂糖の保水性を利用した処理法です。
砂糖を加熱すると状になります。これは砂糖のもつ保水力が強いために素材の表面に水を塗ったような艶のある状態になります。この性質を利用したきれいな艶のある料理として、きんとん、照り焼き、グラッセなどがあります。
伊達巻玉子
4〜5人分
材料:すり身200g、玉子15個、味醂(みりん)1合、
蜜1合、しょうゆ少々 |
すり身を玉子でのばし、味醂、蜜(水1升、三温糖1kg、塩少々の割合)、しょうゆ少々で食味をとり玉子鍋に流し入れ、オーブンで(120度)15分焼きます。
|
お多福豆
4〜5人分
材料:お多福豆1升、三温糖1kg、塩しょうゆ各少々 |
(1) 豆を灰あ汁く水に一晩漬けておきます。
(2) (1)を火にかけ豆の皮の具合を見て重曹を加え、10分程むらして湯にさらし、重曹(タンサン臭)を抜き水で冷やします。
(3) 鍋に引きざるを敷き、豆が踊らぬようにきちんと縦に並べ、三温糖、塩少々を入れ、穴あきの落とし蓋をし、軽く重お石もしをして煮ていき、仕上げにしょうゆを少々入れます。 |
黒豆
4〜5人分
材料:黒豆1升、三温糖1.5kg、しょうゆ50cc、生姜の絞り汁少々 |
(1) 丹波産の黒豆を4〜5倍量の水に重曹を盃3杯入れ一晩漬けておきます。
(2) 次にそのまま鉄鍋(鍋の内側に金ざるをはめ込んだもの)に移し、火にかけます。こうしておくと還元鉄を入れなくても豆を黒く煮上げることができます。また、鍋底に豆があたることがないので、豆の形が崩れずに煮上げることができます。
(3) 初めは強火にし煮立ってきたら弱火にし、落とし蓋をし、途中で灰あ汁くが泡になって出てくるので、よく取り除きます。
(4) 弱火にして12時間程さし湯をしながら、初めの水位を保ちながら炊き続けます。そのまま冷まし、ぬるま湯程度になったら同じ温度位の湯を別鍋に用意し、手で豆を移し入れます。
(5) それを火にかけ一度沸かして火を止め、ぬるま湯になるまで冷まします。同様に3〜4回繰り返します。
(6) 水1升に三温糖300gを入れ煮溶とかし薄蜜を作ります。三温糖は黒豆1升に1.5kg使いますが数回に分けて加えて行くことが大切です。
(7) 薄蜜中に静かに黒豆を入れ表面がグラッとゆれたら灰汁を取り除きすぐ火を止めます。セロファン紙をかぶせて空気に触れないようにしそのまま翌日までおきます。
(8) 2日目は蜜だけをすくい出し、別鍋に移し三温糖400gを加え5分程煮詰め灰汁を取り除きます。これを再び豆の方に戻し入れ火にかけます。表面が動いてきたら、灰汁を取り火を止め、セロファン紙をかぶせそのまま翌日までおきます。
(9) 3日目は、2日目と同様にします。4日目は同様に行い、灰汁を取り除いた後、しょうゆを50ccと生姜の絞り汁を少々加え5分程煮詰めて仕上げます。 |
珍しくておいしいきんとんの作り方
零余子(むかご)眞砂きんとん
4〜5人分
材料:零余子4合、塩少々、重曹小さじ2分の1、甘藷300g、上白糖 |
(1) 零余子4合を包丁で皮を薄く剥き水にとり、その水を2、3回取り変えて良くさらし、灰汁のぬけたところでざるにあけ、水をきり、塩を薄く振りかけざるを振って塩をまわし、10分程おきます。その後、零余子が浸る位の水を鍋に入れ火にかけて煮立ったところで重曹を小さじ2分の1程加え、この中へ先の零余子を入れ柔らかく茹だったところでざるに生揚げにします。重曹を加えると零余子が薄青く茹で上がります。
(2) 甘藷150gの皮を剥き、縦7mm位に打ちかけに切り(へぎ切りにし)、さらに小口から7mm程に切ります。水に取り洗い、ざるにふきんを敷いて、甘藷の水気をきっておきます。
(3) (1)の零余子を鍋に入れ、零余子の5割の水と5割の上白糖、塩少々を加え火にかけ、艶が出てきたところでざるに上げます。
(4) 甘藷150gの皮を剥き厚さ7mmの小口より輪切りにし、水に落とし、砂糖湯にて柔らかく茹でざるに取り裏漉しをします。
(5) (3)の汁を火にかけ(4)を入れて煮ます。
(6) 煮汁も程良く煮詰まり艶が出てきたところで(2)を入れ、軽く混ぜ煮詰め、(3)を入れ宮島(杓子)にて混ぜ合わせ仕上げます。 |
煎麦(いりむぎ)馬鈴薯きんとん
材料:押麦1.5合、馬鈴薯小35個、酒、上白糖、
白隠元晒しあん1.5合、塩少々 |
(1) 押麦1.5合を焙烙(平たい素焼きの土鍋)にて煎り、擂鉢にとり、擂粉木にて良く擂り、細かな粉状にし、ふるいにかけます。
(2) 小さな馬鈴薯35個の皮を剥き擂鉢にとり、薄く塩を振り、掌でころがし角をとり、水で洗い柔らかに茹でてざるにとり水気をきっておきます。
(3) (2)の5割の酒と5割の上白糖を鍋にとり(2)の馬鈴薯を入れ、塩少々を加え、火にかけ馬鈴薯に艶がのってきたところで芋を取り出し、冷ましておきます。
(4) (3)の汁を火にかけ、白隠元の晒しあんを1.5合入れ木杓子で手早くかき混ぜます。この時手早くしないと粘ります。
(5) (4)(2)を合わせ仕上げます。 |
自然薯(じねんじょ)の黒胡麻きんとん
|
材料:黒胡麻1.5合、自然薯3本、上白糖、塩少々 |
(1) 黒胡麻1.5合を焙烙にて煎り、擂鉢にとり油が出る程に擂っておきます(市販の当たり胡麻を使うと便利)。
(2) 自然薯3本を水洗いし、長さ10cm程に切り、皮のまま、柔らかに茹で生揚げにし、その後、皮を剥き、幅の広いところは縦2つに切り、小口から幅1.5cm位に35切れにします。残った部分を裏漉しにかけておきます。
(3) (2)を1.5cmに切った自然薯の量の5割の水と5割の上白糖を合わせ鍋に取り煮立て艶の出てきたところで塩少々を加え(2)の切った自然薯を入れ4、5回煮立てて、すくい取って生揚げにします。
(4) (1)に(3)の煮汁を少々加え練っておきます。
(5) (3)の煮汁を火にかけ(2)の裏漉した自然薯を入れかき回しながら煮て艶の出てきたところで(4)を入れ衣加減に練り(3)を加え崩れないようにかき回しながら煮上げ、仕上げます。 |
防腐効果のある砂糖
カビや微生物は水分がないと繁殖しません。砂糖をたくさん使ったようかんやジャムなどは、なかなか腐りません。これは食品の水分を砂糖がしっかりかかえて離さない性質があるためです。牛乳は砂糖をたっぷり使って練乳として貯蔵したりしました。砂糖は天然の防腐剤や保存剤としての効果があります。
近年は糖分控え目という傾向が強まっていますが、砂糖の濃度が薄いと、微生物は逆に糖分を栄養源として繁殖し、カビがはえてきてしまいます。
酸化防止としての砂糖
バターや油を使った食べ物は、空気に長いことさらされていると味が悪くなったり、イヤなにおいがしたりします。これは脂肪分が酸素と反応して劣化(酸化)するからです。
バタークリームのように砂糖が入っていると油の中の水分が砂糖と結合して酸素が溶け込み難くなるという性質により脂肪の酸化が抑えられます。その他、色や香りの変化、ビタミンCの酸化を防いだり、遅らせるのに役立っています。
砂糖は果物をゼリー状にする
熟した果物に砂糖をまぶしておくと、中の水分が外に染み出て、しんなりします。
その水分に砂糖が溶けて、煮るとどろっとしたゼリー状になります。砂糖の働きで水分をたくさんかかえこみ柔らかくなります。
アップルパイのりんごやいちごジャム、マーマレードなどが挙げられます。
砂糖はパンのふくらみを助ける
食パンは、小麦粉、水、イースト菌、砂糖で作りますが、砂糖水の中で発酵させてイースト菌の働きを活発にしてから小麦粉にこのイースト菌を混ぜると砂糖はイースト菌の働きで炭酸ガスを生み、このガスがパンの中に気泡を作り、口当たりの良い生地を作ります。
泡立ちの保持
砂糖は卵白の泡立ちを安定させ、長持ちさせます。メレンゲを作る時、卵白に砂糖を加えると、砂糖が水分をかかえこんでキメ細かな泡ができ、しかも艶が出て泡は丈夫になり、なかなか消えません。
塩と砂糖
しめサバを作る時、一般的にはたっぷりの塩で身をしめますが、3枚におろしたサバに砂糖をし1時間おきます。表面がしっとりしてきたら、砂糖を取り除き、べた塩をして4時間程おき、塩を洗い落とし、食酢に20分漬けます。サバの水分を砂糖で抜くことにより、後から塩をしても、内部まで塩が浸透しないため塩辛くなるのを防ぎ、適度な塩味になります。
酢と砂糖
酢の物にも砂糖はよく使われます。砂糖の甘味を強く感じられる分、酸味は抑制されます。すっぱい夏みかんやグレープフルーツに、砂糖をかけると酸味が和らぎ食べやすくなるのと同じです。
顆粒糖は、自動販売機などで使われる砂糖でプレーン・ヨーグルトなどについてくる溶けやすい砂糖です。アイスコーヒーや果物に振りかけて食べることもあります。
氷砂糖は溶けるのに時間がかかります。焼酎に入れておくと徐々に溶けて果実酒を作るのに最適です。アルコールの中に果実のエキスが出てくるのと砂糖がまろやかな甘みとともに溶けていくのが同時にゆっくり進むと、おいしいものができます。
コーヒーに砂糖を入れると苦みを弱め口当たりが良くなり、おいしく飲めます。特にグラニュー糖は、甘みにくせがないので、コーヒーや紅茶のような風味を味わうものには、よく合います。
このように砂糖にはいろいろな種類があり、その使い方によってそれぞれの砂糖の特性が生かされます。
上白糖やグラニュー糖のような白い砂糖もあれば三温糖や中双糖のように褐色の砂糖もありますが、砂糖の白さは、精製工程により白くなるもので漂白剤を使っているわけではありません。どの砂糖もすべて安全な自然食品であると言えます。毎日の食卓に上手に取り入れて、おいしくいただきたいと思います。