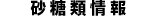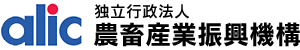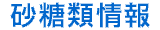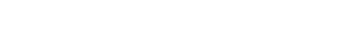
[2000年1月]
直播栽培導入による省力安定生産(千歳市 清水利一氏)
はじめに
北海道の空の玄関「千歳空港」で知られる千歳市は石狩平野の南端に位置し、大平洋と日本海の気象の影響を受ける分岐点となっている。
耕地面積は6,077ha、うち畑作面積は4,157ha他は水稲316haなどで農家戸数は369戸である。主な作物の面積は、小麦1,240ha、豆類912ha、てん菜775ha、ばれいしょ183haなどで乳牛5,900頭、肉用牛1,510頭。農業粗生産額は97億100万円で、内訳は鶏33%、小麦、豆類、てん菜、ばれいしょ、米など23%、乳牛24%、野菜8%、果樹・花4%などである。
経営の概況
清水氏(29歳)は千歳市市街から北東へ約20kmに位置する東丘地区で営農している。東丘は丘陵地からなり土壌は火山性土である。清水氏の家族は4人、労働力も4人、雇用労働力は年間延べ約50人。耕地面積は39.6haで作付状況は表1のようにてん菜などの畑作4品目を主体にしているが、野菜なども取り入れている。
| 表1:清水氏の作付け状況(平成10年) |
| 作物名 | てん菜 | 秋播小麦 | 普通小豆 | 大納言
小 豆 | 大 豆 | ばれいしょ | 人 参 | 計 |
| 面積(ha) | 15.5 | 2.3 | 3.6 | 6.0 | 8.0 | 2.7 | 1.5 | 39.6 |
| 比率(%) | 39.1 | 5.8 | 9.1 | 15.2 | 20.2 | 6.8 | 3.8 | 100.0 |
| 収量(kg/10a) | 5,815 | 390 | 250 | 230 | 150 | ― | ― | ― |
|
てん菜の生産実績
過去5カ年の清水氏の生産実績は表2の通りである。平成8年は多雨による湿害が発生した低収年であったが、清水氏の直播は一部に連作が行われ、根腐病も多発し低収となった。しかし、平成10年には施肥機の改善により多肥が可能となり直播でも高収量が得られた。
| 表2:清水氏の生産実績 |
| 項 目 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 |
栽培面積(ha)
収量(t/ha)
根中糖分(%) |
12.92(2.8)
53.27(35.00)
16.3 (14.4) |
16.80(7.0)
45.56(51.00)
16.7(16.4) |
16.78(3.8)
40.58(36.70)
16.6(16.4) |
8.25
58.94
17.4 |
15.50(3.2)
58.15(8.00)
16.3(17.2) |
市平均収量
市平均糖分 |
54.26
15.0 |
48.14
17.0 |
43.29
17.5 |
50.87
17.0 |
56.79
15.5 |
地域平均収量
地域平均糖分 |
54.44
15.0 |
48.21
17.0 |
41.31
17.5 |
51.07
17.1 |
57.19
15.7 |
|
| 注:( )内は直播の値 |
輪作と地力対策
てん菜→小豆→野菜→ばれいしょ→小麦の5年輪作が確立されており、麦跡に緑肥えん麦を栽培し鋤き込んでいる。また、堆肥を豆類またはてん菜の作付け前に10a当たり1トン程度施用している。特に直播では短期輪作にならぬよう注意している。
排水対策
多雨年は減収となっていたことから、排水対策が重要と考えている。暗渠の施工は平成9年は前年秋に、平成10年は春に排水不良ほ場に対して行っている。
健苗の育成
移植栽培がまだ経営の基幹となっているので健苗も高収量の要因の1つと認識し、健苗育成に努めている。
播種は3月20日過ぎから3戸共同の播種プラントで行う。潅水・温度管理に留意し、徒長させぬよう健苗育成を行う。育苗中に除草剤は使用しない。間引きの際に除草する。苗ずらしは2回程実施する。移植直前にトビハムシ・根腐病防除のため殺虫殺菌剤を処理する。
ほ場準備・移植と直播播種
前作が小麦なので秋耕を行っている。サブソイラーは秋に施工。砕土・整地はスプリングハロー→ロータリーで行っている。昨年は5月1日から7日間に移植した。栽植密度は畦幅66cm株間22cmで10a当たり7,200本を目標としている。直播は平成10年から狭畦栽培を行い畦幅45cm株間22cmの10a当たり10,100本を目標としている。
直播播種の際、風害防止のためえん麦または小麦も同時に播種する。現在の総合播種機で施肥・てん菜ペレット種子・麦類種子播種の作業が同時に可能である。てん菜より発芽の早い麦類により風害防止に効果が認められている。
施肥
平成10年の施肥内容は表3の通りで直播の施肥量を多くしている。直播を始めたのは平成6年であるが、直播は肥料焼けが起こりやすいので施肥量を控え目にしていたが、その後、側条施肥が可能な施肥機に改善したことによって平成10年から増肥が可能となり、これが高収量の要因になったと推測している。
| 表3:清水氏の施肥内容(平成10年度) |
項目
肥料名 |
移 植 |
直 播 |
| 施肥量 |
窒 素 |
リン酸 |
加 里 |
施肥量 |
窒 素 |
リン酸 |
加 里 |
N 202
ペレット状けいふん
チ リ 硝 石 |
180
10
12.5 |
21.6
0.3
2.0 |
36.0
0.3
|
21.6
0.1
|
180
10
25 |
21.6
0.3
4.0 |
36.0
0.3
|
21.6
0.1
|
| 合計 |
| 23.9 | 36.3 | 21.7 | | 25.9 | 36.3 | 21.7 |
|
|
注:直播きのチリ硝石は追肥
|
中耕・除草
中耕は移植では2回程度行っているが狭畦直播では1回行ったら葉が畦を覆うので、2回目は行うことができないので、追肥と深耕爪中耕を同時に1回のみ行っている。
除草剤は移植ではベタナール、レナパックの2回散布、直播は土壌処理のクロロIPC、麦を殺草するための、セレクト、ナブなどを用いる必要があり、平成10年は6月6日セレクト、6月13日ナブ、レナパック、ベタナールと使用したが、6月6日の散布がやや遅れたのでイネ科除草剤を2回も使わざるを得なかったので、今後さらにイネ科除草剤の散布適期について検討したいとのことである。
病害虫防除
糖業原料センター・農協・農業改良普及センター等の情報を参考にして適期防除に努めている。直播だからといって特別の防除は行っていない。
収穫作業
狭畦直播では国産収穫機を狭畦用に改造したものを使用したが、収穫の精度・能率が劣り機械の改良が必要と考えている。
今後の取り組み
以上のように、清水氏は経営の一部に直播を導入し、その直播栽培方式を狭畦とし、施肥法の改善などにより高収量を得たが、今後、収穫機の改良・根腐病の発生防止・より効率的施肥法の実施などの技術開発によりさらなる安定収量を獲得する狭畦直播栽培を求めていきたいと結んだ。
畑作酪農で高収益を実現(美深町 十亀孝宣氏)
はじめに
美深町は、上川管内の北部に位置している町で西は中川町、北は音威子府村、東は宗谷支庁管内の枝幸町・歌登町に接している。内陸に位置するため、夏は時折、真夏日になることもあるが、通常、気温は年間を通し低めで積雪期間が長く、無霜期間は短く、概して厳しい気象条件にある。
平成9年度における農業粗生産額の構成は、畜産61%、小麦、デントコーン、てん菜など19%、野菜11%、米9%となっている。主な作物のおおよその作付面積は水稲300ha、小麦300ha、デントコーン300ha、てん菜221ha、牧草2,600haで、乳牛4,000頭、肉用牛7,300頭、豚1,600頭などを飼育している。
辺渓地区は、市街から南東へ約6〜9kmの所に位置し、耕地土壌は仁宇付川の影響を受けた沖積土(褐色低地土)が主体となっている。
経営の概要
明治の末に曾祖父が現在地に入植してから孝宣氏(46歳)で4代目。元々は稲作を営んでおり、ピーク時には10haの全面積が水稲だったが、米の生産調整が始まる昭和40年代前に畑作中心に切り換えた。また、現在耕作している面積は34haであるが未使用地を含め総保有面積は47.9ha。現在の作付状況は表4の通りで、てん菜、ばれいしょ、小豆、秋まき小麦、牧草、デントコーンを作付けし畑作酪農の複合経営である。乳牛は土地を肥やすためということで、昭和29年から導入を始め、その後現在の頭数(経産牛・育成牛合わせて33頭)まで増やしてきたが、酪農の規模は畑作が維持できる程度と考えている。てん菜の作付けは昭和30年代の直播時代から始めており、小麦とかぼちゃは5年程前から始めた。
家族は8人で、うち4人が農業に従事している。農業機械は、トラクター4台(うち管理作業専用50PS1台)にビートプランタ、スプレーヤ、ビートタッパ、ビートハーベスタ、マニュアスプレッダ、ライムソワー、ブロードキャスタ等を所有し、適期作業を可能としている。
耕作地の地形はおおむね平坦で大部分が砂質土壌で部分的に礫層が浅く作土にも礫を含み、排水は全体的に良好である。
| 表4:十亀氏の作付け状況(平成10年) |
| 作物名 | てん菜 | ばれいしょ | 小 豆 | 秋播小麦 | かぼちゃ | サイレージ
用コーン | 牧 草 | 計 |
| 面積(ha) |
454 | 204 | 406 | 378 | 100 | 230 | 1,630 | 3,402 |
| 比率(%) |
13 | 6 | 12 | 11 | 3 | 7 | 48 | 100 |
|
てん菜の生産実績
過去5ヵ年の平均収量は、10a当たり5,881kg、根中糖分は17%で、特に収量は石礫が多いため干ばつの影響を受けた年もあるが、5年輪作体系の確立、酪農による堆肥を投入する等により土づくりを徹底したことによって市平均を大きく上回っている(表5)。
| 表5:十亀氏の生産実績 |
| 項 目 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平 均 |
作付面積(ha)
10a当たり収量(kg)
同上市平均対比(%)
根中糖分(%)
同上市平均対比(%) |
3.10
5,064
107
16.9
99 |
3.09
5,942
113
17.3
101 |
2.98
5,033
108
17.7
101 |
3.97
6,029
140
17.2
96 |
4.54
7,339
124
16.1
98 |
3.54
5,881
118
17.0
99 |
| 市平均 |
市平均収量
市平均糖分 |
4,730
17.1 |
5,273
17.2 |
4,657
17.5 |
4,307
17.9 |
5,921
16.4 |
4,978
17.2 |
|
輪作と土づくり
輪作は5年を基本としており、以前は牧草を組み入れて、牧草→コーン→てん菜→小豆→ばれいしょであったが、最近は小麦を加えて、ばれいしょ→コーン→てん菜→小豆→小麦としている。堆肥はコーンとてん菜を中心に投入し土づくりに努めている。まずコーンの播種前に施用し、その後作にてん菜を作付けするほ場には、コーンの収穫後、秋に再度施用している。施用量はいずれも2〜3トン/10a。
土地基盤整備は除礫にかなりの投資をしており、補助事業で全面積を実施、50ミリ以下の礫は、ストーンピッカーを個人で導入し現在も必要に応じて除礫を行っている。一部の排水不良地には、暗渠を実施しており、現在排水不良のほ場はない。
てん菜の栽培技術
品種はリゾールを使用、育苗は平成10年から育苗センターのポットを使用し40〜45日育苗としている。苗床の潅水は、ポット設置3日後に行う。苗を徒長させないよう温度と水管理には細心の注意を払い、苗ずらしは1回実施している。立枯病防除としてタチガレン液剤を潅注。その他、液肥を2回散布。てん菜ほ場の融雪促進は昨年は3月27日に融雪剤120リットル/10aを散布した。耕起は堆肥散布後に秋耕し、春に再度耕起、耕起深は30cm程度。土壌改良剤として粒状生石灰を80kg/10aを散布。施肥の内容は表6の通り。土づくりが順調に行われ地力が高いため、施肥量はほぼ地区の平均程度であるが、高い収量を得ている。通常5月1日を目途に早期移植に努めており、昨年は4月30日に移植を開始し、途中中断し、5月7日に終了した。栽植密度は、60cm×22cm、株立本数は7,575株/10aとし、中耕は2種類のカルチベータを使い分け、1〜2回目は5月下旬、6月中旬に株間除草(スプリングロータリカルチ)、3回目は6月下旬に畦間除草(2段耕カルチ・サブソイラ使用)に行い、除草剤は使用せず、ホー除草も行っていないが、拾い草は2回行っている。
病害虫防除は褐班病の4回防除と防除徹底を図っている。また、最終防除のときに糖分上昇に効果がある成長調節剤エルノーを散布している。
| 表3:十亀氏の施肥内容(平成10年度) |
| (kg/10a) |
| 肥料名 |
施肥量 |
要 素 量 |
| 窒 素 |
りん酸 |
加 里 |
苦 土 |
| N202 | 140 | 16.8 | 28.0 | 16.8 | 5.6 |
|
今後の取り組み等
今後の取り組み等について、十亀氏は「てん菜は収益性が安定しているので、今後も経営の柱として作付けしていきたい。」と述べたが、家畜との複合やばれいしょ収穫時の手拾い等の作業労働がつらい現状にあるので、「作業の共同化・地域ぐるみのコントラクター化等の検討も必要ではないか?」と労働の軽減を図る経営が今後必要と話した。また、輪作体系遵守と土地生産性、面積の拡大等で機械に頼らざるを得ない状況の中で、コスト上の問題点はあるが、「地力増進など条件を整えながら、さらに収量を向上させ収益増で補っていきたい。」と力強く結んだ。